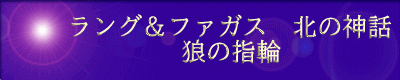
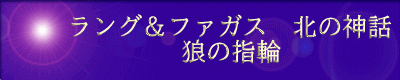
「こら、ピー。宴会のご馳走に手を出すんじゃない」
テーブルの上の料理に手を伸ばした少女の手を、ファガスが押さえた。
魔術師ギルド所属の二級魔術師ファガス・モニメント・アリスタナル。
このどことなくネズミを思わせる貧相な小男が、ミッドガルト界でも五指に入る名門アリスタナル家の御曹司だとは、いったい誰が思うだろうか。古代小人族の血を色濃く引くアリスタナル家は、そもそもの初めからミッドガルト界を構成する五大種族の一つを代表するものであった。太古からの地所と、いつ作られたのかも判然としない莫大な財宝の数々は、アリスタナル家に代々生まれる財産運用の才能がある当主のおかげで、今もその威容を保持し続けていた。
アリスタナル家の次期当主筆頭候補のファガスが家を継ぐのを嫌い、魔術師となることを宣言したときの騒ぎは、いまでも一族の語り草となっている。当然ながら一族は反対したが、そのぐらいではファガスという人物の、強情で頑固で意固地な決意を翻させることはできなかった。彼は今ではギルド登録の二級魔術師となり、日々怪しげな実験に勤しんでいる。
ファガスの住んでいるこの森は、古くからの地名の名残で、周囲からは妖精の森と呼ばれていた。もちろん、いまでは妖精など滅多に見かけることはない。ここはアリスタナル家の古くからの地所であり、彼はその森の中心部に盛り上がった小高い丘の中腹辺りに家を建てて、自由気侭な生活を楽しんでいる。
家と言ってもその大部分は地中に埋没している。古い小人族の洞窟の跡をここにみつけたファガスは、それに手を加えることで、居心地の良い部屋と大きな実験室のある自分の住居を作りあげてしまったのだ。それよりも何よりも、失敗した作品を放りこんでおくための広大な地下空間の存在こそが、洞窟を利用した最たる目的とも言える。壊れた魔法の道具というものは、裏庭に放置するには余りにも危険な存在なのだ。
執事のバイスターに案内されて、ラングたち一行がようやくファガスの家の庭に並べられたテーブルにたどりついたとき、この家の主人である小男は少女と取っ組みあいの真っ最中であった。ファガスにピーと呼ばれた少女パットは、小人族のファガスとほぼ同じぐらいの体の大きさだ。これでは勝負がつくわけがない。
おほん、と一つ、大きな咳払いをすると、ラングは前に出て、二人を捕まえた。その大きな両手の中に、二人を向かい合わせに吊り上げる。
「こら、ラング。降ろせ」ファガスが喚いた。
大きさというのも原因の一つだが、もともとラングは巨人族の血に潜む恐るべき怪力を生まれながらに授かっている。ファガスがどうあがこうと、ラングの巨大な手はびくともしなかった。
「あなた、女性のあつかい方をもっと勉強するべきよ」
同じくラングの手に持ち上げられたままで少女が抗議した。こちらは最初から抵抗する素振りさえ見せない。
「パット様。騒がない、と約束していただければ、わたくしめからラング様にお願い申し上げてもようございますが」
執事のバイスターが提案した。
「やくそく、する」パットと呼ばれた少女は、ぷうっと頬を膨らませて答えた。
「それともう一つ。料理はご自由にお取り下さっても構いませんが、手づかみはお止め下さい。約束してくださいますね」
「やくそく、する」
もう一度少女は答えてから、泥塗れの手で自分の耳の辺りを掻いた。ぽろぽろと泥の小さな塊がバイスターの足元に落ちて来る。
「最後にもう一つだけお願いがあります。お食事の前にその手を洗っていただけますね?」
「バイスター。あなた、執事のくせに、なまいきよ。将来、ファガスのお嫁さんになるのはあたいだからね。つまり、あたいはあんたの主人の奥さんってこと」少女が断言した。
「こら、ピー。勝手なことを言うな」ファガスが喚いた。まだラングに吊りあげられたままだ。その姿勢のままで、じたばたと暴れた。
「ええい、ラング。降ろせ。降ろさんか。さもないと」
「さもないと?」ラングが興味津々と言った顔で尋ねた。
それに答えて、ファガスは自分の手を突き出して見せた。金色に光る指輪が一つ、その中指に光っている。
「新しく開発した道具を使わせて貰う。自動指絞り器というやつだ。パデルスの街の拷問組合からの特注品だが、人体実験がまだ済んでいない。ファガス魔法具製作所はただいま犠牲となる応募者を募っている」
「実に面白い。ファガスよ。実に面白い」
ラングが重々しく肯いた。そうしているとラングは巨大な岩の彫像にも見える。溢れ返らんばかりの力を一杯に詰めこんだ人型の巨大なオブジェだ。
「わたしの指に合う道具が、この世の中に一つでもあると聞くとうれしくなるね。たとえそれが拷問道具でもな。
さて、試して貰おうか。その指輪がわたしの指を潰すのか、それともわたしの指がその指輪を潰すのかを」
その言葉通りに、ラングはファガスをつかんだ指に軽く力をこめた。ラングが周囲にそう見せようとしたほどには強くなかったが、ファガスは大袈裟に悲鳴を上げてみせた。これは二人のいつものゲームなのだ。
「前言を撤回する。こいつは繊細過ぎて、きみの指に合うような品ではない。しかたがない。他の志願者を募ろう」
ファガスはしらりと言ってのけた。
「絶対にあたしは志願しないわよ」
少女がピンクの舌を突き出すと、侮辱の仕草をこめてファガスに見せる。それを聞いて、まだ宙に吊るされたままのファガスが目をむいて見せた。
「そんな! とんでもない。女性に使うような拷問道具を、この俺が作るとでも思っているのか?」
ファガスは金の指輪をはめた手を振って見せた。
「これはもちろん男性専用だ。女性の指に装着した場合には、それなりの安全装置が働く仕掛けだ」
興味津々でここまでのやり取りを眺めていたベスが言った。
「ファガス先生も少しは紳士なのね。見直したわよ」
それを聞いて、ラングがやれやれという口調で言った。
「ベス。きみはファガスというものの性格を理解していないな。その安全装置とはどういうものだね? ファガス」
「それは決まっているだろう。自爆装置だ。女性がこれを填めさせられようとすると、指輪は自動的に爆発する。つまり女性に敬意を払わない拷問師の指が吹き飛ぶという仕組みだ」
ファガスは得意げに言った。
「で、その指輪を填めさせられる予定の女性の指はどうなる?」ラングは指摘した。
「そりゃ、当然、一緒に吹き飛ぶ」そう言ってから、ファガスは喉を詰まらせた。
そんな指輪をつけさせられるぐらいなら、どんな女性だってその前に自白するほうを選ぶだろう。
「な、わかっただろう。ファガスは天才で、どんな魔法具でも作り上げてしまうが、少しだけ思慮が足りないところがあるんだ」ラングが説明した。
「ねえ、ベス。ものは相談なんだけどね」ラングの手の中の少女が機会を捉えて言った。
「同じ女性のよしみとして、このあたしをここにいつまでも吊り下げておくつもりの、気の効かない大男のお尻を一つ蹴り上げてくんない? あたし、この場所はもう飽きちゃったの」
それを聞いて、ぽい、と言った感じでラングがファガスを放り出した。続いてその横にそっと泥塗れの少女を降ろす。
「こら、でかぶつ。あなたも少しは紳士としてのたしなみを取り戻したようね」
「きみたちのような勇敢なる女性のたゆまぬ努力のおかげでね」
ラングは大きな目でウインクをした。
「ピー。いったいお前は何をしに来たんだ。俺は招待した覚えはないぞ。料理をつまみ食いするためか」
ファガスが落ちた時に打った部分をさすりながら言った。
「あたしの名前はピアシング・パット・プアイ。ピーじゃないよ」
ファガスに向けて舌を一つ突き出してから、少女は続けた。
「この世の全てを司る大いなる予言に仕える森の老婆からの伝言だよ。大火事になる前に火遊びは止めなさいってね。ついでにあたしも言っておくけど、あんた、きっとおねしょするわよ」
「このピー・パー・プーめ。俺は火遊びなんかしていないぞ」ファガスが抗議した。
「おばあさんはね、あんたのことを、己の手の中にあるのが命を奪う毒蛇であることにも気付かないで、精一杯の力で握り締めている愚か者って、そうつぶやいていたよ」
言うだけ言ってせいせいしたという顔で、少女が立ち上がった。
「という訳で伝言は終わり。ああ、お腹が空いたっと。バイスター。お皿とフォークを取ってよ」
「パット様。手を洗って下さるという、わたくしめとのお約束はどうなさいました?」
バイスターは指摘した。
「ええい、もう、あんたったら、どうしてそんなに石頭なの」
苛立たしげに抗議するが、それでも勝てないと見たのか、少女はおとなしく手を洗って来る。バイスターはその手をしげしげと検分してから、食事の許可を出した。
皿一杯に料理を盛りつけた少女が、片端からそれを平らげるのを横目でにらみながら、ファガスはつぶやいた。
「毒蛇だと」それから眉根を寄せてつけ加えた。「下らん」
「さて」ラングは言った。
かちりと音をさせて右手の人差し指と親指の先を打ち合わせると、そこから飛び出した火花を使って、ラングは口に咥えたパイプに火をつけた。
これはラングのお気に入りの動作である。もちろん火を召喚する魔法の一つだ。いくら堅い指とは言え、打ち合わせたぐらいでそうそう火花が出るものではない。目には見えない呪文を巻きつけた指同士を叩きつけることで、合成された呪文が発動する。その結果が指からはじき出される火花となるのだ。
パイプはラングの口に合わせて作った特大のものである。その先端から凄い量の煙が宙に立ち上る。天頂へと進んでいた満月が空の上で煙たがるのではないかと、そう人に思わせるほどだ。
そのそばではベスが凄い目でラングの吸っている煙草を睨んでいるが、ラングはわざとそれに気付かない振りをしている。ベスはそもそもこういった肉体に害のあるものを取ることを極端に軽蔑する性格なのだ。彼女はあの手この手でラングのこの悪癖を止めさせようとしているが、今のところそれに成功はしていない。
「さて?」
手にした酒杯を何か大事なものであるかのようにしっかりとつかみながら、ファガスが問い返した。
「ごまかすんじゃない。ファガスよ。お前がわたしたちをここに呼んだわけが聞きたい。単に食事に来て欲しかっただけじゃないんだろう?」
「それは確かにそうだが。バイスターが喋ったのか?」
ちらりと背後に目をやってから、ファガスは言った。執事のバイスターは家の中に戻って、食事の後片付けと次の酒壷を温めなおしている最中だ。
「きみがルーン円盤を使って何かを行っているとな。それ以上は何も言っておらん。彼は本当にきみのことを心配しているんだよ。だからわたしにきみが何をやっているのかそれとなく確かめて欲しかったのだろう。きみには勿体ないほどの良い執事だよ。バイスターは」
「それはわかっている」ファガスは何かを考えこむかのようにむっつりと言い放った。
「良いだろう。実験の直前まで隠しておこうと思っていたのだが。ここしばらく俺が何をしていたのか話そう。そうしないとバイスターが心配するからな」
「ルーン円盤だな」ラングが畳みかけた。
「そう。ルーン円盤だ」
「ルーン円盤って何よ?」テーブルの横で、苺の絞り汁をベースにした飲み物を飲んでいたパット少女が尋ねた。
「ルーン円盤はルーン円盤だ。ピー。話の邪魔をするんじゃない」ファガスはパット少女に向けて舌を突き出した。
「いつかその舌に噛みついて上げるからね」そう言いながらも少女はお返しに舌を突き出して見せた。
「その言葉そっくりそのままお返しする」ぶすりとした表情でファガスが言い返した。
「喧嘩は後にしてくれんかね。話が前に進まん」
ラングが困ったものだとばかりに両手で大きなゼスチャーをして見せた。その手の動きにつれて、空気が動くのが感じ取れた。
「ふむ。よし、ではあらためて説明しよう。ベスもいることだしな。魔術師となる勉強の大事な一部だ。ルーン円盤はアリスタナル家、すなわちファガスの一族の秘宝の一つだ。魔法大学ではそれほど詳しいことは教えていない。そうだな、どこから話せばいいのかな?
いや、ここはファガスに頼もう。何と言っても彼の一族のことだからな」
ファガスは椅子からテーブルの上によじ登ると、その上に腰掛けた。
「わかった。手短に話そう。俺の先祖が小人族であることは知っているな。まあ、この体を見てもわかるが。さて、小人族の血を引く者は数多いが、その中でもアリスタナル家は極めて純血に近い。アリスタナル家では代々近親結婚が行われて来ていてな、その結果と言うわけだ」
「近親結婚って何よ?」少女が口を挟んだ。いつの間にか、また泥だらけになっている。
「極めて近い間柄、つまり、兄弟姉妹で結婚するってことだ。小人族の血はかなり長い間に渡ったこの伝統により遺伝的な欠陥は除かれているからな。いまでは変異体に対する魔法治療さえ行う必要がないほどだ。この伝統の利点の一つは財産の分散が防げるということだ」
難しい言葉の部分はすべて聞き流して、パットは意見を述べた。
「へえ。あたいのとことは大違いね。あたいの所はね。おばあさんがあたいをどこかから拾って来たの。あたいもおばあさんの歳になれば、どこかからあたいの子供を拾って来るの」
「ずいぶんと奇妙な性教育をしているんだな。お前の所の鬼婆は」
ファガスが感心したように言った。
「まあ、ともかくそういうわけで。アリスタナル家には過去の小人族の遺産がそっくりそのまま残っている。金銀財宝は言うに及ばず、その中でももっとも重要なものは、今では手に入らない古代の魔法材料だ。それとそういった類のもので作られた魔法による道具や武器だな。例えばアリスタナル家の秘蔵と言われるマナンの鎧。今ではあれほどの強度を持った鎧を作る魔法はどこにもない。古代に生きていた神々の魔法もその記憶もすべて消え去って久しい。
ルーン円盤はそういった財宝の一つだ。こいつはな、魔法的に強化された破壊不可能の円盤状の石版で、遥か昔の時代に生きた俺の先祖たちが、自分たちででっち上げた発明品や歴史の記録を刻んで残したものだ」
「あたいの所もそうだよ。お婆さんの大事な泉はやがてはあたいのものになるの。でも、あたいはあの泉は嫌い。だって誰かの目玉が一つ、水の中に転がっているんだもの」
「ピー。話の腰を折らないでくれないかな」ファガスが厳しい口調で言った。
「い~だ。あたしはピーじゃない、パットだよ。何度言ったらわかるの」
「じゃあ、パット。いや、パットお嬢様。わたしめの話が終わるまで、しばし口を閉じていて下さいますかな?」
ファガスが執事バイスターの口調を真似て言った。
「もう、あんたって嫌な奴ね。お婆さんがあたいの花婿にあんたを選んだんじゃなきゃ、あんたが何しようと知らないのに」
ファガス目掛けてもう一度大きく舌を突き出すと、パットはベスに向き直った。
「ねえ、物は相談なんだけど、そのリンゴ、あたいにくんない? 食べている間は、だまっていてあげる」
それを聞くと、ベスは微笑みながら果物を差し出して言った。
「あたしは別に黙っていて欲しいとは思わないけどね。でも先生たちのお話を邪魔するのは良くないかも知れないわね」
パットが果物に噛りつくのを見て、ファガスは深いため息をついた。やれやれ、このままではファガスの家の甘い物は、ことごとくこの少女に食い尽くされてしまうことだろう。パットの親代わりの老婆、泉の予言者と呼ばれている老女は、パットが虫歯になることを予言してはいないのだろうかと、ファガスは不思議に思った。
むろん実を言えば、それは予言済みで、しかも現在進行形なのだが、ファガスがそれを知ることはなかった。
言葉を失ったファガスの後を繋いで、ラングが説明を再開した。
「ルーン円盤の唯一の問題というのは、その表面に刻まれた文字を誰も読むことができないということだ。ルーン文字を記録に応用することはそもそも不可能だという現実がある。ルーン文字の本質は魔法であり、魔法の本質はルーン文字だからな。ルーン文字を刻むことで魔術の道具を作ることはできても、記録をすることはできない。魔力を秘めた言葉で書かれた本は、それ自体が意思を持つ」
「意思ですか?」ベスがつぶやいた。
「そう。意思だ」ラングは頷き、自分の女弟子を見つめた。
ベスが魔術師になることを目指して魔術師ギルドに入学したとは、ラングにはとても思えなかった。有り体に言えばベスは恐ろしく不勉強だったのだ。ルーン文字と記述に関する講義は、魔法理学の基礎と言ってもよい。ヴォネガット魔法大学での一般履修教科必修科目であるはずの講義を、ベスがどうやって突破したのかを、ラングは常々疑問に思っていた。
「ルーンの本は自意識を持つ。炎の魔術について書かれた本は本能的に周囲のすべてを焼き尽くそうとする。徹底的に、そして無差別にだ。その結果、自分自身も焼け落ちて終わる。これではルーンを使って本を書くのは危険の一言に尽きる。かといって、魔術記号であるルーンを使うことなく魔法の解説をすることには無理がある」
ラングは説明を続けた。ベスが魔術師を目指していようがいまいが、それでも魔術師として一人前に育て上げるのが、弟子を預かった者の義務だとラングは考えている。
「じゃあ、ルーン文字の部分だけでも別の文字かなんかに置き換えたらどうなんです?
ほら、お隣の国で使うザンガ文字なんかぴったりかも」
ベスは指摘した。ラングがその瞳の奥で何を考えているのかを、女性ながらの直感で知っているのだ。魔法の師匠たるラングの意向を裏切り続けていたら、終いには弟子を解任されて魔法大学に戻されかねない。
「それは不可能」ぴしゃりとラングは言った。「ルーン文字を別の言葉で置き換えても、やはり魔法は働く。かなり歪んだ形でだが。ルーン文字そのものを使わなくても、元の関係性が残っている以上、魔法は容赦なく活動する。上を下だと言い張っても投げた石は落ちてくる。それと同じだ。さて、ルーン円盤においては、それをきわめて特殊なやり方で回避しているんだ。どういうやり方かわかるかね? ベス」
「ええと、わかりません。ラング先生」ベスはあっさりと降参する。
「パズルにしたんだ。全体を。ルーン円盤全体を、答えであるルーン文字で埋める代わりに、その答えを引き出すための質問で埋めたんだ。古代魔法を熟知している人物ならば、簡単にわかる形で。魔法の活動には、必然性はあっても知性はないから、パズルで作られた魔術式には反応しない。実に巧妙で有効なやり方だ。少なくとも古代の魔術師にとっては」
ラングは腕を組んだ。太い丸太が二つ、組み合わさっているような形だ。実際にはラングの体には、余分な脂肪は一切ついていない。ラングの体が大きいのは、太っているのではなく、骨格そのものが巨大なのだ。
「いまでは誰も知らない古代神聖文字で綴られた、失われた古代魔法の複雑なパズルだ。我々の歴史の中には、ルーン円盤の解読に成功した人物はいない。一人もだ。ところがファガスと来たらそれができる。実に曖昧な解釈だが、どういうわけかファガスにはそれが理解出来るんだ」
「俺は天才だからな。魔法に関しては、一部でも見れば全体は自ずからわかる」ファガスは小さな胸を精一杯大きく張ると断言した。
「あんたが天才?」少女がそれを聞いて笑い転げた。
「ファガス先生。本当にご自分のことをそう考えているのですか?」ベスが冷たく答えた。
「いや、ファガスは確かに天才なのだよ。でなければどうしてルーン円盤の一部と言えども解読できる?」ラングが助け船を出した。
酒壷のお代わりを持って来た執事のバイスターが、それを聞いて答えた。
「そうですとも、ファガス坊ちゃまは天才ですとも。このバイスターにはそれがわかります」
「何だかお尻がむずがゆくなって来た。前言は撤回する。俺は天才なんかじゃない。ルーン円盤? いったい何のことだい?」ファガスが嘯いた。
ラングはパイプから燃えカスを叩き落とすと、わざと大きなため息をついてみせた。
「本当にファガスがルーン円盤のことを忘れてくれたらなと、わたしは願うね。ルーン円盤がアリスタナル家の門外不出の品ということになっているのは、それが解読できないからではないんだ。古代の魔法は余りにも強力過ぎて、今の時代では影響が大きすぎるというのがその真の理由なのだ。記録があまりにも少ないので詳しくはわからないのだが、それでもあちらこちらに残された遺跡がその威力を物語っている。山脈を叩き潰し海を煮え立つ泥沼に変えてしまうような魔法は、ただの災厄でしかない」
「だからこそ、解読できればそれこそ快挙というものさ」
ファガスが身を前に乗り出すようにして力説した。その姿勢を鋭く指差してラングは言った。
「今みんなも聞いたように、ファガスに取ってのルーン円盤は猫に取っての魚に等しい。アリスタナル家はファガスに対してさえも、ルーン円盤の持ち出しを禁じているのだが、こいつはそれをまったく無視している」
「お陰で大奥様ときましたら、ファガス坊ちゃまが円盤を持ち出すたびに、ひどくお怒りになられております。今回もそれはそれはお怒りでして、このままでは血圧が上がり過ぎて大奥様が倒れてしまわれるのではないかと、わたくしめは心配しております」執事のバイスターが口を挟んだ。
「あんなくそ婆あなんぞ、倒れてしまえばいいのさ」ファガスが吐き捨てるように言った。
「坊ちゃま!」バイスターの叱責が飛んだ。
それを聞いて、ファガスは椅子に沈みこむ。
「すまん。言い過ぎた」
本音を言えば、ファガスは大祖母には感謝していた。
アリスタナル家の当主に成りたがっている親戚は幾らでもいる。そのために最高継承順位を持つファガス本人を追い落とそうと、罠を仕掛けてくるような輩もだ。貴族として被る善人の仮面など、世界の富を支配する一族の頭首となるためとあれば、喜んではずすものなのだ。味方の面をして後ろから刺すような手合いには、ファガスはうんざりとしていた。
暗殺。策謀。だまし討ち。誘拐。誹謗中傷。そんなことの連続だ。
だがファガスがアリスタナル家を離れたのは、権力闘争が嫌いだったからではない。やられた行為はすべて、やり返して来た。それがファガスだ。自分を睨みつける目には目つぶしを。噛みついてくる歯には堅いハンマーを。つねに倍以上の強さでやり返して来た。戦うこと自体には不満はない。
しかしいかに自分が努力して成果を出して来ても、そのすべてがアリスタナル家を前提としたものであるかのように言われることにはうんざりしたのだ。
ではどうするべきか?
アリスタナル家を離れて成功するのだ。自分の身分を隠して、本当の自分の力だけで大成功を納めてみるのだ。
実業家になるのでは意味はない。アリスタナル家と富の張り合いで正面から拮抗しても無駄だ。実業家としてどれだけ成功しようが、アリスタナル家を背景にのし上がったと言われるのがオチである。
ミッドガルド界を別の方向から支配する魔術師ギルド。三人の魔術支配者以外の何者にも屈しないこの魔術界で大成功を収めることこそ、自分の価値を示すことであると、そうファガスは信じていた。
そうなれば、あれがアリスタナル家の跡継ぎだ、血筋の幸運さだけであそこまで登った奴だとは誰も言うことはできないだろう。
ファガスの名を知るはずもない、僻地の魔法大学を選んだのはそのためだ。
二級魔術師ファガス。名門アリスタナル家に取っては、とんでもないスキャンダルだ。
しかしそれでもいまなお、ファガスがアリスタナル家から追放されないでいるのは、ひとえに大祖母のお陰であることは理解していた。
それにアリスタナル家の懐刀とも言える執事頭のバイスターを、わざわざ自分の所に送りこんだという事実も、いかに大祖母がファガスに期待しているのかの表われであった。
しかし、ひねくれた自分の性格では大祖母に対する感謝の気持ちを一言でも口に出すわけにはいかない。それを口にすれば、意地というものの支えが折れてしまう。
屈折してはいたが、それでも正しい動機に押されて、ファガスは真面目に自分の人生を歩んでいるのだ。それはいつでもとんでもない事件に発展してしまうのだが。
「だが、ラング。今度は絶対にいけると、俺は信じているんだ。凄いぞ、今度のルーン円盤の中身は」ファガスは強調した。
「凄いだって?」ラングはその大きな両側の眉毛の間に皺を寄せてみせた。
「ルーン円盤の魔法が凄くなかった試しがあるか?
思い出してみろ。魔術師として独立したときの最初の事件を。世界最大かつ最小の船を作ろうとして、出来上がったのがいったい何だったのかを」
「だが、実験は成功だった」ファガスは抗議した。
ラングはゆっくりと首を左右に振った。
「ああ、確かに大成功だった。もっとも大きく、同時にもっとも小さな船は、ルーン円盤の理論通りに動作した。そのついでに大損害を食らったバイキング運送はわたしたちの命を要求することに決め、おまけに危うく魔術師ギルドの資格まで剥奪されるところだった」
ラングのこの意見に、ファガスは鼻白んだ。
「それが俺の責任だと言うのか?」
「いや、お前だけの責任じゃない。わたしの責任でもある。だが、中途半端にルーン円盤を読むことがどれだけ大変な問題を引き起こすのか、わたしは学んだつもりだ」
二人の議論がただの口論に移りかけていることを察して、そこでベスが口を挟んだ。
「ラング先生」
「ああ、すまん。ベス。今のは昔の話だ。わたしとファガスがお師匠さまから独立した直後のな。今度きみにも話して上げよう。とにかく、その一件でわかったことは、ルーン円盤の理論が我々の知っている魔法理論を遥かに越える高度なものであることと、その効果が予測不可能であるということだ。
いいかね。わたしたちの使っている魔法が寒い夜に体を温めるための焚き火だとしたら、ルーン円盤に秘められている魔法は太陽そのものに匹敵する。一つ間違えれば炎の悪魔スルトのように、世界そのものを焼きつくしかねない」
「そんなことはない。この俺が以前の失敗から、何一つ学んでいないとでも思うのか」
ファガスは強調した。
「今度のは比較的におとなしい魔法だ。大量の物資も必要としないし、炎や氷が関係するわけでもない。ささやかな静かな魔法だよ。しかも理論は完璧に近いほどに理解している」
ラングの大きな手が上がると、自分の両耳を塞いだ。
「信じられない。いや、信じない」
ラングの動作をまったく無視してファガスは指を一つ鳴らした。
「とにかく説明しよう。バイスター。円盤を持って来てくれ」
「あたしも手伝います」ベスが立ち上がった。
「それには及びません。ベス様。円盤は驚くほど軽いのでございますよ」
一言残すとバイスターは家の中に消えた。
沈黙を嫌ってファガスが口を開いた。
「いや、驚いたね。いつものように実家の倉庫の中を漁っていたら」
「いつものように?」ラングが繰り返した。いつの間にか、耳を塞いでいた手は下ろしてしまっている。
慌てたように咳払いをしてから、ファガスは答えた。
「いや、あの。たまたま金庫の扉が開いていてね」
「アリスタナル家秘蔵の高価な品物を一杯に詰めた金庫が、たまたま開いていた?」ラングは指摘した。
「そうだ。たまたま開いていたんだ」ついにファガスは開き直った。
「そこに転がっていたルーン円盤を見て驚いたね。『黄金』と書かれていたんだ。黄金だよ、黄金」
「ほう」ラングは相槌を打った。そのまなざしは疑念に溢れている。
ベスはそんな二人をおかしそうな表情で見つめていた。いつでもこの二人は、こんなやり取りをやっているのだ。パットはいつの間にか、テーブルにもたれて眠ってしまっている。
「正直に言おう。ラング。俺は錬金術の魔法を見つけたんだ。古代小人族が使っていた黄金生成の秘法をだ。伝説の中での彼らが黄金の山を持っていたのも不思議はないな。彼らは知っていたんだ。黄金創造の秘密を」
「ファガス」ラングは大きなため息をついてみせた。
「魔術師ギルドが、所属している魔術師が行った詐欺行為について、どんな罰を加えるのか知っているのか?
神人族のトランス審判師を使った完全裁判だから、真実は確実に暴かれる。ごまかしようはない」
「これは嘘でもないし、詐欺でもない」ファガスは強調した。「とにかくルーン円盤を見てもらえばわかる」
「いいだろう。見てやろう」
そう答えてから、自分がすっかりとファガスのペースにはまっていることに、ラングは気がついた。
やがてバイスターが、大きな陶器の皿を思わせる円盤を一つ、両手に抱えるようにして持って来た。ごとりと重い音を立ててそれを野外テーブルの上に置く。
ベスがその音を聞きつけると、そっと円盤を引っ張ってみて、それから驚きと共に言った。
「凄い重さじゃない。バイスター。腰は大丈夫だった?」
「平気ですよ。ベス様。してみるとわたくしめも、まだそれほど歳は取っていないようでございますな」
二人のやり取りに気付く間もなく、ルーン円盤を覗きこんだラングが大声で怒鳴った。
「なんてことだ。赤だぞ。ファガス。この円盤は赤じゃないか。それも真っ赤な、燃えるような赤だ」
大気が震えた。滅多に見せたことのないラングの怒りの声を聞いて、バイスターとベスは茫然と立ち尽くした。
「そう怒鳴るな。確かに円盤は赤だ。だがそれは何かの間違いだ」
ファガスが必死に弁明した。小さな顔一杯に汗をかいている。
「ルーン円盤には間違いというものは在り得ない。大量の魔力と高度な魔法で作られたものに間違いを残すなどという、そんな杜撰なことをするはずがない。これは赤の円盤だ」
ラングが円盤の上側をその太い指で指差した。丁度そこの部分に小さな丸い窪みがあり、何かの魔法的な光りで内側から鮮烈な赤色に光っている。数千年の時を越えてもなお、その魔法が動作し続けていることの驚異を、その場にいたどれだけの人間が気づいたことか。
怒りで一際大きくなったかのようなラングの体から、すうっと力が抜けた。驚くべき自制の力でラングは自分の怒りを押し殺した。すぐに怒るのは蛮族の証拠、すぐに怒るのは蛮族の証拠と、口の中で二度ほどつぶやいてから、ラングは平静に戻った。
何が起こっているのかわからないまま立ちすくんでいる二人に向けて、ラングが自分の最前の怒りを恥じるかのように説明した。
「いいかね。ルーン円盤の文字自体はまだそれほど解読されていないが、円盤が役割に応じて色で区別されていたことは判明している。茶色は小人族の歴史を綴ったもの。これは彼らの生きる大地の色に絡めているのだろう。緑は治療用の薬剤に関したものだ。そして赤は」ここでちょっとばかり言葉を切ると、ふたたびラングは続けた。
「赤は武器を表わす。色が濃くなればなるほど、それは強力な魔法ということだ。以前、作った至高の軍船というやつは、移動用の乗り物を表わす黄色。だがそれもこれほどの輝きは持っていなかった。
誓ってもいいぞ。これは武器の知識を封じこめたルーン円盤だ。それも世界を滅ぼしかねないほどの威力を持ったやつだ。いや、ミッドガルド界だけじゃない。下手をすれば世界樹自体をも枯らすほどのものだろう」
「それが間違いだと言うんだ。この中のルーン方程式は、黄金を作り出す錬金術の魔法について記述されている。武器じゃない、絶対にだ」
ファガスはペロリと舌を出してみせた。
「実はもう作って見たんだ」
「どこに!?」ラングが目を剥いた。今にも自分の周囲が大音響とともに吹き飛ぶのではないかとの怯えを含んで。
「ここに」ファガスが手を突き出して見せた。その指に金の指輪が光る。
「拷問組合の注文品じゃなかったのか。まさかそれが」
「そう。お尋ねの武器とやらさ。もっともこいつは火も吹かんし、雷も産まない」
「どうなるんだ?」
ラングがおそるおそると聞いた。まるでその言葉に答えて、ファガスの指にはまった指輪が何か恐ろしいことを始めるとでも思っているかのように。
ファガスは自慢げに金の指輪を見せびらかすと言った。
「簡単だ。こいつの名前はドラウプニル。材質は純金。ただし、ちょっと面白い特性を持っている。1ムーン、つまり満月の晩になるごとに、こいつは七つの子供の指輪を産み落とす。自分とそっくり同じものをな。考えてみろ。全部純金だぞ。それが満月の晩ごとに七つ、手に入る」
「ニーチャムの経済魔法則に反しているぞ」ラングはうめき声を発した。
「錬金術は可能だ。だけど決して経済的には成り立たない。一単位の黄金を生み出すのには、最低でも三単位の黄金が買えるだけの材料が必要となる。そうでなければ、今頃、金の相場は大混乱だ」
「これは経済じゃないんだ」ファガスは答えた。「何かを変換するんじゃない。創造するんだ。無から有を生み出すのに経済は必要ない。指輪は子供を産むんだ。つまりこれは生物学の問題であって、経済学の問題じゃない。どうだい、俺の考えは。逃れようのない法則に対する実に見事な解答だろ?」
「本当にそれだけなのか? 子供の指輪を産むだけなのか?」
ラングが疑い覚めやらぬ口調で問い詰めた。ファガスの指に光る金色の指輪は実に無害そのものに見える。だが一般人の護身用に出まわっている炎の指輪だって、同じように無害に見える。それが実際に炎を吐き出すまではの話だが。
「俺を信じろ。この指輪の機能は、満月の晩に子供を七つ産むこと。それだけだ」ファガスが断言した。
「何だか、罠にはまったような気分だ」
ラングは巨体を揺らしながら、小さくうめいた。