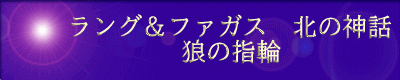
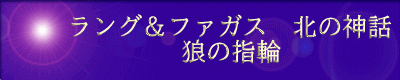
「ああ、ひさしぶりの背伸びだ」
ラングはその言葉通りに大きく伸びをした。大きく作られた建物だ。ラングが背伸びをしても、頭が天井にぶつかる恐れはない。無理な姿勢に押しこまれていた背骨がボキボキと派手な音を立てた。もし停滞の魔法がかかっていなかったら、三日のソファー座りは拷問に等しかっただろう。
「おいおい、ラング。まだ助かったと決まったわけじゃないぞ」ファガスは指摘した。
「こんな話になるとはな。お偉方が縄張り意識で争ってくれてよかったよ」ラングはため息をついた。
「ところがそうじゃないんだ」声がした。
その人物は開いた扉から半身を乗り出して、扉を内側からノックしてみせた。白いものが混ざった髪が印象深い。短く刈られた灰色の顎鬚の中で、口がにやりと笑いの形に歪む。
「エストリッジ教授!」ラングとファガスは同時に叫んだ。
教授は扉を閉めると、踊るような足取りで、二人のところに進んで来た。
「例の魔法消失事件のお陰で、発掘が進んでね。魔法兵も動かなければ、呪いの発動もなし。いや、遺跡発掘があれほど簡単なものだとは初めて知ったね」
エストリッジ教授は椅子を引き寄せると、二人の前に座りこんだ。
「わたしがきみたちの弁護人だ。というより、バイスターから報せを聞いてね。わたしの方がアージャン師に頼みこんだんだ。処刑の前に、ここに間に合ってよかったよ。
おっと、知っていたかな?
わたしがアージャン師の直弟子だったってことを。まあ、あの人の弟子は他にもたくさんいるがね」
「なんとお礼を言ったらよいか」ラングは恐縮した。
「いや、いや、礼を言うのはまだ早い。まだ何も解決はしていないのだから」
何が楽しいのか、浮き浮きとエストリッジ教授は言った。手にした書類をすばやくめくる。ざっと目を通してから、嫌な顔をしてみせた。
「うえっ。何てひどい報告書だ。伝聞に、噂に、未確認の事実。誤認に、誤字におまけに脱字だ。事実関係の認定も、事件の再構築もいい加減だし。これがもしわたしのゼミの生徒なら、ためらわずに落第点を上げるところだ」
「それでもわたしたちを死刑にするには十分です」ラングが静かに言った。
「そうだろうな」エストリッジ教授はあっさりと肯定した。
「だが、トランス審判師が呼ばれたのは救いだった。おまけに専門の質問師がいないというおまけつきだ。これならなんとかなるかもしれない」
エストリッジ教授は懐からペンを取り出した。
「さて、いったい何があったのか、いったい何をやらかしたのか、全部、包み隠さず、詳しく教えてもらおうか」
「しかし、教授。ここは盗聴されています。透視も」ラングが小さな声で指摘した。
「もちろん、そうだとも。このテーブルにも仕掛けがあるし、そっちの壁もだ。ついでに言うならば、きみの背中にもちょいとした魔法がくっついている。壁の向こうで透視している魔術師は数えないとしてもだ。だが、大丈夫だ。これがある」
エストリッジ教授は、小さな金属球をポケットから出してみせた。
鏡のように磨かれた完全球だ。その表面をさまざまな色彩が駆け抜ける。
「魔法遺跡からの発掘品だ。盗聴も透視も、この球の近くでは働かない。というより、そういったもののすべてを、これが惹きこんでしまうのだ。結果として、外から覗きこんでいる当事者たちは空っぽの鏡の中を覗いていることになる。自分ではそうと気づかずに。そこから得られる情報は完全に零。見事な仕掛けだろう」
ファガスの視線が完全球に釘付けになっているのを見て、エストリッジ教授は手を伸ばすと、ファガスの目を覆った。正気に戻ったファガスが顔を上げると言った。
「わお。すごい仕掛けだ。教授。わかりました。こいつの中身がどうなっているのかを」
エストリッジ教授はにやりとした。
「説明してご覧。ファガス。その中身というやつを」
口を開きかけたファガスは、言葉を切ると、額に皺を寄せて考えこんだ。
「あれ?」
「駄目だ。駄目だ。ファガス。この球の中身を想像しては。いまこの球はきみの意識を呑みこんで、きみの思考をどうどう巡りさせていたんだぞ。この球の中にきみの意識を惹きこんで、素晴らしい発見をしたように思いこませていたんだ。だがこの完全球から、結果として得られる情報は完全にゼロ。白昼夢を見るより、もっとたちが悪いんだ」
エストリッジ教授は説明した。
「それと最初に言っておくが、こいつを研究するなんて言い出すなよ。分解も駄目。複製も駄目だ。滅多にない発掘品なんだから」
「エストリッジ教授」ラングが言った。「発掘品を持ち歩いていいんですか?」
「そりゃ駄目さ。そんなこと、遺跡発掘の研究者としては許されることではない」
エストリッジ教授は明確な口調で断言した。
「これはたまたまだ。この球の研究中に、きみたちの話が飛びこんで来てね。うっかりポケットに入れてきてしまったらしい。いや、わたしとしたことがとんだドジを踏んだものだ」
悪戯っぽく笑うと、エストリッジ教授はペンを取り上げた。
「さて、どこまで聞いたかな?」