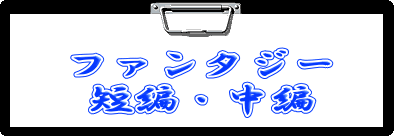
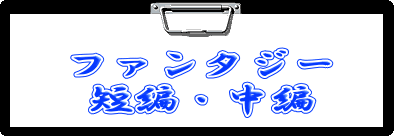
アイルランドの古い民話の一つに、自堕落で放蕩者のタイグ・オ・カハーンという名前の男が、深夜の道で異形の者たち、つまり妖精に出会うというものがある。
妖精たちは彼に人間の死体を背負わせ、夜が開けるまでにそれを埋めて来いと命令する。こうして恐怖の一夜を過ごしたタイグ・オ・カハーンは、それ以降、自分の行いを改めて、まっとうな人間に生まれ変わるという筋書きである。
一般に伝えられている話はここまでである。だが、人々が集まる酒場の片隅でも、あるいは家族の集う炉端の明かりの中でも、決して語られなかった幾つかの事柄が存在することを知る者は少ない。
語られなかったことの一つは、妖精たちがこのゲームを仕掛けたのは、タイグ・オ・カハーンが最初でもないし、最後でもないということである。
そしてもう一つは、妖精たちが出会った人間のなかの一人に、アイルランドでもっとも変人だとその名も高い、ケイン・コナガンが含まれていたことである。
その夜、酒場を千鳥足で出たケインは、空にかかった半月の照らす道を、灯りもなしに歩いていた。したたかに飲んで酔いがまわった頭はご機嫌であったが、たっぷりとお代を払わされた懐具合はやや不機嫌という状態で、それでも家に向けての歩みを進めていた。
そんな様子であったから、道の向こうから何か怪しげな者たちがやってくることに気づいたときは手遅れであった。
それは背の低い異形の者たちであった。姿形こそ人間に似てはいたが、見れば見るほどそれらが人ではないことが判った。多くは白髪を生やしており、そして共通する特徴としてどれもひどく醜かった。
自分が妖精と呼ばれる存在に出会ったことを、ようやくケインは酔った頭の片隅で理解した。ケインがそれに気づくと同時に、向こうもケインに気がついた。
どちらも自然に歩みを止めた。
睨み合いの中、ケインの腰の辺りまでしか背のない妖精たちの中から一人が進み出て言った。
「ほー、ほー、ほー。こりゃ驚いた。ここにいるのはケイン・マクドウガルじゃないか。何という偶然。わしらはお前に用があったのじゃよ」
背筋を貫く恐怖の中でケインが痺れたようになっていると、また別の妖精が前に進みでて言った。
「ケイン・マクマホーン。どうしたい? 猫に舌でも取られたか?」
それに続いて、妖精たちの群れのなかから声が飛んだ。
「間違えんじゃないぞ。名前はケイン・コナーだ。そうだ。そいつだ」
最初に進み出た、妖精の長と思われる人物が肩をすくめて答えた。
「名前などどうでもよい。どうも人間の名前は難しくていかん。言葉にするのも難しければ、それを聞いてもちっとも本人の姿と結びつかん。さて、ケイン・バルハラ。もうわかっておるとは思うが、わしらはお前さんを探しておった。お前さんを妖精のゲームに招くためじゃ」
一呼吸の間をおいて、妖精の長は続けた。
「すぐに始めたほうがよいと思うがな。ゲームは長くかかるものじゃし、ぐずぐずしていれば夜明けなどあっという間じゃ。時間がくれば、お前さんは負けとなる」
「こりゃまた、グッドピープル。それは何かの間違いじゃないか」
ようやく驚きが去ると、ケインは言った。妖精相手に抗議するのは危険な行為だったが、酔いがそれを手伝っていた。
「おれは妖精のゲームに参加しないといけないほど悪いことはしていないぜ」
「誰しもそう言っては、口先だけで妖精のゲームから逃れようとする」妖精の長は頷きながら言った。「それが無駄ということを全然理解しておらん」
「では尋ねよう。公明正大にして、敬虔なるこのおれ、ケイン・コナガンがいったい神に疎まれるような何をしたというのか。教えて欲しいものだな。大地の人よ」
妖精の長は、ケインの全身を上から下までじろりと眺めつけると、揶揄するような口調で言った。
「神聖なる御方の名を口にする資格がお前さんにあるのかどうか、わしは知らん。だが、お前さんの名前が妖精の書にしっかりと載ったのは確かだ。ケイン、とな。それにわしの見るところ」
ここまで言ってから、わざとらしく妖精の長は、その大きくて尖った鼻をひくつかせた。
「この酒の匂いからすれば、お前さんが自分で言うほどには、真面目な生活をしていないことは明らかじゃな」
いいじゃないか。たまの酒ぐらい。ぶつぶつとそうつぶやく声は、ケインの喉の奥深くで立ち消えた。
ケインのそんな様子を満足気にみながら、妖精の長は続けた。
「さて、ケイン。お前はわしらの三度の呼び掛けにすぐに返事をしなかったから、わしらはお前さんをどうにでもできるわけだ。皆の衆、あれを持って来い」
待ってましたとばかりに、妖精たちの群れが二つに割れ、中から人間の死体が一つ、引きずり出されてきた。
半月の淡い明かりのなかでも、その腐敗した死体のひどい有り様がよく見て取れた。
「これは、というか、こいつは、夜明けまでにお前さんが埋めなくてはならん死体じゃ。埋める場所はどこでもよいというわけではない。まず最初はティムポール・ディムスの教会に埋めるのだ。ただし、教会の床の上にほうり出しておけばそれでいいってわけじゃない。きちんと敷石を開いて穴を掘り、埋めたら元の通りにしておかねばならん。夜明けまで教会が無人であることは保証するが、朝になって気づかれて、死体が掘り起こされることだけは避けねばならん。わかったな?」
「わかるもの何も。おれはまだやるなんて一言も言っちゃいないぜ」ケインは抗議した。
「往生際が悪いぞ。ケイン。さて、話にはまだ続きがある。ティムポール・ディムスの教会が他の死体で一杯ならば、そこに埋めることは許されぬ。その場合は、キャリック・ファド・ビク・オーラスに埋めるのだ。そこでも駄目ならば、ティムポール・ロウナンに持って行くしかない、しかしまあ、あそこも最近は繁盛しておるから、場合によってはイムロウグ・ファダに行かねばならぬかも知れん。もしそこでも駄目ならキム・ブリーディアへ行くのだ。あそこなら間違っても埋められないということはない。
さあ、いま並べ立てた教会のどこで、この死体を埋めることができるのかは言うわけにはいかん。しかし、そのどれかに死体を埋めることができることは保証する。
夜明けまでに死体を埋めることができれば、このゲームはお前さんの勝ちじゃ。埋める前に夜が明ければ、わしらの勝ちとなる」
「おれが勝てば何をくれる?」ようやく、ケインは口をはさむことができた。
「お前さんが勝てば、わしら妖精の好意を得ることができる」
「それが大したものとは思えんな」思わずケインは言ってしまった。
「口に気をつけろ。ケイン」ぴしりと妖精の長はたしなめた。
「なんならここで即座にそちらの負けとしてもよいのだぞ。お前さんが負けた場合には、わしらはお前さんを妖精の国に連れてゆくことにする」
「そこは住みよい所なのかな?」
普通人なら口にはせぬ質問だが、アイルランド一の変人であるケインに、そんな常識が通用するはずもなかった。
「一説によると、キリスト教で唱えるところの地獄が、わしらの国に当たるとも言うな。実にもって聞こえの悪い話じゃ」
しみじみと妖精の長は答えた。
「ぶるるる。そいつはいただけないな」
ケインは震えてみせた。妖精たちを初めて見たときの恐怖は、すでにケインの体から立ち去ってしまっていた。
「では、妖精のゲームを開始しよう。みなの衆、その死体をケインに担がせろ」
妖精の長は命じた。
「待った。それには及ばない」ケインが叫んだ。
「自分で担ぐというのか。それはよい心がけだ」
妖精の長が感心したように言った。
「違う。おれはそのゲームとやらに参加する気はないということだ。森の人々よ」
ケインは指を振り立てながら言った。
「拒絶する。いやだ。駄目だ。認めない」
「では力づくで担がせるまでだ」
妖精の長はそう言うと、背後で待ち構えていた妖精たちに合図した。わっと妖精たちは歓声を挙げながらケインに飛びかかった。
妖精たちの幾人かが殴り倒され、代わりにケインの顔に、妖精たちの爪による引っ掻き傷が無数についた。
「なんと! 信じられん。妖精と喧嘩する人間なぞ、初めてみたぞ。やめろ。みな、止めんか」
妖精の長が叫ぶと、妖精たちはみな背後に引いた。痛みのうめき声がして、怪我をした妖精の幾人かが、さらなる暗闇を提供している森の中へと逃げこんだ。
妖精たちの形作る輪の中に、背中に死体を縛り付けられたケインが、乱れ髪のまま荒い息をしながら立っていた。
「お前さんは、妖精の呪いが恐くはないのか? わしらに手出しをするなんて」
妖精の長が嘆きながら言った。
「呪いは恐いさ。妖精を恐れぬ人間なんているものか」
息を整えながら、ケインは言った。次の戦いにそなえて握り拳を両側に構えている。
「だがそれとこれとは話が別だ。おれはゲームに参加しないと言っている。死体を担がせたからって、おれを無理にゲームに参加させるわけにはいかないぞ」
「では自動的にお前を負けとして、妖精郷へと引きずりこんでもよいのだぞ。あるいはお前に妖精の呪いをかけて、一生不運が続くようにしてもよいのだぞ」
「そんな行為を何というのか。そう、脅しだ。今度は逆におれのほうから質問させていただこう。世界で一番、頑固で強情で誇り高い民族は何か?」
「バスク人だ!」
妖精たちの中の一人がそう叫んだが、たちまち他の妖精たちの手により、暗闇のなかに引きずりこまれた。
「アイルランド人だ」しぶしぶと妖精の長が答えた。
「その通り。この体に流れるアイルランドの血の誇りにかけても、おれは脅しには屈しないぞ」
「よかろう。お前が脅しに屈しないのはお前の自由だ。だが、それならば、お前をどうするかはわしの自由だ」
怒りに燃える声で妖精の長が宣言すると、その体が膨らんだ。いまやその背丈はケインを大きく越え、のしかからんばかりに成長していた。闇がその背後で渦を巻き、妖精の持つ脅威を強調している。
「お前を妖精郷のなかでも、もっとも深い闇のなかに閉じこめてやろう。最後の審判の日が来るまでそこにいるようにしてやろう」
「では、おれは!」ケインが怒鳴った。
「その最後の審判の日に神様の前に出て、お前たちが不当にもおれを閉じこめたと訴えてやろう。人生これからというときに、生きるすべての輝きを奪われ、聖なる信仰に目覚める余裕さえ与えられることなく、妖精たちに拉致されたのだと、声を大きくして言ってやろう。いかにグッドピープルと呼ばれていようと、その魂が神の王国の門をくぐることがないように、おれは証言してやろう」
「なんてことを言うのだ! こいつは」
ケインの言葉を聞いて、妖精たちが悲鳴をあげた。
「ただでさえ神の心証が悪いこのおれたちを。そんなことをされたら、審判の後の再生も復活も有り得ないじゃないか」
「長よ! われらの長よ! この男を永遠に闇に閉じこめてしまえ! 最後の審判が終わった後も、ケインの魂は捕われ続けるのだ」
口々に妖精たちは喚きたてた。
売り言葉に買い言葉とはいえ、おのれが言った事の反響の大きさに、ケインは身震いを覚えた。
「まて。黙れ。黙らんか! 皆の衆」妖精の長があわてて命令した。
「滅多なことを言うでないぞ。そんなことをしたら、審判の日に魂の数が一つ足らぬことを、神が見つけだすのは間違いがない。そうなれば草の根どころか、世界のあらゆる片隅が探されて、結局は見つけ出されることになるのがわからんのか!」
その言葉を聞いて、今まで一斉に喋っていた妖精たちは、今度は一斉に黙りこんだ。
「うう、ぶるるる」妖精の長は口を震わせた。「ケイン。お前さんはなんて厄介な男なのじゃ」
「そりゃまた、どうも。誉め言葉と取っておくよ。じいさん」
ケインはさらりと言ってのけた。その実、内心ではひどく脅えていたのだが。
「お前さんは大変な問題をわしらに押しつけたのだぞ。妖精の書に名前が載った以上は、お前さんはわしらとゲームをせねばならぬ。それは確実なことだ」
「だれがそいつを決めたんだ? あんたかい? それとも、妖精の王と呼ばれる御方かい?」
「それよりもっと上におられる御方じゃよ。お前さんは、女とみれば見境なしに手を出すし、酒は毎日あびるように飲む。おまけに仕事は一切せずに、ただ一族の財産が転がりこんで来るのを、いまかいまかと待っているだけの暮らし。こうとなれば、だれがそれを罰しないでおかれようか。だからこれから、お前さんは妖精のゲームに巻きこまれて、その腐った性根を入れ替えざるを得ないようなひどい目にあうのじゃ」
「ひどい言われようだな。おれはそこまで言われるような、悪いことはしてないぞ」
「妖精の書は間違いをおかさぬ」ケインの抗議に、ぴしりと妖精の長は言った。
「だがそれでも、そのゲームとやらに、おれを無理矢理巻きこむことはできない」
「おお、何と頑固なことなのか」ついに妖精の長は嘆息した。「ではこうしよう。ケイン。妖精の好意などとあいまいなことはもう言わん。お前さんがこのゲームに勝てば、その両手に抱えきれないほどの金貨を提供しようではないか」
「そりゃまた、有り難いことで」ケインは疑いの目で妖精の長をながめた。「で、おれが負ければどうなる?」
「その場合は、妖精の丘の中で、長い下働きを努めてもらう」
「長いっていったいどのぐらい?」罠の匂いをかぎつけてケインは尋ねた。
「そうだな」しぶしぶと妖精の長は答えた。このような問答で嘘をつくことは許されていない。嘘をつけばそれだけで、契約は無効となる。
「ざっとみて、二、三百年ぐらいかな」
「その条件じゃ駄目だ。一山の金貨と三百年の労働じゃ釣り合わない」
ケインは断った。
「むう」妖精の長はうめいた。
「ではお前さんに賭けの賞品を決めさせてやろう。勝ったときに、なにが欲しいか言ってみるがいい」
「別に欲しいものはないなあ」ケインは答えた。右手の小指を使って、ぼりぼりと耳の穴を掻いた。
「もう行かせて貰っていいかな? 明日の朝は早いものでね」
「冷たいぞ! ケイン。同郷の徒であるこの死体を、埋めることもしてやらないとは」
妖精たちの中から声が上がった。たちまちにして、野次がとんだ。
「こうなればおいらたちは歌にして広めるぞ。いかにケインが仲間を見捨てたかを」
「アイルランド人のケインは、友達の苦難を見て見ぬふりをするってな」
「氷の心を持つケイン。助けを求めるアイルランド人を突き放す」
これにはさしものケインも顔を真っ赤にして怒った。
「なんだって! 聞き捨てならんな。このおれが冷たいだって? このおれは、アイルランド中で一番、心が温かいので有名なんだ!」
ケインは死体を指差した。
「いいだろう。そいつを埋めて来てやる。賞品なんかいらないぞ。あくまでもこいつは、アイルランド魂から出た、男気ってやつだ」
「一体全体、どういうことだこれは」妖精の長が途方に暮れた表情で言った。「脅してもすかしても、何としてもゲームへの参加をこばんだくせに、冷たいやつだと言われたくないばかりに、その場で命賭けのゲームを引き受ける。そなた、本当にケインか? わしが聞いた話とだいぶ違うぞ」
「おれは確かにケインだよ」
自ら死体の手を引くと、やっとばかりに背中に担ぎあげながらケインは答えた。
「さあ、じいさん。妖精の長よ。ゲームとやらを始める気があるのか、ないのか? どっちにしろ、おれはこの死体をきちんと葬ってやるよ。同じアイルランド人だからな」
突然襲いかかってきた目眩いを抑えようとするかのように自分の頭に手をやると、妖精の長は言った。
「ああ、わしの最初の目論見とはずいぶんと違うが、始めよう」
「で、どこの教会に埋めるんだって? 悪いな。もう一度教えてくれんかね」ケインは尋ねた。
「ティムポール・ディムスだ。最初は」疲れた声で、妖精の長は答えた。
「ええとそれからキャリック・ファド・ビク・オーラスにイムロウグ・ファダ、最後にキム・ブリーディアだ」
「はて、変だな。一つ足りないような気がするが」ケインは首をかしげた。それにつれてケインの背中の上に乗せられたままの死体の頭もかしいだ。
「ティムポール・ロウナンが抜けているぜ。お頭!」妖精たちの一人が叫んだ。
「ああ、そうだ。その通りだ」妖精の長も叫び返した。
「ティムポール・ロウナンにキャリック・ファド・ビク・オーラス。キム・ブリーディアにイムロウグ・ファダ。それと、ああ、ティムポール・ディムス。これで五つだな?」
妖精の長は周囲に確認すると、ケインに言った。
「よし、さあ、始めてくれ。夜明けまでに、いま言ったどこかに死体を埋めるのだ」
「いいだろう。確かにそのゲームに乗った」ケインは応じた。
ケインが驚いたことに、背中に担いだままの死体の腕が動き、ケインの首にしっかりと絡みついた。
「さあ、ゲームの開始だぞ。ケイン。夜明けに間に合おうと思えば、急がねばならんぞ」
死体がかすれた声で言った。それとともに周囲で騒音をたてていた妖精たちが、一斉に消えた。妖精の長もだ。
静けさが、邪悪な期待とともに、夜のしじまの中へと戻ってきた。
「どうした? ケイン」死体がもう一度口を開いた。
「何でもないさ」恐怖は敢えて無視して、ケインは答えた。「死体が喋るのを聞いたのは初めてなんでな、ちょっとばかり戸惑っただけだ」
「そりゃ、普通は死体は無口なものさ。喋るってのは、死人にとって結構な重荷なんだぜ。生きている人間ならば、息をするついでに喋ればいいが、死人ではそうはいかんからな」
「そんなものかね。さて、どこに行くことになっているのだったかな?」
ケインは尋ねた。内心では、この死体が行き先を覚えていないとまずいことになるのではないかと思っていた。なにぶん、ケインはしこたま酒を飲んだ後なので、記憶に自信が無かったのである。ケインがほっとしたことに、死体はすんなりと行き先を告げた。
「最初はティムポール・ディムスの教会だ」
ティムポール・ディムスの教会は、道を東に向けて少し進んだ所にある。ケインは元々から頑健な男だったので、背中の死体の重さも苦にせずに、道を元気よく歩き始めた。
まだ足下が酒でふらついていたために、時間はいつもの倍かかったのだが。
半月のもたらす明かりというものは、役に立ちそうで、その実まったく役には立たない。その上に暗い森の中に切り開かれた小道では、夜の道行きはいっそう厳しくなる。
ケインにとって、それよりも参ったのは背中の上の死体の気持ちの悪さである。同じ人間の体でも、生きているときと死んだときとでは、これほどまでに感触に違いがあるものかと、ケインは不思議に思った。
「ティムポール・ディムスか。そこは死んじまったあとの人間には、住みよい場所なのかい?」
気まずい沈黙を何とかしようと、ケインは尋ねてみた。返事は期待していなかったが、死体はすぐに答えた。
「住みよい場所だとも。そうでなければどうして、わざわざ妖精たちに頼んで埋めてもらおうとするものか」
「どうして妖精になんか頼んだのだ? 親族が遺言通りにしてくれなかったというわけか?」
「天涯孤独の身の上でね。病気で死んでしまったら、たったいままで仲間と思っていた野郎どもが、埋葬どころか、死人の身ぐるみはいで川へどぼんよ。このまま川の底で骨になるのかと覚悟していたところを、妖精たちに拾われてな。以前にちょいと、妖精たちの頼みを聞いてやったことがあったから、そのお返しをしてもらえることになったのさ」
「へえ、そりゃまた奇妙な話だな」
死人と話をしているという奇妙さには気づかずにケインはぼんやりと答えた。
「おれが勝てば、あんたは見事にお望みの墓地に埋めてもらえるってことか」
「そういうことだ」言葉少なめに死体は答えた。
なにかが変だ、とケインの頭の中で声がした。暗い道行きを急ぎながら、ケインはそのことを考え、そして違和感の正体に気がついた。
その考えを言葉にしてみた。
「妖精たちはあんたみたいな死体をいくつも抱えているのかな? こういうゲームを楽しんでいるところを見ると」
「まあそうだな」死体はあいまいな口調で答えた。
「そりゃそうだな。死体が一つこっきりじゃ、人間側が勝ってしまえば、それで終わりだ。ゲームの駒が無くなってしまうからな。そうそう都合よく、妖精たちが手出しできるような死体がそこらに転がっているとは思えないし。ほら、普通は死ぬときに臨終の秘儀を受けるじゃないか。そうなったら聖別されたことになるから妖精たちは手が出せないんだろ?」
ケインの背中の上の死体は黙っていた。
「それじゃもうちょい教えてくれるかな?
あんたの仲間、ええとつまり死体の仲間ってことだが、そいつは十体より多いのかな?」
またもや死体は何も答えなかったので、ケインは再び尋ねてみた。
「五体か?」
恐ろしい予感に貫かれて、ケインは叫んだ。
「まさか三体というんじゃないだろうな!」
これにも答えがないものとケインは予期した。そうであれば、単に死体はお喋りに飽きただけなのだと、自分を納得させることができる。
だが、ケインのそんな期待を裏切るかのように、死体ははっきりした声で答えた。
「一体だけだ。つまりはオレだけだ」
「一体だけだって。じゃあ一度でも妖精側がゲームに負けたら、もうゲームは続けられないじゃないか。ということはもしや、このゲームは人間側の負けに必ず終わるってことか?」
もし死体に呼吸ができたならばここでため息をつくところだった。
「まったく変なところに気づく奴だな。その通りだ。人間側が勝つことは滅多にない」
「で、負ければどうなる?」尋ねたくない質問だったが、尋ねねばならなかった。
「そりゃ当然、約束通りに妖精の国に連れて行かれる」
「そういえばあの妖精のじいさんは三百年の労働とか言っていたな。そこは実は住みよい場所という可能性はないのか?」期待薄だなと思いながらケインは尋ねた。
「馬鹿を言え、そんなに住みやすい場所ならば、とうの昔に皆が移住しているさ。妖精の国は死者の国。いわば煉獄という表現が一番近いのかもな」
「気楽に言ってくれるな」ケインはうめいた。
ようやく、自分がどんな罠の口にはまったのか理解できたのである。このゲームに人間側の勝ち目はない。おまけに一度始まったゲームは途中で止めることはできない。
「まあ、他人事だからね」そっけない口調で死体はつぶやいた。
「くそ! お前のような奴はそこらの沼にでも放りこんでやる」
ケインはそう喚くと、背中の死体を振り払おうとした。すると死体の手が万力のような力をこめてケインの首に巻きついた。死体の両足はケインの腰骨をがっちりとはさみ、ぎゅうぎゅうと絞り上げた。
「無駄なことはやめな。おれはいま、半分は妖精の魔力に浸されている。つまりはただの死体じゃないってことだ。おれを埋めるべきところに行き着くまでは、決して離れはしないぞ」
その言葉を聞いて、ケインは諦めた。すでに妖精のゲームにどっぷりとはまっているのだ。彼らのルールには従うしかないのだ。状況がどれだけ不利でも、そのルールの中で最善を目指すしかない。
ケインが静かになったのを知って、死体は力をゆるめると満足そうに言った。
「よおし、よし。ようやく本気でゲームをやる気になったようだな。まあ、安心しな。少なくともおれだけは、お前さんの味方だ。妖精の持ち物であることには変わりないが、それでも地面の下でゆっくりと眠りたいというのは、おれの本心だからな。確かにこのゲームは妖精側に有利にできてはいるが、それでもまったく勝てないってわけじゃない。それに変な仕掛けがあるわけでもない。賭けの対象にするには、イカサマサイコロは向かないからな」
「賭けだあ? あいつらはこれを賭けの種にしているのか?」
「当たり前だろ。賭けをするから勝負は一段と面白くなる」
「神よ!」ケインは叫んだ。
「神は今夜は休みだ」死体がきっぱりと言った。