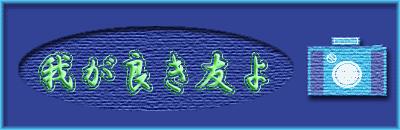
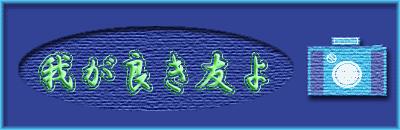
精神学科の浜口教授のフィールドワークに俺と鬼口は引っ張り出された。
内容は心霊スポット巡りをして俺と鬼口の反応を見るというものだ。正直こんな課題はたまったものではないが、精神学科のゼミの単位を人質に取られたら否も応もない。
せめてもの抵抗に、現場に行く車の運転手には山岸を推薦しておいた。山岸は仲間内でも零感で有名な男だ。色々な心霊スポットに一人で行くという剛の者で、今まで一度も怖い思いをしたことがないというのが自慢の男だ。
「はっはっは」
浜口教授は豪快に笑った。教授の印象は某フライドチキンの店頭に立つ例の人形に似ている。
「そんなにびくつくことはないぞ。中山君。人間はな二つの横並びの点と下に一つの点を見ると顔と認識する。これはシミュラクラ現象と呼ぶ。幽霊と言われるものは大概がこれだ」
「そんなものですかね」
「そうだとも。怪奇現象などこの世にない。すべて科学で説明できる。例えばこれを見たまえ」
教授は手にした紙を見せてきた。揺れる車の中で書類の類は見たくないが俺は見た。そして後悔した。それは写真だった。広い屋敷の中に椅子が一つ。人が一人その椅子に座っている。周囲に無数の顔が浮かんでいる。
「これはね、一枚の写真を顔認識AIを通して見て、人の顔と認識したものを再度焼き付けたものだ。この絵の中で実際の人間は椅子に座った者のみ。後はAIがシミュラクラ現象を起こして勝手に顔を描き加えたものだ」
「でも、でも、教授」俺は抗議した。
「なんだね?」
「もしかしたらAIの方が正しくて、実際はそこにはたくさんの顔が浮かんでいて、我々人間の方がそれが見えていないという可能性は?」
「はっはっは。中山君は実に想像力が豊かだね」
そこで車が急停止した。
「おい、山岸。車を止めてどうした」
「あそこ」
山岸は指さした。周囲は暗い木立に囲まれた夜道だ。郊外なので人家の明かり一つない。それなのに車のヘッドライトの光の中に女性が一人浮かび上がっている。
山岸が運転席の窓を開けて怒鳴った。
「おい、あんた。こんな夜中にどうした。事件か? 警察呼ぼうか?」
女がすうっと近づいてきた。若い女だ。年のころは二十歳ぐらいか。長い黒髪。それに白いワンピース。確かにこんな寂しい道に一人で居てよい人間ではない。
「彼氏にこんなところで放り出されちゃって。どこか電話できるところまで乗せてくれませんか」
これに答えたのは浜口教授だ。
「これからちょっと用事があってね。それが終わるまで車の中で待っていてくれるなら、どうぞ」
女が乗り込んできた。そして一緒に吉村が乗り込んできた。
「出た!」鬼口が叫んだ。
「幽霊か?」と期待に満ちた声で山岸。
「吉村、どうしてここに」
「ひどいなあ。ボクを置いていくなんて。ボク、ずうっと君の後をつけてきたんだよ」
「待て!」
俺は奴の言葉を遮ると状況を整理した。
「山岸。ここに来るまで車かバイクがつけてきていたか?」
「いんにゃ。なんにも」と山岸。
「吉村。お前どうやってここまで」
「この車の後ろに張り付いて」
普通の人間がそんなことができるか。この変態が。俺は怒鳴ろうとした。
「はっはっは。いいじゃないか。犠牲・・いや、被験者は多いほどありがたい。吉村君、実験を手伝ってもらうよ」
教授の一言には逆らえない。俺たちはドライブを続けた。
「さて、最初の実験場所だが」
浜口教授は資料を広げた。運転中の山岸を除いて皆が資料を覗き込む。
「有名な心霊スポットの廃屋だ。ここは結構曰くがあってね。まずは一家惨殺」
浜口教授は写真を何枚か広げた。
「ご覧の通りに血の海だ。犯人は一家の主人で、奥さんと子供三人それと祖父祖母が犠牲となっている」
うえええ。写真など見なければよかった。俺は心底後悔した。無残な死体の写真まである。
「生首だ。生首だ」鬼口がつぶやいた。
「美味しそうだね~」吉村がボケた。鬼口がすかさずその頭を殴りつけた。
浜口教授は欠片も揺るがない。
「事件の後に調査が進んだところ、この家に以前に住んでいた四つの家族がいずれも行方不明や自殺で全滅していることがわかった」
ぐう。言葉が詰まった。浜口教授。よりにもよって何てえ場所を選ぶのだこの人は。
「今回の実験の目的は一つ。この場所に入り、決まった時間を過ごすこと。その間に君たちの心拍と呼吸数の計測を続ける。後でそのときの心理についてレポートを出してもらうから何らかのメモを採っておくことをお勧めする」
「あの、浜口せんせい」鬼口がおずおずと言った。
「なんだね?」
「せんせいはどうするんで?」
「私も被験者だよ。もちろん君たちと行くさ」
俺と鬼口はほっと胸を撫でおろした。浜口教授なら廃屋の中に一人で行けと言い出しかねない。
「山岸君は車に乗ったまま待機してくれ。吉村君は一緒に来てくれ」
いつもなら吉村を山岸に押し付けるのは歓迎だが、今回だけは俺は抗議しなかった。怖い場所に行くなら人数は一人でも多い方がよい。
しばらく闇の中を走った末に、車のライトの光の中に崩れかけた一戸建てが見えてきた。目的の廃屋だ。
「んじゃ、俺、ここで待機ね」
車を止めると山岸が言った。教授たちと廃屋の中に入るのと、ここで一人で車の中で待つのと、どっちがいいのだろうかと俺は思った。
浜口教授が降り、吉村が続き、鬼口と俺が渋々という感じで車の外に出る。山岸が運転席の背もたれに体を沈め、目を瞑る。
浜口教授が持ってきた機材を廃屋突入組の腕に巻き付ける。心拍と血圧、そして呼吸数を測ることのできる優れものだ。
よし、行くぞ、という所で何か変だと気づいた。
「あれ? 女の人は?」
そう言えば、どこにもいない。
女性が座っていたはずの側のドアを開けると、シートがぐっしょりと濡れている。
「まさか!」
浜口教授がシートを濡らす水を指につけて匂いを嗅ぎ、感想を漏らした。
「おしっこだ」
吉村がシートを舐めた。
「本当だ。おしっこだ」
「この変態がああ!」
俺は吉村の尻を蹴った。
「ボクね。濡れたものを見ると反射的に舐めたくなるの」
吉村が説明した。俺はそれを聞かなかったことにした。
「シート洗わなくちゃ。ものすごく迷惑だ」と山岸。
「うん、粗相をしたので挨拶もそこそこにして、車がついたときに降りたのだろう。シートは作業が全部終わってから掃除するとしよう」
いやいやいやいや。教授。ずっとドアを開けていないのだから、降りるも何もない。幽霊以外の何者でもありません。
でも単位を失うのが怖いので、俺は反論はよしにしておいた。
「家の中に誰かいるぞ」
鬼口が震える声で指摘した。
鬼口が指すところ廃屋の二階の窓に顔が並んでいた。俺は悲鳴を上げた。
「シミュラクラ現象、シミュラクラ現象。きっと壁の染みかなんかが人の顔に見えているのだろう」
浜口教授が断言した。
二階の窓に並ぶ顔の一つが手を振った。
「きゅううじゅうううう。あれ、手を振りましたよ!」
「錯覚、錯覚。風で中の何かが揺れたんだろう。さあ、行くよ」
浜口教授は存外に力が強い。俺と鬼口は廃屋へと引きずられて行った。
「思ったより暗いな。懐中電灯はどこかな?」
浜口教授がポケットをまさぐった。
ぽっと灯りが灯った。赤い光が周囲をふわふわと飛び回る。
「ひ、人魂」
俺はかすれた声で言った。叫びすぎてもう声が出ない。
「プラズマ、プラズマ。人魂と言われるものは全部プラズマだ」浜口教授が繰り返した。
人魂の中に人の顔が浮かび上がった。何かを訴えかけるかのように口を動かす。俺がそれを指さすと、浜口教授はまたもや繰り返した。
「シミュラクラ、シミュラクラ。おや、中山君、心拍数が凄いね。やはりこのような雰囲気では心理的なストレスが大きいのだな」
二階へ通じる朽ち果てかけた階段を何かが駆け下りて来た。俺は床に落ちていた棒を掴むと、その何かをぶん殴った。
それをひらりと避けると吉村が口を尖らせた。
「危ないなあ。何をするの」
「お前、いま、二階から、来た」鬼口が言った。
「あ、あのね、ボク。ここの人たちに招かれたの。みんなこっちに連れておいでって」
「誰が行くかあ!」俺はまた吉村を殴ろうとしたが、またもや避けられた。
「ふむ。吉村君ばイマジナリフレンドの持主か。幽霊一家を想像して、それが現実にあるものとして行動しているのだね。いや、実に興味深い」
「きょうじゅう。ヤバイ。ヤバイですよ。ここ。帰りましょうよ」
「中山君。約束を破るなら単位はあげないよ」と浜口教授。
「さあ、二階に上がってみようじゃないか。きっと面白いものが見られるに違いない」
「鬼口、逃げよう。二人で落ちれば留年も怖くはない」
「お前が行くならオレも行く。お前が決めろ。お前がどんな決断をしようとも俺は恨まない。いいか、俺はお前を恨まない。たぶん」と鬼口。
ああ、鬼口、ずるい。決断は俺次第かよ。
結局俺は浜口教授の後ろについて二階に上がった。
二階に上がって俺は絶句した。大広間と言ってよい大きさの部屋に、一面にべたべたとお札が貼ってある。壁も窓も天井も床もなにか文字が描かれたお札だらけだ。その張り方がもう狂気としか言いようがない。予想に反して部屋の中は無人だ。畳は存外に綺麗でしっかりしている。
窓もお札だらけなのに、どうして外から顔が見えた?
答えの出るはずのない疑問は俺の口の中で消えた。
浜口教授は遠慮なく部屋の中央に進み、俺と鬼口は恐る恐るそれについて行った。吉村は俺の後ろにぴったりと張り付いている。吉村の体温が物凄く不快だ。
いきなり背後で音がした。たったいま上がって来たばかりの階段へと続く襖がいきなり閉まったのだ。
それと同時に周囲にいきなり人影が涌いた。子供が数人、大人が数人。いずれも姿がぼうっとしている。
『お兄ちゃん。遊ぼう』子供たちが飛びついてきた。
「きゅううじゅううううう。出ました」俺は叫んだ。
「シミュラクラ、シミュラクラ」浜口教授は答えた。
『ようこそ・・われらの家へ・・』大人の幽霊が声を出した。
「きょうじゅうう。シミュラクラじゃないです。喋っています」
「耳鳴りだろう。背景雑音のレベルが低いと人間の脳は周囲の音を人間の声に変換する。脳はイタズラものなんだよ」
浜口教授はポケットを探るとタバコを取り出した。
「ここは禁煙かな? ええと、火はないかな。ああ、あったあった」
浜口教授は飛んでいる人魂の一つにタバコの先を突っ込むと、すうっと息を吸い込んだ。吸われた人魂がみるみると小さくなると教授が咥えたタバコの先端に火が点った。教授は深くタバコの煙を吸い込むと、ぷはぁと吐き出した。吐いた煙が人の顔になってから四散する。
この人の頭の配線はどこか壊れている。俺は心底そう思った。
「まだ納得いかないかね。では先ほどから録音しておいたのでそれを再生してみよう。このレコーダは先月買ったばかりの最新製品なんだよ」
浜口教授はもう一つのポケットからレコーダを出すと再生した。俺と鬼口とさらには周囲を取り囲む幽霊たちもそれを覗き込む。
レコーダーから声が流れ出した。
『お前も早くこっちにおいでぇぇぇぇぇ』
「はっはっは。どうやら録音をミスったようだ。こりゃ三年前に死んだ私のお婆さまの声だ。メモリーの片隅に残っていたんだな。いや、参った参った」
「きょうじゅ」俺の声はもはや泣き声だ。
「うん、中山君の心拍数は二百。通常の二倍か、相当速いな。血圧二百五十は流石にまずいな。鬼口君も態度には出さないが同じぐらいか。吉村君はなぜか普通だな。君の精神構造は実に興味深い。よし、最初の実験はここで終了としよう。みんな、引き上げるよ」
『逃がすものかああぁぁぁ』
それを合図に幽霊たちが一斉に浜口教授に掴みかかった。子供の幽霊たちでさえも教授の足にしがみつく。それを完全に無視して浜口教授が振り向くと、その拍子に幽霊たちが弾き飛ばされた。
「はっはっは。いま何か触れたような気がしたが、気のせい気のせい」
ずかずかと階段へと向かう。途中を遮る襖に手をかけるが開かない。
「おや、建付けが悪い家はこれだから。すまないが鬼口君、これを開けてくれないか」
鬼口は無言のままそれに従った。その手が襖にかかる。やはり開かない。ふん、と鬼口の頬が膨らんだ。蒸気が鬼口の鼻の穴から噴き出す。その肩が盛り上がると腕に力が籠った。
襖がめりめりと裂け、鴨居が嫌な音を立てた。さらに鬼口が力を籠めると、どこをどうしたものか柱が撓み始めた。ベキベキバキバキと破壊の音を立てて階段への道が開いた。
鬼口は吉村のような変態ではないが化け物の一種だ。俺はようやく結論にたどり着いた。だがそれでもまだ我慢できる化け物だ。
『おのれ、待てええええぃ』
幽霊たちが再び飛びついてくるのを見て、俺は教授の後ろについて逃げ出した。鬼口が俺の後ろに張り付いていた吉村の首筋を掴むと、背後の幽霊たちに投げつけて逃げ出した。
俺たちは外で待つ山岸の車に飛び込んだ。廃屋の中でドタバタと何かが暴れる音がする。
「山岸! 車を出せ!」
俺は運転席の山岸を小突いた。こいつ、まだ寝ているのか。
山岸の頭が後ろにぶらりと折れた。白目を剥いて何かをブツブツとつぶやいている。
「ご免なさい、御免なさい、ごめんなさい」
「おい、しっかりしろ、山岸」
俺は喚いたが、それよりも鬼口の動くのが素早かった。山岸の両頬を張り飛ばす。
「いてえ!」
鼻血を流しながら山岸が正気に戻った。
「何するんだ。そりゃ確かに寝ていたけど、叩いて起こすこたぁないだろ」
「寝ていたあ!?」
「何も起きないし、退屈だったからな。心霊スポットなんて実際には何も出ないんだから面白くもなんともないんだよ」
山岸はエンジンをスタートしながら不満げに言った。
ようやく真相がわかった。山岸は零感なのではなく強烈な霊媒体質で、おまけに取り憑かれたときの記憶がすっぽりと抜ける口なのだ。それを自分では零感だと勘違いしているのだ。
車が動きだした。浜口教授は実験の結果のメモを整理している。シミュラクラとプラズマという文字が並んでいるのを俺は見てとった。
この教授大丈夫かと思いながら車の後ろを見た俺は驚愕した。
「てけてけてけてけ」吉村が叫んでいる。
その吉村の腰に無数の人影がすがりついている。吉村はそれらをぶら下げていて、その余波で両足が宙に浮くことになっている。その姿勢でもこいつは両手だけで走って車を追いかけていた。
これは鬼口が見せる怪力とは別の能力だ。なんという変態なのだ、吉村は。
だが車の方が早い。俺は安心した。車はやがて速度を上げ、吉村の姿は背後の闇の中に消えた。
「次の試験場所は廃ホテルの予定だ」
浜口教授が地図を広げた。
「きょうじゅうう。まだやるんですか」
「情けない声を上げてどうしたね。中山君」
「もうやめましょうよお」
俺は泣いた。情けないといわれてもいい。次はどんな恐ろしいことになるか。
「それはできない。まだシミュラクラ現象とプラズマしか証明できていない」
「あれはそんなものじゃありません! 鬼口。鬼口も止める方に賛成だよな!?」
「オレは・・オレは続ける」鬼口が言った。
「うらぎりものおおおぉぉぉぉ」
「仕方ないんだ。この単位が取れなければオレは留年する。留年なんかしたら親父とお袋に」
そこまで言ってから鬼口は言葉につまり、ごくりとツバを飲み込み、絞り出すように残りを言った。
「・・殺される」
鬼口の顔は真剣だった。それを見て俺は押し黙った。こいつは物事を大げさに言う男ではない。
鬼口には何か複雑な家庭の事情があるのだろう。
「結論が出たかね。では説明する。
次の廃ホテルは客室百六十人の最新設備を誇るホテルだった。主に大企業の研修の宿泊所に使われていた。だがある日、火事が出て大勢が死んだ。それからはさまざまな怪奇現象が起きるという噂が流れ、廃業へと至った」
またもや写真だ。真っ黒に焦げた部屋が写っている。それと手足を縮めた真っ黒な何か。
浜口教授の携帯が鳴った。
「ああ、うん、ええ。すぐに着きます。ええ、こちらは三人」
浜口教授が携帯を切るとポケットにしまう。
「教授。今のは?」
「ああ、ホテルの部屋の予約の確認だよ。このホテルは完全予約制でね。ホテルの部屋で十五分間滞在して君たちの心拍なんかを計るのが今回の目的だ」
「予約って! そのホテル、倒産したんですよね?」
「ん? ああ、そう言えばそうだな。気づかなかったよ」
浜口教授は携帯を調べた。
「おや? 発信記録が載っていない。うん、私もボケたかな」
いやいやいやいや。俺たちも携帯のベルを聞きましたから。これ絶対に罠だ。
物凄く嫌な予感に苛まれながらも、俺たちは廃ホテルへついた。
暗い。くらい。もの凄く暗い。
夜空の星も今夜はどことなく暗く感じる。その星空を背景にしてホテルの残骸が黒くそびえたつ。だが外はまだマシだ。灯りというものが一切ないホテルの廃墟へと俺たちは進んだ。
山岸は例によって車で待機だ。それでも俺たちと一緒に車から出てきて、ブツブツ言いながらフロントガラスを拭き始めた。
「まったくもうどこの馬鹿ガキだ。ガラスにベタベタ手形なんかつけやがって。こりゃ、赤絵具かなんかだな」
「おい、山岸。今何時だと思っている。子供が出歩く時間か」
「最近のガキは夜更かしなんだよ。よく深夜にガキの笑い声が聞こえるだろ。最近の親は子供が何時に寝るかなんて気にしないんだ」
しばらくガラスを拭いてから、不思議そうに言った。
「あれえ。これ内側についているな。俺が寝ている間に誰か中に入ったな」
ひぃ。俺の喉から小さな悲鳴が漏れた。
「山岸君。お留守番はよろしく頼むよ。さあ、みんな、行くよ」
浜口教授が先頭に立つとホテルに入った。ホテルの中は星の光さえ無い真の暗闇だ。こうなると各自が持つ懐中電灯だけが頼りだ。
正面ロビーのガラスはことごとく割れ、吹き込んだ風にゴミが揺れている。じゃりじゃりとガラスを踏む音をさせながら、浜口教授はロビーの受付へと真っ直ぐに進んだ。まったく教授は度胸がいいというか何か大事なものが欠けているというか。俺は感心した。
受付のカウンターの上に真新しい宿泊簿が開かれたままで置かれているのを見て俺はぞっとした。普通のホテルならあって当然だが、廃ホテルにあってはならないもの。それが真新しい宿泊簿だ。
浜口教授がそれを覗き込んだ。
「おや。中山君たちの名前が書きこまれている。いったいいつの間に。私の名前は抜けているな」
浜口教授が隣に置いてあったペンを取り上げてサラサラと自分の名前を記入した。その欄に書かれていた部屋番号を読み上げる。
「十三階の四号室だ。行ってみようじゃないか」
この教授、どこまでやるつもりなんだ。宿泊名簿はきっと教授の仕込みだろう。うん、そうに違いない。そうでないと、俺は困る。大変に、困る。
エレベータが開いた。教授を先頭にして乗り込む。
「十三階っと」ボタンを押してから気が付いた。
「どうして電源が止まっているのにエレベータが動く?」
「予備電源がまだ生きているのだろう」
浜口教授はタバコをつけた。正直狭いエレベータの中でのタバコはマナー違反だ。
エレベーターが止まった。まだ四階だ。いつの間にか四階のボタンが押されている。
扉が開く。ドアの向こうで待機していたものたちが一斉に開いたドア目掛けて殺到する。
浜口教授がふうっと大きく煙を吐くと、そいつらが怯んだ。そのすきにドアが閉まった。
「きょうじゅ! 今の見ましたか!」
「うん。私も見たよ。集団幻覚という奴だね。君たちが怖い怖いと思っているからこちらまで引きずられるんだな」
「集団幻覚とか言っていたら何でも集団幻覚になるじゃないですか」
「はっはっは。良いところに気がついたね。その通り。集団幻覚という言葉はどんなものにも使える魔法の言葉なんだ。それを言うならこの世のすべては集団幻覚だよ。我々は実は存在せず、ただ集団幻覚だけが存在の夢を見ているとも主張できるな」
「全然理解できません。教授」
ベルと共にエレベータの扉が開いた。十三階だ。今度は何も待機していない。それでも廊下は真っ暗だ。背後のエレベータから漏れる明りだけが場違いな感じだ。
「四号室はこちらだな」
浜口教授を先頭に、俺と鬼口が恐る恐るついていく。
教授ががちゃりとドアを開けて中を覗き込む。
「ほう。中々綺麗じゃないか」
俺も覗き込んだ。ごく普通の部屋だ。奥にシングルベッドが二つ並んでいる。小さな常夜灯が上に一つ点いている。
浜口教授は躊躇わずにずかずかと入り込む。俺と鬼口も置いていかれまいと後に続いた。廊下に一人で残されるのだけはご免だ。
「変だぞ」
鬼口が口を開いた。
「ホテルは廃墟なのにどうしてこの部屋だけは普通なんだ? それにここ、確か火事があった階だよな」
「おにぐちぃぃぃ。それ言っちゃダメなやつ」
「はっはっはっ。まあ、そんなこともあるのだろうさ」
浜口教授は灯りのスイッチを入れた。室内が光に満たされる。
今まで闇に隠れて見えなかった無数の人影がざわめき、光を避けて動いた。
長い黒髪の女が一人、さっとベッドの下に隠れる。薄っぺらい紙でできたような女は上に伸びあがると掛けてある絵の後ろに滑り込んだ。残りは壁に張り付くと壁紙の模様の中に溶け込んだ。
ひぃ。思わず悲鳴が出た。ベッドの下に潜り込んだ女が片目で俺を睨む。
「きょうじゅううう。出た、出た」
「シミュラクラ。シミュラクラ」
浜口教授はそう唱えると、もう一本タバコを取り出して火をつけた。
ここ喫煙可の部屋かい。そんなことを思った。あまりのことに頭が現実逃避しようとしている。
「二人とも心拍数百五十か。打ち続く恐怖に慣れて来たんだね。いや、実に興味深い」
そのときだ。外に面する窓がガラリと開いた。
「ボクを置いていこうたってそうはいかないんだからね」
窓の外から吉村が顔を出した。そのままずるずると這いながら部屋に入ってくる。腰に一杯何かがぶら下がっている。
「吉村。お前何を連れてきてんだ!」
俺は叫んだ。ここが十三階であることは敢えて指摘しない。相手は吉村だ。つまり十三階分の壁を登るなどコイツにとっては造作もない。
吉村はきょとんとした顔をすると、首を真後ろに向けた。
「ん? なにもいないよ」
「見えないのか。それほどいっぱいぶら下げて」
「またまたあ。ボクを怖がらせようってそうはいかないよ」
吉村は笑うと、そのまま首を回し続け、正面を向いた。
「ば、馬鹿野郎。吉村。お前首が一回転してるぞ」
「ボク、体柔らかいんだ」
「ば、化け物」
「何が化け物だい。これぐらい、練習すれば誰でもできるんだよ」
360度曲げた首のまま、吉村はそう言い放つ。
「うわああああああ!」
今度の悲鳴は鬼口だった。今の吉村の動きを見て、ついに正気の限界に達したらしい。
鬼口は両手で絵の額縁を掴むと壁から引きはがし、額縁に張り付いたままのペラペラ女ごと吉村にぶつけた。その手が浜口教授に当たり、口から吸いかけのタバコが落ちる。
「落ち着きなさい。鬼口君」
浜口教授は横目で額縁と一緒に転がった吉村を見ると、メモに何かを書きこんだ。
「よし、鬼口君の精神も限界のようだし、ここでの実験は終わりとしよう。さあ、みんな帰るよ」
俺たちは浜口教授を押すようにして、三人でエレベータに飛び込んだ。背後で幽霊たちと取っ組み合いをしている吉村は敢えて無視した。
やはり押してもいない四階のボタンが点灯し、エレベータは止まりかけた。ドンと大きな音がして鬼口の拳がエレベータの壁にめり込んだ。内部の鉄骨が嫌な音を立てて曲がる。
「ここで止まったら。オレは暴れる」
鬼口は宣言した。目が真剣で怖い。一旦止まりかけたエレベータがまるで何事もなかったかのように動き続ける。点灯していた四階のボタンが消えた。
偉いぞ、鬼口。よっ、日本一!
ホテルから出ようとすると、今度はホテルの玄関に半透明のドアボーイが立っていた。
「お客様。チェックアウトで御座いますか。お会計が終わっていませんが」
「中にまだ一人残っている。お代は彼から貰いたまえ」
浜口教授が涼しい顔で答えた。やっぱり教授にも幽霊が見えているじゃないかあ。何が集団幻覚なものか。
「お一人様で払えるものではないと存じますが、他ならぬ教授のお言葉、確かに了解いたしました」
ドアボーイは深々と頭を下げた。
「またのお越しをお待ち申し上げます」
山岸はやはり車の中でうつろな目でぶつぶつ言っていた。
「おかあさんおかあさんおかあさんおかあさんおかあさん」
鬼口がふたたび往復ビンタをかませた。
「ん、ああ、寝てた」山岸は言ってから、視線を上げた。
「あれ、なんだ?」
俺たちは振り返って、そして見た。車のライトと懐中電灯の灯りしかない暗闇の中に、もう一つ明かりが加わっていた。
火だ。炎の舌がホテルの高い位置から吹き出している。
「おや、火事か。火の気もないところなのに」浜口教授がとぼけた。
「誰か、寝タバコでもしたのかもしれませんね」
「おい、どうする?」
運転席のシートベルトを締めながら山岸が言った。
「ほっておきなさい。どのみち消防署に連絡しても無駄だろう。このホテルには予め予約を取らないと誰も辿りつけないという話だから」
炎の中に無数の黒い人影が踊っているのが見えたような気がした。微かに悲鳴が聞こえるような気もした。今彼らは絶対にもう一度見たくなかった光景を見ているのだろう。
山岸がアクセルを踏み込み、俺たちはそこを離れた。
「さて、最後の実験の舞台は廃病院だ」
浜口教授は説明した。もう俺も鬼口も文句を言う気力がない。
「ここは凄いぞ。今までの心霊スポットと比べても格が違う。もしかしたら実際に何か出るかもしれん」
「何かどころかすでに色々と出ていますが。きょうじゅううぅぅ」
浜口教授は俺の言葉を無視した。
「この病院には曰くがあってな」
「それはそうでしょう」俺は合いの手を入れた。
「ナナサンイチ石井部隊は知っているかな?」
俺と鬼口は顔を見合わせてから頭を横に振った。
「第二次世界大戦時の日本帝国軍の科学戦細菌戦研究部隊だ。中国大陸で恐ろしい人体実験を繰り返したことで知られる。中国人は言うに及ばず、通りかかっただけの外国人なんかも犠牲にされている。
さて、戦後に部隊は解散させられたのだが、この病院はその伝統を継ぐ一つでね。戦後も違法な人体実験を密かに繰り返していたという噂がある。実際にかなりの数の患者が行方不明となっている」
「止めましょう」
「特にここの手術室は違法な手術のオンパレードで」
「帰りましょう」
「潰れた後に敷地から大量の白骨死体が」
「きょうぅぅぅじゅうううぅぅぅ」
「目的地はこの手術室だ。さあ皆覚悟を決めなさい」
俺は車の窓を開けると飛び降りようとした。鬼口が俺の頭を殴り、俺は忘却の海へと沈んだ。
目が覚めたときはすでに病院の中だった。窓は割れ、壁は剥がれ、床のあちらこちらには穴が開いている。
「起きたようだね。後は自分の足で歩きたまえ」
浜口教授が鬼口に命じて俺を床に降ろさせた。
「よかったよ。中山君が眠ったままでは実験が進められない」
「ここまで来たら諦めろ」鬼口が俺に引導を渡した。
俺は仕方なく二人の後をついていった。
二人が角を曲がる。俺も慌てて角を曲がった。
誰もいない。俺の懐中電灯の光だけが空しく寂れた廊下を照らしている。
「あれ? きょうじゅ、おにぐち~」
光を左右に振る。どこかの部屋に入ったのか?
俺はドアの一つをあけた。どことなく悲鳴を思わせる軋み音を上げながら扉が開く。
暗闇の中、テーブルの上に女の子が座ってしくしくと泣いている。俺は一瞬びくっとし、それからきっと心霊スポット探検で一人置いていかれた女の子ではないかと自分に言い聞かせた。
うん、そんなことはあり得ないってことも、自分が現実から逃避しようとしていることも、よおく分かっている。
「きみ、大丈夫?」
声をかけるより先に女の子がつぶやいた。
「あたし・・あたし、死んじゃったの?」
おい! 俺は身構えた。その先が予想できたから。
いつの間にか女の子を取り囲んでいた人影たちが女の子の頭を撫で始めた。
「だいじょうぶ、だいじょうぶ」
「死ぬのは怖くないんだよ」
「すぐに迎えが来るからね」
ひぃ。小さな悲鳴が出た。
「でも一人じゃ寂しいんだろうね」
話が嫌な方向に向かっている。俺は後ずさりを始めた。ドア、ドア。取っ手はどこだ?
「ちょうどいい。もう一人きた。彼に一緒に行って貰おう」
ドアを叩きつけるように背後で閉めて全力で逃げ出した。ドアの上の霊安室と書かれたプレートが一緒に落ちる。
ドアをいくつも通り過ぎた。一つのドアから明かりが漏れている。教授たちだ。俺はドアを蹴破って飛び込んだ。
灯りが灯る部屋の中で、ハダカの男と女が抱き合っている。その体はうっすらと透けている。
二人がこっちを見て言った。
「み~た~な~」
「お願い。旦那には言わないで」女が訴えた。
「信用できない。口を封じよう」男が続けた。
またもや廊下に飛び出しながら俺は毒づいた。幽霊に不倫なんてものがあるのかどうかは知らないが、死んでからもやることはそれかい。
ようやく前方に手術室と書かれた扉が見えた。明かりが漏れている。今度は一旦立ち止まって、そっと扉の隙間から覗いてみる。
「あ、来た来た」吉村が言った。
再び扉を閉じて逃げようとしたが、それより先に鬼口の手が伸びてきて俺を引きずり込んだ。
「逃げるな。お前がいないと実験が進まない。教授が帰ろうと言ってくれない」
鬼口が自分に言い聞かせるかのように俺に説明した。
手術室の中央のテーブルの横には浜口教授がいた。
「よし、これで全員揃ったな」
その横に並んだ新しい浜口教授が後を続けた。
「実験を続けよう」
「教授が二人いる」俺は指摘した。
「はっはっは。何を言っているのかね。中山君。私が二人いるわけないだろう」
「集団幻覚、集団幻覚」
「シミュラクラ、シミュラクラ」
「錯覚という奴だね。いや、統合失調症が発症したという可能性もある」
もはやどちらが本物の浜口教授かわからない。俺の横で鬼口も困っている。
「おっといけない。中山君は脈拍百二十か。だいぶ恐怖にも慣れてきたようだね。鬼口君は・・」
浜口教授の一人はメモに何か書きつけた。
「鬼口、こっちの教授を殴れ」俺はもう一方の教授を指さした。
避ける間もなく鬼口の拳が飛び、浜口教授に化けていたなにかをぶっ飛ばした。
「そっちも」おれは吉村を指さした。
こちらにも鬼口の拳が飛んだ。だが吉村はそれをひらりと躱して天井に張り付いた。
「くそっ。すばしこい」鬼口が毒づいた。
「ひどいなあ。鬼口君、なにするの」
吉村が天井で抗議した。こいつ、どうやって天井に張り付いている。それとも変態というものは重力を無視できるのか。
「よし、これで予定の実験は全部終わりだ。後は帰ってレポートを書くだけだ」
浜口教授が宣言した。
安堵のあまり俺の膝から力が抜けた。
『帰れると思っているのか』
どこかから声がした。
「空耳、空耳」浜口教授が断言した。
手術テーブルの下からぬらぬらした何かが這い出して来る。それは無数の人間の臓器を結合したように見えた。あちらこちらに小さな赤ん坊の顔がついている。
俺は絶句した。あまりにも恐ろしいものを見ると、人間は言葉を失うものだと初めて知った。
天井に張り付いたままの吉村が口を開くと、そこから驚くべき長さの舌がムチのように飛び出てきてその這い出してきた何かをベロリと舐める。
「美味しい」と吉村。舌がさらに伸び、その何かに巻き付いた。
人間のものではない悲鳴が轟いた。
吉村が変態行為をしている隙をついて、俺たちは手術室を飛び出した。その衝撃でドアの上のランプが手術中に替わる。
「早く逃げろ。吉村があの何かを舐めまわしている内に」
俺たちは浜口教授の背中を押しながら廃病院を飛び出した。
車の中では山岸がうつろな目でおとうさんおとうさんとつぶやいている。その横ではあのお漏らし幽霊の女の人がかがみこむようにして山岸の耳に何かをささやいていた。
「降りろ!」
鬼口が怒鳴るとむんずとばかりに女の首を掴んで外へ放り投げた。そのまま素早く山岸の頬を張り飛ばして起こすと、車を発進させる。
「鬼口君。女性の扱いはもっとお手柔らかに」
浜口教授が言った。
「教授も幽霊が見えているじゃないですかぁぁぁ」
俺はあきれた。今までのシミュラクラとかの戯言はいったい何だったのか。
「当然だよ。あれだけはっきり出てしまってはね。
でもね。中山君。考えてもみたまえ。
仮にも精神医学の教授が幽霊を認めたりしたら、商売上がったりだろ。お客さんがカウンセリングに来る代わりにお祓い師のところに行くようになってご覧。お医者さまの面子丸つぶれだ。だからこそ我々は絶対に怪奇現象を認めるわけにはいかん。いかに事実を捻じ曲げようが決して認めてはいかんのだ。
幸い、我々には都合の良い言葉が揃っておる。それに欠片ほどの真実も含まれてはおらぬとしても。すべては錯覚であり、集団幻覚であり、統合失調症なのだよ。シミュラクラこそ神であり、プラズマこそ正義なのだ。
見えないものは存在しない、ではなく、存在してはいけないものは見てはならない、が正しいのだ。
それより山岸君、もっとスピードを上げた方がいいと思うな。もうそろそろ追いかけてくる頃合いだ」
背後では星空の下に黒々と聳える廃病院の影が揺れていた。嫌な悪意がそこから吹き出してくる。鈍い山岸もさすがに何かを感じたのかアクセルを全力で踏み込む。
「おや、またタバコを落としてしまったな」
浜口教授が呑気な声で言う。それを裏付けるかのように背後で火の手が上がった。
その後のことはよく覚えていない。何とか家にたどり着き、布団を頭から被ってひたすら寝た。布団の外で誰かがぶつぶつとつぶやいているような気がしたが無視した。
次の日、山岸が車の中に何故かカルテがあった病院に返しに行かなくちゃと喚いていたが、俺はそれも無視した。これ以上こんなことに巻き込まれてたまるか。
俺と鬼口のレポートはシミュラクラとプラズマと集団幻覚と統合失調症という言葉でびっしりと埋まった。浜口教授は秋の学会での研究発表の資料として使うらしい。一応約束通りに教授はゼミの単位をくれた。
吉村はあれ以来、大学に来ていない。よっぽどあの這い出て来た何かの味が気に入ったのだろう。
だから今も奴はあそこに居る。