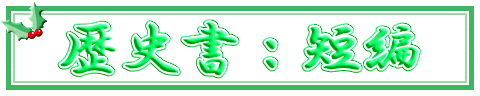
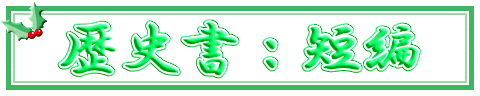
レムリア賛歌)
ああ、我が麗しのレムリアよ。
そは壮麗にして繊細、優雅にして荒々しく、流暢にして華麗、そして永遠に輝く美なり。
ああ、我が麗しのレムリアよ。天に挑戦する人類の偉業よ。
塔という塔には華麗な旗が翻り、王宮から溢れ出る輝きは眼下に広がる市街をもまた満たし、その威光に目がくらむ。
毎夜開かれる舞踏会には煌びやかな貴族と裕福な市民が共に笑い、共に輝き、無数のロマンスの花が尽きせぬ喜びを与える。
下町の酒場には喧噪と喧嘩が絶えず、売春宿では女たちの嬌声が上がる。庶民は自分たちのお楽しみにふけり、生の喜びを謳歌する。
ああ、我が麗しのレムリアよ。眠りを知らぬ素晴らしき帝都よ。
帝国中から集められた素敵なものは、歩き尽くせぬほど広き街の市場へと集められ、人々の目と耳と舌を楽しませる。青年たちは野望に燃え、娘たちは恋に堕ちる。
磨き抜かれた甲冑を着た金の儀仗兵たちが、街の通りを闊歩する。
空を往くは竜騎兵の一群。口吐く炎にて夜空を彩り、天威を示す。
軍楽隊は尽きせぬ調べをまき散らし、偉大なる英雄たちの物語を紡ぐ。
ああ、我が麗しのレムリアよ。命の輝きは汝のもの。
青も鮮やかなバジュイの果物、黒の黒たるレンの果実、甘やかなるムーのサプロ実、色とりどりの商品を満載して、山とも見紛うダンダビュロスの荷獣が地響きを立てて歩む。賢者の一団の横を、誘惑の匂いを撒き散らしながら花の女たちが微笑みながら歩く。色鮮やかなボールを投げ上げながら、道化師たちが金貨を求めて競い合う。
ああ、我が麗しのレムリアよ。
夜ごとの夢に苛まれ、顔を覆いし両手の中にて涙する。
汝はいま、いずこなりしや?
1)発端
レムリア帝国に居場所が無かったわけじゃない。
年の離れた長兄が管理している公爵領は豊かで広大だし、父の残した館には皇帝の宮殿に匹敵するほどの部屋数と金貨の詰まった部屋がある。兄弟姉妹はたくさんいるが、誰と仲違いしているわけでもない。
レムリア帝国自体が大きな大きな国だから、そこから出るだけでも長い長い旅が必要となるのだが、それでも俺は外の世界が見てみたかった。まあ、若い時分には誰でもかかる熱病ってやつだ。
着の身着のままで家出という手段もあったが、もちろん、そんなことを許すような長兄ではない。
金にあかせてレムリア帝国渉外警備将校の地位を手にいれると、俺にその役を押しつけた。おまけに退役したレムリア正規兵たちも相場の三倍の値でひと山買い、俺の部下とした。もちろん、どれも豪華な装備品付きでだ。
金で象嵌された鎧に紋章の刻まれた剣。するどい穂先を見せる火炎杖に我が一族の記章がついたヘルメットとサーコート。それが一糸乱れぬ隊形で俺の前に並ぶと自ずから誇りが沸き起こってくる。
流石に執事とメイドの一群は断った。身の回りの世話にはお付きの兵だけで十分だ。
でもきっとこれだけで済むわけがないと覚悟していたら、レムリア商業評議会議長をやっている三番目の兄から連絡が来た。新しい貿易路の強化開拓を頼みたいという話だ。こちらが返事をする間も無く、大部隊のキャラバンが黄金と宝石が一杯に詰まった大箱と共に送りつけられて来た。
巨獣ダンダビュロスの背中に設えた大きな荷物カゴ一杯には、さまざまな貿易品が積まれている。ただし護衛部隊は無しだ。それは新しく俺の配下になった部隊で十分だと考えたらしい。やれやれ。三番目の兄さんときたら物凄く計算高い。
最後に五番目の兄から連絡があった。手紙には皇帝の宮殿に来いと書いてある。黄金の飾りのついた宮殿への通行証もついている。ということはこれは皇帝じきじきの命令と同じということだ。宮廷主席参事官である兄が、どのような理由で俺を呼んだのかには興味があった。
とにかくレムリア皇帝の宮殿は大きい。レムリアの首都そのものが広大な大きさを誇っているのだが、その中で一際威容を誇る建物なのだから大きいのは当然である。宮殿の入り口で馬を下りると、宮殿の門の中で宮廷専用の馬をまた借りる羽目になった。それでも文句は言えない。徒歩で動き回るには宮殿はあまりにも広すぎる。
流石に皇帝に謁見するところまではいかなかったが、それでも宮廷お付きの賢者の中でも第三位のアモデス賢者に会うことになったのには驚いた。この人物は皇帝の信任篤きお方で、その日常は多忙の一言に尽きる。
「手短に話そう」
賢者特有の落ち着きのある声でそう言うと、宣言通りに実に手短に話してくれた。
用事はスパイの任務をしてくれということだ。ターゲットは謎の男。このところ、他の国の知識階級の中に奇妙な男が出没し、異端の考えを広めているとのことだ。
もちろん、レムリア帝国は子飼いのスパイを無数に抱えているし、諜報を専門とする部署だけでも俺の知る限りでは六つもある。ところがそういった連中の必死の努力をあざ笑うかのように、謎の男は未だ謎の男のままで、異端の活動を続けているらしい。
そこで白羽の矢が刺さったのはスパイなんか全くやったことのないこの俺だ。
どうも賢者という輩は、問題が煮詰まってしまうと、とんでもない結論へと飛びついてしまう人種らしい。
2)出発
これから夏になるという季節を見計らって俺は密かに出発した。
・・・というわけには行かなかった。当たり前だ。いまや巨大なキャラバンへと膨れ上がったこの一行は、小さな丘と言ってもよい荷役巨獣ダンダビュロスだけでも十頭はいる。
ダンダビュロスはレムリア帝国特産の荷駄獣だ。小山を思わせる巨大なトカゲで足は左右合わせて二十本ある。もちろん、性質はおとなしい。これでもし凶暴だったら、国を滅ぼすに十分な力がある。
ダンダビュロスは普段はレムリア帝国の東にある草原地帯で草を食べているが、渡りの時期になると、背中にさまざまな荷物を載せての交易に駆り出される。背中の上に木で足場を作り、倉庫や家を建てて動く街に変えるのだ。それを数頭から数十頭並べて、レムリアの交易キャラバンを構成する。
草原で食べた草を皮下脂肪に変えたダンダビュロスは、渡りの時期にはほとんど食事を取らずに移動する。歩みは遅いが、その代わりに休息は必要としない。
通常はキャラバンには通常一頭か二頭の武装ダンダビュロスが加わる。その背中に載っているのは一種の要塞で、そこにはレムリア帝国軍が駐留している。
一般的な構成ではキャラバンの先頭に武装ダンダビュロスが来る。そして大きなキャラバンでは最後尾にも武装ダンダビュロスが配置される。それらの背中の上の要塞砲と、周囲を走り回る騎兵がキャラバンの護衛の中心戦力となる。
これらとは別にキャラバンには大勢の商人や別キャラバンが追随している。彼らはダンダビュロス・キャラバンとは護衛契約を結んで同行している。
護衛契約というのは旅の途中で盗賊団に狙われたときの保護契約だ。これを結んでおけば、いざと言うときは本体のキャラバンの周囲を警護しているレムリア帝国軍が守ってくれるというものだ。
さらにはキャラバンと何の契約も結んでいない連中も旅には同行している。
彼らは小規模の商隊や移民たちで、勝手にキャラバンの後をついてくる連中だ。
キャラバンに随行していれば、旅の途中で食料や水が尽きた場合にはキャラバンから買い取ることができる。病気になった場合には金を払ってダンダビュロスの背中の上の街へ泊まることもできる。
色々な意味でキャラバンに付いていくのは非常に心強いものがあるのだ。
こういった関係は旅行者を狙う盗賊団も熟知しており、武装されたキャラバンそのものを狙うことはしなくても、こういった一般商隊を狙うことはよくある。保護旗を出していない無契約の商隊は狙われるが、彼らはどうしようもなくなればその場でキャラバンの保護権を買い取ることもできる。
盗賊騎馬隊に襲われている真っ最中に、襲われている商隊の頭領がキャラバンの募集軍曹と保護費用の掛け合いをやることもある。
周囲で何が起きても、ダンダビュロスはその歩みを早めもしないし、止めもしない。頭の上に作られた小屋に住まう飼い主の命令以外は聞かないように躾けられている。
ダンダビュロスが移動するための交易路は良く整備されている。途中の川には引き込み路が作られ、ダンダビュロスのための水の飲み場となる大きな溜池が作られている。ダンダビュロスが一頭づつここで水を飲んでいる間だけがその動きが停止する時間だ。
その間に大慌てで荷車が集まり、ダンダビュロスの背中の倉庫から交易品を持ち出したりする。キャラバンの先頭が水飲み場についてから最後尾が水飲み場を出るまで、ほぼ一日が経過するので、その間に契約された荷物を相手に届けて帰って来るという実に忙しい商売である。
さて、ざっとキャラバンについて述べてみたが忘れていることはないかな?
無いようだ。よし、話を続けよう。
3)パレード
占星術師たちが計算で割り出した吉日を機に、キャラバンはレムリア帝都を出立した。
先頭はやや大きめの武装ダンダビュロスだ。前方に向いた要塞砲が一門、左右に二門が周囲を威嚇している。監視所と小型飛竜の発着場まで備え付けられている。
二頭目のダンダビュロスは高価な交易品と大量の金貨、他の国家への贈り物などを積んでいる。もっとも価値があり、それ故にもっとも厳重に護衛されている。
その他に手紙の類もここに積まれている。遠い他国に住む親戚に対しての手紙は各国での取りきめに従い、手紙を出すときに運賃の半額を払い、手紙を受け取るときに残りの半額を払う方式だ。
これが意外と大きな金額になることに俺は驚いた。手紙の類は軽くてかさばらないので運ぶ方も助かる。もろもろの事情も合わせて、手紙の運送はある一定以上の大きさのキャラバンにだけ許されている。
それに続くダンダビュロスは旅行客用の宿泊所、そして小規模な歓楽街を載せている。さらには山海の珍味を食べさせる料理店すらある。
その次からは貨物ダンダビュロスが続く。貨物ダンダビュロスは動く倉庫だ。頑丈な木で作られた窓の無い倉庫群が背中の上に聳え立っている。
最後尾はまた武装ダンダビュロスが固める。これがキャラバンの全貌である。
この一行の周りを見事な馬に乗った帝国騎兵が取り囲み、その後に歩兵の一隊が続く。さらには煌びやかに飾り立てた大きな馬車の一群が続き、その中の一つはキャラバンに遂行する娼婦たちが占領して華やかな笑い声を上げている。彼女たちは歓楽街ダンダビュロスの淑女たちに比べると一段落ちるが、それでも素晴らしい美女ぞろいだ。
巨獣ダンダビュロスの背中の上には、数階建ての倉庫が設えてある。その中に入り切れなかった小さな交易品は、倉庫の外側に乱雑に積み上げてある。これらはたまにダンダビュロスの歩みに連れて周囲に落ちることがあり、浮浪者や子供たちがそれに群がって、この思いもかけぬ贈り物を奪い合う。
中でも人気は甘い匂いのする果実で、これはレムリア特産のアーシャントだ。四角い果皮の中にみっちりと詰まった黄色の果肉は一口食べれば病みつきになる。賢者たちが施した停止の術のおかげで、痛むこともなく、先の市場に運ぶことができる。
二番目の姉の嫁いだ先が、この帝都の式典一切を取り仕切っている名家であることは話したかな?
もちろんその名家はこの機を逃さずに盛大な壮行会を開いてくれた。帝都のあらゆるところから花火が上がり、極彩色の美しい鳥が放たれ、楽芸隊が陽気な音楽を鼓膜も破れよとばかりに吹き鳴らす。
空を旋回して見送ってくれているのは、八番目の兄が率いる帝国無敵竜騎軍だ。これもレムリア特産の飛行竜で、その恐るべき力でレムリア周辺の国を震え上がらせている。
花びらが惜しみなくまき散らされる中を、重々しくダンダビュロスが歩む。片側十本の芋虫を思わせる足が順に持ちあがり、前へ進む。どの足にも恐ろしい重量がかかっているはずだが、動きがゆっくりしているので地響きは立てない。ただ踏まれた敷石が自分に課せられた重量にうめき声をあげるだけだ。
ダンダビュロスの歩みに連れて、周囲の女たちが歓声を上げ、集まった子供たちが笑う。男たちはと言えば、振る舞い酒に我を忘れて、あやうく後続の馬車に引かれそうになる。
帝都を出るまでに三日がかかった。その間ずっとこの馬鹿騒ぎは続いた。広大なるレムリアの国境に辿りつくまでにそれから一カ月。
やがて道は砂漠地帯に入る。
夜に起き、昼は巨大なテントの中で午睡をする生活が始まった。
多くの遊牧民がキャラバンの噂を聞きつけ、食糧や水や酒を売りに来た。ダンダビュロス自体は眠らずに歩くことができるが、交易のためにときどき歩みを止めて店を開くのが習慣なのだ。
盗賊の下見をする連中もその中にいたに違いないが、レムリア護衛兵の姿を見るとすごすごと引き揚げた。
身分は退役兵だが、どれも歴戦の勇士たちだ。古傷だらけの体から発する貫禄だけでも並みの連中なら逆らう気力は失ってしまう。
それに巨獣ダンダビュロスは専門の調教師がついているから良いようなものの、何かのはずみで怒らせると実に厄介なことになる。踏みつぶされたくなければ迂闊には近づかないことだ。
巨獣ダンダビュロスはトカゲの変種なので、長い間水を飲まずに歩くことができる。体の中を通っている気孔から火傷するほど熱い風を吹き出すことで体温を調節しているのだ。
砂漠に入ってほぼ一週間で、砂漠の都ロウランに着いた。
ロウランはこの砂漠の中央に位置する大きな湖を囲むように作られた都市である。
砂漠の交易路の中心地でもあり、尽きることなく水の湧き出す湖を取り囲むように、終わることの無い市場が開催されている。
当然ながら、俺たちは歓迎された。レムリアの威光はここにも届いている。もちろんこの都市の支配者が一番歓迎しているのは俺達キャラバンが落としていく金であり、それも決して少なくはない金額であった。
黄金の都市ロウラン。それが旅人の間での呼び名だ。
兄貴が付けてくれたキャラバンの会計士たちが真面目に働いてくれるお陰で俺は楽ができる。金勘定をやるために国を出たわけではないのだから。
十頭もの巨獣ダンダビュロスが湖の水の半分を飲み干している間に、キャラバンからは多くの品物が市場に下ろされ、また同時に多くの品物が買いつけられた。
レムリア製の繊細なガラス細工の中では金の象嵌付きのが特に人気がある。レムリアの果物の半分も売り払い、ついでに眠りの術をかけて連れて来たレムリアの珍しい小鳥も美しい宝石細工の鳥カゴごと売った。
キャラバンについてきた娼婦たちもここぞとばかりに稼ぎ、土産に異国の珍しい酒を手にいれてきた。
実に平和だ。
キャラバンの随行員にまぎれて来た皇帝直属の諜報員たちもさっそく現地の人々の間に混ざり、いろいろと噂話を集めて来た。俺はお飾りとは言え彼らのトップを務めているので、否応なく報告の一部を聞くことになった。もっとも集まった話は例の異端者の話ではなく、この都市の支配者層のスキャンダルだけだったが。
一度に十二人の王妃との情事を行う王の話に興味があるかな?
それはそれはすごい話だったぜ。
もろもろの事が片付くと、俺達は次の目的地へと向かった。
そろそろ砂漠も尽きようかという頃になって、馬に乗った盗賊の集団が襲ってきた。とは言っても、狙いはこちらのキャラバンではなく、キャラバンに付いてきた連中の方だ。キャラバンの護衛であるレムリア兵との間には距離を置いて、隊列の後ろに伸びる人々の群れを襲い始めた。
恐怖の悲鳴が上がり慌ててキャラバンに逃げ込もうとするのをレムリア兵が阻止する。すぐにキャラバンの会計士たちが飛び出て、キャラバンの傘下に入るための金額の提示を始めた。いわゆる保護費だ。
金を払った者たちには保護旗が配られ、それを自分の荷物に立てると盗賊連中は襲わない。襲えばたちまちにして護衛の騎兵たちの的にされるからだ。
俺としては彼ら全てを助けてやりたかったが、それでは高い金を払ってキャラバンに保護されている他の客を馬鹿にしたことになる。惨いようだがそれが現実だ。無料で彼らを救うために大事な兵の命を捨てることはできない。
この期に及んでもまだ保護費を出し渋る連中がいるのには呆れた。彼らはできる限りキャラバンに近づき、保護旗を掲げている連中の仲間の振りをしようとする。盗賊たちは目ざとくそれを見つけて、隊列から引きずりだす。
これは言ってみれば一種のギャンブルだ。自分の運の良さに賭けた連中は金を払わずにやり過ごそうとする。彼らは命よりは金が大事なのだろう。
俺はしばらく様子を見てから、配下のレムリア兵たちに指示を出した。要塞砲が宙を目掛けて威嚇射撃を行い、騎兵たちが突撃を始めると、状況の変化を見て取った盗賊たちは逃げ始めた。たちまちにして盗賊たちは消え去る。少しとはいえ戦利品もあったので、わざわざ正規兵相手に命のやり取りをするまでも無いというところだろうか。
後に残されたのは盗賊たちに身ぐるみ剥がされた連中だ。可哀そうなので食糧と水だけを恵んでやり、先へと進んだ。
砂漠は荒れ地へと替わり、やがて塩水湖へと到達する。ここからは湖を右に見ながらの旅だ。湖とは言え広大で、幅は大したことはないが前後には長い。対岸に聳える崖がかろうじて見える距離に霧をまとって佇んでいる。
どこの湖でも水上生活者の船が浮かんでいるものだが、ここの湖には一人もいない。レンの大地の周囲の湖には一匹の魚も棲んでいないからだ。
キャラバンの進行についてくるかのように、対岸の崖の上を巨大な形容し難い何かが動いている。キャラバンもキャラバンに付いてきている隊商たちも敢えてそちらを見ようとはしない。それに魅入られた者はレンの大地に呼ばれて帰らぬ者となるのは有名な話なのだ。
帝国調査団の三度に渡る全滅以来、レンの大地は禁足地として指定されている。こういった場所が交易路の傍にあるのは恐ろしいことだが、湖という境界を越えない限りは無害なので敢えて放置されている。
無限に広がる大地の中にはこういった危ない場所は多々あり、それらには触れないのが賢いのだ。
やがてその忌まわしい大地が見えなくなった頃に、道行は緑の丘の連なりへと変わり、全員が胸を撫でおろした。
今度の国は一つ目の巨人たちが住む国だ。さっそくお迎えの巨人たちが現れ、規定の手数料を徴収した。
ここのサイクロプスたちはかっては人喰いの巨人として近隣の国から恐れられて来たが、今は文明化されて牧畜をして暮らしている。人間の肉を食うよりも、羊の肉の方が美味いと気づいてからは国も開けて文明化した。
今では羊毛を専門に扱う業者も入り、質の高い毛の服まで輸出するようになっている。その他にも他の国に出稼ぎに行ったり、傭兵になるものさえいる。あちらこちらで見かける巨石建築は彼らの労働力で作られたものだ。
レムリアでも大きな建物の建築に数体の巨人を使っている工房もあるので、俺は巨人を見慣れていると言えば見慣れている。付き合ってみればそう悪い連中でもない。ただ飲み代だけは割り勘にはしない方がよい。やれば間違いなく破産する。
巨人たちの国の中にはダンダビュロスのための待機所があり、数頭のダンダビュロスがいつも屯している。旅の途中でダンダビュロスが病気になった場合にはここで替えを手に入れることができる。
我々が到着したときにはちょうど一頭のダンダビュロスが出ていく所だった。レムリア帝国の長期遠征調査隊だ。調査隊は基本的には武装ダンダビュロスで、小型砲と補給物資倉庫と単純な住居で構成されている。新しい文明を見つけて交易路を形成するたびにレムリアは裕福になっていく。彼らこそは無限に広がる大地を探索し続ける冒険者たちであり、真の勇者たちだ。
そこを越えると次は氷の国だ。住んでいるのは犬人間。頭が犬で、体が人間という連中だ。ここにもレムリアの駐屯地があり、体調の悪い兵士を数人、そこに置いていくことにした。キャラバンは帰りもここを通るので、そのときに拾って貰えば良い。
とにもかくにも寒い国だった。一つ目巨人の国で仕入れておいた毛布が役に立ったし、犬人間たちも毛皮の類を山ほど売りに来たので、それほど難渋はしなかったが。
サブジェ、ラルン、ヘスカトの国を通り抜けるうちに、持って来た商品の半分が入れ替わった。どの国でも入国税を取られはしたが、大箱の中の金貨は増えるばかりだ。貿易というものがこれほど儲かるものだとは俺は思いもしなかった。なるほど上の兄貴が夢中になるわけだ。
そうしてついに、一行はギリシアの国についた。
ここが終点だ。
4)ギリシア
キャラバンには今までで一番忙しい時期が訪れた。
レムリア産の果実や工芸品を下ろし、代わりにギリシアの珍しい彫刻を積む。薬になる植物も集めたし、レムリアでは産出しない大理石の板も仕入れた。金塊のかなりの部分は銀の延べ板へと化け、オリーブ油の壺を木の枠に固定して載せる。
読めない字の書いてある巻物。それにレムリアを見たいという大金持ちの観光客。この地のワイン。異国風の家具。ネコなどの愛玩動物。どこかからこっそりと運んで来られたミイラまであった。
変わりどころとしては錬金術で作ったフラメル謹製の賢者の石などというものもあった。そいつが本物かどうかは俺は知らない。
この国にもあるレムリア兵の駐屯地にキャラバン護衛兵の半数を入れ、代わりに帰国予定の兵を入れる。帰りのキャラバンの護衛が今度の彼らの務めだ。国に帰れば駐屯手当と成功報酬を貰っての裕福な生活が待っている。どの兵も笑顔でダンダビュロスに乗り込んだ。
俺はここでキャラバンを離れることにした。商売もそろそろ飽きて来たからだ。
もちろん、俺一人で行動しようと言うのではない。レムリアからここまで一緒に来た皇室護衛官たち、つまり諜報員たちも一緒だ。それとレムリア私兵たちもぞろぞろと引き連れることになった。
ここまで来てようやく、例の異端の人物の消息が入って来た。
異端狩りの始まりである。
まず手始めとして俺はアテネに腰を落ち着けることにした。何よりも調査の拠点が必要だ。
キャラバンの会計士が儲けの中から俺の取り分である一割を置いていったので、適当に屋敷を買って、その中に金貨の入った大箱を積み上げた。大きな部屋から溢れそうになる金貨の世話をするために、この都市にあるレムリアの駐屯地から正直そうな商人を引き抜いて全てを任せた。
これでようやく俺は諜報活動に専念できる。
最初は広く思えたこの屋敷も、帝国の諜報員に兵たち、それと現地で雇いいれた案内人たちを加えると、ひどく手狭になってしまった。一日中かがり火を焚いて、まさに不夜城の様相を呈している。近所から苦情が来たが、俺は無視した。
そうこうしている内に、最初の情報が入った。
今夜、都市の公共広場で異端の者の演説会があるそうだ。
いよいよ俺の出番だと思うとようやく冒険に出た実感が湧いて来る。
この国の公共広場は街の一番広い道の交差点に作られている演説台とそれを取り囲むように配置されている半円形の座席で構成されている。囲いというものはなく、通行人でも外側に立って講演を聴取することが許されている。
レムリア人から見るとレムリア人はすぐに分かるが、どういうわけかギリシア人には両者の違いが分からないらしい。
そこで通行人に紛れ込ませて諜報員を十人ほど配置した。通りがかりの人間がふと気を惹かれて演説を聞いている。そんな風に偽装した。
俺は最前列に席を取った。煌びやかなマントを着て、宝石で指を飾り、逆に目立つようにした。高貴な外国の使節が招待されてという形に見てもらえれば上々だ。俺が目立てば目立つほど配置した諜報員には気が向かなくなる。
やがて講演開始の口上が告げられると、黒いローブを着た一人の男が壇上に立った。そいつは何かを喚き始めた。俺はワインを飲みながらそれを大人しく聞いていた。じきに男が何を言っているのかが分かって来た。
男の主張はこうだ。
大地は丸い。そして太陽の周りを廻っている。
あり得ない。
世界は無限に広がる平板な大地だ。そしてその周囲を太陽と月とアーモンデが回っているのは子供でも知っている。
地球が丸いなどという狂った考えをこの男はどこから得たのだろう?
さらに注意を集中して聞いてみた。
男が主張していたのは、海の向こうから船が近づくときはマストの先から現れるという現象だった。それは大地が丸みを帯びているためだと述べていた。男は石板にその絵を描き、大地が丸い場合はマストの先端から見えるということを説明していた。
だがここは学術を売り物にする街アテネだ。知恵の女神の名を冠したこの街で、こんなトンデモ理論が受け入れられるわけがない。
講演が終了した後で、諜報員たちに黒ローブの男の後をつけさせて、俺は自分の館に戻った。
その夜、調和通信機を使ってレムリアのアモデス賢者に連絡を取った。
調和通信機はレムリア調和魔術の産物だ。どれだけ距離が離れていようが映像で通信ができる。もちろんこいつの値段は恐ろしく高いし、レムリアでさえも数えるほどしか存在していないレア品だ。これ一つでダンダビュロスが数頭買えるぐらいの値段がする。
動き出すと調和通信機はアモデス賢者の幻を作り出した。当然向こうにも俺の姿が投影されているはずだ。
今日何があったのかを手短に話す。俺の話を大人しく聞いた後でアモデス賢者は話始めた。
「今まであやつらは密かに活動してきていたのだが、ついに表に現れたのか。となると計画は相当進行しておると考えねばならん」
「計画とは?」
「大地球状化計画と名付けておる。言葉通りにこの大地を丸くするつもりだ」
俺の目の焦点がぶれた。アモデス賢者は何を言っている?
アモデス賢者は俺の表情を見て取った。
「世界構築原理は知っているかな?」
「知りません」
「勉強不足だな」
「すみません」
仕方ないだろう。俺は象牙の塔に棲む賢者では無いんだ。それにアモデス賢者よりも賢い人間はこの世にはいない。いや、無限に広がる大地のどこかには彼より賢い人間がかならず一人はいるはずだが、二人はいないと断言できる。それぐらい、彼は賢い。
「世界構築原理とは簡単に言えば『世界はそこに住む人間の認識に合わせて変化する』ということだ。今我々は大地が平面であると知っているから大地は平面だが、大勢の人間が大地が球だと信じれば大地は球になる」
「わかりません」
俺の返事をアモデス賢者は無視した。実に賢い態度だ。
「正確に言えば知識階級の大勢がだな。普通の人間は大地が平面だろうが球状だろうが気にはしない。だから彼らの投票は中立に数えられる。つまるところ残りの知識階級がどう考えるかですべてが決まる。知識階級の大部分が大地は球状だと信じれば、世界はそうなる」
「大部分ってどのぐらいですか」
「一つのポリスにつき十人程度だな」
そんなに少なくて良いのか。俺は驚愕した。ということは一つの都市で本当に頭を働かせている人間は十人に満たないということか。それもびっくりだ。
「でもまだアテネだけです」
「そうでもない。カルトの連中はこれまでの秘密主義をかなぐり捨てて各地で一斉に活動を開始したようだ。すでにギリシア近辺の幾つもの地域から似たような報告が挙がっておる。やがてこの間違った知識が普及したときには世界に大変動が起きるだろう」
「でもまた大地が平面だと信じさせたら元に戻るのでしょう?」
「そうはならない。なぜなら平面の世界よりも球の世界の方が存在させる費用が安上がりだからだ。一度安い方に落ち着けば、二度と高い費用を払いたがらないものなのだ」
「誰が費用を払わないですって?」
「世界がだ」
俺の耳の穴からしゅっという音と共に蒸気が噴き出した感じがした。うう、賢者ってやつはこれだから。
しかし大変だ。どうしよう。世界が終わってしまう。でも慌てても仕方がない。
俺は頭を振り、この考えを追い払った。
「で、結局のところ、大地は平面なのですか球状なのですか」
「無論、平面だ」
「でも今日の講演では船のマストが先端から見え始めるのは大地が球状だからと説明していましたよ。実際そう見えるし」
「ごまかしだよ。いいかね」
こほんと一つ、アモデス賢者は咳をした。
「海にはいくつもの波が同時に存在している。大きな波ほど数が少なくなるが、その上にさらに小さな波が無数に重なりあっているのが海というものだ。さて、今その大きな大きな波の底に船が浮かんでいたとする。このとき陸地から見えるのは船のどこの部分だね」
俺はちょっと考えて答えを見つけ出した。窪地の底に船がいるなら、平地から見えるのは・・。
「マストの先端です。残りの部分は大きな波の下に隠れています」
「その通りだ。後は波が盛り上がるにつれて船の残りの部分も見えてくるようになる。つまりはその黒ローブの男は人間の誤解を招くように誘導して大地は丸いと信じさせようとしているのだ」
「大地が丸くなると何が起きるんです。我がレムリア帝国はどうなります?」
「そうだな」
アモデス賢者はしばらくぶつぶつと何かをつぶやいていた。
「ギリシアの地が最初の変動の出発点となる。そこを中心にして球に収まるように世界が切り取られるだろう。必要な重力係数を繰り込んで、世界の湾曲率に挿入する。それからあれとそれを足し合わせて、三乗根を作り出すと。
ギリシア周辺の土地とそうだな、レンの大地あたりまでが新しい丸い大地に取り込まれるのではないか」
「となるとレムリアは?」
「存在が許されない領域ということになる。このワシでもその結果がどうなるのかは正確には分からない」
大変だ。俺の故郷が消滅してしまう。
「お主の任務は極めて重大なものとなっておる。何としてもそやつらの正体を暴き出し、これ以上の活動を止めなくてはならん」
調和通信機が沈黙し、アモデス賢者の姿が消えた。
大変なことになったぞと俺は思った。責任の重さに押しつぶされそうだ。
5)追跡行
例の演説者を捕まえることはできなかったが、その足跡がメガラ・ポリスに向かっていることが分かった。
俺は配下のレムリア兵をかき集めると、急遽メガラ・ポリス目掛けて出発した。飛竜が使えたならばこの距離程度なら数刻で到着するのだが、残念ながらギリシアの気候では飛竜たちは病気になってしまう。そこでどうしてもこの地の乗り物を使わざるを得ないのだ。
四頭立ての馬車を何台も借り切り、レムリア護衛官の印を掲げ、あらゆる関所を止まることもなく突破した。
ギリシアはレムリアとの貿易は長く、一種の同盟関係にある。だからこういったときには相当な無理がきく。もっとも下手にこの馬車軍団を止めようとしたならばレムリア兵の火炎杖が物を言うことになっただろう。
メガラ・ポリスはドーリス人たちが作ったメガリス平野の中心都市である。まあここは言ってみればオリーブとブドウを主に生産する農業都市だ。ここが産出するオリーブ油とブドウ酒はレムリアとの重要な交易品ともなっている。
街の少し先は大きな港になっていて、いくつもの色とりどりの船が行き交っている。
先に走らせておいた伝令が街で一番大きな宿屋を抑えておいたお陰で、我々は着いたその場で諜報活動を始めることができた。
すぐに情報は集まり、ここの中央広場でも例の演説会が行われることが分かった。
これに間に合ったのは何という幸運。
広場に着いてみると、その中央に何か奇妙な機械が据えられていた。
枠組みの中にロープで大きな振り子が吊り下げられている。振り子は丸い形状をしていて重い金属でできているように見えた。錘の下側から細い棘が伸びていて、それが下に敷かれた砂を掻いている。
その横にあの黒ローブの男が立っていた。顔に道化の仮面を被っている。
滑稽な絵面。学問を論じる場で道化の仮面とは。
彼の周囲にはこの街の学者たちが椅子を並べて座っている。学者の弟子たちがその後ろに立っていて人垣を作っていた。
「このように」黒ローブが大声で叫ぶ。「振り子は地球の回転から独立して動くために、一日につき一回転します。これは振り子が回転しているのではなく大地が回転している証拠なのです。すなわち地球は丸く、自転することで見かけ上の太陽の出入りを作っているのです」
黒ローブの背後には大きな石板がおかれ、炭の欠片で丸い地球が描かれている。その地球は太陽の周りを回っていると説明されていた。
振り子は重々しく揺れ、砂に模様を描き続ける。
設置したのは半日ぐらい前か?
周囲の学者たちはお互いに頭を突き合わせて議論に熱中している。ということは大変に不味い。恐らく彼らは黒ローブの男の説明を受け入れかけている。
部下たちに合図して、広場を取り囲む。どちらにしろ、黒ローブを捕まえてしまえばこちらの勝ちだ。
全員が配置についたのを確認してから、合図を出した。
むくつけき男たちが広場の中央目掛けて一斉に飛び込んだ。学者たちとその取り巻きが大騒ぎをし、パニックになった群衆が逃げまどう。
二人の部下が黒ローブに跳びついた。黒ローブはその男たちの頭上に跳びあがると、聴衆の頭の上を踏みながらその手を逃れた。
ローブの裾から山羊の肢がちらりと見えて、俺は自分の眼を疑った。
黒ローブは次々に人々の頭を踏んづけて行くと、たちまちにして包囲の輪を越えて消えてしまった。
何という身の軽さ!
男の追跡は部下たちに任せて、俺は屋敷に戻った。
調和通信機を起動し、アモデス賢者を呼び出した。何が起きたかを詳細に説明してから尋ねてみた。
「大地が回転していないのなら、あの振り子はどうして回転するんです?」
「まったくお前という奴は大地力学の授業を真面目に受けていなかったのか」
アモデス賢者は一つ大きなため息をついた。
「太陽は無限の彼方で大地の回りを回転する。世界が周囲で回転していた場合、中心にある物体は逆方向への作用力を受けるのと等価になる。従ってその振り子の振動面は一日に一回転することになる。つまり大地の回転と天空の回転は相互に置換可能なのだ」
「では地動説と天動説はお互いに鏡映しということですか」
「そういうことになるな。だからそれだけではどちらが実像でどちらが虚像かは決定できない」
「そうか。実はどちらでも同じ現象となるものを、あいつは地動説の証拠として誘導しているのですね。そして地動説が成り立つのならば無限の大地論は嘘だと説明するつもりなのですね」
「そうだ」アモデス賢者は答えた。「そしてその結果、儂らの世界は歴史の中から消滅する」
どんどん問題が進行する。敵の狙いははっきりしているし、その手段も明確なのに、すべて後手後手に廻ってしまっている。
今のところポイントで大差が付けられているとも言える。
借り切った宿の大食堂の中を苛々と歩き回る。ときおり配下が飛び込んでくると短い報告を上げてまた飛び出して行く。
黒ローブの足取りは依然として掴めない。
侍従役の兵士が昼食の手配をして、大きなテーブルの上に料理を並べ始める。帰って来た密偵がそれをかき込むとまた次へと入れ替わる。
俺も歩き回るついでにヤマネの唐揚げを攫い取り、自分の口に押し込んだ。とにかく体が資本だ。今の内に食べるだけ食べておこう。
塩辛い物ばかり食べていたら喉がバカみたいに乾いて来たので、水で割ったワインをガブ飲みしていたら、いつの間にか寝てしまった。
その密偵が飛び込んで来たのは明け方だった。ついに黒ローブの足取りが掴めたらしい。
「船です!」密偵は叫んだ。「奴は船に乗り込んでいます」
「行き先は?」
「ナクソスです」
ナクソスはギリシア領の島だ。大きな島なのでそこそこの大きさの都市がある。
大急ぎで配下の者たちを集めて宿を飛び出した。背後に金貨の詰まった大箱を引き連れてだ。
くそっ。まだこの都市の売春街さえ訪れてもいないというのに。どうしてこんなに忙しい。冒険の楽しみも何もあったものじゃない。
メガラ湾の港につくと大声で訪ね回った。残念ながらナクソスへ廻る船はない。
目についたうちで一番大きな貿易船を見つけると、配下全員を引き連れて乗り込んだ。
「なんだなんだ」船の乗組員が騒ぐ。
じきに船長が現れた。一目で分かる。レムリア人だ。レムリア人の中にはこうして外地人に混じって生きることを選んだ者もいる。
相手に誰何される前に叫んだ。
「船主は?」
「このお人だが」船長が気圧されたように隣に立つ人物を指す。「お前はいったい」
レムリアの身分証をその眼の前に突き付ける。知る人ぞ知る金と宝石で飾られた王族の身分証だ。船長の目がぐりんと回った。船長に耳打ちされると船主の目もぐりんと回った。
「この船を買いたい。船員も込みでだ」
「ここはギリシアだぞ。乗組員は自由雇用契約だ」船主が抗議した。
「全員一年雇用保証。賃金は三倍。前払い」俺は言った。
「それが全部でどれだけ大きな金になるのか理解しているのかね?」
言葉をつっかえながら船主がかろうじて言った。
俺は背後に合図した。金貨の詰まった大箱が運ばれてくると、船主の前に重々しい地響きを立てて置かれる。山のような金貨を見てそこにいた向こう側の人間全員が目を剥いた。
「これで足りるか?」
6)大海原へ
船荷を大急ぎで放り出し、食料と水を大急ぎで積み込んだ。
ナクソス島にはレムリアの駐屯地は無いはずなので、後続のレムリア兵たちが追いついて来るのを苛々して待った。金貨の入った大箱の納まった部屋の周囲を船員たちがギラギラした目で歩いているのを見ると、レムリア兵無しでの出航は自殺行為に思えた。
この期間を使ってナクソス島について調べる。
ナクソス島は群島の中でも一番大きな島であり、豊かな農業と豊富な水の御蔭で貿易船の寄港地となっている。神殿があり、学問所もある。黒ローブの次の講演には絶好の場所だ。何より聴衆が多い。貿易都市の特徴で、文字の読み書きができる人間が多いのだ。
一番重要なのは、ここを経由されてしまうと黒ローブの追跡は不可能とは言わないが困難になることが予想されることだ。
ようやく追いついたレムリア兵を乗船させるとすぐに帆を上げて出航する。
穏やかな波、都合の良い季節風。船は飛ぶように進んだ。
やがて幾日かの行程の後にナクソス島が見えた。
完全に接岸するのを待たずに船から飛び降りる。後ろにレムリア兵を引き連れて港のど真ん中を走った。
何事が起きたのかと騒ぎになるなか、レムリアの旗を翻しながら俺たちは進んだ。
町の広場が見えた。そしてそこに予想通りに黒ローブがいた。
今度は大きなボードにロウ石で月の絵が描かれていた。その前に置かれているのは二つの球の模型だ。一つは大きく、一つはやや小さい。太陽に照らされた大きい方の球の影が小さい方の球に落ちる形になっている。
黒ローブが大きな声で叫んでいる。
「このように月食という現象は、地球の影が月に落ちているのが観測されることで生じます。すなわち、地球は丸い球なのであります」
アモデス賢者に聞くまでもなくこれなら俺も知っている。
月食は、天空を廻る闇の太陽アーモンデのせいだ。この目には見えない闇の太陽は常に太陽の対極として天空に存在し、力のバランスを保っている。その極性は太陽と月に関係づけられているために、星の光は遮らないが月の光は遮ってしまう。月の輝きは太陽の輝きが反映したものだからだ。
レムリアでは子供でも知っているこの科学を、ギリシアの人間は知らないように思えた。
「そいつを捕まえろ!」俺は叫んだ。
レムリア兵と密偵たちが突進すると、大混乱のステージの中へとなだれ込んだ。
黒ローブへと伸ばした手が宙を掴み、その頭の上をまたもや黒ローブが跳んだ。
ローブが翻り、伸びた角と山羊の足、それと逆棘のついた尻尾が顕わになる。だがどれも一瞬のことで、奴は恐るべき素早さで器用にも群衆の中を駆け抜けると、港の方へ逃げ出した。
「追え! 追え! 追え!」
俺は叫び、自らそれを実践した。目の前で右往左往する群衆を突き飛ばし、邪魔をしかけてきた街の警備兵を殴り倒した。
荒い息をつきながら港へと走り込むと、ちょうど奴は離岸しつつある船の上にいた。
「帰せ! 戻せ!」
叫んでは見たが無駄なことは分かっていた。
こちらも船に乗り込み、出航を急がせる。配下が半分戻って来た所で無理を言って船を出させた。なに、取り残された兵は後で迎えにくれば済むことだ。
後少しで奴に手が届く。
水平線ぎりぎりの所に奴の乗った船のマストが見える。船の残りの部分は視線の届かぬ波の下だ。
風よ吹け。波よ起これ。我が船を矢と変えよ。レムリアの神々よ。我が願いを聞き届けたまえ。
俺の祈りが通じたのか二つの船の距離は徐々に縮まり始めた。
「接近戦用意!」
部下たちに命じた。俺の声に応じて、レムリア兵たちが装飾付の剣を煌めかせる。黄金で縁取りされた鎧がずらりと並ぶ様が実に頼もしい。
「船長。こちらの船をあちらに接舷させろ!」
船がきしみを上げて突進する。
向こうの船が帆を下ろすと、船長らしき老齢の男が出て来てこちらに向けて怒鳴った。
「いったい何の用だ!」
「レムリア巡視隊だ!」俺は怒鳴った。「黒ローブの男を出せ!」
船が接舷した。ロープが投げられ、板が渡される。
「何のことだ?」と相手の船長。
「黒ローブの男が乗っただろう。どこだ?」
「前の船室だが、あんたがたは一体?」
この手の船は前は客室、後ろは貨物倉庫だ。
答えずに全員で突撃した。廊下に突入し、船室の扉を片っ端からけ破る。
商人風の男。びっくりしたような顔で見つめる貴族。抱き合っている男女。どれも違う。
一つの扉の向こうの客室の窓板が破られていて、そこを黒ローブの男が這い出すのが見えた。こちらが跳びつく前にするりと船外に這い出す。
「外だ!」
また全員が甲板にまろび出す。
「いたぞ!」誰かがマストを指さした。
帆を下したマストを伝って黒ローブがするすると上に登る。
「もう逃げられないぞ。お前が誰だかは知らないが、大人しく投降しろ」
俺は宣言した。レムリア兵が二人、剣を抜いてマストの根本に迫る。
「もう逃げたりはしないさ。おい、お前、ずいぶんとしつこかったが鬼ごっこもこれで終わりだ」
黒ローブはそう言うと、自らローブを脱ぎ捨てた。
真っ黒な体。醜い顔。長く伸びた角に、山羊の肢。逆棘のついた尻尾に、歪んだコウモリの羽が肩から生えている。
異形の存在。異界の怪物。
いくらローブで全身を隠しているとは言っても、今までだれもこれに気づかなかったとは信じられない。
「聞こえないか。もうすぐそこまで来ている」
そいつ、いや、それは言った。
「何がだ? いやそれよりお前は何だ?」
「俺かい? 俺は悪魔だ。これから兄弟と一緒にこの世界を支配するものだ」
「支配だと?」
「支配だよ。平面の世界はユートピアだ。どこまでも続く大地はいつでもそこに希望が待っていることを示している。だがそれはもうじき丸くなる。世界は地平線の彼方で繋がり、有限と化す」
うん、わけが分からない。謎かけがしたいなら賢者連中とやってくれ。
「それが支配とどう関係がある?」俺は尋ねた。
マストの周囲ではレムリア兵たちがじりじりと包囲を狭めている。
「球の世界ではあらゆるものが最後には尽きる。それは希望もまた同じ。希望無き世界こそ俺と俺の兄弟、つまり悪魔と神が支配する世界。人類は弱り、やがて主人の座から転落して俺たちの奴隷と化すであろう」
十分だ。俺は指を鳴らした。
「そこでいつまでも歌っていろ。こちらはこちらで任務を果たさせてもらう」
レムリア兵が火炎杖の狙いをつけた。
そのときだ。船が大きく揺れた。
バランスを崩して倒れた俺の上をレムリア兵が転がっていき舷側から放り出された。悲鳴が長く続き、ふつりと途絶える。
青空を白い光が引き裂いた。何か大きな力が天空を歪めている。
「ははははははは。ついに始まったぞ」悪魔が吠えた。
船よりも高い大波が沸き上がり、俺たちの上に落ちかかって来た。
7)大変動
大地が揺れた。大海が揺れた。大空が割れた。
世界そのものにヒビが入った。
俺たちの乗った船は木の葉のように揺れ、大波に翻弄された。船長が叫び、航海長が叫び、操舵手が叫び、水夫が悲鳴を上げた。
緊急の際に使われるあらゆる装具が持ちだされ、高価な魔法が惜しげもなく放たれた。
そのどれもが無駄だった。
今、俺たちの目の前で起きているのは、世界そのものの変貌。人間の営みなど意にも介さない何か大きくて重いものが転がり落ちる姿だった。
海が割れ、水平線が盛り上がる。空のどこかで存在理由を失った黒い何かが断末魔の悲鳴を上げて消滅する。
視野に映る無限の彼方のどこかで、水平線と地平線が交わり、世界を形作る何か大事なものが歪んだ。
空から伸びた亀裂は海と大地へと渡り、それを粉砕し、そして繋ぎ合わせた。
予言の時が成就し、その真の姿を現す。
俺が乗った船は海の底へと引きずり込まれ、海水が俺の喉へと殺到すると、俺は速やかに意識を失った。
目が覚めたとき、俺は自分の船の上に転がされていた。
レムリア人船長の心配そうな顔が上から覗き込んでいる。
「息を吹き返したぞ」
ほっとしたような声で言った。
起き上がって周囲を見回す。穏やかな海。雲一つない青い空。
「あれは夢か」思わず呟きが漏れた。
「夢ではありません」船長が答えた。「世界が一度壊れたんです。そうとしか言えません。こちらの船は幸運でしたが、あちらの船は後かたも無く消えました。海の上に浮かんでいるあなたを見つけたのは奇跡ですよ。いったい世界に何が起きたんでしょう」
その答えを俺は知っている。
世界は丸くなったのだ。そう、もはや、この世界は平らでは無い。
調和通信機はもう作動しなかった。ここ、世界の表側と、あちら、世界の裏側はもはや繋がってはいない。
やがて俺たちの船は名も知らぬ港を見つけ、上陸した。水夫の半分が船を逃げ出し、後釜が見つからなかったので、俺たちは今度はあてもない陸地の旅をすることになった。
驚くべきことにあの大変動では、こちらでは誰ひとり死んでいないことが判った。
消え去った人々もきっと死んではいない。ただ、どこかへ行ってしまっただけなのだ。とすれば海に沈んだあの船も本当に沈んだのではなく、取り残された世界の側に送り込まれたということになる。
哀れなレムリア兵たちが向こうに帰れたことを心の底から願った。
とは言え、陸地の地図は大きく変わった。
隣の村があった場所にはただの荒れ果てた沼地が広がり、隣の街があった場所には、見知らぬ顔の見知らぬ人々が住む要塞が建っていたりもした。
こうなればもはや悪魔を追うどころではない。それにこれが奴の目論見だったとしたら、もう追跡を続ける意味は無い。
追いかけっこは奴の勝ちだ。
俺たちはレムリアを探して旅をした。北へ向かって旅をし、西へ向かって旅をし、南に向かって旅をした、それでもレムリアが見つからないので、意を決して、東へ向かって旅をし続けた。
馬を使って旅をした。奴隷の担ぐ輿に乗って旅をした。大海原に着くと、再び船に乗って旅をした。どこまでもどこまでも昇る太陽目掛けて旅をした。
それでもレムリアは見つからなかった。
ほんのときたま、レムリアから来た貿易品を見つけることがあり、その来歴を追ったこともある。
ほんのときたま、レムリアへの道を知っているという案内人を見つけて一緒に旅をした。結局は道に迷って終わったが。
霧の中に懐かしきレムリアの塔の姿を見て、三日も荒野を彷徨ったこともある。
やがてそのようなことも稀になり、辿りついた街の人々の中にレムリア人を見つけることすら無くなった。レムリアの話をする者もだんだんといなくなり、ある日それが遠い時代の遠い国の伝説として語られていることに気がついた。
レムリアだけではない。
遥か彼方の滅んだ国アトランティス。旧き神々が目覚める日を待ってひたすら眠ると言うレンの乾いた大地。砂漠の中の楽園アスウェル。手を伸ばすだけでいくらでも手に入る豊かな果実と素晴らしき夢を見せるブラックロータスに満ちたルトスの国。
どれもが伝説やおとぎ話と化し、実在から非実在へと姿を変えて消えていった。
この世界は最初からそのようなものが無かったかのように振舞おうとしている。平面の世界の記憶は誤った歴史として忘れ去ろうとしている。それが分かった。
東へ、東へと進んでいた俺たちは、ある日、見覚えのある景色に出くわした。ついにレムリアへの道を見出したのかと思ったのもつかの間、そこがあの大変動のとき、最初に辿りついた港であることに気が付き、俺たちは絶望した。
最後まで一緒についてきていたレムリア人の船長が言った。
「賢者たちの言うことが正しいなら、つまり俺たちは丸くなっちまった大地を一周したということだな」
俺は答えなかった。船長の指摘が正しいと判ったからだ。
「もうレムリアは、俺たちの故郷はどこにも無いんだ。世界が丸く畳まれたときに、その外側へ零れおちてしまったんだ」
船長は嘆いた。
きっとレムリアは世界のどこかにある。大地のどこかに引っかかって、危うく儚く揺れながら、それでも壮麗で華美なその運命を歩み続けているに違いない。レムリアは俺たちのいるここ、丸い地球のどこかの裏側にあり、そこには普通の手段では辿りつくことは決してできはしない。
俺は泣いた。船長も泣いた。他の皆も釣られて泣いた。
そしてそれを境に誰もが散り散りとなり消え去った。船長もこの世界にいるはずの家族を探すといって立ち去った。
見知らぬ人々の中で生活するよりはと、いまや独りとなった俺は荒野に入り、そこに居を構えた。小さな小屋を建て、そのてっぺんにレムリアの旗を飾った。
幾つかの品物は、無くならないように小屋の前の地面に埋めた。残ったのはレムリアの金貨が数枚。レムリア風の装飾のついた短剣。それと小さな羅針盤が一つ。最後にもう動かなくなった調和通信機。
世界には、もう探検すべき場所など無い。
この有限でちっぽけな世界には、無限の大地がもたらす無限の贈り物はもう無い。ここにあるのは息のつまるような狭さと枯渇していく資源。ただそれだけ。
文明は衰退した。ときたま訪れる旅人たちが教えてくれる話から、世界が色褪せ、窒息しかけていることが聞きとれた。新しい地を開拓する代わりに、人々はたがいの懐から盗みあうしか手が無いのだ。
これがあの悪魔の狙いだったのなら、それは成功した。この絶望に満ちた狭い世界の中では、神に縋ることなしではとても生きてはいけまい。あるいは悪魔にか。
そして俺はまだ夜毎のことに夢見るのだ。あの古き麗しい美しきレムリアの夢を。
夢だけはまだ広大無辺なのだから。