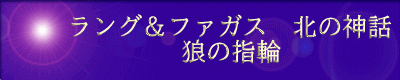
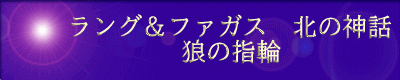
大いなる森の予言者たる老婆は、泉の前に立った。
暗い夜であった。
半分に欠けた月が、泉の水面に浮かんでいる。
水草の類は一切生えてはいない、静かなそしてどこまでも澄んだ泉である。真っ白な砂に囲まれて、その涼しげな外観をくずしたことさえない。
ミーミルの泉とは決して一つの泉だけを示す言葉ではない。ミッドガルド界全域に伸びる世界樹の根によりつながれた泉のネットワークなのだ。それらの泉の中でも、大いなる森の老婆が管理する泉は、最大を誇るものの一つであった。
老婆の背後で小さな灯を浮かべている家の中から、パット少女が遊んでいる声が聞こえた。だがそれでも、パットは老婆の邪魔をしようとはしない。この神聖な夜の儀式を乱してはならないと知っているのだ。
風もないのに一瞬だけ水面が揺らぎ、半月の姿が歪んだ。分裂した月の姿の間から、透き通った水の層を通して、何か泉に相応しからざる物が底に沈んでいるのが見えた。
眼窩より引き抜かれた眼球が一つ。それは周囲の水の中を見通そうとするかのように、自ら動いていた。
半月の姿が戻り、それをまたもや覆い隠す。
続いて泉の水面に無数の顔が浮かんだ。どれも例外なく老婆だ。それも恐ろしく歳を取っている。
その一つが、歯の無い口をむき出しにすると、もごもごと喋る。泉の上を声が漂った。
「まったくパットは落ち着きがないねえ」
他の顔の一つがそれに答えた。
「仕方ないさ。あの娘はまだ幼い。小人族の血が入っているのだから。寿命が長い分だけ、成長も遅いものさ」
「しかし、少しはたしなみというものを教えないと、名門のアリスタナル家ではやっていけないぞえ。たとえそれが運命の女神たちの望みとは言え、実際の生活での苦しみがやわらぐものではないものだぞえ」
一番若く見える老婆が指摘した。
大いなる森の老婆は、杖を握った手をゆっくりと振って、泉に浮かぶ顔すべての注意を集めた。
「まあ、みなの衆。パットの教育はわしにまかせるがよい。心配せいでも、あの子はうまくやるよ。それよりも何よりも、今日の会合はもっと先に論じることがあるじゃろう」
全員が口々に同意のつぶやきをもらした。その中の一人が思い出したように言う。
「そうそう。こちらの泉は先日のことだが、奇妙な示唆を行ったよ。ファガスの実験は失敗し、世界は狼に食われると」
この発言に、大いなる森の老婆の額に、さらなる皺が寄った。
「他の衆はどうだえ。ミーミルの泉たちの動きに変化は?」
ざわざわと顔たちが会話を繰り返す。
「ふん。なるほど。他はどれも同じ結果かえ。となると、狼が生き残る予言は、極めてまれな結果ということになる」
「それでも可能性は残るわな」老婆の一人が指摘した。
「しかし本当にこんな方法でしか世界は救えないのかい。一度世界を滅ぼすことでしか、それを救うことができないとは、なんとも変な話だ」
「しかたないわな」大いなる森の老婆がため息をついた。
「狼の力は強い。絶滅魔法戦争を無傷で生き延びたのは、あやつだけだ。封印されていたがゆえに、逆に生き延びるとは。中途半端な攻撃では、あやつを痛めつけることはできはしないさ。いかに知識と予言を操るあたしらでも、できるのはこれが精一杯」
「そういえば、ウルフェスは餌に食らいついたようだね」顔の一つが言った。
「ウルフェス?」顔の一つが聞き返す。
「ザニンガムのミドルネームだよ」
「ああ。あの石頭の男かい」
「やつには肝心なときのラングの動きを抑えてもらわなきゃね」
「どうせなら、ラングをファガスから引離したらどうだえ?」
「それができりゃ苦労せんわな。女神たちは二人を引離すことを望んではおらぬ」
「まあ、ファガスにドラウプニルを作るように仕向けたのは、驚くほどうまく行ったわい」
「一応、予言者の勤めとして警告はしたんだよ」大いなる森の老婆は言った。「予想通り逆効果だったけどね」
「ありゃあ、わたしたちが何もしなくても、ひょっとすると自分から作ったね」
全員が自分たちだけにわかる冗談で大笑いをした。泉の表面が揺らぎ、通信が乱れ始める。
「おっとっと」一人が慌てて泉をなだめようとした。
「まあ、今回のことについてはパットにも一口乗ってもらうことになるがね」
大いなる森の老婆は、そうつぶやくと、閉会の言葉を唱えた。
「創造者ライドの意思により、この世界を守る」
全員が復唱した。
「創造者ライドの意思により、この世界を守る」
魔法が消えた。泉の水面に細波が立ち、顔のすべてを消し去った。
波紋が広がり、また戻る。
一瞬の静寂。大いなる森の老婆は、水の底から、またたくこともできない瞳が自分を見つめていることを知った。
「ふん。いま見たことを、ご主人のオーディンに注進したいのかい。あいにくだね。あんたはそこから出れないんだよ。あんたのご主人自らが泉に捧げた物なんだからね。そこであたしたちが、世界を救うさまを見物しているがいいよ」
大いなる森の老婆は、泉に背を向けると、家へと向かった。
寒いという時期ではなかったが、これほどの老齢ともなると夜風は体に悪い。
泉の中では、満天の星空を見つめて、目玉が一つ、自分の時間を過ごしていた。