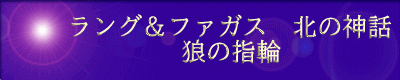
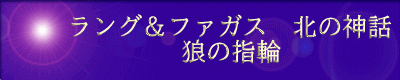
「まったく今回は危なかった」
ビールを一気に喉に流しこみ、一息ついたという感じで、エストリッジ教授は笑い顔をみせた。
「ラング。それに、ファガス。お前たちの騒動を見ていると、寿命が縮んでしまうぞ。これならばまだ、魔法遺跡の発掘現場で魔法兵と戦っていたほうが気が楽だ」
ここはファガスの家の中庭だ。テーブルの上には、バイスターが腕によりをかけて作ったご馳走の残骸がうず高く積まれている。
「あらためて感謝いたします。エストリッジ教授」ラングは謝辞を述べた。
「お師匠さまが、手品が上手だとは知らなかった」とはファガス。
エストリッジ教授は頷いた。
「ある意味ではそうなのだよ。一つの物事には無数の真実がある。わたしはその真実の一部を取りだして、観客にみせただけなのだ。彼らが欲しい姿にしてな」
「しかし、わたしたちは確実に死刑にされると思っていました」ラングは身を屈めると言った。人間族相手に話をするのは、単純に高さの問題から、存外に大変なのだ。
「それに教授が説明した内容でも、わたしたちを死刑にするのは十分だったように思います。どうしてギルド長たちはそうしなかったのでしょう?」
「おいおい、ラング、きみの言葉を聞いていると、死刑にされなかったのが残念なように聞こえるぞ」笑いながらそう答えると、エストリッジ教授は真面目な顔になった。
「なに、簡単なことさ。ラング。彼らは別に死刑が欲しかったわけじゃないからさ。
よく考えてご覧。ギルド長たちが欲しがっていたのは、今回の事件の原因が魔術師ギルドにはないという御墨付きだったのさ。そして王国側が欲しがっていたのは、今回の騒ぎに対する報復と、それが二度と起きないという保証だった。
たいていの人々は、実は真実なんか欲しがっていない。彼らが欲しがっているのは、真実のように見える、自分たちに都合の良い主張。それだけだ。
わたしはそれを彼らに与えたのだ。受け入れないわけがないだろう」
ラングは押し黙った。エストリッジ教授の言葉を考えているのだ。
「結果として、フェンリル教徒が犠牲になったわけですね?」そう言ったのはベスだ。
「構わないよ。わたしは」エストリッジ教授は冷たく言い放った。
「宗教とは、それに触れた人間の魂を癒し、苦しみを取り除くものでなくてはいけない。それが存在するだけで、周りの者の苦痛が増すようなものは、わたしは宗教とは認めない。フェンリル教徒は宗教と名前をつけたただの破滅願望の集団にすぎなかった。彼らを犠牲にすることには、わたしの心は痛まない。可愛い弟子たちを救うためなら、なんでもやるさ」
可愛いと表現されて、ラングとファガスはおそろしく居心地の悪い感覚を味わった。そんな二人を横目で見てから、エストリッジ教授は付け加えた。
「まあ、しかしそれも、わたしへの連絡が間に合えばこその話だ。ファガス。きみの執事によく礼を言うのだな」
テーブルの上を手早く片付けながら、バイスターは会釈をしてみせた。
「今度ばかりは間に合わないかと、このバイスター、肝を冷やしましたとも。本当のお手柄はパットさまです。ファガス坊ちゃまが出先からさらわれるところを目撃していたのですよ。それで、わたくしめに伝えに来たのです。ベスさまに尋ねてみると、ラングさまも行方不明とのこと。これは何かあったなと、アリスタナル家の調査機関を総動員してみたのでございますよ」
エストリッジ教授が後をついだ。
「わたしに連絡したのはベスさ。ちょうど発掘も終わり帰途についていたときだ。それで何が起きたのか推測して見ると、どうも魔術師調査局が怪しい。
知っていたかね? 魔術師ギルドの本部周辺に戒厳令が敷かれていたのを。
何ともまずいやり方だ。これから重大なことが起きますよと周囲に通知するようなものだ。まあ、お役所仕事なんて、いつでもそんなものだが」
「しかしそれは変だな。パット。お前はどこでおれのことを見ていたんだ?」
ファガスは、横に座りこんでお皿をなめていたパット少女に尋ねた。
「それは、ひ・み・つ」パット少女はソースだらけの舌を突き出して答えた。
バイスターの手が伸び、少女の手の中の皿を素早く奪い取る。
「あん! バイスター、何すんの」
「パットさま。すぐにデザートをお持ちいたします。それまでご辛抱ください」
バイスターは忍耐強く言った。
「でもトランス審判師はいったいどうやってごまかしたんです?」質問したのはラングだ。
「ごまかしてなんかいないよ。よくわたしの質問を思い出してみなさい」
エストリッジ教授は指を一本立ててみせた。
「問題の一番。二人がいなければフェンリル狼は目覚めなかったのか。答えは、いいえ、だ。
何もしなくてもいつかはフェンリル狼は封印を逃れて覚醒する。二人がいなくてもそれが起きたということと、二人がそれを引き起こしたということは、実は深い関連性がない主張なのだ。泥棒というものは他人の家に勝手に入りこむ。それを止める手段はない。しかし、だからと言って、泥棒に罪がないとはいえないのが本当のところだ」
次の指を立てると、エストリッジ教授は続けた。
「問題の二番。フェンリル狼は事件に関っているのか? 答えは、はい、だ。
だが、今回の事件に関っているとはどの程度のことを言うのか。ベスもパットも、あるいはトバリの街の住人でさえも、多少は今回の事件に関っているのだ。魔力消失により被害を受けた人々はすべて今回の事件に関っていると言える。
問題の三番。フェンリル狼は魔力を食うことができるか? もちろん、できる。
しかし諸君も知っている通りに、今回の事件ではフェンリル狼は魔力を食っていない。逆にドラウプニルの指輪に食われた側だ。だがこの質問を聞いた人には、狼が魔力を食ってしまったことが事実であるかのように思われるのだ」
胸の上で手を組むと、エストリッジ教授は椅子に背をもたれかけた。
「人はみな、壁に開いた穴から向こうを覗きこもうとしているような存在だ。壁に開ける穴の位置を調節してやれば、事実とは違うまったく別のものを見せることができる。転がっている石が見えるように穴を開ければ、壁の向こうは岩場だと錯覚するだろう。木だけが見えるように穴を開ければ、壁の向こうは森だと錯覚する。向こうに見えるものが自分の見たいものならば、もうそれだけで事物の真偽などどうでもよくなってしまう。
あの法廷での、トランス審判師の答えのほうは、どれも真実だ。ただし、質問のほうは微妙に論点をずらしてある。決して真実を真っ向から切りこむことなく、その答えを聞いた人間が、こちらの誘導した真実を想定するようにしてある。
これがトランス審判師を使うときの問題点なのだ。
答えは真実だが、質問は完全な真実ではない。この欠点を補う目的で、トランス審判質問師という職業が存在する。今回の法廷は、専門の質問師を欠いた時点で、事実とはほど遠いものとなることが保証されていたのさ」
「闇のスボークも杜撰なことをしたものですね」ラングはやや呆れた口調で言った。
「いやいや、彼の責任ではないさ」エストリッジ教授はにやにやと笑った。
デザートの皿を持って戻って来ていたバイスターは、表情を崩さずに答えた。
「あの周辺に居住する審判質問師を一人残らず休暇に出すようにと、エストリッジさまから依頼があったときは、奇妙に思ったものです。坊ちゃまはお怒りになるかもしれませんが、アリスタナル家の力を少々お借りいたしました。大奥さまからは、救出のために私設軍を投入してもよいと言われていたのですが、これ以上、問題を大きくするのはどうかと思いまして」
「それで正解だよ。バイスター」ラングは静かに言った。「アリスタナル家と魔術師ギルドの全面戦争なんて、フェンリル狼が目覚めるよりも、まだ悪い」
「そうそう、そのフェンリル狼のことなんだが」エストリッジ教授は椅子から身を起こした。
「今度の遺跡発掘で面白いことがわかった。遺跡の記録の中に、フェンリル狼をつなぐ魔法の封印の話が出ていたことは、すでに話したな。調べたところ、この封印にはある種の限界があると述べられていることがわかった。フェンリル狼が月の魔力を長い間に渡って食っていたのはそのためなんだ。十分に魔力を貯えて成長すれば、フェンリル狼は封印を破壊できる。記録に残っていたのは、フェンリル狼が封印を破壊する予想時間だった」
「フェンリル狼が放たれる」ラングがつぶやいた。「何とも恐ろしいことだ。で、教授。それはいつなんです?」
「当ててみなさい」茶目っけたっぷりの表情で、エストリッジ教授は言った。
「千年後」ファガスが言った。エストリッジ教授は否定のジェスチャーをして見せる。
「もっと短い」
「百年後」ラングが言う。これも間違い。
「十年後」とはベス。
「まさか・・一年後」ラングが真剣な顔でつぶやく。
「ええい、明日だ」ファガスが叫んだ。
エストリッジ教授は首を横に振った。それから夜空に上る月を見つめた。
頭上に輝く月は金色から、元の落ち着き冴え渡った銀色に戻っている。
「答えを教えてあげよう」上を見上げたままで、エストリッジ教授は言った。
「魔法遺跡の記録に書かれていた計算内容は恐ろしく正確だ。それにフェンリル教徒が打ち上げていた供物の量を補正してみたところ、予測されたフェンリルの解放は今夜。誤差は三日前後だ」
全員の視線が月に集中した。
「おっと、勘違いしてはいけないよ」エストリッジ教授は付け加えた。
「すでに危機は去った。今回の事件で、最終魔法兵器であるドラウプニルの指輪は、フェンリル狼が蓄積していたすべての魔力を吸い尽くした。いわば、フェンリルは嘔吐剤を飲まされたようなものだな。月の上に残された金の指輪に関しては、フェンリル狼がもう平らげてしまったようだが、それだけでは絶対的に力が足りないはずだ」
「すると狼の解放は?」ラングが恐る恐るといった調子で尋ねた。
「さあね。千年先か、ニ千年先か、いずれにしろ遥かな先のことになるだろう。どんな気分だね? ラング? ファガス? きみたちは世界を狼の顎から救い上げたのだ」
「わお」ファガスが感嘆の声を上げた。
「誰にも言うわけにはいかない」ラングが釘を刺した。「おれたちがあの大騒ぎを起こしたと知れれば、世界を救ったかどうかに関りなく、私刑にされるぞ」
「まあ、そういうわけだ」エストリッジ教授は肯定した。
「しっ!」ベスが鋭く制止した。「誰か来ます」
森の中から、腰の曲がった老婆が杖を突きながら現れた。背後では狼の吠え声。森番のフェラリオだ。
「泉の予言の老婆だ。ピーの育て親だよ」ファガスが言った。
老婆は近づいて来ると、背中を伸ばして、腰を軽く叩いた。
「大いなる森の老婆と呼んで欲しいね。ファガス。言葉は正確に使うものだよ」
「今夜は何のご用で?」ぶすりとファガスは尋ねた。
「もちろん、パットを迎えに来たのさ。幼い子供を夜の森で遊ばせるのはよくないからね」
老婆は手を伸ばすと、椅子の上で寝ている少女の肩を揺さぶった。
「ほら、パット。帰るよ」
バイスターは手際良くデザートの一部を包むと、眠たげに目をこすっているパット少女の手のなかに押しこんだ。それを見て、老婆はつぶやいた。
「やれやれ、この娘がじきに虫歯になることは予言するまでもないね。まあでも、バイスターとかいったね。礼を言うよ。さあ、パット、おいで」
それから老婆は、ファガスとラングのほうに向き直った。
「そうそう、忘れるところだった。いつもパットの面倒を見てくれている礼に、あんたたちに泉の予言を告げてやろう。
まずはラング、あんたからだ。
『己を映す鏡を見つけよ』
それはあんたのすぐそばにあるんだ。踏んづけて割ってしまう前に、それを拾い上げたほうがいいね。そうしないと、ザニンガムのように自分の本当の姿がわからなくなる。
それにファガス。あんたにはこうだ。
『小さいは大きい、大きいは小さい』
この意味がわかる頃には、あんたも少しはましになるだろう。
ベス。あんたには言うことはないね。
『正しいとは思わず、正しい道を歩む』
あんたは賢い女だよ。
最期にバイスター。あんたにはこの予言を上げよう。
『旅はいまだ終わらず』
苦労はするだろうね。でも、それは報われる苦労だよ。
さて、長居をしてしまったようだね。パットがまた眠りこむ前に、引き上げるとしよう」
エストリッジ教授が椅子から立ち上がった。
「では森の外れまでお送りしましょう。このごろは何かと物騒でしてな。さあ、大いなる森の老婆どの」
エストリッジ教授は身を屈めると、パットを背中におぶさった。たちまちにして、またもやパットはその背中の上で眠りに落ちる。
三人が森の中に消えるのを見送ってから、ファガスが肩をすくめた。
「お師匠さまが、あんな老婆が趣味だとは知らなかったなあ」
「こら、ファガス。ちょいと言い過ぎだぞ」ラングがたしなめた。
「予言か。小さいは大きいってどういう意味だ?」ファガスがつぶやいた。
「実際にそれが成就されるまで、予言の意味というのはわからないものなのだ」ラングはため息をついた。
森の中の小道を歩きながら、エストリッジ教授は含み笑いをもらした。その背中の上で眠りこんでいるパットが身じろぎをする。
「さてさて、ここらで、お別れするとしようか。大いなる森の老婆よ」
「そうだね。予言の時は過ぎたようだし。パットも死ななくてすんだ」
「迎えに来る途中で何をしたのか、できればこのわたしにもそっと教えてくれないかな?」
「なに、簡単なことさ。パットを殺す予定だった、ちょっとした悪漢を退治したのさ。ホーバートって名前だったかな。今回の大騒ぎの原因がフェンリル教徒の仕業であるとの噂を、魔術師ギルドが流したせいだね。その報復だよ」
「半分の真実」エストリッジ教授はつぶやいた。すべてを知っているぞという色が、その瞳には浮かんでいる。
「半分は謎」大いなる森の老婆は言葉をつないだ。「それでいいんだよ。丸ごと一つぶんの真実は、人の身には耐えがたい」
「ミーミルの泉の秘密もそうなのかな?」エストリッジ教授は背中の上の少女を振り返った。「この子もやがては、その秘密を負うことになる?」
「誰かがやらなくちゃいけないことなんだよ。それがどんなに大変な未来でも、誰かがしっかりと見張っていないと」
「運命の女神たち。ノルンが見張っているさ」鋭くエストリッジ教授は言った。
「ノルンたちは、ただ運命を紡ぐだけさ。その結果がどうなるのか、気にもしていない。彼女たちがやるのは糸を紡ぐだけで、その糸を織るのは世界樹に住むすべての生物が自分でやることなのさ」
大いなる森の老婆は答えると、音のした背後の森を振り返った。
赤緑青茶の色鮮やかな生物が藪から這いだして来た。無数の蛇が形作る巨大な玉。
蛇玉だ。
それは自分から生えた無数の蛇の頭を使って周囲の大気の臭いを嗅ぎ取ると、ふたたび森の中へ鈍い動きで這いずりこんだ。
「見てごらん」大いなる森の老婆は蛇玉の消えた辺りを示した。
「あれが、あたしたち、人間の姿そのものだよ。個々の人間はそれぞれ自分勝手に生きていながらも、その実、大いなる意思に導かれて生きている。あたしたち、泉の予言者は少しでもそんな未来の先を見通そうと努力しているのさ」
エストリッジ教授は老婆の方に向き直った。
「その努力の結果が今回のこれかね? もう少しで世界が滅んでしまうところだった」
「しかたないことさ。もうちょっと時間と力があったら、何か別の手段を見つけただろうけどね。なにぶん、フェンリル狼は別物だ。あれは創造者ライドがこの世界に来る前から存在していた怪物だからね。あたしたちの手には余る代物なんだよ」
「だが、そういった努力のすべてが、この世界に運命づけられているラグナロクの日を引き寄せる。予言は広がれば広がるほど、自己実現の能力を発揮するものなのだぞ。そういった意味では、わたしは予言の泉の存在には深い疑問を持っていると、言わざるをえないな」
大いなる森の老婆は、じっとエストリッジ教授の瞳を見つめた。それから深いため息をつくと、言葉を紡いだ。
「きっと創造者ライドには何か考えがあったのだろうよ。泉は予言を通じて世界を軌道に乗せ、あんたは黄昏の力を通じて世界の中に均衡を作りだす。その先に理想郷が出現するのか、それとも世界の破滅が待っているのか。その答えはまだどこにも出ていないんだから。
あんたには言うまでもないことだろうけどさ。ラングとファガスからは目を離すんじゃないよ。あの二人の運命の糸には何か特別なものがあるんだ。あたしはそう思う」
エストリッジ教授は頷いた。
「その点では、わたしも同意見だな」
大いなる森の老婆は言った。
「さて、パットを起こして、家に急ぐとするかね。歳を取ると、夜更かしはきついんだよ。泉の秘密は誰にも言わないでおくれ。二つの顔を持つ男よ。そうそう、あの魔術法廷での摺り代わりは見事だったね。認証魔法を使うときは本物。その後は偽者とはね」
それに答えた声は、エストリッジ教授の声であり、全く非なるものでもあった。
「そちらも誰にも言わないで欲しいものだな。大いなる森の老婆よ」
老婆はまったくひるまなかった。
「お互いさまにね。この世の中は真実よりは秘密のほうが多いものなのさ」
むずかるパットを起こし、地面に立たせると、その手を引く。
老婆は振り返らなかった。
エストリッジ教授が森から出て、ファガスの家に戻ると、そこは大騒ぎの真っ最中だった。ラングとファガスが何かをめぐってつかみ合いをしている。
「いったい何が起きたんだ?」
エストリッジ教授は、二人の争いを見つめているバイスターに尋ねた。
「金属の球でございますよ。エストリッジさま。ファガス坊ちゃまがそれを分解しようとしまして、それを止めさせようと、ラングさまが取ろうとなされているのです」
「坊ちゃまという言い方をやめろ! バイスター」
ラングの手の下を素早くかいくぐりながら、ファガスが叫ぶ。それに負けじと、ラングが叫ぶ。
「ファガス。それを教授に返すんだ。だいたい、どうしてお前がそれを持っているんだ?」
「まて、ラング。その手をどけろ。ちょっとだけ、これを分解して、中身を見るんだ。いいアイデアがあるんだ。ラング! すごい儲け話だぞ」
「わたしは信じない!」ラングは叫んだ。
またもや取っ組み合いの大喧嘩となる。ラングは太い腕を振り回し、なんとかファガスを捕まえようとしている。ファガスはラングの腕を素早く這い上ると、するりとその背中に回りこむ。
まるでじゃれあっているかのような二人を見ながら、エストリッジ教授は腰に手を当てた。
「やれやれ。なあ、バイスター」
「なんでしょうか? エストリッジさま」
テーブルを片付けながら、執事のバイスターは聞き返した。
「こいつらは、きっと、またやるぞ」エストリッジ教授は断言した。
「それはもう」バイスターは静かな笑みを浮かべた。
「賭けてもよろしゅうございますとも」