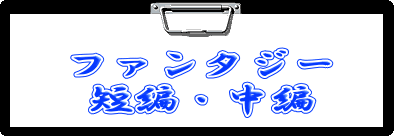
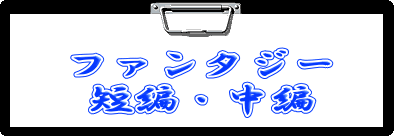
7)
見た目は冷静に見えるがアンドレア・V・ノーラスは怒り狂っていた。だがそこまで愚かではないので激発は抑えていた。
だから背後の壁際に積み上げてある瀕死の人狼たちも殺さなかった。ここで彼らを殺せば二度と人狼傭兵は雇えなくなる。吸血鬼の護衛に人狼を使うことにはそこまでのメリットがある。
頭の中でダークを百回は殺した。あらゆる拷問を与え、悲鳴を聞き、命乞いをさせる想像をするのに忙しかったので、背後の人狼の血に染まった壁の上に小さな目玉がつけられているのには気づかなかった。それには魔法偽装が掛けられていたが、冷静に注意深く観察していればあるいは見つけることもできたかもしれない。
盗聴不可能な特殊回線の携帯電話のベルが鳴った。待ち望んでいたモーリスからの電話だ。
ノーラスは携帯電話を取り上げた。幾重にも張られた魔法の網が通信回線を保護する。
「俺だ。ああ、早く言え。どこだ? いつ?
よし、こちらの人数は三人だ。それは譲れない。俺と護衛一人、それと魔導士が一人だ。当たり前だろう。魔導具が本物かどうか調べる必要があるからな。そうだ。どのみちお前は条件を呑むしかない。それとも何か? お前の元の女王さまのところにそいつを持っていくのか?
さぞや歓迎して貰えるだろうさ」
しばらくノーラスは携帯電話と言い合いをしていたが、最後には合意し、携帯電話を置いた。
モーリスが指示してきたのはバッテリー・パークに朝の十一時だ。
モーリスめ考えたなとノーラスは思った。
高位の吸血鬼は耐性があり強い太陽光線の下でも活動はできる。だが魅了を始めとする吸血鬼の権能のほとんどは使えない。太陽の光で灰になるのを防ぐのに手いっぱいで権能を使う余裕がないのだ。おまけに水辺の近くだ。いざとなればモーリスは川を泳いでの逃走を試みることはできる。吸血鬼は流れる水を渡ることはできない。だからコウモリに変身できない以上、モーリスを追いかける手段はない。
慎重な男だ。もしかしたら吸血侍従にしても損はないかもしれないとも思った。
これから始まるだろうリビア派閥との戦争において役に立つかもしれない。少なくとも吸血鬼である以外に取り柄のないボンクラ配下よりは。
コツコツと指でテーブルを叩く。
配下を他に潜り込ませるか?
モーリスに奇襲をかけて魔導具を手に入れるというのは魅力的な案だ。
だが昼間の陽光の下では、高位吸血鬼とは言え能力は人間なみだ。
そこで背後に積み上げている人狼たちを見た。時間が来る前にどれか一匹が動けるようになるだろうか?
夢想を中断するかのように再び携帯電話が鳴り、それを取り上げる
「俺だ」
モーリスからだった。約束の時間を一時間遅らせて欲しいという頼みだ。快諾した。その方が人狼たちの回復の時間が稼げる。
背後の壁で、これらを見ていた目玉が静かに自壊して灰に変わった。
モーリス・ヴァルナクスは準備に余念が無かった。
今日の取引で魔導具はモーリスの手を離れ、代わりに命が手に入る。
すでにモーリスの体はかなりの老いが進行している。だがそれも血の膏薬が手に入ればすべて解消する。吸血鬼の真祖であるボスの血から精製する軟膏を塗れば、また若さが戻って来るのだ。
再び若くなって、自分を陥れた連中に復讐をするのだ。
ノーラスとの取引で得る寿命は十年分。だが、それに加えて一億ドルを要求した。それだけあればもう一度事業を立ち上げ、再び大富豪となることができるだろう。
もちろんこれから先の生涯を夜の女王リビアに付け狙われることになるが、それは支払わねばならない犠牲と言うものだ。リスクを恐れていては何もできない。
モーリスが隠れているのは以前に持っていた貸家の複雑な部屋割の中にこっそりと作っておいたセーフハウスだ。入口は巧妙に偽装してあり誰もそこに部屋があるとは気づかない。ずいぶん昔にある呪術師から買い取った『隠れ家』のシジルがその場所に対する魔法的な追跡を断ち切っている。
このシジルは高い買い物であったが、実際に役に立ったのだからモーリスは満足していた。備えあれば憂いなしとはよくも言ったものだ。
昔ライバルを事故死させるときに雇った爆弾魔に今回新たに作らせた起爆装置の動きを確かめる。
そいつは自分の手で殺したからこの方面から足跡を辿ることはできないはずだ。
遠隔起爆装置を自分の腕に嵌めたまま、プラスチック爆薬にテープで貼りつけたネックレスをまた眺める。
そのネックレスはとても美しく、いつまでも眺めていたいと思わせる妖しさを秘めている。中央の不思議なカットの宝石を巡る七つの宝石はどういうやり方でか相互に位置を入れ替える。驚異的な魔法の力があるという話だが、それを考えに入れなくても見事な芸術作品であることは間違いない。
これを破壊するようなことにならなければ良いがと思った。芸術品の破壊者は人類の敵だというのが常からの持論であった。
まあそれも自分の命に関わらなければの話だが。
時間だ。モーリスは隠れ家から出た。
頭から被っているのはかなり昔に手にいれた魔導具だ。『私は誰』という名称だったように思う。一種のフードで、それを被ると何者の注意も惹かなくなる。銃を構えた銀行強盗の横を何食わぬ顔で通り過ぎることもできるすぐれ物だ。
これが無ければとうの昔にリビア配下の吸血鬼たちに見つかっていただろう。昼の日中でも動ける吸血鬼は存在するのだ。
これがあっても夜ならば高位の吸血鬼はモーリスを見つけることができるだろう。だから取引は昼に行うしかないのだ。それでこそリビア派閥の吸血鬼の目をごまかせる。
約束のジョン・エリクソン記念碑につく。
ジェームズ・アール・フレーザーの像の下に腰を下ろしてそこから周囲を観察した。通行人がいるがこちらに注意を向ける者はいない。だが油断してはいけない。
左手のスイッチを握りこむと、デス・スイッチが起動した。これで正しい解除手順を使わない限り、スイッチが手から離れた瞬間に足下のスーツケースは爆発する。発信機の電波が遮断された場合も同様だ。
しばらく待った。もうすぐ約束の十一時だ。隠れ身のフードを脱ぎ、リビア派閥の吸血鬼に見つかる恐怖に耐えてひたすらに待つ。
目の前に影が落ちた。顔を上げると三人の男が立っていた。みなサングラスをかけている。
心臓が割れ鐘のように鼓動を打った。
眼鏡をかけた小男と背の高い男を残して、やや太り気味の男がモーリスの横に座った。
慌ててモーリスは言った。
「前に言った通りに、ネックレスには爆薬が仕掛けてある。おかしな動きをすれば爆発する」
「分かっているさ。モーリス・・だな?」隣に座った男が言った。
「俺がノーラスだ。時間を無駄にするつもりはない。邪魔が入る前に取引を始めよう」
モーリスは右手で一枚の紙片を取り出すとノーラスに渡した。
「ギースの文言だ。この通りに私にギースを掛けてもらいたい」
「まあ焦るな」
ノーラスはその紙片を連れてきた眼鏡の魔導士に渡した。その内容にざっと目を通してから魔導士は紙片を返した。
「問題ありません。これにより私が魔導具を確認した後に、モーリス様はノーラス様の吸血侍従として認定され、保護を与えることになります。有効期間は十年。後の取引により期間の延長はありますが、短くすることはできません」
「一億ドルも忘れないでくれ」
「いいだろう。それだけの価値があるとこちらが認めた場合だけだがな」
ノーラスが即答すると魔導士が口を挟んだ。
「契約が成立しなかった場合はこの魔導具は永遠に我らの所有とはなりませんのでご注意ください」
「分かった。お前はいつも口数が多い」ノーラスが苛つきながら答えた。
「ギースを」モーリスが急かす。
ノーラスはギース開始の身振りをする。モーリスは半吸血鬼とは言え、魔力はないので自らギースを使うことはできない。
ノーラスは手の中の紙片の文言を一言一句違えずに読み上げる。それからギース完了の身振りをした。
ギースを司る亜神が取引内容を解釈するまでには一瞬の間がある。それから帳が周囲に降り、首筋に冷たい慄きが走った。ギースが受け入れられた合図だ。
「ではその魔導具を渡せ」
モーリスはスーツケースに番号を打ち込んだ。一度、もう一度。それぞれ別々の番号だ。
カチリと音がして爆弾が解除されると、スーツケースが開いた。
魔導士は中からネックレスを取り出すとすばやく布に包んだ。周囲には通行人がいるのだ。これを見られるわけにはいかない。
軽くネックレスに魔力を流し込むと魔導士は頷いた。
「たしかに古代魔導具です。それも相当強力な。機能はまだわかりません」
ノーラスはモーリスに向けて右手を差し出した。
「良い取引ができて嬉しかったよ。モーリス」
それを合図とみたのか背の高い護衛が近づいてくると、爆弾が詰まったままのスーツケースを取り上げて空に向けて放り投げた。恐ろしい膂力だ。スーツケースはまるで鳥か何かのように空高く飛び、川の中に落ちて水しぶきを上げた。
「危ない玩具は片付けないとな」
護衛の男が呟く。
ノーラスは立ち上がった。
「さて、モーリス。ここでもう少し待っていてくれないかな? 迎えを寄越す手配をしてあるんだ」
一人で!?
モーリスは緊張したが、自分はすでにノーラスの吸血侍従で彼の保護下にあるのだと思い出した。再び隠れ身のフードを被る。
「あまり長く待たせないでください」
「約束する。それほど待つ必要はないさ」
上機嫌なノーラスはそう言い残すと二人を連れて去った。
一時間は待たされなかった。
ベンチの上でじりじりと待つモーリスの前に再び三つの影が落ちた。
希望と共に顔を上げると、そこにはノーラスの顔があった。だが何かが先ほどと違っていた。
残りの二人も違う。今度の二人はサングラスはかけていなかったし、一方は髭面だ。
「ノーラスさま?」
「モーリスだな?」ノーラスは言った。「ブツは持ってきたか?」
「あの、何を言っているのです。魔導具はすでに渡しましたよね?」
モーリスは嫌な汗が背中を滑り落ちるのを感じた。
「何のことだ?」冷たい声。「約束の時間を延ばせと言ったり、魔導具を渡したとか訳が分からんことを言う。まさかこの俺と取引をする気がないと言うのか」
ノーラスの体が怒りで膨れ上がった。
「待て。待ってください。お願いします。確かに貴方に渡したんです。ギースも掛けてもらえましたし」
「ギース? 何のことだ。俺は何のギースも使っていないぞ」
ノーラスは背後のボディガードにモーリスの殺害の合図を出そうとしたが、周囲の目に気づいて止めた。大声で怒鳴りあったのだ。注意を惹かないわけがない。
陽光の下の吸血鬼は無力に近い。ボディガードの人狼にはその制限はないが、人々の注意を惹くことは厳禁だ。対策局は怖くはないが、人前で闇の存在を暴露してしまう行為には、あらゆる魔物のグループから非難が殺到する。彼らの多くは影の中での暮らしに満足している。
ノーラスはモーリスの横に座った。先ほど偽ノーラスが座っていた丁度その位置にだ。そして、そっと手を伸ばすとモーリスの手を取った。
「いいかい。良く聞きなさい。モーリス」
ノーラスはできる限り優しい口調で言う。モーリスの顔に希望の光が灯った。
ノーラスの口調がいきなり変わった。怒りで顔が歪んでいる。
「俺は周囲の注意を惹きたくない。だからお前はこれから俺が何をしようとも、決して声を上げてはいけない。一言でも声を上げたら、お前の首をその場で折ってやる」
そこまで説明してから、ノーラスはまた優しい顔に戻った。
「いいかい。まずは小指からだ」
言うなり手の中のモーリスの小指をへし折った。枯れ枝を踏んだかのような音がした。
あまりの激痛にモーリスは手を引っ込めようとしたが、ノーラスに捕まれた手首は万力に挟まれたかのように動かない。古い血の吸血鬼の筋力は普通人の二十倍に達する。
「しーっ。静かに。泣き叫ぶんじゃないぞ。これはお前が俺を騙した分だ」
「ノーラスさま」
「声を出すな。心を落ち受けて苦痛を楽しむようにするんだ。いいか、これは昼の日中に俺を呼び出した分だ」
もう一本へし折られた。モーリスは必死で悲鳴を抑え込む。
「これは俺をぬか喜びさせた分」
容赦なくさらにもう一本。
モーリスは絶叫したかったが、ボディガードが横に座ってモーリスの首の周りに手を置いているのでそれもできない。こちらも恐ろしい握力だ。
大粒の涙がぼろぼろと零れた。激烈な痛みに本能が悲鳴を上げる。無残な有様になった自分の手を見つめる。
「ノーラス・・さん。違う。私は・・」
その口をノーラスの手が優しく抑えた。
「俺はもうお前の声は聞きたくない。言い訳も、悲鳴も」
後二本。さすがに親指が折れるときは大きな音がした。モーリスの体が抑えようもなく痙攣する。
ノーラスはモーリスの残骸となった右手を開放し、自分の手を改めて差し出しながら言った。
「さあそちらの手も」
「とんでもない無駄足だったな。帰るぞ」
そう言いながらノーラスはベンチから立ち上がると踵を返した。
「モーリス。次に俺と闇の中で会ったら覚悟しておけ。楽には死なせんぞ」
そこでふんと鼻を鳴らした。
「もっともその有様では後数日で塵になりそうだがな」
「そんな。ノーラス様。ギースが! ギースが!」
無残な有様になった両手を振りながらモーリスは叫んだが、無情にもノーラスたちは立ち去ってしまった。
スモークガラスの車の中で、ファーマソン神父は椅子に深く体を預けた。運転席ではシェイプシフターのアラバムがハンドルを握っている。顔の横にも目を作り、周囲を油断なく見張っている。
アラバムが肩越しに紙を私に差し出した。
「我が魔王・・いや、神父。これをお返しします」
紙片を受け取る。そこには自分が描いたノーラスの精密な似顔絵が描かれている。吸血鬼は写真には写らないのでどうしても手描きの肖像画に頼ることになる。
くしゃくしゃに丸めて捨てようと思ったが、将来必要になるかもしれないと思いついて、綺麗に畳んでポケットに納める。
横でネックレスを調べていた魔導士のアーダラクが顔を上げて言った。
「確かに古代魔導具です。処理できる魔力量が桁違いですし、魔法材料が現代のものとはまったく違います」
「そいつにはどんな作用がある?」
「精神操作系だと思いますが詳しくは持ち帰って調べねば判りません」
答えながらもアーダラクの声に希望が籠る。
「ダメだぞ。アーダラク。研究したいのは分かるがそれはリビアに返さないといけない。対策局がそれを接収したらただちに戦争が勃発する」
「吸血鬼にこれを返してよいものでしょうか?」
アーダラクは当然の疑問を口にする。
「『究極の三』のような超破壊力を持つ古代魔導具ならともかく、その種のアイテムなら元の持ち主に返しても大丈夫だろう。今までリビアが持っていて問題を起こしたことはないのだから」
「我が君がそうおっしゃるのならば仕方ありません」
アーダラクはしぶしぶという様子でネックレスを包んだ布ごとこちらに渡してきた。本当に残念そうだ。少し胸が痛んだが、彼の望みを叶えるわけにはいかない。
古代魔導具を研究できる折角の機会を失い、あまりにも残念なので、アーダラクは無理にでも話題を変えたようだ。
「しかし究極の三はいったい誰が持っているのでしょう。伝説では恐ろしい破壊力を持つと言いますが」
「ああ、それなら天界の宝物庫にあるぞ。もっとも今は『究極の二』だが」
ネックレスを目の前にぶら下げて見ながら迂闊にもそう答えてしまった。いけない、このネックレス。見ているだけでも精神干渉を引き起こすぞ。
「なんですと!」
アーダラクの手が伸び私の肩を掴む。
「我が君。どうか、今すぐ天界に連れて行ってください。お願いです」
「ダメだ」私は冷たく言い放った。
「君はあれを分解するつもりだろう。それで暴走したら天界都市が消滅してしまう」
「大丈夫です。我が君。対策局の私の自室に持ち帰って調べますから」
「それはなおさら悪いぞ」
思わず厳しい声になってしまった。あれを絶対に渡してはならない相手がいるとしたら、それはこの魔導士に他ならない。
「お願いです。我が君。見るだけ。見るだけだと約束しますから。絶対に触りません」
そこまで言ってからアーダラクは何かに気づいた。
「究極の二ですと? 究極の三ではなく?」
「ああ。一つは私が使ったからな。ほら、あの闇大戦の最後で、悪魔たちの要塞である万魔殿が半分吹き飛んだだろう。あれだ」
ああ、いかん。また口が滑った。
私はもっと見ていたいという欲望を抑えながらネックレスを布で完全に包むと懐に納めた。これは本当にヤバイ代物だ。
「あれは我が君の仕業だったのですか!」
アーダラクは目を剥いた。
「いや、ちょっとあの城に穴を開けるつもりだったのだが。まさかあそこまでヤバイ代物だとは思わなくてな。あれの目盛りをもう一つ進めてなくてよかったよ」
魔導士は毒気を抜かれて椅子に力なくもたれかかった。
「今の話も秘密だぞ」念を押しておく。
まあ今回の作戦ではアーダラクが作ったスパイ装置が役に立ったから、後であの魔導具の絵でも描いてやろう。彼ほどの魔導士ならそこからも何かを汲み取るだろう。
もちろん例えできるにしても、あれのコピー品などは作らせないが。作ったりしたら取り上げて太平洋のど真ん中にでも捨ててやる。それとも妖精の道の誰もたどり着けない闇の中に投げ込むというのがいいか。
「しかしあのギースの帳はどうやったんです?」
そう訊ねたのは運転席のアラバムだ。
「簡単だ。君はノーラスに化けていただけだからいかにギースを掛けようが、ノーラスに特化した契約のギースは最初から働かない。その代わりにアーダラクがギースに似た魔法の感覚を作り出したんだ。モーリスはただの半吸血鬼だし魔力も無ければ魔法も使えない。だからあの偽物のギースを見抜けなかった」
私は車の外を眺めた。彼を騙した罪悪感が少しだけある。だがモーリスの死の原因はひとえに夜の女王リビアから盗みを働いたことにある。古き血の吸血鬼女王なのだ。この世にこれほど確実な死刑執行令状はない。
「彼がもっと魔法の経験豊かだったら騙せなかっただろうな」
「お見事です。我が魔王、いえ、我が神父」アラバムが感想を述べる。
私は十字を切った。
「神よ。我が詐術の罪を許したまえ。アーメン」
存在しない神に許しを請わねばならないとは、本当に奇妙な話だ。
8)
二人は先に返した。
人狼とシェイプシフターと魔導士が三人一緒にいると、分かる存在には分かってしまう。注意を惹く前に分散するのがよい。
私は夜になるとスーツから神父服に着替えてリビアが棲む高層マンションを訪ねた。
誰何も無く中に通された。その分、マンションの周りはリビア配下の吸血鬼により隙間なく監視されているということだ。
女王の間の豪華で大きな扉を開くと、リビアが居た。いつもの大きなソファの上だが、寝そべってはいない。その目が私を真っ向から見つめる。
「ダーク。首尾は? まさかダメだったなんて言わないでしょうね」
言葉の裏に今まで聞いたことのない真摯さと欲望がある。そこまで大事なネックレスなのだと分かった。
少し意地悪をしてやろうとも思ったがリビアが余りにも真剣なのでやめておいた。私は懐から布で包んだネックレスを取り出すとリビアに渡した。
「ああ」リビアの口から甘いため息が漏れた。
ネックレスを愛おしそうに撫でると、それを自分の首に巻いた。
色とりどりの宝石がキラキラと光をまき散らす。
「壊れてはいないわね」リビアの表情が優しくなった。「ダーク。有難う」
「どういたしまして」
私は答えた。何、大したことじゃない。一匹のボス吸血鬼に喧嘩を売ってきただけだ。
「モーリスは?」
して欲しくない質問だ。
「もうすぐ死ぬだろう」
嘘ではない。彼の寿命はあとわずか。
「首が欲しかったのに」リビアは残念そうに言った。
「生首は神父が運んで良いもののリストには入っていない」
「あら? ダークは気にしなかったわよ」
リビアへの答え代わりに、私は自分が着ている神父服を強調した。やはりこれが私の立場を示すトレードマークというもの。
リビアはソファに座りなおすと、通話機のスイッチを入れた。
「監視室。これから人払いをするから、この部屋の監視を切って」
「しかしマダム」通話機から抗議の声が漏れた。
「いいから。私が呼び出すまで中からどんな音が聞こえても誰も来てはダメよ。見た者はこの私が直々に殺します」
おや、おや、リビア。穏やかではないな。何をするつもりだ?
「あなた方もよ。部屋から出て行きなさい」
部屋の中のボディガードたちも追い出す。
最期に残ったのがリビアと私だけになると、リビアは立ち上がった。その手が動き、胸元のネックレスを撫でる。
「ダーク。この魔導具がなにか分かる?」
「いいや。アーダラクは精神に作用する魔導具ではないかと推測していたが」
「アーダラク。あの狂える魔導士? さすがね。これは祖母から譲られたものだけど、副作用がひどいからあたしの代では使わなかったの。その頃には『血の盟約』派閥もこれに頼る必要はないぐらいに大きくなったし」
「副作用?」
「使った分だけ歳を取るの」
ああ。私は納得がいった。
基本的に吸血鬼は血を飲む限りは年を取らない。きっとこの魔導具の副作用は吸血鬼の生理を無視して加齢を引き起こすのだ。魔法の働きは奥深い。特に古代の魔法は。
そういえばシャンドリア長老がリビアの祖母をあの婆めと呼んでいたな。あれはそのものズバリだったのか。
リビアの祖母は魔導具を使いすぎて実に珍しい吸血老婆になったのだ。
リビアが両手の先をネックレスに触れる。宝石の輝きが一層強くなる。虹色の靄がそこから広がった。
嫌な予感がした。いったいリビアは何をしようとしている?
「でもこの仕事の前には魔導具がどんな働きをするか知らないと言ったじゃないか」私は指摘した。
「馬鹿ね。ダーク。女性は嘘をつくものなのよ」
リビアは嬉しそうに笑った。魅力に溢れた笑顔。その持ち主を愛さずにはいられない。そんな笑顔。
「この魔導具は女吸血鬼専用なの。その力は持ち主の魅了魔法を増大する。何者も抗えないほどに。どんな魔法もこれを防ぐことはできない。ねえ、だからダーク。今日こそは再びあたしのものになってもらうわよ」
「止めろ! リビア。それをやるんじゃない!」私は叫んだ。
しまった。リビアに説明をする暇がない。私の中の魔法の罠について。
「いやよ。ダーク」リビアが魔法のネックレスの最後のロックを解いた。
ネックレスの光が膨れ上がり、私を飲み込んだ。
ダークの時代、魔導士アーダラクと長い間議論したことがある。精神作用系の中でどの魔法が一番危険なのかを。出た結論は魅了の魔法だった。
魅了それ自体は弱い魔法でいくつかの強化魔法を組み合わせないと実用にはならない。かろうじて、吸血鬼だけが性的魅力を加えることでそれを実用の範囲にまで引き上げている。
魅了の厄介な点は、一度それにかかると自ら魅了され続けようとすることだ。例えるならば酒に酔った人間が酔いを醒ますのを嫌がるのと同じだ。
だから屈強な者が一度魅了にかかると、魅了の解除に全力で抵抗するために、実質的に解除する方法が無くなってしまう。
魔王が魅了されると自分の軍団を自分で壊滅させかねない。それだけは困る。
だから相談の末に、アーダラクは私の中にある魔法を組み込んだ。無意識領域の奥深く。信頼している人間にしか絶対に触らせない場所にだ。
反転する感情。アーダラクはそう名付けていた。
このカウンター魔法は、魅了の力が働き無意識領域の奥にまで届いたとき、魅了が作り出す感情を反転させる。
愛情から、憎悪へと。より強い愛情はより強い憎悪となる。相手を殺すまで決して止まらない憎悪に変えてしまう。
今がそれだ。
甘い誘惑が鼻孔を満たし、反転して沸き上がった真っ赤な怒りが視界を染めた。目の前にいる憎悪の対象を俺は睨んだ。それは美しい女性でただちにこの世から抹殺するべき対象でもあった。この女をバラバラに引き裂きたい。それだけが望みだ。
喉の奥からごぼりと何かが這い上がって来た。それは俺の顎を大きく開くと外に出てきた。
怒りの咆哮だった。
悲鳴にも似た咆哮が周囲を満たし、部屋の壁をビリビリと揺らす。音は高音から低音へと滑り落ち、代わりに床が大きく揺れた感じがした。
「ダーク! あなた!」女が叫んだ。
とても耳障りだ。
消し去るべき声だ。
ゾアントロピー。獣化現象。
体中の筋肉が膨れ上がり、伸びきった服が耐えきれずに弾ける。鋼より硬い剛毛が全身に生える。爪が硬化しこれも鋼鉄を越える硬さとなる。
尻尾が長く伸びるのを感じる。人狼の尻尾はそれ自体が鋭利な刃の植わった武器だ。
俺の殺気を感じて、リビアも変じた。戦わねば死ぬと直感したのだ。吸血鬼の戦闘スタイルへの変貌。牙が伸び、目が赤く光る。爪が伸び鋭い刃になる。筋肉はうねる鋼鉄のロープとなる。耳全体が大きくなり、その先が尖る。
俺は再び咆哮した。リビアも吠え返した。
先に動いたのは俺だ。戦車の装甲鉄板ですら引き裂ける爪で切りつける。リビアも己の爪でそれをはじき返す。
派手な火花が散った。左右から目にも止まらぬ速度で繰り出される俺の爪を、同じくリビアの爪が迎え撃つ。
空中が無数の火花で埋まった。まるで工事現場のような騒音が轟く。これが爪と爪のぶつかり合いで生じているとは誰が思おう。
俺は本気モードに入った。目まぐるしく位置を変え、相手の防御の隙を突く。間に挟まったテーブルが細かい木の欠片になって飛び散る。驚いたことに女吸血鬼は俺の速度についてきた。お互いに後ろを取り合い、宙を飛び、壁と言わず天井と言わず蹴り続けて飛び続けた。ここにはすでに重力はない。俺たちが戦っている場所に元の形を保っているものはない。
それは刃の旋風。死の大鎌。
壁には大きく引き裂かれた痕が残り、その背後の装甲鉄板がむき出しになる。それもすでにズタズタだ。
女吸血鬼が配下を呼ばなかったのは正解だ。この戦いの中に誰が飛び込んできても次の瞬間には挽肉に変わってしまうだろう。
古い古い血。歳月を経て、成長し、磨かれた古い血。俺よりも古い血だ。この吸血鬼の名前は何と言ったか。思い出せない。
だが強い。
俺は自分の中の魔力を引き出そうとした。誰かが俺の中に埋め込んだ魔力の壺に手を伸ばす。これを開けば今の十倍にも俺は強くなることを俺は知っている。
その時、女吸血鬼が叫んだ。超音波が俺の鼓膜を叩き、頭蓋骨を揺らす。強烈な頭痛が俺の意識を乱す。
くそっ。魔力の壺を開くための精神集中ができない。
女吸血鬼もそれ以上の攻撃はできない。人間ならこれを聞かされ続ければ脳が破壊されるが、人狼はそこに至る前に治ってしまう。
どちらも決め手に欠ける。俺たちはお互いの爪を迎撃し続けた。
ついにこの衝突に耐えられずに俺の爪が砕け飛んだ。同時に女吸血鬼の爪も崩れ落ちる。
俺の爪は砕けた手ごとすぐに再生した。女吸血鬼の手も一瞬黒い霧に変わると再び元の姿に戻る。崩れた手の細胞を小さなコウモリに変えて、また集結させたのだ。
これでは終わりがない。再生型種族間の戦いは無限地獄となる。だがそれでも飛び散った血だけは回収できない。どちらも大量の血を失えば無限の生命力も最後には尽きて死ぬ。
俺は攻撃の方針を変えた。
女吸血鬼の爪が皮膚を切り裂くのは無視して、拳をその腹に叩き込む。
女吸血鬼の体が吹き飛ぶと、内臓をまき散らしながら壁に激突する。そのまま突進すると壁に貼りついたままの女吸血鬼を殴り続けた。見る見るうちにその体がただの肉片に変わったが、最後にその体が弾けて細片になると無数のコウモリに変身して宙を満たした。
高位吸血鬼、それも最上級の吸血鬼である真祖にだけできる技。
羽虫ほども小さくなったコウモリの霧が俺を襲った。鼻や口から潜りこんでくる。思わず吸い込んでしまった。
次の瞬間、胸が焼けた。肺の中に入った虫コウモリたちが俺の肺を内側から蝕んでいると気付いた。肺が無くなればいかな人狼といえども呼吸ができない。酸素が取れなければやがて身動きができなくなる。
俺は床を転がった。それでもどうにもならない。敵は俺の体の中に居るのだ。
残りのコウモリが部屋の反対側に集まり、元の体の再構築にかかっている。
このままでは死ぬ。そう思ったとき、俺の中の何かが対処法を述べた。昔誰かが俺の中に埋め込んだ魔術だ。体内奥深くに埋め込まれた魔力核を開放し、体内温度を上げる。摂氏六百度。生体発火には十分な温度だ。
肺の中の虫コウモリたちがたちまちに焼け死んだ。同時に俺の肺も焼けたが、すぐに再生を始める。
息をすると口から煤が噴き出した。
こんな物騒な魔法、いったいどんな狂人が埋め込んだんだ?
女吸血鬼が再構築を終えて立ち上がる。心なしか体の大きさが少しだけ小さくなっている。
「ダーク。止めて」
ダーク? 何のことだ?
この女吸血鬼が新たな手を考え付くまでに殺さねば。ただそう考えた。
吸血鬼を殺すにはどうすればいい?
そう考えたとき、俺の手は勝手に動き、腰からナイフを引き抜いた。
銀の嫌な臭いのするナイフと特殊鋼のナイフだ。
それの使い方は俺の手が知っていた。ナイフの柄を押すと聖水が刃に沿って流れ落ちる。
直観的に分かった。これで相手の心臓をえぐれば死ぬと。
女吸血鬼が部屋の隅に走った。壁に飾ってある何かの棒に飛びつく。魔導具の一種か。俺は衝動に任せて突進した。
咄嗟に投げつけた銀のナイフが女吸血鬼の前に伸ばした手を壁に縫い付けた。魔導具らしき棒のすぐ手前にだ。聖水がついているために、手をコウモリに変身させることができない。
血しぶきをまき散らしながらナイフから手を引きはがしたときにはもう俺はその体に激突していた。
相手の残りの手を叩いて砕くと、一度のローキックで彼女の両足を折った。
コウモリに変わる時間は与えない。その体を掴んで床に叩きつけるとその上に馬乗りになった。
聖水を垂らしたナイフを振り上げてその胸の上に狙いをつける。ナイフから噴き出した聖水はわずかだが、彼女が心臓をコウモリに変えるのを邪魔するには十分だ。
「ダーク。止めて。お願い。殺さないで!」
女吸血鬼の悲鳴をどこか遠くに聞きながら、俺はナイフを振り下ろした。
9)
その木の葉は俺の目の前でふわりと踊った。
葉脈が光で出来た不思議な木の葉。マドウフ・ベイルがカタログの栞に使ったものだ。
破れた俺の神父服のポケットから飛び出した木の葉が目の前で旋回する。止めようもなく振り下ろした俺のナイフはそれに触れた。
小さな破裂音と共に木の葉が弾けて、小さな光が広がり、すぐに消えた。
お日さまの匂い。熱い南国の風。ライムの香り。煌めく光の渦。
それは俺の心の中を駆け抜け、あらゆるものを満たし、洗い流した。
心の中の怒りの炎が一瞬で消滅した。私、ファーマソン神父は自分を縛っていた憎悪の鎖から解放され、体の制御を取り戻した。
原初の光に触れて真っ白なリビアの肌が一瞬焼け、すぐに再生を開始した。
「ダーク。お願いもう止めて」
リビアが泣きながら繰り返す。
私はナイフを捨てた。
「ダークじゃない。ファーマソンだ。間違えるな。リビア」
彼女の目に浮かんだ安堵を見て、自分が危ないところまで来ていたことにようやく気付いた。アーダラクの魔術はいつもやりすぎる。
ドアが外から叩かれている。
リビアの配下たちが心配して扉を叩いているのだ。リビアの絶対の命令が出ているので勝手にドアを開けることはできない。
部屋の中はひどい有様だ。あらゆる家具が巻き込まれて壊れている。壁にも大きな傷跡が刻まれている。なぜか中央のソファだけが無傷で生き延びている。
体を再生したリビアが首から魔法のネックレスを外す。コウモリになっている間、それはいったいどこにあったのだろう。吸血鬼の権能にはまだまだ謎が多い。
「それを二度と私に使うな。次は止められない」
私が注意するとリビアは頷いた。そのままソファの中に組み込まれている金庫の中にネックレスを納めると、扉の外で喚いている部下たちに説明をするために部屋から出て行った。
今のはリビアが悪い。私は謝らないぞ。
それでもまたリビアと顔を合わせるのが何だかバツが悪かった。カーテンを引きちぎるとそれを両側に広げて私は八十一階の窓の外へと飛び出した。
その日の夜にはSNSに怪奇ムササビ男のピンボケ写真が掲載されているのを見て、私はウンザリした。なんと小うるさい時代なんだ。
一人で旅客機に乗り、一週間ぶりにロンドンの対策局に帰って来た。さすがにもうあの大騒ぎも終わっているだろう。
自分のオフィスにたどり着くと中は本で埋まっていた。
どれもアメリカンコミックだ。スパイダーマンから始まって最近発売のニュー・スーパーマン。新連載のバイルトマンまである。それらが天井近くまで積みあがっている。
何本も生やした手に段ボール箱を持ったアラバムが駆け込んでくる。
「あああ、我が神父。すみません。アーダラクからコミックを借りたのですが、トラック何台分も届いたのです。置くところが無くて神父が出張中だったので一時ここに」
私は本の山の上に座り込んだ。何だかどっと疲れが出た。
「そうか。できるだけ早く片付けてくれ」
続いて魔導士のアーダラクが飛び込んできた。
「我が君。お帰りと聞いて飛んで来ました。どうか、究極の二についてお聞きしたいのですが」
ああ。そうだったな。
私は荷物の中からスケッチブックを取り出した。飛行機の中で暇つぶしにあの古代魔導具に関して思い出せる限りを描いておいたのだ。いくらアーダラクでもこの絵だけであれを再現はできないだろう。
絵を受け取ったアーダラクの目が丸く見開かれた。その視線は私の尻に向けられている。
「まさか。我が君、その下に敷いているのは!
1962年刊行のマーベルコミックですよ。稀覯本なんです。それを尻に敷くとは!
ああああ、なんてことだ。もう二度と手に入らない本なんですよ。どいてください。今すぐ!」
「あの、マスター」
騒ぎの最中にアンディがフードを被った女性の手を引きながら部屋に入ってきた。
匂いで分かる。その女性はエマだ。
エマの手は綺麗だ。魔法の毛は時間切れで全部抜け落ちたらしい。
「その」アンディは意を決するとエマのフードを剥がした。
頭の上に毛の一本もないエマが、目の隅を真っ赤に腫らした顔でそこに立っていた。頭だけじゃない。眉毛もまつ毛さえも無い。
アンディが説明した。
「あの。どうしてもエマが毛むくじゃらに堪えられないというので、魔法薬学で脱毛剤を作ったんです。でも何か手違いがあったようで」
「たった一滴なんです。一滴だけ手に垂らしたんです」エマが泣きながら言う。
それ以上は続けずにわあっと泣きだした。
マグダラ尼僧が怖い顔でエマの背後に現れた。手にボロ切れを持っている。
「ファーマソン神父。これはいったい何です。
確かに綺麗に洗濯してあります。アイロンもかかっているし、洗濯ノリも効いています。
で、神父服の腰の部分以外はいったいどこにあるんです?
もちろん、納得の行く言い訳を聞かせて貰えるのでしょうね!?」
彼女が一歩前に出ると、私の横のコミックの山ががさりと動いた。
皆が見つめる中でコミックを振り落としながら牛ほどもある大きな犬が顔を現した。もちろんそれは犬ではない。頭が三つあるような犬はこの世にはいない。
一声大きく吠えると、止める間もなくその地獄の番犬は腰を抜かしているマグダラ尼僧の横を駆け抜けると廊下に飛び出した。
「魔獣だ。まさか今までここに隠れていたのか!」アーダラクが叫んだ。
「これ以上の被害を出す前に捕まえろ!」私も叫んだ。
全員でドタドタと後を追った。
前方で地獄の番犬は向きを変えると対策局の共同オフィスに飛び込んだ。
内部で大理石のテーブルに地獄の番犬が突っ込む音がした。それに続いて周囲に無数の小さなガラスの駒が落ちる音がした。
一瞬の静寂。
アナンシ司教の怒り狂う叫びが轟いた。その圧力に耐えきれずに共同オフィスの窓ガラスが一瞬ですべて砕け散る。
私はその場で回れ右をすると、一目散に逃げだした。
今度の出張は一か月はかかるだろう。