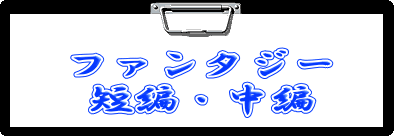
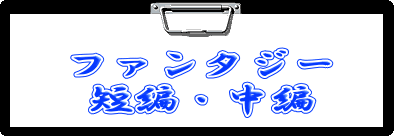
4)
リビアのところを去る前に、自動記録されている監視カメラの映像はすべてチェックした。ついでにマンションの監視カメラもだ。高級マンションの警備主任は最初は渋ったが、リビアが口利きするとあっさりと折れた。実はこのマンションはリビアがオーナーだとは後で知った。道理で壁に装甲鉄板を埋め込んでもどこからも抗議が来ないわけだ。
確実ではないがそれでモーリスという男が取った行動が大体分かった。
ネックレスを盗んだ後、堂々と正面のエレベータで階下に降り、その直後に高級マンションのサービスの一つである洗濯物サービスの収集所に潜り込む。洗濯物の山の中に隠れて、予め買収しておいた係員に運ばれてトラックの荷台に移ると、そのまま逃走した。まあそういうところだ。
リビアは彼の血の味と匂いを知っているので追跡は可能だが、実際には相当近くにまで行かないと見つけ出すことはできない。この点では人狼に大きな分がある。だからあれほど護衛に人狼を雇えと言っているのに。
元やり手の実業家だけあって、モーリスは賢い男だ。慎重に計画を立て、正確な一撃をむき出しの相手の弱点に食らわせる。こういうのを策士と言うのだろう。
お陰で彼を探し出すのは容易ではない。おそらく身を隠すのにも何らかの準備をしていたに違いない。
だが古代遺物の魔導具とくれば、何としても回収してリビアの下に戻さなくてはならない。それが齎す影響は現代に作られた魔導具のような半端なものではないのだ。
場合によっては危ういところで保たれているこの世界のバランスを根底からひっくり返しかねない。
ではどうやって?
目についたバーの片隅に陣取って考える。神父服のままで酒を飲むのは周囲の好奇の目が痛かったが敢えて無視した。
モーリスは何のためにリビアの魔導具を盗んだのか?
冷酷なリビアへの仕返し。無論それもある。
だが一番の目的は、尽きかけている自分の命をつなぐことだろう。そしてそれができるのは吸血鬼だけだ。
ならば彼が取れる手段はただ一つ。
盗んだ魔導具をリビアとは別の吸血鬼派閥へ売りつけること。その代償としてそこの吸血侍従にしてもらうこと。
吸血鬼派閥の電話番号は電話帳には載っていない。となると裏の情報屋に渡りをつけるしかない。
頭の中で裏の情報屋のリストをざっと眺める。魔導士のアーダラクが私の頭の中に埋め込んだ『忘れじの花』の魔法の効果で、一度覚えたことはいつでも引き出すことができるのは有難い。
この魔法は副作用として使うたびに脳にダメージが出るので再生能力にすぐれた魔物にしか使えないのが難点だ。
ニューヨークの情報屋の中で闇世界の情報を扱っているのは二人。以前は三人いたが一人はすでに死んでいる。たしか体を二つに切断されて死んだはずだ。ダークの秘密を売ったために殺されたと噂が流れていたのを覚えている。
残り二人の内で一人は詐欺師だ。いい加減な情報を売りつけて生きている。となると最後の一人が当たりだろう。確かこいつは深夜にしか営業しない。
スマホの電源を入れてチェックするとエマやアンディからたくさんのメールや電話が来ていたが、問題なしと判断するとすぐにまたスマホの電源を切った。ぐずぐずしているとアナンシ司教から電話がかかって来る恐れがあるからだ。
ニューヨークの空から見える星の数は少ない。スモッグのせいだ。数少ない星が中天高く輝くまで待ってから私はバーへ向かった。
どうして人間たちは綺麗な空気と綺麗な空が嫌いなのだろうと考えながら、バーの扉を押し開ける。
人気の無い薄暗いバーの一番奥まったテーブル席。そこだけはさらに一段と照明が暗い。
置いてある小さなテーブルの前には背の低い髭面の初老の男。いや、前に見たときよりももっと歳を取り背が丸まっている。もうすっかりと老人だ。当たり前だ。前に見かけたのは闇大戦の前だからもう何年も前だ。人狼などの長命生物は時間の感覚が人間のそれとは大きく異なっているため、こういうことは良くある。
「やあ、ザムラン」私は声をかけた。
「お客さんかな」
ザムランは眼鏡をずらして私を見た。たしか前は眼鏡はかけていなかった。
通称ザムラン。偽名かどうかは知らない。知ることに意味がないからだ。彼はアザースのような表の世界の情報屋も兼ねるようなことはしていない、ニューヨークで古くからやっている闇の世界の生粋の情報屋だ。
当然、彼の周囲は隠された魔術だらけだ。敵意を持った者は近づくどころかこの場所を見つけることもできはしない。敵対者を焼き殺すように作られたシジルの上にわざと立つと私は言った。
「一つ聞きたいことがある」
「神父さんがこんなところに来るとは珍しい。あんたの神は飲酒は禁じていないのかい?」
「別に十戒は酒を禁じてはいないな。モーゼのも教会のも」私は答えた。
「そりゃそうだな。下手に酒を禁じたら入信者が減っちまうだろうしな」
「ここ、いいかな?」
彼のテーブルの向かいの椅子に座る。
私が正面に来ると彼の目が細くなった。私の顔をじっと見つめる。その目が大きく見開かれた。
「まさか、あんた」
「ファーマソン神父だ。今の私はそれ以外の何者でもない」
「そ、そうだな」
彼は自分の椅子に深く座りなおした。ここで慌てふためいでも何もならないと覚悟したようだ。たしかに彼はアザースよりも度胸がある。
「何が聞きたい? いや、それより前に酒か」
彼が合図するとラム酒が縁一杯にまで入った酒のグラスが私の目の間に置かれた。中に注がれているのはロンリコ151。度数151度という狂った酒だ。
酒が出るということは私が客として合格したということ。不合格の場合は銃弾が飛んできているはずだ。この椅子の周りに深く染みついた古い血の匂いがそれを教えてくれる。
もっとも私が誰かということを知っていて彼が銃弾をチョイスするとは思えない。それはC4爆薬を撃つのと同じ意味になる。
私はその酒を一気に喉に流し込んだ。別に酒が飲みたいわけではないが、相手の歓待に対する礼儀だ。アルコール純度75.5%の酒が喉を焼きながら滑り落ちていく。瞬時に私の肝臓がそれを分解する。耳の穴から蒸気が噴き出したような気がした。
「モーリスという男があんたに話を聞きに来たはずだ」
私は言った。強い酒で声が掠れなかったかな? よし、大丈夫だ。もう喉粘膜は再生している。
「客の情報は売れないな」彼は答える。
声は平常、ただし彼の体から恐怖のフェロモンが噴き出している。
ダークの時代にはにこんな口ごたえをする人間はいなかったな。いても次の瞬間にはいなくなっていた。それが普通だった。
「値段次第だろ?」私は指摘した。
もちろんそうだ。情報屋に取ってはどんな情報も商品だ。ただしモノによってはこの世の誰も買えない値段になるだけ。そしてモーリスの秘密にはそこまでの値段はつかない。
「断っておくがモーリスの居場所についての情報は商品棚には並んでいない。売る売らない以前に本当に場所を知らないんだ」
「それはこっちで調べる。私が知りたいのはモーリスとの会話の内容だ」
ザムランは眼鏡の位置を正すと私をもう一度見つめた。どのぐらい吹っ掛けられるか改めて値踏みしているのだ。そしてどこまで吹っ掛ければ私が怒り狂って彼を殺しにかかるのかも考えている。もし私が以前のダークのままだったら、値段はゼロだ。協力を断った瞬間に確実に命を失うことになる。
ザムランはようやく決意した。
「二百万ドルだな。モーリスは口止めは依頼しなかったからこの値段だ」
「払おう」私は即決した。スマホを出して操作する。適正な価格なのかどうかは分からないが、金を節約している時間も節約する必要もどちらも無い。
今度使った口座は確か悪魔の一派に頼まれて敵対する別の悪魔の一派を滅ぼしたときに得たものだ。作戦の指揮を執ったのは魔導士のアーダラクで結局何の支障もなく作戦は終了したと覚えている。あいつは殺した悪魔の体を魔術実験に使いたくて自ら参加したんだ。
あのときのヤツは本当に狂っていたな。ちょっと懐かしく感じた。
「確かに受け取ったよ。お前さん。景気がいいな。それとも神父さんってそんなに儲かる商売なのかね?」
ザムランは手にしたスマホの銀行口座の画面を見ながら満足そうに呟いた。
「神様は気前がいいんでね」私は嘘をつき、それから訊ね返した。
「モーリスの依頼は何だったんだ?」
「ヤツが欲しがったのは吸血鬼派閥の連絡先だ」
予想通りの答えた。
「どの派閥だ?」
「二つ。一つにつきあいつは百万ドルを支払った」
相槌は打たずに私は待った。それだけの金額ならモーリスのなけなしの財産のほとんどに当たるのではないか?
「闇の牙、それと血の呼び声だ」
どちらも吸血鬼の武闘派閥だ。
「ありがとう。それで十分だ。他に私が知っているべきことは何かないか?」
「特にないな。ただモーリスはひどく具合が悪そうだった。あの高齢なら不思議はないがな」
一週間前までは若さを誇っていただろうに。老衰はすべての吸血侍従が最後に辿る道だ。
話は終わりだ。私は立ち上がった。
ザムランは一瞬だけ引き留めた。
「いったい何が起きているんだ? 昨夜からひっきりなしに吸血鬼どもが訪れてくる」
「気にするな」私は彼に背を向けながら、昔のダークの口調で答えた。「知ればお前は死ぬことになる」
古代遺物の魔導具が盗まれた。ザムランはそのことを知らない。恐らくはニュヨーク中でモーリスを探している吸血鬼たちもその捜索の理由は知ってはいまい。
もしザムランが盗まれた魔導具を知っていると匂わせていたなら、私はこの場で彼を殺していただろう。それぐらいにこの情報はヤバい。アメリカ全土で闇の勢力による争奪戦が始まるぐらいに。これは絶対に広めてはならない類のゴシップだ。
暗い街路を音もなく歩きながら、私は考えた。
二つの派閥はいずれも武闘派と呼ばれる連中だ。武闘派というのは戦いを好むという意味ではなく、この世を支配するのは人間ではなく吸血鬼であるべきだという思想を持つことを意味する。
これに対してリビアの派閥のような穏健派は人間との共存を理想としている。まあつまり人類という種に寄生して生きる道を選んだということだ。
なぜモーリスがこの二つの派閥を選んだかの理由は推測がつく。
リビアが大事にしている魔導具を不当に手に入れるということはリビアの派閥と明らかに敵対するということになる。弱小派閥は最初からそんな危険を冒すことはできない。吸血鬼派閥同士の戦いは協定で禁忌とされているが、派閥間で力の差があるときはときたま破られることがある。
その場合は一つの派閥の巣と真祖である派閥ボスが一晩で綺麗に滅ぼされて、後に空っぽの巣だけが残るという形になる。
武闘派の一つ。『闇の牙』は武闘派ではあるが、今までに騒ぎを起こしたことがない。恐ろしく統率が取れているのだ。実際に世界を支配できる機会が訪れるまではただひたすらに静かに耐えている。それ故にアメリカに存在する五大派閥の中で対策局が一番恐れている吸血鬼派閥がこれである。
長老はシャンドリア・V・バランティ。アメリカ移民の時期にヨーロッパから移動して来た貴族の血筋で、リビアと同じく古い血に属している。
もう一つの武闘派は『血の呼び声』。例の吸血鬼バカ息子リチャード・V・ノーラスの父親であるアンドレア・V・ノーラスの派閥だ。
こちらはとにかく騒ぎを起こすのが好きな連中で対策局の悩みの種である。
この派閥は前回の事件以来、明確にリビアの派閥との対立姿勢を取っている。
対策局ニューヨーク支局に連絡を取り、そこで引き出した情報からざっと今後の行動を決めた。
まず手始めに吸血鬼のボスどもに会いに行かねば。たった一人で。
5)
最初に会いに行くのは『闇の牙』派閥の長であるシャンドリア・V・バランティだ。
彼はアメリカとカナダの国境付近の街であるアボッツフォードに居を構えている。正確に言うと国境線に敷地がかかるように建物を建てているのである。
人間に取っては国境線はただの地図の上に引かれた線に過ぎない。だが魔物に取っては違う。それは魔法の法則上での厳として存在する壁として作用する。彼はその居城を利用してアメリカとカナダの二つの国に同時に手を伸ばすことができる。
そのための場所だ。
有難いことにまだ使える妖精の道の一つがその近辺に繋がっている。それならたいして時間をかけずに訪れることができる。
セントラルパークまでタクシーで行き、入り組んだ木々の間に足を踏み込む。決まった時間になると一本の木の陰が他の影と交わり、小さなアーチを形作る。
短い呪文を唱えながらその影のアーチを潜る。そして歪んだ世界。妖精の道へと足を踏み入れた。
無数の闇の視線の中を駆け抜け、下り坂を登り、飢えに身震いする道を忍び足で通過する。
花開く肉食植物の葉の下を潜り、石畳の道は後ろ歩きで進んだ。一つでも対処を間違えればその道の所有者と殺し合いになる。
中央大分岐点につくと巨大なネズミが待ち構えていた。
そいつは私を見ると挨拶をしてきた。
「やあ、ダーク」
「どちら様でしたかな?」
「フィズだよ」
巨大ネズミは頭を掻いた。もちろんその正体はネズミではない。妖精だ。
「おや、フィズ。しばらく見ない間にでかくなったなあ」
「不思議だろ。何だか急に体が大きくなっちゃって」
「通行料は以前と同じだろうな。その大きさに見合う分だとこちらが干からびてミイラになってしまう」
「それは心配しないでくれ。値上げは来週からだ」
彼の気が変わる前に私は一滴の血を支払った。
あまりやるとまたフィズが大きくなってしまう。もっともフィズ自体は自分の成長の原因に気づいていない。天界で吸収した魔力を豊富に含んだ血を飲めばどんな生き物でも急速に成長してしまう。大盤振る舞いは失敗だった。あのときは気が動転していたからと言い訳しよう。
妖精の道から出た先は目的の吸血鬼の館のすぐそばだ。偶然ではない。シャンドリア長老もまた妖精の道の使用者に間違いない。
陽光の中に立つ吸血鬼の館は大きな古い石作りの洋館だ。百年も前から繁茂しているに違いないツタがその全体を覆っている。微かな血の匂いが館全体から立ち上っている。
日差しの下でもやっぱり暗くて陰気で不気味。実に魅力的な館だ。
一見人気が無いように見えるが、この館の中は怪しい気配で一杯だ。
少なくとも高位の吸血鬼が十体は潜んでいる。ここの戦力だけで人間の軍隊一大隊に匹敵すると見た。同じ魔物でもゴブリン・ギャングとは大違いだ。
錆びた門を押し、前庭に入る。
綺麗な花が一面に植えられている。これは実は大変なことだ。
吸血鬼が棲む場所の近くは生命力が乱れる影響で植物がすぐに枯れてしまう。恐らくここは一か月毎に庭の植物を植え替えている。この綺麗な前庭は驚くばかりの労力で維持されているのだ。
地上に存在する地獄の出張所の中にさらに作られた楽園の花畑。なんという自虐的な美なのか。
道を歩いて館の玄関へとたどり着く。
一応電話で予約は入れておいたので拒絶される心配はしていない。
ドアノッカーを鳴らす。
通常、吸血鬼は夜に活動する。だがここのシャンドリア長老は違う。無理に昼のリズムに合わせている。
それは背伸びというよりは、吸血鬼というくびきに対する挑戦だと思えた。
自分たちは太陽を恐れていないという表現だ。
何と誇り高いこと。
大きなドアがゆっくりと開くと、中から初老の男が現れた。慎重にドアが落とす影から踏み出さないようにしている。
高位の吸血鬼は直射日光にも耐性がある。だがそれは即死しないというだけであり、光をまともに浴びれば人間で言うならば火傷に相当する傷を負う。
さすがに光の精霊マドウフ・ベイルのような純粋な原初の光には高位の吸血鬼でも耐えることはできないが、あれはもう例外中の例外だ。
夜行性は私も同じだ。ドアの向こうの暗闇の中に恐れもみせずに滑り込む。
ドアを開けたのは執事の一人か。館の奥へと案内を始めた。周囲の壁の向こうで吸血鬼の気配が右往左往していたが、あえて無視する。
彼らは興味津々の割には私の目に見える範囲に出ないように注意している。
ゲストの扱いに関してかなり厳しく命じられているに違いない。臆病なのではない。ただ単に統率が取れているのだ。
執事の後ろ姿を観察する。匂いからしてやはり吸血鬼だ。吸血鬼は歳を取らないのでメイクで初老に見えるようにしているのだろう。
背後に装甲鉄板が隠されている廊下を抜け、奥の部屋へと導かれた。この辺りの作りはリビアのフラットと同じだ。
二重隔壁、ガンオイルの匂い、銀の匂い、酸の匂い、強くなる血の匂い。焼けた鉄に配線のビニールが微かに焦げる匂い。火薬それもプラスチック爆薬の粘っこい匂い。
この館全体が強固な要塞として建てられている。
何者かが襲ってきても、夜が来て全員がコウモリになって飛び立つまでは抵抗できるようになっている。
人間の内臓の匂いはしない。悲嘆を示すフェロモンの匂いも。ここでは派手な食事はしないことになっているのだろう。
少し気分が良くなった。賢いヤツは好きだ。たとえそれが敵であっても。
最後のドアが開くと大きな執務室が現れた。執事はそこに私を置くと姿を消した。
そこに居たのは二人。いや、二匹。
一匹はシャンドリア・V・バランティその人。オールバックに黒く撫でつけた髪。高級そうな、そして実際に目の玉が飛び出そうな値段のスーツ。均整の取れた体はスポーツ選手のものだ。彫りが深い顔立ち。穏やかな目つき。これはどこかの雑誌に出てきそうなナイスミドルと呼ぶべきか。
「やあ、ダーク。久しぶりと言うべきか」
「シャンドリア。たしかに久しぶりだな」
闇大戦の前に彼に会ったことがある。天界への闘争に加わるようにとの要請を携えてだ。賢くも彼の派閥はダークの頼みを断った。
あのときは危うく彼の派閥との大戦争になるところだった。
ダークは何にでも噛みつく愚か者だったから、リビアが間に入らなかったら悲惨なことになっていただろう。
「それと今の私はダークではない。ファーマソン神父と呼んでくれ」
自分が来ている神父服を強調して見せる。マグダラ尼僧のお大事の一品だ。
「神父の恰好とはひどい変装だな。ブラックジョークにしか思えない」
シャンドリアは眉を顰めてみせる。私は軽く十字を切って返す。彼はキリスト教徒ではないからこのシンボルは効き目がないと承知している。
「それと彼は」シャンドリアは隣の男を示した。「私のボディガードだ」
私よりも頭一つ大きい男が前に進み出ると右手を差し出した。肩の辺りが筋肉で膨れ上がっている。
どこのボディビル雑誌から抜け出して来たんだ。この男は?
それから以前見たファイルを思い出した。
三大人狼の一匹。通り名は巨狼のトライド。文字通り一匹オオカミの人生を送っていた男のはずだが、就職先を見つけたらしい。
私も右手を差し出して彼と握手をした。それから体内の魔力の壺を開いた。相手の方が体が大きいのだ。フェアプレイなど最初からやる気はない。
二つの右手が爆発的な力でお互いを握りつぶそうとぶつかりあった。
推定握力数十トン。大型プレス機の世界。間に挟まれたものは何でも潰れる強度だ。
魔力を1レベル増大し、右手に流し込む。ぎりぎりと周囲の空気が焼ける感じがした。
驚いた。私の力についてこれるものはそうそういない。
もう1レベル増大。推定握力数百トン。深海艇の強化外郭でも握り潰せる力だ。
急に相手の手から力が抜け、私も慌てて力を抜いた。もう少しで相手の手を握り潰すところだった。
「ボス」彼はシャンドリアに向けて真っ赤になった右手を振りながら言った。「彼は前よりも遥かに強くなっています」
闇の存在にとっては私を殺すことには多くのメリットがあるから、私が弱いと見たらここで殺すつもりだったのだろう。よくあることだ。
シャンドリアの顔に面白そうな表情が浮かんだ。
「お前でも敵わないのか?」
その問いに巨狼のトライドが答える。
「彼がアルファです。彼がその気になれば我々は終わりです」
「では丁寧に対応しなくてはな」
シャンドリアは私に目の前の椅子を示すと、自分も対面に座った。食えない『紳士』さまだ。
応接セットは豪華だった。吸血鬼の派閥はどれも金持ちだ。どこも金持ちの吸血侍従をたくさん抱えてそこから大金を吸い上げている。
シャンドリアはテーブルから葉巻を一本取ると、私にも勧めてきた。もちろん断る。人狼の類は例外なく匂いが強すぎる葉巻は嫌いだ。
「そうか。では私は遠慮なく」
そう言うとシャンドリアは伸びた爪の一本で葉巻の先端を切り落とすと火をつける。吸血鬼の爪はどんな刃物よりも鋭い。
「さて、君がここに来た理由は分かる。リビアのところから盗まれた古代魔導具の件だな」
私の体に走った殺気に反応して、彼の背後に立っているトライドがびくりとした。
「そう緊張することはない。どうして私がそれを知ったのかって? 別にそういう噂が流れているわけではない。簡単だよ。モーリスに聞いた」
私は彼の目を見つめた。これは罠か?
「モーリスとは電話で話しただけだよ。直接会ったわけではない。結構吹っ掛けてきたよ。魔導具と引き換えに永遠に吸血侍従にしろと言っていたな」
「で? その提案に乗ったのか?」
いけない。つい声が厳しくなってしまった。一歩間違えればこの館の中にいる高位吸血鬼の群れすべてを含めての戦いになる。
「乗るわけがない。確かに古代魔導具は貴重だ。それを手に入れるためならば戦争も辞さないほどに。だがこの魔導具にはそこまでの魅力がない。実はそれがどんな魔導具か知っているんだ」
「なに!?」
「元はリビアの祖母が持っていたものなのさ。弱小派閥だったリビアの派閥がここまで大きくなったのはその祖母の働きが大きい」
初耳だ。リビアの祖母となると一万年も前の話になりかねない。
「ひどいクソ婆だったよ」
上品なシャンドリアの口から出るとは思えない汚い言葉だ。そうせざるを得ないほど実際にひどい人物だったのだろう。
「だからあの魔導具は良く知っている。だが私には使えない。だから興味はない。そんなもののためにリビアの派閥と戦争を起こす気はない」
彼は真実を言っているのだろうか?
ギースを使えば真偽を確かめるのは簡単だが、そんなギースをシャンドリアが受けるわけがない。古い血の吸血鬼は絶対に人に話せない秘密の百や二百は抱えているものだ。下手に真実のギースを受けて、その直後に別の質問をされたらまずいことになる。
「私も無用なトラブルは好まない。これならどうかな?」
私の心を読んだかのように、シャンドリアはギースの仕草をして言葉を紡いだ。
「ギースの誓約の下、私シャンドリア・V・バランティはモーリスと魔導具の取引をしていないことを証言する」
取引の対価を必要としない一方通行のギースだ。私はそれを受ける。ギースの魔法の帳が降り、契約が成立した。ギースが成立するということは、彼が真実を述べているということだ。
シャンドリアは手の中の葉巻を消して、両手を叩き合わせた。
「さあ、トライド。お客さんはお帰りだ。玄関まで送って差し上げなさい」
促されるままに私は館を後にした。
妖精の道はまだ開いたままだ。私はそこに足を踏み入れた。
6)
さて、こうなるとモーリスと取引する可能性があるのはアンドレア・V・ノーラスだけだ。
特に彼の派閥『血の呼び声』はリビアの派閥『血の盟約』に深い恨みを持っている。あの吸血鬼の馬鹿息子リチャードのせいだ。
この馬鹿息子はよりにもよってリビアの縄張りで大増殖を始め、その結果として鋼鉄のシェルター内に無酸素状態で封印された。そしてこれから先数百年はそのままにされることになった。そのとき、対策局に手を貸したのがリビアだ。
つまりは逆恨みということだ。リビアが口を利かねば封印どころか滅殺されていたろうに。
アンドレアに取ってはリビアの方から戦争を起こしてくれるなら望むところだろう。吸血鬼派閥間での戦争は一応タブーだからだ。最初に戦争を始めた派閥には誰も手を貸さないことになる。
アンドレアが公開している電話番号に連絡してみたが応答が無いので、対策局ニューヨーク支部に電話をして、彼の動向を聞いてみた。
「しばらくお待ちください」
冷たい声の受け付けの声が返って来た後に回線が切り替わり、いきなりアナンシ司教の怒鳴り声が響いてきた。その場でスマホをゴミ箱に投げ入れたくなったが、何とか抑えた。
「どこで油を売っている! すぐに帰ってこい」
私が今何をしているのか言うべきかどうか。
言うべきだ。対策局の情報は必要だ。ここで時間を食えば、モーリスが取引を終えてしまう。今アナンシ司教に邪魔をされるわけにいかない。
「ハンバーグを探しています」
「なに?」
電話の向こうでアナンシ司教が目を剥くのが想像できた。
対策局では一か月毎に秘密の暗号コードを変える。今月の符牒表ではハンバーグは古代魔導具を意味する。絶対に使わないだろうと思っていたコードだ。
「友人の自宅からハンバーグが盗まれました。今それを追っています。見つけて元の持ち主に返さないと、コアラがパーティを始めてしまいます」
コアラは吸血鬼で、パーティとは戦争だ。吸血派閥は大勢の人間の大富豪と関わりがあるのでその影響は人間界にも広く及ぶことになる。
「本当か?」アナンシ司教は疑り深い。
「本当です」
それ以上は何も言わない。彼の中で悪い想像が膨らむに任せる。
「分かった。確実にそれを片付けてこい。それができたら今までのことは不問にする」
「了解です」
電話を切った。長く話していると今度は何を言いだすかわからない。
見つけた古代魔導具を対策局に納めろなどと言われたら困る。そんなことをしたら対策局とリビアの派閥での戦争になってしまう。
再び対策局ニューヨーク支部に繋ぐ。先ほどのオペレーターが出た。
「ファーマソン神父。最優先権が貴方に設定されました。何をいたしましょう?」
さすがアナンシ司教は仕事が早い。色々性格には問題がある人物だが、こと仕事に関しては有能かつ真摯だ。彼は仕事自体には私情を挟むことはない。
「吸血鬼派閥『血の呼び声』のアンドレア・V・ノーラスの居所を調べてくれ」
対策局の仕事の一つに各吸血鬼派閥の長老級の人物の監視がある。だから答えはすぐに帰って来た。
「ノーラスは居城に居ません。二日前に名だたる幹部を連れてニューヨークに向かっています」
ビンゴだ。
モーリスと取引したのはコイツだ。半吸血鬼であるモーリスに警戒厳重なニューヨークの境界を越えて貴重な魔導具を運ばせるよりはと、自ら足を運んで来たのだ。
ニュヨークのどこかに居るモーリスの下へ赴き直接取引するつもりだろう。
考えてみた。
モーリスが一番避けたいのは魔導具をノーラスに奪われることだ。吸血鬼がその気になれば普通の人間と大して差のない半吸血鬼のモーリスには為す術もない。
自分をノーラスの吸血侍従にさせるにはギースを使わせるしかない。モーリス自身は魔法を使えないから、ギースをかけるのはノーラスでないといけない。
どうやってノーラスにギースを迫る?
答えは爆薬だ。魔導具のネックレスに爆薬を仕掛けてその解除をギースの条件に盛り込むのだ。吸血侍従化とネックレスの無事な譲渡の取引だ。その文言もすでに熟考してあるに違いない。
ギースを遠隔でかけることは可能だが、距離が離れるほどにギースを成立させるのに必要な魔力の量は増大する。ギースによる生命力枯渇で死にたくなければ対面で掛けるのが鉄則である。
といいうことはノーラスから辿れば、モーリスへと辿りつくはずだ。問題はノーラスが魔導具を手に入れる前にモーリスを見つけることができるかどうかだ。
いくつかの作戦を考えてみてから、私は連絡を取っておいた魔導士のアーダラクとシェイプシフターのアラバムが到着するのを待った。
これには二人の力が要る。
ノーラス一行はニューヨークの有名ホテルの最上階を1フロアまるごと借り切っていた。ペントハウスになっているやつだ。
リビアもそうだが高位吸血鬼は高いところに住みたがる。太陽光線に少しの間でも堪えられるならば、最上階はコウモリになって逃げるときに有利だし、襲撃するにも困難だからだ。
逆に低位吸血鬼は地下の穴蔵を好む。憎むべき太陽からできるだけ離れようという本能が強いためだ。
一応アポは取った。私は喧嘩を売りに来たのではないからだ。
エレベータを出るとそこで待っていたのは二匹の吸血鬼だ。高価なスーツに身を固めて見かけだけの上品さを纏っている。
私の顔を見ると、左側の一匹がハンドトーキーに向かって喋った。
「ボス。ダークの野郎が来ました」
ダークの野郎? なんてひどい言いざまだ。
もし私が本当にダークだったら、こいつはその場で首をむしり取られていただろう。
「ファーマソン神父だ」改めて自己紹介する。
「どちらでもいい。通んな。奥でボスがお待ちかねだ」
そう言いながら胸のホルスターに吊るした銃を見せつける。そこから銀の匂いがする。
誰もが思う。俺は銀の弾丸を持っているから人狼を恐れることはないと。
そして人狼と実際に戦ってみると誰もが思う。どうして弾が当たらないんだと。
相手の得意げな顔が絶望に歪むのを見るのが、実を言えば私は好きだ。ダークは神の経験を得てファーマソン神父に成長はしたが、持って生まれた性格というものはそう変わるものではない。ただ単に、それを抑えることを学ぶだけなのだ。
二匹の間を抜けて、私は奥に進んだ。耳の奥に小さな無数の嗚咽が聞こえる。左のドアの奥からだ。怯えた人間が放つフェロモンが匂う。それと大量の血だ。
廊下の一番奥にあるリビングルームにノーラスは陣取っていた。
ノーラスはかなり太った中年の男だ。髪は豊かだが、若くは見えない。顔は整っているが、退廃の色がその上を濃く覆っていて、だらしなく見える。
背後に見覚えのない三匹の人狼が立って護衛している。対策局に未登録の連中で、いわゆる野良と呼ばれる人狼傭兵たちだ。
吸血鬼がどれも美貌に恵まれるのは、その時代その時代での美男美女を食料とするからだと言うのが、対策局所属の科学者の結論だ。彼らは吸血の際に獲物の遺伝子を取り込むことができると見られている。
ノーラスがあまり美しくないのは、吸血相手を選んでいないためだ。手当たり次第に人血を飲んでいるに違いない。その体形が語る通りに恐ろしく大食いなのだろう。
ノーラスは椅子を勧めようとはしなかった。それどころか椅子に体を沈め、テーブルの上に足を載せて、その汚い足の裏を私に向けている。
この親にしてあのバカ息子ありかと納得した。
先に口を開いたのはノーラスだった。
「何の用だ。ダーク。対策局に文句を言われるようなことはしていないぞ」
バカ息子の大繁殖騒ぎは無かったことにしているようだ。あれはあらゆる方面にかなりの遺恨を残している。
「私がここに来た理由はわかっているだろう? ノーラス」
私は彼の足が載っているテーブルの端に腰かけた。
テーブルの上には高級ブランデーと氷、そしてやっぱり葉巻が置いてある。
もしかしたらこいつはあのシャンドリア長老に対抗心を燃やしているのか?
私は断りもせずに葉巻を取ると、先端を毟り取ってからそれに火をつけた。鼻を刺す煙が葉巻から立ち上る。
「今はリビアの頼みで動いている。対策局はこれには関わっていない」
「ほう。あのアマがどうしたって?」
「分かっているだろ? 悪いことは言わない。モーリスとの取引は止めろ。吸血鬼戦争を始めるつもりか?」
「もしそうだと言ったら?
それに、ダーク。お前はそういうことを気にするタマだったかね?
むしろ騒ぎは大歓迎じゃなかったか?」
おやおや、大きくでるなあ。その昔はダークに会いたくなくて逃げ回っていた癖に。しばらく見ない間に吸血鬼は変わるものだ。そんな心の中の思いをぐっと堪える。
「ダークはそうだろうな。だが今の私はファーマソン神父だ」
「分からんな」
ノーラスは背後の人狼たちに合図をした。
「それよりも、ダーク。お前の腕が鈍っていないか試してやろうか。ずいぶんヤワになったと聞いたからな」
じゅうと音がした。私が手にした葉巻をノーラスの足の裏に押しつけたからだ。慌てたノーラスは足を引っ込めた拍子に椅子から転げ落ちた。
まったく、吸血鬼特有の優雅さもない男だ。これが一大派閥の長だというのが頭が痛い。遠からず彼の派閥は次の闇大戦の種となるだろう。
三匹の人狼たちがざわついた。戦いのときと見て獣化現象を起こしその体が膨れ上がる。体毛が濃くなり、人間の顔が変形して狼のそれに取って替わる。
今日は満月でもないのに獣化できるということはそれなりに訓練を積んだ人狼ということだ。人狼傭兵と見た私の目は間違ってはいなかった。
いきなり私は咆哮を放った。その声は部屋中どころかホテル全体に響いた。
狼王の咆哮だ。
魔王の咆哮だ。
死の遣いの咆哮だ。
雄叫びは世界のすべてを埋め尽くし、聞いた者の魂を畏怖と絶望へと貶める。
轟轟と荒れる風の中で何か恐ろしい存在が自分を見つめている。そう感じさせる狼の咆哮だ。
三匹の人狼が床に伏せた。いずれも両耳を抑えて、その場にうずくまる。
ぐらぐらする頭を押さえながらノーラスが怒鳴った。
「馬鹿どもが。攻撃しろ!」
一匹が申し訳なさそうに答えた。
「勝てません。ボス。彼がアルファです」
「雇い主は私だぞ。前払いはしてある。お前たちは死ぬまで契約に従う義務がある」
恐らく彼らにはギースをかけてある。契約を破れば確実に死ぬ。
「わかりました。ボス」
三匹はよろよろと立ち上がった。死を避ける本能とボディガードの義務の板挟みになっている。ここで雇い主を見捨てれば彼らの誇りもキャリアも粉々に砕けてしまう。それ以前にギースの報いが来る。
善しと私は思った。死を恐れるなど人狼にあってはならぬことと、子狼のときから叩き込まれるのが我ら人狼の定めなのだ。
「いいぞ。お前たち」俺はにやりとした。「俺に逆らうことを許す」
狼フォームに変身はしない。この状態で変身したら神父服が裂けてしまう。そんなことになったらマグダラ尼僧に後で何て言われるか空恐ろしい。
先頭の人狼が飛び掛かって来た。両手を前に伸ばし、鋼鉄の強度になった爪と大きく開いた顎による攻撃だ。防御は完全に無視の人狼スタイルの攻撃行動だ。
一瞬で私の手の中にナイフが現れる。特殊鋼のナイフと銀のナイフだ。
特殊鋼のナイフで相手の左手を切り落とし、銀のナイフの先端で相手の右手を貫く。蹴り上げた足で相手の顎まるごとを下から蹴り上げて粉砕する。
相手は一瞬で脳震盪を起こし、その場に崩れ落ちた。切り落とした方の腕の血管がみるみる内に塞がり出血が止まる。そいつが脳震盪から立ち直る前に首を蹴り飛ばし、頸骨を折る。人狼にはこれは致命傷にはならないが再生して動けるようになるまでしばらくかかる。
左後ろに居たヤツは自分でも銀のナイフを出してきた。俺のよりも長めものだ。人間の目では見えない速度でそのナイフを突き出して来る。
俺は前進し、突き出されたナイフを指で掴んで止めた。相手は人狼の怪力でナイフを引っ張ったが、俺はそれ以上の力でナイフを固定した。
少しの間の力のせめぎ合いの後に、銀のナイフが中央から折れた。反動で相手が後ろにたたらを踏んだところで、俺は折れたナイフの欠片をそいつの足の甲に打ち込んで床に縫い留めた。
動けなくなったそいつの両肩に連続で蹴りを叩き込み、砕けた関節の隙間に自分の銀のナイフを突き刺しておく。こうなるといくら人狼でもすぐには治らない。傷口についた銀の粒子が再生を阻害するからだ。そいつから離れざまに背骨を蹴りつけて綺麗に折っておく。
最後の一人が使ったのは銃だ。自動拳銃を私に向けて銀の弾丸を連射した。銃のスライドが停止したときには俺はすでに彼の前にはいなかった。拳銃程度の弾速では俺の動きについてはこれない。
素早くナイフを腰のホルスターに納めてから、そいつを殴った。
鋼よりも硬い拳がそいつの体をただの肉袋になるまで砕く。三十発まで数えたところで拳を引き、壁に貼りついた人狼の残骸を眺める。
ここまでやっても人狼には致命傷にはならない。だが普通の人狼だから再生するには丸一日は優にかかるだろう。
私は手首から小さなカプセルを出すとそれを砕き、手のひらに転げ出てきたものを壁についた派手な血のシミの中に貼り付けた。それは素早く魔法を発動して透明化し、見えなくなる。
私の背中に隠れて、ノーラスにはこれが見えていなかったはずだ。
これで良し。細工はできた。
それからまだ床に転がっているままのノーラスの上に立った。
「有難うよ。ノーラス。面白い趣向だったぞ」
まだ俺はダークのままだ。血を見ると、いつもダークはこの世に居座りたがる。
私はノーラスに顔を近づけた。
ノーラスの目がすっと細くなる。彼は一切怯えていない。さすがに吸血鬼派閥のボスだけはある。
ノーラスは私を避けて立ち上がると、服の埃を軽く払う。
「ずいぶん弱くなったと噂で聞いたのだがな。どうやら間違いだったようだ」
優しさを弱さと勘違いする輩は多い。こいつもその類の馬鹿だ。
吸血鬼五大派閥のボスともなれば簡単には殺せない。殺せば派閥間の危ういバランスが崩れて吸血鬼大戦が始まってしまう。そしてそれは第二次闇大戦の引き金になりかねない。
ヤツはそれを良く知っている。仮にも対策局に身を置いている者がそんな危険は冒さないことを。
ノーラスは背後の壁に貼りついたままの人狼の残骸を見ると顔を顰めた。
「高い金を取っておいてこの体たらくか。まったく役立たずの人狼どもが」
私の手が無意識に動き、特殊鋼のナイフをノーラスの喉首に突き付けていた。
「殺してはいない。死んだように見えていても。再生するまで大事に扱え。もし一匹でも死んだと分かったら、俺はお前の前に帰って来る」
ナイフを引いた。
「そのときは吸血鬼派閥がどうなろうが気にしない。人狼を殺してよいのは群れのボスである俺だけだ」
別に人狼たちから選ばれたわけではない。だが俺は生まれながらにして人狼の群れのアルファなのだ。
ノーラスは部屋の外で機会を伺っている高位吸血鬼たちを呼ばなかった。吸血鬼にしか聞こえない超高周波音で動くなと命令を下しているのだろう。
襲い掛かってくれればよかったのにとはダークの思いだ。
「とにかく、モーリスとの取引はするな。ただでさえ騒がしいこの世の中をひっくり返すな」
ノーラスは何も答えない。下手に言葉を紡ぐと、ギースに繋がりかねないからだ。口は災いの元という言葉は魔法が働く世界では真理だ。
私は扉を押すと廊下に出た。そこでは高位吸血鬼たちが殺気に満ちた表情でずらりと並んでいる。だがどいつも私に手は出さない。吸血鬼に取ってボスの命令は絶対だからだ。
ノーラスが魔導具を入手すれば、それですぐにリビア派閥との戦争が起きる。ここで私と本格的な騒ぎを起こしたりすれば彼の戦力は相当な被害を受ける。そうなればノーラス派閥は詰むことになる。
つまるところ、私はノーラスに手が出せないし、ノーラスも私には手が出せない。その前提の下で両者は危ういゲームをしているのだ。
廊下を歩く。背後にぞろぞろと吸血鬼どもが脅すようについて来る。私はわざと振り返りもしない。
ホテルのエレベータの前に立ったところで、門番役の二匹の吸血鬼が待っていた。
早く帰れと言わんばかりに、一匹がエレベータの呼び出しボタンを押す。
それを完全に無視すると私は足を止めて右手のドアの前に立った。あの小さな悲鳴が聞こえていたドアだ。
どうせ鍵がかかっている。それを確かめる手間などかけない。
吸血鬼どもが止める間もなくドアの両側に手を埋め込んで壁からまるごと引きはがした。大音響とともに金具が弾け飛び壁が崩れる。
周囲で吸血鬼どもの怒気が膨れ上がったが無視した。部屋の中は暗いが人狼は暗視ができる。瞳孔が素早く開き一瞬で明確な視界が戻る。
部屋の中には大勢の女性が身を寄せ合っていた。全員ひどく怯えている。隅に二人ほど横たわって動かない女性がいる。
吸血鬼の食糧庫。
明かりのスイッチを見つけてつける。
明るくなると惨状はもっと明確になる。あちらこちらに血が飛び散っている。彼女たちの服装はまちまちだが若いのだけは共通している。どこかのバーやクラブから言葉巧みに誘拐されてきた女性たちだろう。
外からの光の中に浮かんだ私の神父服を見て、彼女たちの瞳にようやく希望の光が灯る。この乱暴な闖入者が吸血鬼の仲間ではないと分かったのだ。
私は彼女たちの注目を引くために手を叩いた。
「さて、みんな、答えて欲しい。この中に契約の下に彼らに買われて来た、もしくは奴隷となった者はいるかな? いるならば手を挙げて欲しい」
契約の下に自分を売った者たちに対策局は手を延ばさない。それは魔物たちと対策局の約定に定められている。彼らがそうなら私も助ける気はない。契約は常に順守されるべきものだからだ。でなければこの世は無法で満ちてしまう。
私の問いに女性たちは黙ったままだ。
「君たちはニュヨーク在住?」
手近にいた女性が弱よわしく頷く。
「では君たちは違法に誘拐されたことになる」
ここで言う法とは吸血鬼の法だ。
ニューヨークはリビアの縄張りだ。ここに住む人間を他の地域の吸血鬼が許可なく狩ることはできない。
そしてリビアがノーラスに狩りの許可を出すことはあり得ない。
ノーラスは勝手にニューヨークで狩りをし、契約もしていない人間の血を飲んでいたのだ。これだけでも相当にやばい行為だ。
「よし、じゃあ皆お家に帰る時間だ。全員こちらに来なさい」
「何を勝手なことを」門番の一匹が前に出た。
次の瞬間、そいつの首は私の手の中にあり、千切られた首から呪われた血を噴き出す自分の体を見つめていた。
高位吸血鬼の感覚は人間よりも遥かに鋭いが、高速モードの私の動きを見ることができる者はその中でもわずかにしかいない。
私は手の中の首を門番の片割れに押しつけて言った。
「誘拐の現行犯として対策局の権限で犯人を処罰した。それをボスに渡し、そう伝言しなさい」
実際には伝言などしなくても、この群れのボスであるノーラスには分かっているはずだ。これらの行為を命じたのはもちろんノーラスだが、それを声高らかに糾弾するわけにはいかない。まだその段階ではないのだ。
目の前で何が行われたのかようやく理解した吸血鬼たちが私を殺そうと殺到しかけたが、その動きは止まった。耳の奥で微かに耳鳴りがする。ノーラスが配下に超音波の命令を下している。内容は私に手を出すな、だろう。
怯えている女性たちを一人一人引き出すと、上がって来たエレベータの中に押し込む。
「できれば誰にも何も言わないよう」そう念を押した。背後で牙を剥いている吸血鬼どもを指で示す。「噂を聞きつけるとまた彼らが君たちの家を訪れることになる」
全員を逃がすまでにエレベータを五回ほど往復させた。ホテルのロビーは今頃大騒ぎだろうが、それ以上のことは起きない。警官隊が呼ばれることもなければ新聞記者が寄って来ることもない。
吸血鬼派閥は大富豪の吸血侍従を抱えていて、実に悲しいことに金は人間世界のすべてを律している。
最期の一人をエレベータに押し込むと私は言った。
「これからは夜遊びはほどほどにするように。神の加護があらんことを。アーメン」
存在しない神の加護というものがどんなものかと想像してちょっと憂鬱になった。
吸血鬼どもの憎しみの視線を無視して、部屋の中に入ると横たわっている二人の女性の死亡を確かめる。血液はすべて吸い尽くされている。吸血行為は被害者を殺さなくても行えるのにわざと死ぬまで吸ったのだ。
いつかこの吸血鬼どもも報いを受ける日がやってくるだろう。あるいはダークのように償いの日々を送るようになるのかもしれない。
天の定めを誰が知る?
死体二つを抱え上げ、私もエレベータに乗った。ここに捨て置くのはあまりにも可哀そうだから。