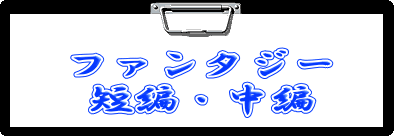
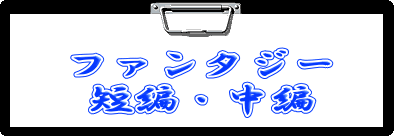
私の名前はファーマソン・W・ライト。もちろん偽名だ。皆の間ではファーマソン神父として通っている。
本名は何かって?
おいおい、勘弁してくれ。バチカン特殊事例対策局の中で本名なんか使っていた日には、明日の朝には死体になっている。あるいはもっと別の何かにだな。この部局の中では現実と非現実という言葉が別の意味を帯びている。
その日、私はバチカンの古文書保管室の中で稀覯本を探していた。古文書保管室と言っても表のヤツではなく、裏のヤツだ。ここには絶対に部外者の目に触れさせるわけにはいかない古い書物が厳重な管理の下で眠っている。
古文書保管室に入れるのはバチカンの中でも一番高いセキュリティを持っている者だけ。この部屋に封印されている本の一冊でも外へ出たら、恐らくは巷のあらゆる稀覯本収集家やオカルチスト、それに悪魔崇拝の連中が争奪戦を繰り広げることになる。それからそういった騒ぎが鼻で笑えるほどの大災害が起きる。
ソロモンの大いなる鍵の完全本など市井に流れたりしたら一体どうなるかは神のみぞ知るだ。だからこそ、この部屋は核爆弾が落ちても大丈夫なぐらいの魔術で守られている。そんじょそこらの魔導士や軍隊程度では近寄ることもできはしない。
もちろん私でさえもこれらの本を勝手に持ち出すことはできない。持ち出そうとすれば管理官に銀の弾丸で撃ち殺されてしまうことになる。
あちらの部署にお百度を踏み、こちらの部署に百科事典並みに分厚い書類を出し、そちらの司教頭の肩を揉み、最後に法王の恥ずかしい秘密をどこかから掘り出して直接に脅す。そこまでしてようやく許可は下りた。
探していたテウルギア・ゴエティアを見つけ、手の中で身をよじるその本を苦労して抑えつけながら、目的のページを見つけ出す。この本はソロモンの小さな鍵と呼ばれる五冊のシリーズの内の一つで、精霊と悪魔の使役法が書かれている魔導書だ。
目的のページの記述を何度も読んで心に刻みつける。この本から読み出すことができるのはその内の一ページだけという制限を持つ。それも常に注意していないと記憶から抜け落ちてしまう。それは制限というよりは忘却の呪いに近い。
おまけにこいつはコピー機も写真機も一切受け付けない。電子回路は焼き切れて故障するし、フィルムはその場で燃え上がる。ペンは割れ、紙は燃え上がり、石板に刻めば粉々に割れる。つまりは頭の中に記憶するしか呪文を持ち出す方法は無いということだ。
本の所有者だけが本の呪文を自由に使える仕組みになっていて、ある意味では本が所有者を縛り付けているとも言える。
これはすべて本に宿る魔法の力というヤツで、今の時代にはこういった古代魔法を操れる魔導士は存在していないのだからまったく持って厄介な話だ。
私が必要としているのはある悪魔の名前と使役法だ。それがつまり今抱えている案件の解決の鍵なのだ。
悪魔の召喚と言ってもそう簡単な話ではない。まず最初にその悪魔の苦手とする精霊か天使を呼び出し、その監視下で目的の悪魔を呼び出す。でなければ悪魔の最初の生贄は召喚者自身ということになりかねない。
ああ、どうしてこう私の下に来る案件は面倒なものばかりなのだろう。
何度も頭の中で悪魔の名前を唱えながら回廊を歩いていると、助手のアンディが私を見つけた。
アンディはまだ若い神学生だ。以前にちょっとした事件でバチカンの秘密に触れてしまい、半ば強制的に私の助手とされてしまった可哀想な若者だ。もっとも本人はそれほど自分の境遇については気にしていないようだが。
「ファーマソン神父」
アンディは紅潮した顔で呼びかけてきた。走って来たのか、息が切れている。
「V案件です」
さらなる面倒の始まりを知って、私は背を伸ばした。
*
大きな大理石の机を前にして豪華な椅子に座っているアナンシ司教は対策局の総責任者だ。どうやればこんなに太るのかと言うばかりに恰幅の良い男で、恐らく体重は五百ポンドを越えている。どう考えても暴食という大罪の徒なのであるが、彼が実際にたくさん食べている所を見た者がいないので、それが責められたことはなかった。
まあ、対策局の全員から恐怖と畏怖の目で見られている彼を責めようなんていう人間はどこにもいないのが真相なのだが。
大理石の大きな机の上には何を表すのか分からない奇妙な小さな大理石の像が所狭しと並べられている。その一つ一つが世界のどこかから報告された事件を示している。いくつかの大理石の像の横には青いガラスで作られた小さな像が置かれている。この青の小像が対策局の局員を示している。
置いてある大理石の像に比べて青ガラスの小像の数は余りにも少ないのが分かる。
アナンシ司教は青ガラスの小像を一つ取り上げると自分の前に置いた。
つまりはこれが私を表す像だ。像はオオカミの形をしている。
「V案件と聞きましたが、場所はどこです?」
余分な挨拶はせずにすぐに本題に入った。アナンシ司教も余計なことは言わずに簡潔に返した。
「ニューヨークだ」
少しばかり驚いた。ニューヨークは夜の女王と異名を持つ吸血鬼リビアの縄張りだ。そこで今更V案件が起きるわけがない。リビアがバンパイアハンターに滅ぼされでもしない限りは。そしてリビアを滅ぼせるようなバンパイアハンターはこの世にはもういない。以前に私が殺したからだ。
「チャーター便を用意した。すぐに飛んでくれ。詳細はこれだ」
アナンシ司教はテーブルの上に書類を投げた。お行儀が悪いが、あの体重ではきっと椅子から立ち上がるのが面倒なのだろう。ちなみに彼の座っている椅子は特注品で、象の体重にも耐えられるという触れ込みだ。
四の五の言わずに空港へ急ぎ、バチカン対策局ご用達のジェットに乗った。正確に言うと超音速巡航が可能な戦闘機にだ。これ自体は試作のみで終わった機体で型番は無い。マッハ5で真っすぐ目的地へ向けて飛んだと言えばどんな物騒な代物かは分かると思う。
Gスーツを着せられた飛行の間中、複座席の後ろにしがみつく羽目になった。もちろんサービスの機内食も無ければキャビンアテンダントも無し。まったく無粋な旅行だよ。まあ自分で操縦するのではないだけマシかもしれないが。対策局の人使いの荒さは有名なのだ。
その間ずっと、古文書保管室から持ち出した知識を頭の中で反芻していた。この古文書の魔法の呪文は忘却の呪いと一セットになっている。常に反芻して記憶を新しくしないと頭の中から消えてしまう。もちろんこの作業はものすごく辛い。この新しい仕事を終わらせて中断した仕事に戻るまで、この苦痛は続くことになる。
すべての努力を放棄してあっさりと呪文を忘れてしまうことも考えた。その場合はあの面倒で退屈で嫌みな承認の手順をまた最初から繰り返すことになる。
ぶるるるる。それだけは勘弁願いたい。私の以前の行いのせいで、バチカンの上層部は私に対しては特に厳しい態度を取っていることが恨めしい。
空港での入国審査も特別に免除された。ああ、偉大なるかな我がバチカンの権力よ。そのままタクシーを飛ばしてリビアのフラットへ向かう。私の着ている神父服に免じてチップは負けて貰えた。
ああ、見知らぬタクシーの運転手よ。貴方の魂に祝福があらんことを。
リビアが棲んでいるのは八十一階建てのタワーマンション最上階だ。そのフロアを丸ごと買って自分の城に改造してある。つまり装甲鉄板を壁に埋め込んで要塞化してあるのだ。窓の傍には自動対空砲座を設置して空からの攻撃も防げるようになっている。まあ立場上仕方がないとは言え、怖い女性だよ。まったく。
もちろん彼女は大金持ちだ。この国の吸血鬼の総元締めだし、それ以外にも大勢の人間の臣下を抱えている。彼らはリビアが与える永遠の命を求めてあらゆる物をリビアの足下に捧げる奴隷なのだ。
羨ましいかって? 確かに。
代わりたいかって? ノーだ。あんな重責のある立場にはなりたくない。
すでに夕刻だ。リビアの居る最上階には昼間はエレベータが上がらないようになっている。日が落ちて初めてリビアの下へたどり着けるようになっているのだ。
かなり前に教えて貰ったパスワードはまだ有効で、私は八十一階への専用エレベータに乗ることができた。ロケットよりも速く上昇する高速エレベータの扉が開くと、目の前には自動小銃を構えたリビアの僕たちが待ち構えていた。リビアによる軽い魅了の魔法にかかってはいるが普通の人間たちだ。
「リビアにアポは取ってある。ファーマソン神父だ」
「いらっしゃいませ。何かご身分を証明できるものはお持ちでしょうか?」
護衛の一人が慇懃に尋ねて来た。身に纏っている暴力の雰囲気にそぐわない口調は、生き延びるための方便だ。リビアの客たちは気の荒い者が多い。来客の機嫌を損ねた時点で殺される可能性が高く、その場合には彼らが構える自動小銃など子供の玩具に過ぎなくなる。
もっとも対峙する相手が何者かが分かっていればまた別の話だが。
この自動小銃には銀の弾丸が装填されているのだろうか?
身分の証明か。取り合えずこの護衛の一人を爪で八つ裂きにするというのがいいかな。それとも彼らの目に見えない速さで先頭にいる一人の首を一回転させて元の向きにするというのも捨てがたい。そんな物騒な衝動が沸き上がって来るのを無理に抑えて、私は彼らに唇を剥いて人間ではあり得ない発達した犬歯を見せた。
「その人を中に通しなさい」
恐らくはスピーカーからの声だ。護衛たちが緊張を解くと左右に道を開けた。もちろん周囲には監視カメラが埋め込まれていてリビアはそれを見ていたのだろう。
左右に豪華な調度の並んだ廊下を進む。壁には値も付けられない古くて貴重な風景画が並んでいる。どれも何百年も昔の画家が描いたものだ。
リビアのここ千年での趣味は芸術家の青田買いだ。まだ名も売れていない芸術家を見つけて援助する。その対価としてその芸術家が作り上げたものの中で最高傑作を差し出すことになる。
過去には差し出さずに逃げた者もいたが、その中で逃げ切れた者はいない。人間には昼と夜があるが、リビアは夜の女王なのだから夜にいるときはその眼を逃れることはできない。
突き当りのこれも豪華に装飾された扉を開くと、そこはリビアの謁見室だ。巨大な漆黒の玉座に彼女が座っている。流れる黒い滝のような長髪は今は頭の上に丸く結い上げている。無数の金と銀と宝石に飾られて嫣然と微笑む美の塊がそこに居た。
ニューヨークの吸血鬼のボス、リビア・V・アルマニス。その人だ。
そして彼女こそ今回のV案件、つまりバンパイア事件をバチカンに報告してきた通報者だ。
「久しぶりね。ダーク。二百年ぶりかしら」
そう言いながら彼女は眼差しを向けて来た。傾国の美女という言葉は、彼女にこそふさわしい。その眼差しを我が身に得るためなら己の血のすべてを捧げても良いという男は無数にいるだろう。
「せいぜい十年という所だよ。リビア。それに今の私の名前はファーマソンだ」
「そういうことね。ファーマソン神父。今はバチカンの対策局員をやっているのよね」
それから小さくつぶやいた。
「信じられない」
最後の部分は私に聞かせるために言ったのではない。だが私の耳はもの凄く鋭い。
「これも時代さ。それより報告のあった件だが」
リビアは玉座の上で姿勢を変えた。さらさらした生地のドレスが揺れ、足元が少しだけ顕わになる。普通の男ならそれを見ただけで欲情してしまうだろう。高位の吸血鬼はその動きの一つ一つが性的な意味で彩られている。それは彼らから発散されている大量の性フェロモンと相まって絶大な効果を発揮する。この動きがそもそも本能的なものなのか、それとも何百年という歳月をかけて磨き上げたものなのかは分からない。少なくともリビアは最初にあったときからこうだった。
かっては恋人だった時期もある。それももう遠い昔の話だ。
「リチャード・V・ノーラスという男をご存じ?」
「記憶にはないな」私は首を横に振った。
実はすでに対策局のファイルでその名前を見ている。だが世の中というものは知らない振りをした方が相手から多くの情報を引き出すことができるものなのだ。
「元はうちに客人として預かっていた別分派の吸血鬼だったのよね。それがいま暴走しているの」
現在世界中の吸血鬼は五人の長老がそれぞれ率いる五つの派閥で構成されている。その内の四つが人類と共存を望む穏健派で、残る一つが人類を支配しようと狙っている武闘派である。無論、この武闘派には対策局による厳しい監視がついている。
夜の女王であるリビアは穏健派閥『血の盟約』の長老で直接の支配地域はニューヨークであり、さらにその影響力はアメリカ大陸全体に及ぶ。つまりこの大陸の他の都市に棲む吸血鬼の小グループはすべてリビアの派閥の下についているということだ。
他の四つの派閥は規模の順に『夜の翼』『闇の牙』『血の呼び声』『赤き目』である。
うえっ。なんというネーミングセンス。吸血鬼って奴はどいつもこいつも中二病なのか?
この内、『血の呼び声』派閥が武闘派で、首魁はアンドレア・V・ノーラス。今回の犯人であるリチャードの父親である。つまりはリチャードは吸血鬼の長老の一人息子であり、甘やかされた馬鹿息子ということだ。
百年ほど前にこいつは対策局との取り決めを破って勝手に吸血鬼を増やし、その結果当時の対策局との間に全面戦争を引き起こした。結果はリチャード以外の吸血鬼の皆殺しに終わり、対策局は彼を他の派閥のボスに百年の間に渡って監禁させることで落としどころとした。その間に少しは賢くなるだろうとの目論見だ。
リチャードが抹殺されなかったのはひとえに彼の親が派閥の長老であったためだ。
リチャードは吸血鬼にしては珍しく普通の出産で産まれている。つまりボス・アンドレアと他の女性吸血鬼がセックスして妊娠し、ごく普通の方法で産んだ子供ということになる。
大概の吸血鬼は吸血行為により眷属を増やす方を選ぶが、ボス・アンドレアには何かの思い入れがあったのだろう。そしてそれと関連して、ボス・アンドレアの息子リチャードへの執着はとんでもなく深いものになってしまったというわけだ。
リビアは吸血鬼種族の中では最大派閥の穏健派の頭だ。そして各派閥は一種の人質として他の派閥の客人を受け入れることがある。吸血鬼社会の複雑で緻密な政治構造がそういった解決法を選んでいる。
「君たちで何とかできなかったのか」
おっとこれは無駄な質問だな。自分たちで片を付けることができるならあらゆる怪物たちが心中密かに忌み嫌っている対策局になど連絡はしない。
「私たちの掟は知っているでしょ」リビアは指摘した。「吸血鬼同士の戦いはご法度。一度でもそれを始めたら収拾がつかなくなる」
それは確かにそうだ。吸血鬼の派閥はお互いにひどく憎みあっている。彼らの間での最終戦争を止めているのは、今まで最終戦争を行ったことがないというただその事実だけである。
「リチャードは革命派よ。人類は吸血鬼の下につくべきだと信じてやまない。以前ちょっとした不始末をやってしまったために、長い間他の長老たちの監視下におかれていたのだけどね、このたび無罪放免。ところが自由になった途端、仲間を増やし始めたの。信じられる? よりにもよってこのあたしの縄張りでよ」
リビアは静かに激怒していた。その怒りの矛先が私に向きませんように。心の中で月の神様に祈りを捧げた。
「で、そいつが増殖を始めたのは何時頃からだ?」
「一年前よ」
その返事に私は固まった。
これは確かに恐ろしい事態だ。
吸血鬼の増殖には時間がかかる。それは大きな弱点だ。一度に増やすことのできる相手は一か月に一人のみ。一人の人間の血を吸い続け、呪いを伝染させるのにそれだけかかる。
その結果、一月後には二人の吸血鬼が存在することになる。これ自体はそう大したことではない。だがそれを繰り返せば一年後には四千人の吸血鬼が生れることになる。これが倍々ゲームの恐ろしいところだ。さらに一年と九か月すれば地球は吸血鬼だけの惑星に変ずることになる。これはさすがに看過できない事態だ。
吸血鬼自体は強い怪物だがまた弱点も多い。特に昼間はほぼ活動できなくなるという欠点が大きい。一時的に吸血鬼のコロニーを作ることもできるが、最終的には昼間動けないときに人間たちに駆逐されることになるし、またそうなってきた。
自らが滅びる選択をするのは生物としては正気ではないが、そういった者がたまに出現することも真実だ。そのためにこそ対策局は存在する。
*
その夜は教会の宿泊所に泊まった。
対策局の予算は潤沢だ。高級ホテルに泊まることもできたし、そうしても誰も文句は言わないが、神の傍にいるという感覚が強くなるので私はこの方が好きだ。教会を居心地良く感じるなんて、以前の私だったら到底考えられないことだ。
それに教会には手が出せない吸血鬼は多い。実際には吸血鬼の持つ信仰やどの派閥の血を引くかでどの宗派の教会を忌避するかどうかが決まる。だいたいにしてここニューヨークでは教会の中は比較的安全だと考えてよい。
多くの吸血鬼は教会の中では本来の力は発揮できない。それを精神的障壁だとしたり顔で説く者もいるが、魔法が働く裏側の世界では精神的障壁は物理的障壁と同じぐらい力がある。
とにかく寝込みを襲われるのだけは勘弁願いたいので、教会に泊まることができるのは有難い。もっとも私自身は吸血鬼と同じく夜行性なのだが。
教会の神父の好意により小奇麗な個室が割り当てられた。短く祈りの言葉を唱えてから部屋に引きこもる。頭の中で繰り返されるテウルギア・ゴエティアの一節が煩わしかったが、折角持ち出した呪文なのだから捨てるわけにはいかない。私は節約家なのだ。
扉にノックがあり、この宿泊所を仕切っている尼僧が入って来た。手に食事の載ったトレイを持っている。
「普通は皆で食堂で食べるのですが、今回は特別と聞きましたのでお持ちしました」
これは有難い。対策局の局員はできるだけ顔を他人に見られない方がよいからだ。
テーブルに置かれた食事に手を伸ばす。
提供されたのはごく普通の質素な食事だ。パンとチーズ。それにスープと少量のハム。果物の切れ端。そもそもここには贅沢をするための食材は用意されていない。
人狼の食事は肉類がやや多めなところ以外は普通の人間と同じだ。不足するタンパク質は明日にでもどこかのレストランで補うとしよう。そうだな。牛一頭分の肉があれば、この私の小さな胃袋も満足することだろう。私は基本的に少食なのだ。
食事を持って来た尼僧はそのままテーブルの横に立っている。食事が済んだらそのまま食器を持って返ることになっているのだろうか。
「君、名前は?」尋ねてみた。
「エマです」
尼僧はまだ若い。顔はどちらかと言えば美人の部類だ。きちんと化粧をして街を歩けばさぞや人気者になるだろう。尼僧には向かない特質だ。
この若さで教会の一部を仕切らせてもらえるということはそれなりに優秀なのだろう。私は失礼にならない範囲で彼女を観察した。
食事を片付けながらちらりとエマの目の色を見る。瞳孔がやや開いている。発散する匂いからしてやや興奮状態。性的という意味ではない。つまりは対策局本部から来た私に興味津々なのだ。
対策局のことはバチカン内部でも話題にしないことが鉄則だが、それでも噂の一つや二つは漏れる。人によっては最近始まったエクソシスト本部と勘違いしているケースもある。バチカン対策局は千年以上の歴史を持つ古い古い機関なのだが、すべてはテーブルの下に巧妙に隠されていて、その存在を知る者は少ない。またそれを知る立場になった者は長生きはできない。それほど危険な職場なのだ。
しばらく彼女と話をした。エマは二十歳。なるほどあらゆる物に興味を持つ歳頃だ。この若さで尼僧になるというのはどんな人生を送って来たのだろうと思ったが詮索はしなかった。
この世には様々な人生がある。
話の中でエマは対策局について色々質問を混ぜて来たが、私はどれもうまくはぐらかした。どのみち真実を話しても信じては貰えなかっただろう。
対策局のメンバーのほとんどが人成らざる者であることなど、いったい誰が信じる?
特にアナンシ司教なんかときたら・・おっと話過ぎたな、ここまでにしよう。
それとなく探りを入れてみると、最近は教会周辺の浮浪者たちの数が減っていることが分かった。リビアの派閥は協定を破って吸血鬼人口を増やしたりはしない。この都市の医療用血液流通を抑えているのだから、食料には不自由はしていないのだ。それに不死を求める金満老人たちを慎重に取り入れることで莫大な資産と財産、そして権力を手にいれている。わざわざ危険を犯す必要は欠片もない。
となるとこの浮浪者たちの失踪は、まず間違いなく吸血鬼リチャード・V・ノーラスの仕業だろう。
ざっと計算して、この一年でニューヨーク全体で新しく吸血鬼になったのは千人から四千人程度と概算を出した。まったく由々しき事態だ。ここから先は一か月経つ毎に万から十万へと膨れ上がる。今が状況を抑えることのできる限界点だと判断した。
厄介だ。とても厄介だ。V案件がぐずぐずできないのはこの性質ゆえなのだ。事が公になった時点ではすでに手遅れ一歩手前になっている。
エマが食器を持って出ていくと、すぐに対策局に連絡をした。
内容は現状報告と援軍の手配。
アナンシ司教は対策局の全員から蛇蝎の如く嫌われている人物だが、少なくとも職務には忠実で、おまけに有能だ。ぐずぐずせずにすぐに援軍を出すと約束した。
これで良し。
後やらなくてはいけないのは、相手への警告だ。これは対策局の慣習であり、対策局が単なる処刑組織ではないことを証明するためのものだ。この場合は私がリチャード・V・ノーラスに会いに行き、直に警告すること。それで相手が警告を聞き、増えた吸血鬼たちを自ら処分するなら問題は未然に防がれる。
どんな組織にも必ず理念というものがいる。それが無ければただの野犬の群れと変わらないと言える。対策局の理念は次のようなものだ。
『公正に、ただし容赦無く殺せ』
*☆
リビアはニューヨークの吸血鬼社会については隅々まで良く知っている。そしてそれを完全に支配している。だからこそ『夜の女王』という吸血鬼社会では最高の称号を受けている。
吸血鬼間の闘争はタブーという決まりが無ければ、この件は彼女が片をつけていただろう。例え相手が長老の馬鹿息子であろうとも。彼女は穏健派ではあるが、闘争が嫌いというわけではない。ひとたび彼女が激怒すれば人間も人外も大勢が死ぬ。それは間違いない。
この私でさえ彼女を怒らせるようなことはそうそうしない。何百年も前に私が別れ話を切り出した後の彼女の暴れ様を思い出すと二度と怒らせようとは思わない。
私はリビアに教えられた会員制のナイトクラブを訪れた。
私が着ている神父服にクラブの用心棒は最初は訝し気な視線を投げつけてきたが、すぐに何かの余興だと判断したようだ。何枚かのドル札と引き換えに中に入れと促した。
何構わんよ。そいつはどうせ対策局の予算から出る金だ。経理に請求するには賄賂の領収書が必要だが、いつものように偽造すれば済むことだ。
ここは会員制の割にはあまり上品なナイトクラブではない。中はタバコの煙と粗野な笑い声で一杯だ。強い酒がビールのように飲まれ、中央のステージで布切れ一枚のダンサーがポールに絡んで踊っている。会員制になっているのは、この部屋の中で大量の麻薬が振舞われているからだ。それは匂いで分かる。それともう一つ別の匂い。吸血鬼に特有の腐った血の匂い。
一番奥の薄暗いテーブルにそいつはいた。どうしてこの手合いはいつもこういったお決まりの場所に居るのだろう。心底不思議だ。かっては私もそういう場所を定位置としていたが、今から振り返るとその理由を全く思い出すことができない。きっとこの世の誰もが同じ悪夢を見ていて、つまりこの薄暗い場所はその悪夢の光景の中心ということになる。
ボス吸血鬼のリチャード・V・ノーラスは細身の背の高い男だった。椅子に深く腰掛け、足をテーブルの上に載せてクロスさせている。部屋の中だというのに帽子を目深に被り、その下から睨みつけてくる。これもお決まりの光景だ。傍から見て自分が如何に滑稽なのかをまったく理解していない。
これでも年齢は二百歳を越えているだろうに。成長しない者はいくら時間が経とうが成長しない良い例だ。
周囲に微動だにせず立っている三人の男はボディガードであり、吸血鬼の直属の眷属だ。吸血鬼にはどこか人形を思わせる所作がある。人間ではああ身じろぎもせずに長時間立っていることはできない。
男のテーブルの前に立ち、向いの椅子を指さして尋ねてみた。
「ここ、いいかな?」
「駄目だ」返って来たのは冷たく厳しい声だ。
ハードボイルドを気取っているのだなと思った。この手の手合いには多いことだ。そんなことには何の意味もないのに。
彼の答えは無視して、私は椅子を引き、座った。ほらな。ハードボイルなんて意味が無かっただろう?
ボディガードたちが動いた。普通の人間なら彼らが瞬間移動したと感じただろう。これは吸血鬼特有の素早い動きだ。二人は私の左右に立ち、最後の一人は私の背後に回って、懐から出した大きなナイフを私の喉元に当てた。
喉元に突きつけられた白く光る刃を見なくても匂いで分かる。銀が引いてある刃だ。してみるとすでに私の身元は知っているということだ。恐らくはリビアの側近の誰かが情報を漏らしている。後で教えてやらねば。いや、リビアの事だからすでに知っているだろう。知っていて私を送りだしたのだ。
リビアは私がどういう存在なのか良く知っている。
これはある意味助かる。一から説明しなくて良いから。
「リチャード・V・ノーラスだな。バチカン対策局のファーマソン神父だ」
「聞いたことがないな」ノーラスは答えた。
ダークと名乗った方が良かったかな?
そちらならこの田舎者でも分かるだろう。だがその名はとうの昔に捨てたのだ。
「別に宣伝しているわけではないからな。まあ、いい。対策局としては一応警告をするのが習わしでな。内容はこうだ。これ以上増えるな。増えたらその段階で君たちは死ぬことになる」
「ああ、確かに警告は聞いたよ」
リチャードはコツコツと指でテーブルを叩いた。少し考えてから、彼は右手で自分の首を掻っ切る仕草をした。
旋風が吹き抜けた。
私の後ろにいた男はナイフを持った右腕を引きちぎった。その体は一回転し、はずみで上から落ちて来た自分の銀のナイフが胸に深々と刺さる。
右の男は首をねじ切って投げ捨てた。左の男には強烈な蹴りを胸に入れた。内臓が背中から弾けだして噴出した。その懐から潰れた銃が滑り落ちる。恐らくこれには銀の弾丸が装填してあるだろう。
すべては一瞬の間に終わり、私は元の位置と姿勢を保ったままリチャードの正面に座り続けていた。
瞬きの間の殺戮。
リチャードは人狼については知っていたが、本当の意味では知っていなかった。普通の人間の十倍の筋力を持つ吸血鬼は恐ろしく素早く動くことができる。だがあらゆる生物は動く速さに制限がある。それは吸血鬼でも同じだ。
唯一の例外として、訓練を続けた人狼はその速さの上限に制限がない。
人狼の特性は大規模な変身である。つまりは肉体を流動させ、破壊と再構築ができるということ。正しく訓練した人狼の体は、筋肉ばかりではなく神経まで再配列されることになる。それはつまりただでさえ膂力に満ちた全身の筋肉を予め命令しておいた順序で完璧なタイミングで動かすことができるということ。その結果は人間どころか吸血鬼の目でさえも捉えられない神速の動きになる。
ましてや今夜のような満月の夜にはそれは最高潮に達する。
銀の武器さえ持ち出せば狼男を倒せるなんて、どこかのファンタジーじゃあるまいし、無理に決まっている。
こちらの騒ぎに気付いたのか、背後で悲鳴が上がる。無理もない。床は吸血鬼の腐った血で一杯だ。
ここらが潮時だろう。私はリチャードの目を見つめながらゆっくりと立ち上がった。
「警告を忘れないように」
くそう。リチャードが名門吸血鬼の馬鹿息子で無ければ、ここで片を付けて仕事は完了したのに。
悪態をつきたかったが止めておいた。神がどこかで見ていらっしゃる。私はまた頭の中での呪文の反芻に戻った。ああ、もう、これはいい加減に鬱陶しい。
*
対策局からの援軍は流石に超音速ジェット機を使うというわけにはいかない。見習い神父の軍団が到着するまでには時間がかかる。それにまずありえない事だが吸血鬼リチャードの気が変わって勢力を増やすのを止めるかも知れない。どちらにしろ今日明日の話ではない。もっとも一か月後というわけでもない。一か月後経てば吸血鬼は倍に増える。
見習い神父と云えども過労死させるわけにはいくまい?
暇なのでエマに案内してもらってニューヨークを見物した。流石に神父服と尼僧服の二人が歩き回ったのでは目立ちすぎるので二人とも私服だ。
昔この辺りはちらりと見て回ったことはあるのだが、当時は見物などという状況では無かったので、大して記憶に残っていない。かろうじて覚えているのは立て籠もり易そうな建物や、武器の集積に使えそうな倉庫、それに街の裏社会の連中の集まる場所。そんなところだ。
今思えば実に味気ない人生だった。暴力と闘争だけ。今もそれに関しては大して変わってはいないが、こうして観光するようになっただけマシとは言える。少なくとも文化を尊重するようにはなった。
尼僧服を脱げばエマはごく普通の若い娘だ。私は一応サングラスで目元を隠して下手な変装とした。私の年齢は数百歳になるが見かけ上は三十歳程度に見える。傍から見てただの歳の差のあるカップルに見えてくれると良いが。
メトロポリタン美術館なんて人生で初めて入った。正直に言うが芸術というのは良くわからない。私がこの世て一番美しいと思うのは満月であり、それに比べるとどのような美術品も色あせて見えてしまう。
そんな私の気持ちには気づかずにエマは美術館の中の様々な部屋を見て回り、解説してくれた。エマの目は美術品の上を廻っていたが、私の目は別のものを捕らえていた。
肖像画の並ぶ回廊の一番奥の絵は偽物だ。顔料の臭いが違う。それは絵ですら無かった。いわゆる変化する絵。絵の形をした化け物だ。
彫像の部屋の真ん中のダビデ像もそうだ。大理石の被膜の下には極めて体温の低い生物が隠れている。捕食頻度は数年に一度ぐらいか。いつの日か不運な犠牲者がその像の下を通りかかるのをじっと待っているのだ。
現代美術の部屋に飾ってあるモービルは極めてレアな怪物だ。いくつもの幾何学の断片が一種の魔法陣を構築するようになっている。それらが整った瞬間だけ深淵よりその真の姿を現す。
すべてメモしておいた。後で対策局に報告しておこう。いつもならそのまま頭で覚えるが今は例の呪文で頭が一杯なので無理だ。
エマは心底この観光を楽しんでいるようで、私はそれに合わせて各美術品に関する蘊蓄を披露してみせた。何、それらが最初に噂になった当時に私がそこに居合わせたというだけの話なのだが。確かにミケランジェロは面白い男だったよ。かなり偏屈ではあったが。
美術館の後はホットドッグを買ってセントラルパークをぶらついた。
二人でベンチに腰かけて青空を眺める。
久しぶりの休日を楽しむエマの横で、私は行きかう人々を眺めていた。人間族に、人狼族が少し。それに人間ではあるが魔力のオーラを垂れ流している魔女たち。首が二つある連中もいれば、手足が八本のアラクネたちも混ざっている。もっともそれらは人間の眼では普通の人間にしか見えないだろう。みんな太陽の光の下での散歩が大好きだ。大変に結構。
後ろの木立の中の一番大きな木にはドリュアドが棲んでいる。木の葉の陰からちらりと私に目で合図した所を見ると、恐らくは対策局には申請済の存在だ。危険性無し、非監視対象、特に保護対象とはしない。そんなものだ。
こうして平和な風景を見ていると、どうしてもっと早く自分がこの境地に達しなかったのかと不思議になる。今の私からみれば人間たちも怪物たちもすべて同じ子供たちにしか思えない。これから先の人生を歩み、経験を積み、成長していく子供たち。彼らはみな保護し慈しむべき対象なのだ。ああ、ダークよ。どうしてお前はああ猛々しかったのか?
吸血鬼でも無いのに、血の海の中を歩いていた。
この散策の間、エマは何度も私の仕事に探りを入れたが、すべてはぐらかした。
やれやれ、若い娘というのは恐れを知らない。好奇心は猫をも殺すというのに。対策局の仕事なんかろくでもないものに決まっているのに。
その内、エマの事が少しは分かってきた。彼女はきっとファザーコンプレックスなのだ。やれやれ、こちらの方が数百歳は年上だと言うのに。
*
夜になり一人自室で色々考えていると窓ガラスに何かが当たる音がした。同時に匂いで外にいる存在に気づく。
高位の吸血鬼は血の周囲に肉の塊を纏わせて分割することで、自身の体をより小さく細分化することができる。大概の吸血鬼はコウモリの群れに変身する。ネズミの群れに変身する者もいるにはいるが極めて稀だ。やはりプライドの問題なのだろうか。
窓を開けると予想通りにコウモリの群れがなだれ込んで来た。それは私の目の前で一つに固まると夜の女王リビアへと変じた。
リビアは驚くべきことに吸血鬼なのにも関わらずキリスト教徒だ。呪われた存在が教会の中に居るというそれだけでも相当な負担が掛かっているはずだが、それをおくびにも出さない。
下位の吸血鬼ならとうの昔に萎びた肉の塊になっているところだ。
「ファーマソン神父。情報を上げるわ」
貸しだとは言わなかった。この情報を提供することは彼女にも利があることだったから。
「リチャードとその眷属の居場所を教えるわ。その代わり、一つ約束して」
「何を?」
「リチャードを殺さないで。彼を殺すとアンドレアとの戦争になる」
アンドレア・V・ノーラスは武闘派吸血鬼派閥『血の呼び声』の長老だ。
「この情報はアンドレアから?」
「そうよ。アンドレアは吸血鬼の革命を起こすにはまだ時期が早すぎると考えている。だから息子を再び監禁したいと考えている。でも息子が死ぬのはノー・サンキュー。そうなればすぐに吸血鬼大戦が勃発するわ。色々アンドレアに確かめてみたけど本気みたい」
提案されたのは先延ばしに妥協に親馬鹿か。まあそれでもこの問題はひとまず収まる。
「いいだろう。その提案を飲もう。私はリチャードを殺さない」
「約束よ」
リビアは誓いを立てろとは言わなかった。魔法のギアスをかけなくても一度そうすると約束したからには私は必ずそうすることをリビアは知っている。
リビアが教えてくれたのは十年ほど前に潰れたダンスホールの建物だった。驚いたことに都心の一等地のど真ん中にある。複雑に絡んだ権利関係のお陰で誰も手が出せなかったらしい。そうでなければ当の昔に再開発の餌食になっていたであろう建物だ。
私は紙を持って来ると、鉛筆の先を舐め、それから素早く一枚の似顔絵を描き上げた。クラブで見たリチャード・V・ノーラスの顔の絵だ。
「似てるかな?」
「そっくりよ。ダーク。貴方にこんな才能があったなんて初めて知ったわ」
「練習したのさ」私はリビアにウインクした。
これは対策局に入ってから身につけた技術だ。なにぶん妖怪や怪物の中には写真に写らないという特質を持つものが少なくない。魔法の原理はこの二十一世紀のテクノロジーとはひどく相性が悪いのだ。だから手配書を作るには似顔絵に頼るしかない。
必要は発明の母と言うだけはある。
リビアが顔を寄せてくると言った。
「ねえ、ダーク。あたしの絵も描いてくれる?」
甘い匂いがした。思わず頭がくらくらする。恐るべきは吸血鬼女性の魅力。
私は再び鉛筆を取ると、リビアの似顔絵を描きあげた。元々が素晴らしい素材に加えて、さらに少しばかり美化した。できあがったものは絶世の美女の似顔絵だ。こんなものがもし道端に落ちているのを見つけたら、誰でも拾って帰って部屋の壁に飾るだろう。そしてその顔を見つめ続けて、一生を終わる。
最後に彼女の瞳の横に小さな皺を二本加えた。一本は彼女のこれまでの人生に敬意を表して、もう一本は彼女の積んできた経験に対して。それで似顔絵にはぐっと重みが出た。それが作り物ではなく、実在の人物を描いたものであるという重みが。
「有難う。あたしは写真には写らないし、画家に描かせるとあたしに見惚れて筆が進まないのよ。だからあたしの肖像画は一枚も無し」
「そいつをどうするんだ?」私は似顔絵を指さした。
「もちろん芸術の回廊の一番奥に飾るのよ。きちんと額に入れて。
あたしの趣味を忘れたの? ダーク。
芸術家の卵を見つけて援助したら、代わりに最高の宝物を貰うの」
私が目を白黒させている間に、リビアは再びコウモリの群れに変身すると飛び去った。
神学生軍団は明日到着する。このリチャードの似顔絵があれば彼を殺さないように神学生たちに指示ができるだろう。