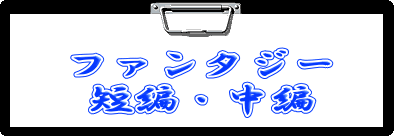
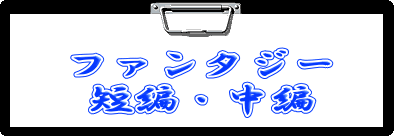
1)
ナイフを持ったアンディが前に出ると、素早い突きを繰り出した。エマは手にした短棒でそれを受けると、もう一方の手に持った短棒をアンディの上に振り下ろした。
アンディの動きは素早かった。首を後ろに振ることで短棒を躱すと、ナイフを滑らせてエマの親指を素早く切りつけた。練習用のナイフに刃はついていないが、それでも皮膚が裂けて血が飛び散った。
「そこまで」私は宣言すると、エマの手から短棒を取り上げた。
エマはこう見えても負けん気が強い。武器を取り上げないといつまでも戦いを続けたがる。
「自分の体の力のみに頼った動きでは、いつまでも経ってもアンディには勝てないぞ」
私が注意するとエマは険しい顔をした。
人狼は無尽蔵の体力と素早い復元能力を持っている。そのため人狼になったものの多くは無敵感を持つことになる。だがその感覚に身を任せることは間違いなのだ。銀の武器を使えばごく普通に人狼に傷をつけることができるし、人狼よりも強い怪物はいくらでもいる。
弛まない訓練こそが生き残るための秘訣なのだ。
二人がやっているのはかなり荒っぽい訓練に見えるがそれは違う。
エマは人狼だから普通のナイフでは死なない。心臓を刺されてもしばらくの間もの凄く痛い思いをするだけですむ。
アンディはそうもいかないので、この練習用の棒はわざと脆い素材で作ってある。殴られたら頭蓋骨の代わりに棒が砕けるようにだ。もっともその衝撃は強烈で、もし殴られればアンディは丸一日はベッドで唸ることになる。だから二人とも真剣に戦うことになる。
もっともアンディには私以外の者には明かしていないある秘密が存在する。そのため単純な攻撃ではアンディを倒すことはできない。エマがその秘密に気付くまではアンディはエマに勝ち続けることになるだろう。
私の胸ポケットの中でスマホがメールの着信音を鳴らし、画面に『クソ野郎』の文字と共にアナンシ司祭の名前が表示された。私はそれを無視しようかとも思ったが、やはりメールを開いてみた。
こと仕事に関してはアナンシ司教はひどく厳しい。仕事をサボった連中にはとてもとても酷いお仕置きが行われることは誰でも知っている。
それ以外の点ではアナンシ司教は話が分かる。エマを勝手に対策局にスカウトしたことにも文句を言わなかったし、彼女を人狼化したことにも不満は漏らさなかった。それどころかエマと二人で平らげたレストラン一件分のステーキの領収書もちらりと一瞥しただけで受け入れた。
その点ではアナンシ司教は良い上司なのだ。
仕方ない。どうせまた厄介な仕事の呼び出しだろうが、働かざる者食うべからずの鉄則がある。
私はアナンシ司教の元に向かった。
アナンシ司教はバチカン特殊事例対策局のトップで、しかも自分の机と椅子から一瞬たりとも離れたことのない人物だ。
当然ながらいくら彼でもトイレや食事には行っているはずなのだが、誰もその瞬間を見たことがないのも事実だ。
アナンシ司教の体は巨躯と言ってもよい。脂肪でできた人間ピラミッドと言えばそのイメージにもっとも近い。それがいつもの定位置にどんと聳えているのだから迫力がある。
彼の存在を知る者が対策局の外部にはほとんどいないことは幸運だった。でなければ世界各地の登山家たちが彼を初登頂しようと群がって来ていただろう。
私が対策局のオフィスに入ると、アナンシ司教はじろりと私を睨み、手にした書類を投げつけて来た。
「スカウトに行ってこい」
「あの化け物ジェット機には乗りませんよ」
一応念を押す。無駄な努力であるが。アナンシ司教がそうと決めたのならば、そうなるのだ。
「心配するな。列車で行ける範囲だ。それにそこまで急な話ではない」
それに対する返答は私の疑いの目だ。
「今回の任務は新人のスカウト。有望株だ。まだ自分が何者なのかに気づいていない」
私はざっとその書類に目を通した。相手の調査報告、それとさらに追加の三枚の報告書。今までに三回スカウトが送られたという証拠だ。そしてそのいずれもが失敗している。全員入院中だ。症状は石化症。次に魔術治療師がここに巡回してくるまで彼らは冷たい地下倉庫で眠り続けることになる。
今回の相手は石化能力持ちということは物凄く厄介な案件ということだ。
「それとその書類に書いてある目標がもし本物なら確保してこい」
ついでのようにアナンシ司教は言った。
もしそれが本物なら、確保は命がけになる。そう心の片隅で思ったが、口にはしなかった。言うだけ無駄だ。アナンシ司教は仕事には厳しい。それはつまり人、いや人狼使いが荒いということなのだ。
私は批難の目を向けたが、アナンシ司教はそれを無視した。きっと対戦車ミサイルを向けられていたとしても同様に無視しただろう。
アナンシ司教は目の前の大きなテーブルの上に並べた小像を動かすのに忙しい。傍から見ていると何かのゲームに熱中しているようにも見える。
その大きな手が動き、狼を象った青ガラスの小像を動かす。私を示す像だ。そのついでにもう二つの小像も一緒に動かし、私の横に並べた。
それ以上は何も答えてくれなさそうだったので、私はオフィスを後にした。
*
旅の荷物と言っても大したものはいらない。替えの下着数枚が入ったトランクと、神父服の下に隠し持っている大きなナイフが二本。そしてこれが無いと格好がつかない携帯用の聖書。それだけだ。
ナイフの内の一本は刃に銀が引いてある。もう一本はごく普通のナイフだ。
銀のナイフはもし万が一に同族の人狼と戦う羽目になったときのものだ。こういった武器がないと人狼同士の戦いはお互いに毟りあうような不毛な戦いが延々と続いてしまう。もっとも私と一対一で遣りあえるような人狼はこの世にはいない。
なぜなら私は人狼の王だから。
いつもの神父服を着て周囲ににこやかな笑みを振りまきながら、駅の混雑した人々の間を抜ける。誰もが私の姿に気づくと微笑みかけてくれる。神父というのは良い職業だ。尊敬と愛情が常について回る。列車に乗り込み、予約しておいた四人掛けのコンパートメントに一人で納まる。
これは別に贅沢をしているわけではない。普通の席に座ると周囲の一般人に迷惑が掛かる可能性があるからだ。対策局の特殊工作メンバーを狙う連中は枚挙に暇がない。
単なる恨みから、魔術装備狙いの強盗まで動機はいくらでもある。用心しすぎということは無いのがこの職業だ。ましてや私の敵は多い。両手の指どころか両足の指を足してもまだ足りないほどだ。百の手を持つ巨人ヘカトンケイルならもしかしたら足りるかもしれない。
車両の臭いを嗅ぎ、爆発物が無いことを確かめる。古い油の臭い。錆びの臭い。三日前ぐらいの精液の臭い。誰かがここでお楽しみを行ったようだ。それと微かに蛇人族が残す警戒臭。だがこれはかなり古いので今は危険はない。
問題はなさそうだ。私は席に深く腰掛けると途中で買った雑誌を広げる。
ドアに影が差すと、アンディとエマが入って来た。匂いで気づかれぬようにうまく風下を伝って来たらしい。
私の批難の視線から目を反らすと、エマが隣に、アンディが向かいに座った。
最初に口火を切ったのはアンディだ。
「二人で休暇を貰ったんです。ついでだからマスターのお供をしようと思ったんです」
もちろんこれは嘘だ。対策局には休暇制度などという立派なものは存在しない。ウチは死ぬまで休みなく働かされる素晴らしくもブラックな職場なのだ。
「今回の任務は本当に危険なんだぞ」私は念を押した。
「分かっています」二人同時に答えた。
いったいいつからそこまで仲良くなったんだ? お前たち。
ここで二人を説得しようとすることは意味がない。二人は正反対の性格だが、強情であることだけは見事に一致している。
エマの強情さは元からの性格に加えて流し込まれた私の血が影響しているにせよ、アンディの強情さはどこから来ているのだろうと、ちらりと思った。
私は今回の仕事の資料を二人に見せた。
しばらく書類を読んだ後、アンディがため息をついた。
「石化能力。確かに厄介ですね。メデューサ、バシリスクいったいどちらでしょう」
「そこまでは判別できていないんだ」
私たちのような怪物には種族に応じてさまざまな攻撃特性があるが、中でも石化能力は特別なものだ。能力としては致命的に危険と分類されるぐらい攻撃的で強いものなのだ。
あらゆる武器に対して不死身とも言える大天使が石化能力により殺された事例すらもある。それを思えば決して侮れる能力ではない。
「あの、マスター」エマが口を挟んだ。「石化能力ってなんです?」
私とアンディはもうこの業界が長い。エマは先日加わったばかりなのでまだ知識がない。今度からは戦闘訓練の合間に座学も取り入れるとしよう。心にそうメモした。
一口に石化能力と言っても数種類に分かれる。
メデューサタイプの石化能力は相手に即座に石化を引き起こす。それはメヂューサの醜い顔に刻まれた魔法陣による効果だ。この能力は見た者すべてに同時に作用する広範囲の攻撃能力なのだが、鏡で反射されてしまうという大きな欠点がある。つまり相手が鏡を持っている時点で攻撃が封じられてしまう。
一方バシリスクタイプになるとまず最初にその視線を受けた人間は気絶する。それからゆっくりと視線の呪いに犯されて行き、死体となった後に石化する。この場合、石化視線は鏡で反射されないので、退治する側は鏡で相手を確認しながら対処することになる。
この両極端な二つの石化能力の存在が、その対処を難しくしている。石化能力のタイプが分からぬ限り、せっかくの鏡を相手に向けるべきなのか、自分に見えるように構えるべきなのかが判別できない。間違えれば即死することになる。
他にも怪物固有の石化条件もあり、単純に対処できるものではない。
今回もそれだ。
「最初の一人は真っ向から石化攻撃を受けた。不意打ちに近い」
私はアンディの手の中の書類を示した。
話が長くなりそうだと見て、エマが持ち込んだ大きな紙袋の中から何かを取り出した。フライドチキンのお徳用パックだ。エマの両手で一抱え分はある。それとコーラの大カップ。
少し気おくれしながらエマはハンカチを膝の上に広げた後にフライドチキンにかぶりついた。
アンディが行儀が悪いと批難の視線を向けたが、私は敢えて無視した。
エマの食欲を止めてはならないと、二人にはすでに教えてある。人狼感染からしばらくの間は人狼はひたすら食べ続ける。全身の細胞が人狼のものに置き換わるのには膨大なカロリーとタンパク質が必要になる。
それを妨害すると惨事が引き起こされる。
人狼が望まぬ食人に手をつけるのはだいたいがこの時期なのだ。強烈な飢餓感は大脳皮質による行動抑制を一瞬で圧倒し、人狼をただの無目的な食人鬼へと変えてしまう。そしてその後は犯してしまった食人の罪悪感から引きこもるか、裏返って殺戮の怪物になるかがお決まりの道だ。
エマのメンターは私なのだ。決してそんなことにはさせない。
「この最初の一人は入院していますね。石化解除が間に合わなかったと見てよいですね」アンディが指摘した。
「見つかったときはすでに全身が石化していたからな。放っておけば元に戻るまで十年はかかるだろう」と私。
「二人目。これは最初の報告を受けてから派遣された者ですね。しかも能力持ちだ」
アンディは書類の記述の一点を示した。
「装備を見ると小さな鏡のキーホルダーを持っていますね。となるとメデューサタイプは除外できるかも」
「あるいは相手側にそれだけの経験があり、鏡を避けて正確に攻撃したかだ。石化能力は視線を橋渡しに使うことが多い。相手の目と見つめ合うのが一番効果が高くなるのだ。もっとも近距離でいきなり見つめ合うケースというのも難しいか」
横で大人しく話を聞きながら、エマは黙々とフライドチキンを片付けている。食べ残された骨がどんどん積みあがっている。
「三人目が分からない。前の二人がやられたのを知っていたのに、今度も容易く術中に落ちている」
「でも死んではいないのですよね。話はできるのですか?」
「話ができるようになるまでこちらも後十年はかかるだろう」
私とアンディはため息をついた。
「埒が明かない。とにかく、石化能力を視線だと仮定する。その場合は目と目が見つめあうことが呪いが活性化する条件だ。サングラスをかけた相手には注意をするべきだな。こちらがサングラスを掛けるという手もあるが、神父服にサングラスはさすがに目立つのではないかと思う」
「いっそ私服にしますか?」とアンディ。
「それもいいが神父服は対策局の正式な制服でもあるからな」
何とも頼りない話だ。もう少し情報があればよいのだが、その情報源がすべて石になっているのでは手の打ちようがない。
私はエマからフライドチキンを一つ分けて貰うと、骨ごと噛み砕いて食べた。
2)
結局三人でサングラスをかける羽目になった。一番色の濃いヤツをだ。神父服に尼僧服、神学生の服。三人揃って怪しいサングラス・トリオの出来上がりだ。
準備ができたのでタクシーに乗り込んで行先を告げると運転手が絶句した。
「神父さん、あんた正気かい。あそこはヤバい所だよ」
「知っている。神のお導きである人物に会いに行くんだ」
「そっちの若い尼さんと坊やは置いていったらどうだい。無事で済む保証はないよ」
この運転手は良い人間だ。わざわざこちらの身を心配してくれる。
神よ、彼の魂に祝福を。
「心配してくれてありがとう。大丈夫だ。あそこがどんなところかは良く知っている」
うん、確かに良く知っている。あそこは地獄もかくやと言うべき吹き溜まりだ。
何とか運転手を説得して目的のスラム街に到着する。我々を下すとすぐにタクシーは消え去った。タイヤの一つも盗まれる前に逃げ出すのは正しい行いだ。
路地に入り、角を三つばかり曲がる。路地はどこもゴミだらけだ。
「マスター?」エマが言った。「つけられています」
「三人だな。気にするな。こちらの行き先がはっきりするまでは手を出してこない。この街の有力者の知り合いだった場合には襲撃者は命を失うことになるからな」
「これから会いに行くのはお偉いさんなんですか?」
「違うな。どちらかと言えば小者だ」
エマとアンディは顔を見合わせた。その手が隠し持っている武器に触れるのを私は見逃さなかった。もちろんそれらは訓練用ではない。
私はビルの階段を登り、部屋番号を確かめた。ここだけは他の部屋とは違い頑丈な鋼鉄のドアだ。スライド式ののぞき窓がついている。昔とちっとも変わらない。
壁に開いた弾丸の痕以外は。
以前と同じであればよいがと思いながら、扉をノックする。
扉についた覗き穴が開き、眼付の悪い太った顔が覗く。ガンオイルの臭い。扉の向こうでショットガンを構えているのだろう。
「何の用だ?」男は聞いてきた。
「アザースはいるか?」
「あんた誰だ。今日は誰もアポは取っていないぜ」
「ダークが来たと言ってくれ」
覗き窓が閉まり、扉の向こうで巨体がもそもそと動く音がした。やがて小さな悲鳴が聞こえ、何かドタバタと騒ぐ音がした。
やれやれ。アザースの野郎。いつになったら私から逃げおおせることはできないと理解するんだろう。エマとアンディをその場に残して、廊下の端まで行き、そこの窓から覗いた。アザースが向かいの建物の上を走っているのが見えた。アザースの住処はいざと言うときすぐに逃げられるように、窓の外に脱出ルートが作ってあるのだ。
私は窓の上枠に指をかけてビルの外に飛び出すと、建物の壁を蹴って跳躍した。そのまま隣のビルの屋上に飛び降りると、今度は三歩の動きでアザースを捕まえた。襟首を掴んでアザースを宙に吊り上げる。
「久しぶりだな。アザース。元気そうで何より」
「ああ、ダークさん。久しぶりです。その服装は一体どうしたんです?」
私の手に吊り上げられて、もしゃもしゃの赤毛の小男が左右を忙しなく見ている。
なんでもいいから何か助けになるものがないかと探しているのだろう。
アザース。本名は誰も知らない。というか彼のことを知りたがる人間などこの世には居やしない。知りたいのは彼が持っている情報。アザースは情報屋なのだ。それも人間の暗黒街だけではなく、闇の世界の情報も握っている珍しい情報屋だ。
「訳アリでね。今は対策局のエージェントをやっている」
私の言葉を聞いてアザースは目をぐるぐる回した。自分の耳が信じられなかったらしい。まあ、無理もない。アザースは昔の私を良く知っているから。
「とりあえず元の部屋に戻ることに異論はないか?」私は聞いた。
「もちろんです。ダークさん。こんな目立つところであんたと話をしていたりしたら、明日には俺は死体になっている」
「そりゃいいな。世界が少しは静かになる」
それ以上は何も言わずに、私は元のビルに跳んで戻った。小脇にアザースを抱えたままでだ。足下には二十メートルの空間。ヤツは恐怖の余りに悲鳴を上げたが、なに、知ったこっちゃない。
窓からアザースの部屋に戻る。ボディガードが目を大きく見開いてから手にしたショットガンを向けようとしたが、私の方が速い。そいつの手から銃をもぎ取って床に捨てた。動きを制限しなかったのでそいつには何も見えなかっただろう。強烈な衝撃と共に手の中からショットガンが消え、私の手の中に現れたように見えたはずだ。彼の指が折れなかったのは単なる偶然だ。
「マック、止めろ」アザースが叫んだ。「向こうに行って大人しくしてろ」
賢明にもマックはそうした。私はちょっとだけほっとした。できたての死体の臭いの中で会話をするのは、あまり気持ちのよいものではないからだ。
無数の鍵のついた玄関扉を開き、エマとアンディを招き入れる。
アザースの家は外からは想像がつかないほど綺麗に片付けられている。ボディガードの大男は家政婦もやっているのだろうか。壁には色々な種類の魔除けが飾られている。見る者が見れば、それがどれも本物のまだ効力がある魔除けだと分かるだろう。
人狼避けの魔除けもあったが、真っ黒に焦げて微かに煙を上げている。何だか悪いことをしてしまったような気がする。人狼避けの魔除けは意外と値が張るのだ。
アザースの仕事部屋は一番奥だ。柔らかそうなソファが小さなテーブルを前にして配置されている。
「さて、ダークさん」気を取り直したアザースが言った。「何をお望みでしょう?」
プロとの会話は、実に話が早くていい。
「最近この辺りで石化を使った者がいる」
アザースは片方の眉を上げてみせた。知っているということだ。アザースは自分の表情を完全にコントロールできる。彼が嘘を吐く気なら、普通の方法では見破ることはできない。
「その話は聞いたことがあります。さて、いくら払えますか?」
私は返事をせずに手近にあったテーブルランプを取り上げた。その真鍮の足を何気なく曲げ、これも真鍮のランプシェードを指の力だけで潰してみせた。これは人狼に取ってはそう難しいことではない。筋肉のリミッターを外す方法を学べば良いだけだ。強い力は筋肉を損傷させるが、人狼に取ってそれは何の問題にもならない。数秒で治る。
「勘弁してください。ダークさん。これは真っ当な商売なんですよ」
「冗談だ」私は言った。「対策局の予算は潤沢だ。ただ私は人に舐められてボッタクられるのが嫌なだけなんだ」
「ダークさんを舐める人間なんてこの世にはいませんよ。いたとしたら死んでいる。特に私は明朗会計です。ごまかしは無し、正当な報酬しか頂きません」
アザースは言い訳をした。匂いで分かる。死ぬほど私を恐れている。今にも破裂しそうな心臓が強烈なビートを奏でている。だがこと仕事の話となるとアザースは一歩も引かない。強欲というわけではない。自分の仕事のスタイルに文字通り命を賭けているだけなのだ。
宜しい。話を先に進める頃合いだ。
対策局の予算は潤沢だが、理由なく無駄使いをするとアナンシ司教に睨まれることがある。私はそれが恐ろしい。
「ゴブリングループが新しいボディガードを雇ったって話があります。俺はそいつが石化使いじゃないかと睨んでいるんです。厄介なことに犠牲者はゴブリンたちが始末しちまうんではっきりしたことは分からないんですが」
「ゴブリン? ゴブリン・マフィアの連中か」
ゴブリンは闇の世界のゴミ拾いだ。小さくて緑色の体。頭もそう良くはない。だがその分、群れる。そして群れを成すと中には賢いヤツも出てきて頭になる。そうしてできたのがゴブリン・マフィアという組織だ。
神が己の姿に似せて創り上げたのが人間なら、悪魔が己の姿に似せて創り上げたのがゴブリンだ。邪悪で欲深でおまけに卑劣。人間の悪いところばかりを煮詰めたような連中と言えば理解してもらえるだろうか。
アザースはゴブリンたちのボスが棲む場所の住所を寄越して来た。
「カードは使えるかな?」
私は対策局から支給されているブラックカードを取り出してみせた。表も裏も真っ黒の無記名のカードで、文字通りのブラックカードだ。リミット無しでいくらでも使えるカードで、もし紛失なんかしようものならばアナンシ司教に八つ裂きにされるという楽しい代物だ。
「もちろんです」
アザースはどこからか機械を取り出してきてカードを通した。ごまかしは無しだ。
アザースはこと仕事に関しては誠実を貫いている。元よりそういう性分というわけではなく、ただ単にアザースが扱う顧客は馬鹿にされたと感じると狂暴になる手合いが多いからだ。その結果、アザースは自分で作ったルールを異常なまでに厳密に守るようになったというわけだ。
私は立ち上がった。
「ああ、それからアザース。今の私は対策局のファーマソン神父だ。覚えておいてくれ。今後はその名前だけを使ってくれ」
「わかりました」
アザースの顔に小狡そうな表情が過った。何を考えているのかはわかる。この情報をどうやって金に換えようかと考えているに違いない。
少しだけアザースには釘を刺しておこう。
「私はダークという名を捨てた。二度とダークには戻りたくない。でももし誰かがファーマソン神父はダークだと言いだしたりしたら、また私はダークに戻ってしまうかもしれない。この意味が分るな?」
私はにっこりと笑ってみせた。
そうして、アザースの表情を読む。顔面の筋肉が緊張する音。発散するホルモンの匂い。呼吸の速さ。心臓の鼓動音。訓練された人狼には人間の全身の『表情』を読むなど造作もない。
アザースは怯えていた。それもひどくだ。ダークの時代には、私はただの一度も笑ったことがないのでそのせいかもしれない。
「わかりました。ファーマソン神父。あなたは今までもファーマソン神父だし、これからもファーマソン神父です」
アザースは本気で言っていた。
彼が私の情報を売らないとは思わなかったが、売るとしてももの凄い値段をつけることだろう。ふたたび怒り狂ったダークに出会うことに見合うだけの金額とはいったい幾らになるだろう?
「うん、二人とも正しい認識に達したようだ」
私はエマとアンディを引き連れてアザースの部屋を後にした。背後で鋼鉄の扉にしっかりといくつもの鍵がかけられる音がした。
その帰り道、予想通りに襲われた。
*
そいつらは若い不良たちのグループだった。破れたジーンズにやたらと鎖のついた服。無意味に染めた髪。腕にはお決まりのタトゥーを入れている。
地元のリトルギャングたちだなと思った。
これがダークだったら行先を塞がれたことに腹を立て、最初の動きでこの半数の内臓を引きずり出していただろう。だが彼らにとって幸いなことに、今の私はファーマソン神父だ。私は自分の中にまだ残っているダークにつけた鎖の手綱を放しはしない。少なくとも今のところは。
「この路地は俺たちの縄張りなんだぜ。通るつもりなら通行料を出してもらおうじゃねえか。神父さんよ」
リトルギャングの一人、一番派手な格好をした男が前に出て言った。髪はトサカ。パンクロックを気取っている。
ここで言い争っても無駄だ。どのみち彼らの言い分には一分の理もない。
「アンディ。彼らの武器は?」私は尋ねた。
「喋っている男はナイフをポケットに入れています。左後ろの男が腰の後ろに拳銃を差しています。右の端の男は鎖をベルト代わりに巻いています。それと隠した手のひらの中にナックルを持っています」
よし、アンディは合格だ。きちんと訓練の成果を上げている。
「エマ。君一人でやってみなさい」
エマは頷くと前に出た。リトルギャングたちがたじろいだ。さすがに尼僧を傷つけるという行為に気後れしたのだろう。
「おい、何か勘違いしていないか。俺たちは別にあんたたちを傷つけようというわけではないんだ。ただボディガード料を・・」
エマの動きは素早かった。ナイフを取り出そうとポケットに手をいれた男の顔面に強烈なパンチを叩きこむと、その体を突き飛ばした。意識を失った体が拳銃を持った男にぶつかる隙をぬって前に出ると、見事な弧を描いた蹴りを拳銃男のこめかみに打ち込んだ。次の瞬間には右に跳び、男の金的を蹴り上げると、最後に残った男の背後に回り、うろたえる相手の腕を逆手に取って抑えつけた。
股間を抑えて蹲った男を見て、私とアンディが顔をしかめた。思わずその痛みを想像してしまったのだ。
ふむ、エマも一応は合格だ。訓練の成果が出始めている。ただ蹴りを使うのは禁止するべきかもしれない。モーションが大きい蹴りは相手が刃物を持っている場合は大きな弱点になるし、なにより尼僧服の下が大きくはだけるのは批難されるべきことがらだからだ。例えスパッツを下に履いていようとも。
エマが締め上げている男に私は顔を近づけた。
「誰に頼まれた」
「誰にも頼まれていません」顔を青くした男が答える。
匂いを嗅ぐ。確かに嘘はついていない。エマが男を解放した。
「今度からは神の使徒は襲わないように」
私はそう注意すると十字を切った。アンディとエマが小さくアーメンと呟く。それから呻いている男たちを路地に転がしたまま、その場を後にした。
子羊たちがこれを機に改心してくれればよいのだが。
*
アンディたちは我々がこのままゴブリン・マフィアのところに直行すると考えていたが、その前にやることがいくつもあった。
最初にやることは手近のステーキハウスの襲撃だ。
これはエマのためだ。変貌初期の人狼は驚くべきほどの大量の食物、つまり肉が必要だ。この時期は軽い飢餓でも急速に人狼の大脳皮質による抑制を弱らせて、たいがいは周囲で一番簡単に手に入る獲物、つまりは人間を襲うようになる。
エマの場合はそうなっても私という存在がいるので大丈夫だが、それでも危険な橋を渡る必要はどこにもない。アンディが飢えたエマに腕を齧られてからでは遅いのだ。
ステーキハウスの中にあった肉の内、アンディが一枚を食べ、私が五枚、そして残りをエマがすべて平らげた。この神父集団の食欲には店のウェイトレスが驚愕の表情を浮かべていた。
これで夕食までは何とか持つだろう。我らの犠牲になった牛の魂に祝福を。
次にやることは手に入れた情報の確認だ。アザースは食えないやつだが、情報屋としては一流だ。自分の仕事には常に真摯に向き合っている。だからその情報の真偽については疑っていない。
だから調べるのはゴブリン・ギャングの別の情報だ。どんな連中で、どのぐらいの規模なのか。用心棒にどんな連中を使っているのか。私ならば情報を集めなくても大抵のことは力づくで解決できるのだが、それは私のスタイルではない。それにそのやり方をアンディたちが真似するようでは困る。これも訓練の内なのだ。
こういった情報すべてをアザースから買い取るのはてっとり早いかもしればいが、そんなことをすればいったいいくらにつくか想像もできない。きっとアナンシ司教は良い顔をしないだろう。予算は潤沢でも神の愛のように無限ではないのだ。
他に二つばかり情報屋を当たりだいたいのところを掴んだ。
このギャング団の規模は百人程度。ゴブリンは元々が群れる習性があるので、この規模は普通だ。主にやっているのはかなりディープでコアな売春だ。フリークスと呼ばれる連中を大勢抱えていて、絶対に身元を明かせない連中を相手にして商売している。
用心棒にはオークが数人使われている。オークは巨体が売り物の怪物で知力は低いが力は強い。分厚い頭蓋骨もあいまって、銃で撃たれたぐらいではそれほどの打撃にはならず、殺すには爆発物が必要になる。闇のギャングの用心棒には最適な種族だ。
その中に最近は新顔が加わっている。これが目標だ。外見上はただの人間だが、石化能力を持つのでもちろん普通ではない。
もしかしたらこの新顔が群れを統率しているのではとも考えたがそれは杞憂だったようだ。あくまでも新顔の用心棒でしかない。これは朗報だ。
ここまで情報を集めてもアザース以上に詳しいものは集まらない。やはり彼の腕は一流だ。
最後にやるべきことは襲撃の作戦を立てることだ。
このゴブリン・ギャングの戦力相手なら私一人でも十分に対抗できる。ただこれに石化の使い手が加わると話は相当に厄介になる。だがこちらにも強みはある。大概の石化能力は目を通じて働く。だから人狼には石化に対抗できる確実な手段が一つあることになる。そしてアンディにも十分に対抗できる強力な手段がある。
邪魔が入らないように最初にゴブリン・マフィアを皆殺しにしておくというのはどうだ?
少し考えてこの案は放棄した。ゴブリンは行動も思考も実に醜い生き物だが、彼らは彼らなりに存在理由を持っている。無暗にそれらを破壊するような真似はしてはならない。
これがダークなら一切躊躇わずに皆殺しにするだろうが、私はファーマソン神父であり神の慈悲を体現する存在だ。あまり派手なことはやるまい。
できることなら目標が一人のときに会いたいが、ここまで情報が出てこないというのはこの少年だか何だかはゴブリンたちが囲いこんでいるということだ。一人になる隙はないだろう。
となると一つだけ、実現できそうな案がある。しばらく考えて結論が出た。ゴブリンは信義というものを持たない。あくまでも自分たちの利だけで動く。だから彼ら相手ならばこの案は可能だ。
3)
背後に二人を引き連れて教えられた番地を訪ねた。タクシーはここまで来たがらなかったので途中からは歩きだ。
驚いたことに拾ったタクシーはまたあの運転手だった。彼は前とまったく同じ会話をして私たちを止めたが、私は前とまったく同じ会話をして彼だけを先に帰した。
どうやら天の上の神様は私を揶揄って楽しんでいるらしい。それともこれは大天使たちの悪戯なのか?
目的の番地に建っていたのは古い大きな洋館だ。建物と言うよりは廃墟と表現した方が正しい。壁一面にスプレーで落書きされ、庭にはゴミが積もっている。窓ガラスはすべて割れ、ご丁寧にもその上から鉄板で補強されている。周囲も廃墟に近いビル群なので、背景には見事にマッチしている。いかにもゴブリンが好みそうな建物だ。
門柱にびっしりと並ぶ弾痕を指で撫でながら、私とアンディとエマは僧服のままで通り抜けた。念のため全員サングラスをかけている。
「それ以上近づくんじゃねえ!」
甲高い声で罵声が飛んだ。姿は見えないが、ゴブリンに間違いない。
「銃で狙っているぜえ。神父さんよ。おっとそこの尼さんだけは通っていいぜ。大歓迎だ」
「マスター」エマが小さく呟いた。
「駄目だよ。エマ。殺しは無しだ」
成りたての人狼は極めて興奮しやすい。私はエマに釘を刺した。ここには喧嘩をしに来たのではないのだ。
その点ではアンディは落ち着いたものだ。アンディはその能力も相まって銃弾の飛び交う中でも悠々と散歩ができるメンタルの持ち主た。
「落ち着きたまえ」私は鉄扉の向こうのゴブリンに声をかけた。
「君たちのボスに用があって来た。取り次いでくれ」
「その前にお前さんは誰だ。少なくとも俺の友達ではないぞ」
門番役のゴブリンが答える。その横に並んでいるのはオークだろうな。
「馬鹿馬鹿しい。いったいどこのゴブリンに友達なんてものがいるのか」
私は指摘した。
「ちげえねえ」ゴブリンは苦笑した。
うん、良いスタートだ。ユーモアは地獄の門すら緩くする。
「お前はまだ答えていねえぞ。どこの誰だ?」
「バチカン特殊事例対策局のファーマソン神父だ。儲け話を持ってきた」
扉の向こうでバタバタと走り回る音がした。それから叫び声と悲鳴。しばらくして洋館の窓という窓から銃口が突き出した。大口径から小口径、拳銃からショットガン、ライフルまで全種類が揃っている。
「お前たち三人だけか?」
先ほどとは違う声がした。
「そうだ。ところでいつまでここで待てばいい?」
「お前たちは招かれざる客だ。歓迎されるとでも思っているのか?」
鋭く答えが返ってくる。
私の中のダークがごそりと動いた。うん、もういいか。とりあえず皆殺しにして入るか。いや、待て。まだ早い。
「これ以上待たされると、君たちに取って大変にまずいことになると思うがね」
私は指摘した。
「それはお前たちに取っても同じだろう」
ゴブリンは言い負けない。小さくて卑怯でひ弱な種族なのだが、プライドだけはヒマラヤ山脈よりも高い。
「そうでもないさ」思わずにやりとしてしまった。
こういう彼我の力の差がわからない奴らは大好きだ。たまにはダークにも餌をやらないと爆発してしまう。私はアンディの動きに注意しながら待った。何かあればまず真っ先にアンディが動くからだ。
しばらく間が空いた後、がちゃりと音がして扉が開いた。
「ボスが会いたいとさ。入んな。下手な真似はするなよ」
扉の向こうには身長ニメートル半はあるオークが両側を固めていた。オークは表情に乏しく頭の悪さが滲み出ている。だがその体は筋肉の丘というべきもので、人狼の私でさえ、これ一体を殺すのに優に一秒はかかりそうだ。
それに比してゴブリンはオークの腰ぐらいまでの背の高さだ。人間で言えば中学生程度。こうして並ぶと実にデコボコな取り合わせだが、主導権はゴブリンの側にある。
「さあさあ入った入った」
そう言いながらゴブリンはエマの尻を触ろうと手を伸ばした。
自分の指がどうして折れたのかゴブリンには最後まで分からなかっただろう。続けてエマの蹴りがその顎に入ったからだ。
派手な音を立ててゴブリンが床に叩きつけられる。
オークがそれに反応して前に出そうになったので、私はサングラスを外すと彼らの眼を見つめた。
暗い洞窟の中。か細い炎を囲んで身を寄せる生き物たち。ひたひたと周囲の暗闇が迫る。その暗闇は、黒より昏く、闇より重い。その中に赤く輝く眼が浮かび、真っ白な牙がその下に浮かぶ。
轟く遠吠えは、運命の時を告げる。
私の中のダークに見つめられて、オーク二体は凍りついた。その脳裏に浮かぶ光景の中で、惨めな焚火に縋り付いているのは自分たちだと、直感的にオークは理解した。
本能が動くなと命じた。その命令はわずかに二つの言葉で構成されている。
『動けば』『死ぬ』
オークとしては賢明な行動をした。二体は天井を見つめてただの彫像と化したのだ。
部屋の奥にいた別のゴブリンに目を向けると、慌てて私たちをボスの元に案内した。
*
豪華な部屋だった。洋館の外側の寂れ具合が嘘のように内装は凝っていた。壁には高価な壁掛けがぶら下がり、趣味は悪いがこれも高価は調度品が部屋を埋め尽くしている。隅には大きな金庫が一つ置いてある。
部屋の奥には大きな革張りのソファがあり、そこに恐ろしく太ったゴブリンが座っていた。これがこの群れのボスだ。眼の前のテーブルには色々な料理が山盛りに置かれている。その両側で金で飾られた燭台が、煌々たる天井の照明の下で意味もなく炎を灯している。
周囲の壁の前にはオークが数体と手に手に武器を持ったゴブリンたち。たいがいは自分の体に合わせた二十二口径の小さな拳銃だ。何人かは奇怪な形状の武器を持っていて、魔術師と見えた。もっともゴブリンという種族には魔術は適合しないので弱い魔術を使うのがせいぜいだろう。
ボス・ゴブリンが口を開いた。
「対策局の人間か。名前は何と言ったかな?」
「ファーマソン神父だ。覚えておいてもらおう」
「俺は忙しい。要件は何だ。さっさと言え。それを聞いてからお前たちをどうするか決める。そっちの姉ちゃんはうちで働いてもらおうか」
こういう手合いはまず相手を脅すところから話を始める。そうしないとまともに会話もできないのだ。実につまらない。私はそれを無視することにした。
「こちらのメンバーが何人かそちらの犯人に石化された。石化したヤツを対策局に差し出して貰おう」
「おい、おい、いったい何のことだ?」
ゴブリン・ボスはとぼけた。目の前の皿からブドウを一粒取ると自分の口に放り込む。こんな奴に食われるブドウが可哀そうになったが、この世のなかは悪い奴ほど旨い食い物にありつけるようになっている。
「無駄な時間を使わせて欲しくないな。すでに調べはついている」
ゴブリン・ボスの顔からにやついた笑いが消えた。
「で、対策局はその代わりに何を差し出すんだ?」
「そうだな」私は頬を掻いた。「こういうのはどうだ。大人しく犯人を差し出すならお前たちが対策局の職員にしたことは忘れてやる。どうだ? バーゲンセールだぞ」
ゴブリン・ボスの顔に赤みが差して、総合的にみて茶色に変化した。ゴブリンは悪魔をベースに作られている癖に反応は人間そっくりだ。
「ふざけんじゃねえぞ。てめえ、何様だ」
「それはこっちの話だ。対策局に喧嘩を売ったことを忘れてやると言っているんだぞ。普通の組織なら泣いて喜ぶ提案だ」
「ウチをそんな組織と一緒にするな。この辺りじゃ最大の組織なんだぞ」
もっと規模の大きい普通のゴブリン組織はたいがいは悪魔が統括している。そういった連中は対策局には極力関わらないし、逆らわない。対策局の中には多くの怪物が飼われていて、下手につつくと恐ろしく厄介なことになると知っているからだ。
闇の世界の中でアナンシ司教を恐れないものは存在しない。
「ならば仕方がないな。交渉は決裂と考えてよいのかな?」
私は再びサングラスを取ると、ゴブリン・ボスに目線を合わせた。今の自分の顔は見たくない。もし鏡を使って自分の瞳を覗きこみでもしようものなら、捨て去ったダークがそこに見えるだろうからだ。
何かがゴブリン・ボスの体を駆け抜けた。例のあれだ。そう、生存への執着と呼ばれるヤツだ。
「待て」手のひらを突き出して言った。それで私の視線を遮ったつもりなのだ。
ゴブリン・ボスはテーブルの上の電話器を取り上げ、電話をかけた。昔は伝書鳩がせいぜいだったのに、最近ではゴブリンまでもが人間の文明のお世話になっている。
私は自分の耳に意識を集中する。聴覚が増感し、ひそひそ声の内容が聞き取れるようになる。
「アザースか。そうだ。マルコーニだ。情報を売ってくれ」
「お安い御用です。マルコーニさん。何をお売りしましょう?」アザースの声が返る。
「いまここにファーマソンって神父が来ているんだが」
アザースの悲鳴が聞こえた。命拾いしたと祝杯を上げていた所にこの電話が入ったのだろう。
「騒がしいな。いったい何をやっているんだ? アザース。
でな、こいつが何者か知っているか」
「それを私に訊かないでください。もちろん知っています。知っていますが言えません」
「金は払う。この神父、何かがおかしい」
「金はいりません。だからいいですか、よく聞いてください。そのお方には絶対に逆らっては駄目です、何でも言う通りにしてください。私はお得意様を失いたくないんです」
「何を言っている?
お前が金がいらないだって?
悪い物でも食べたか?
いいからこいつの正体を教えろ。いくらでも払う。対策局の人間だってことは知っている。それ以外の情報をだ」
いきなりアザースの口調が変わった。恐怖の余りに我慢の限界が訪れたらしい。
「値段はつけられるがあんたには払いきれねえよ」
「いくらだ。言ってみろ」ゴブリン・ボスは動じなかった。
アザースは金額を言った。アザースはプロの情報屋だ。やはり私の情報に値段をつけていた。
「バカを言うな!」ゴブリン・ボスが怒鳴ると、こちらをちらりと見て、また声を潜めた。「街を一つ買おうってわけじゃねえんだぞ」
「それを教えれば俺は地球の反対側に逃げないといけなくなる。いや、たぶん月まで逃げないと駄目だろう。無茶を言っているわけじゃない。これは適正価格だ」
「いったい何者だ。こいつは。じゃあ質問を変える。答えられるなら答えてくれ。こいつの危険度はケルビム級か?」
智天使ケルビムか。可愛い奴らだ。たいがいは群れを成して空を飛び、いつもニコニコしていて、戯れついでに町を焼き払う。そんな奴らだ。
「いいや」震える声でアザースが答える。「もっと上だ」
「トローン級?」
「もっと上だ」
「セラフィム級?」
「もっと」
「おいおい、まさかミカエル級だなんて言うんじゃないだろうな」
ゴブリン・ボスが呆れた。それに対してアザースは真剣に答えた。
「もっと上だ」
「バカを言え。そんな存在が・・」
ゴブリン・ボスは絶句した。そんな存在に思い当たったのだ。
地域のマイナーゴブリンですら知っているある存在に。
「見た目に惑わされるな。そのお方は神父なんかじゃない。それとは対極にある存在だ。絶対に逆らうな。言いつけにはなんでも従え。次の満月を楽しみたければ」
アザースはそれだけ言うと電話を切った。
ゴブリン・ボスもアザースの情報の確かさは知っている。先ほどまでの態度とは打って変わったように態度を変えた。ソファから立ち上がり、顔に追従笑いを浮かべる。
「これはこれはいらっしゃいませ。ファーマソン神父。対策局からの御用ですな。私どものボーンズに用があるとのことで」
くるりと向きを変えると、近くに立ってこの有様を見ていたゴブリンに怒鳴った。
「ボーンズを呼んで来い! すぐにだ!」
命じられたゴブリンが慌てて部屋を飛び出す。周囲のボディガードたちがボスのこの突然の変化にざわめく。オークたちは何が行われているのか分からずに混乱している。
「どうかここにお座りになって」
先ほどまで自分が座っていた豪華なソファーを示す。
エマが嫌な顔をした。そのソファーはゴブリン臭いだろうと想像したのだろう。
三人とも座りはしなかった。これからこの訪問の一番のクライマックスが訪れる。場合によっては大立ち回りになるかもしれないのだ。
エマが料理を指さした。「マスター。これ貰っていいでしょうか」
ゴブリン・ボスが答える前に私は頷き、エマは焼いた鳥足を一つ取るとバリバリと食べ始めた。
骨ごと鳥足を齧る尼僧服姿のエマを見て、ようやくゴブリンたちも彼女が普通の人間ではないことに気がついた。恐らくここのゴブリンたちは銀の武器を用意していない。銀無しで人狼と同じ部屋にいることは致命的なのだといつの日か彼らも学ぶだろう。
それにしてもここに食物があってよかった。エマがオークに食いついている光景は見たくない。肉の硬さは無視できるにしても、オークの肉はひどい味なのだ。
やがて彼女が肉料理をあらかた片付けた頃に、ドアにノックがあり、ゴブリンが一人の少年を連れて入って来た。
「ボス。ボーンズです」
確かに少年だ。年の頃は十五ぐらいか。見たところは人間に見えるが、怪物の中には擬態能力を持った者が多いのでそれは信用できない。
少年は薄汚れて痩せている。
ゴブリンたちはきちんと食べさせているのだろうか?
少年の視線がテーブルの上の料理に飛んだのを見ると、そうではないようだ。
顔はマスクではなく素顔だ。ということは彼はメデューサではない。メデューサは顔の造作に魔法的な秘密があるからだ。何よりメデューサの女王を除けばどれも例外なく醜い。この少年はごく普通の顔立ちだ。
ゴブリン・ボスがにこやかな顔で少年に向くと、肩を優しく叩いた。
「ボーンズ来たか。お前はこれからこの人たちと一緒についていくんだ」
少年は動揺した。
「でもボス。俺にはお勤めが」
「もういいんだ。ボーンズ。もういいんだ。俺たちは自分たちだけでやっていける」
ゴブリン・ボスはどこから取り出したのか1ドル札を丸めてボーンズの胸ポケットに突っ込んだ。
「これは今までの礼だ」
何とも有難いお言葉だ。確かにもし気前の良いゴブリンが居たとしたらそれはゴブリンとは言えない。
「だけど俺がいなくなったら対策局の奴らが押しかけてくる・・」
「いいんだ。いいんだ。ボーンズ。この人たちがその対策局のお方だ。お前を迎えに来たんだ」
少年の顔がこわばった。よろよろと後ずさる。
「ボス、ボス。まさか、俺を売ったのか。俺を見捨てるなんて」
そろそろ割って入るべきか。私はそう考えた。人間というものは追い込むとろくな結果にならない。
その通りだった。
少年がわけの分からない叫び声をあげた。
アンディがその特殊能力を発揮し、エマに飛び掛かると床に引きずり倒した。
少年の額の皮膚が割れ、そこに一つの目が現れた。
怪物カトプレバス。その能力は死の視線。究極の邪眼だ。
背後でゴブリンたちがその視線を受けて悲鳴を上げた。いずれも煙を上げ始めた自分の顔を抑えて倒れている。動きの鈍いオークはその場に立ったままだが、その目が白くなっている。石化プロセスの開始だ。
私は至近距離でまともにカトブレパスの邪眼と視線が合ってしまった。ガンと頭を殴られたような感じだ。視界がぼやけ、暗くなる。カトプレパスの視線を間近で受ければ石化は免れない。ゴブリン・ボスを睨むためにサングラスを外していたのが仇になってしまった。
ピシピシと音を立て始めた自分の顔は無視して、私は素早くナイフを抜き出した。右側に備えているナイフは銀を含まない鋼鉄製だ。ここからは時間の勝負だ。
少年が逃げ出すのが音でわかったが、私は彼を殺すためにナイフを抜いたのではない。
素早い一振りで、自分の顔の前面を切り裂いた。顔ごと石化した部分を削り落とす。顔の前に血の霧が噴き出すのが分かった。霧の一部も石化している。
たちまちにして顔の再生が始まった。床の上では切り離された自分の顔が石のデスマスクと化しているだろう。
眼球の再生と共に、腰を抜かしているゴブリン・ボスの姿が見えた。今の私の顔を見たならば不思議はない。人体模型図もかくやという光景のはずだ。
あっと言う間に肉が盛り上がり、顔面が修復される。もしこのゴブリン・ボスが今までに人狼を見たことがあるなら、これほどの速度で再生する人狼が存在することに驚いただろう。これもダークの時代に受けたあらゆる魔導処置の結果だ。
「マスター」アンディが叫んだ。
「大丈夫だ」私はサングラスを取り出すと顔にかけた。
二人がサングラスをかけたままであることを確認してから、少年の後を追った。