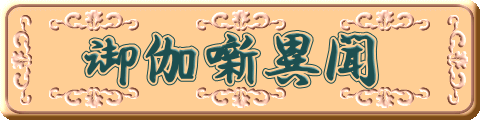
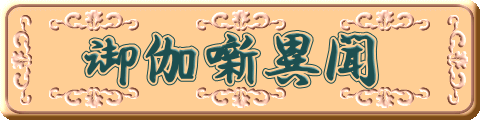
3)天竺火鼠の皮衣
天竺火鼠の皮衣とは、天竺にある火の山に棲む火鼠の革で作った布のことだ。別名で火浣布とも呼ばれる。汚れがついたときはこの布を火にくべると汚れだけが焼け落ちて、綺麗になった布だけ残る。故に火で洗う布ということで、火浣布と名付けられた。
そんな布、右大臣阿倍御主人は今まで一度も見たことは無かった。
さっそく都中にお触れを出すと、多額の報酬に釣られて多くの火浣布が集まった。お代をお払いくださいという商人たちを待たせて、阿倍御主人はそれらの布を片っ端から炎の中に投げ込んだ。いずれも敢え無く燃え尽き、商人たちには刑罰として棒叩きが与えられた。
やがて、布を持ち込む愚か者たちも絶え、阿倍御主人は頭を抱えた。
本物の火浣布は存在しないのか?
輝夜姫はありもしない物を持って来いと言ったのか?
この無茶な要求はそもそもが遠回しな求婚の断りだったのか?
阿倍御主人の脳裏をさまざまな考えが占めた。このまま姫のことを忘れるというのが一番良さそうに思えたが、しかし阿倍御主人は諦められなかった。いくら長く生きようともあれほどの女人にはもう二度とは会えまい。そう確信しているからだ。
陰陽寮を訪れ、陰陽博士安倍公麿に質問をぶつけてみた。
「火鼠の皮衣は存在するのか?」
「然り。存在する」
安倍公麿は言葉少なに答えた。その一言に帝でさえも一喜一憂する。たかが右大臣にそこまで多くを語るつもりはない。だが同じ安倍の姓を持つ者ゆえ、そこまで無碍には扱うまい。
「それは何か。火鼠の皮なのか? 火鼠という生き物は存在するのか?」
「然り。存在する」
「それはどこに居る? 天竺にか? 日の本にはおらぬのか?」
「天竺にも居る。日の本にも居る」
この答えを聞いて阿倍御主人は小躍りした。
「日の本のどこに居る?」
「火山のある所ならどこにでも棲んでおる。ただし」
陰陽寮の頭は言葉を切った。
「火鼠は臆病で滅多に人の目には触れぬ。見つけ出すはよほどの僥倖。ましてや捕まえるは至難の業。故に、火鼠の皮衣は得難い財物なり」
だが阿倍御主人にとってはそこまで聞けば十分であった。
火山は阿蘇の雄山を選んだ。年を通じて常に火を拭き上げ、また火山の多い日の本でも不死の御山を除けば最大の火山であるから。
旅は長く長くかかった。京の都からお供を連れて旅をする。街道があるとは言え、それほど整備されているわけではなく、一行は時間をかけて南下した。こうしている間にも他の求婚者たちが各々の課題を見つけて、輝夜姫の下に馳せ参じるのではないかと苛つきもしたが、かと言って手ぶらで姫の下に行けるわけもない。そんなことになったときの姫の侮蔑に満ちた視線を想像しただけで、阿倍御主人の下腹は冷え、死んでしまいたくなる。
なんとしても火鼠の皮衣をこの手にしなくては。決意は強まるばかりであった。
地元の者でも恐れる火の山に登ってみれば、これはまた雄大かつ威容な山であった。噴煙が吹き上がり、昼間でも空を暗く染めるかのように灰が漂うその様に、阿倍御主人は内心怯えた。怯えはしたが、山に登るのは止めなかった。吹き上げる炎に震えるお付きの者たちを叱咤し、降り注ぐ噴石の合間を縫って、山の頂きへと近づいた。
溶岩の川が溢れ出すその上を、瞬間、小さな影が横切った。
確かに鼠だ。真っ赤に輝く溶岩の上を素早く、しかし焼けもせずに走り抜ける。
「いたぞ! 火鼠だ」
阿倍御主人は叫んだ。恐る恐る付いてきていた者たちもその声にざわめき立った。
「あそこだ。捕まえよ!]
皆で追った。火鼠は思いの他すばしこく、人々の手をすり抜けた。溶岩の上もものともせずに駆け抜けるので、人間では後を追うことができない。その内に地面に空いた穴の中へと飛び込むと、姿が見えなくなった。人一人がやっと通れるほどの穴だ。その中は暗くて見えない。
「追え。追え。あれを捕まえれば褒美は望みのままだ」
その声に促されて、最初の者が穴の中へと潜り込んだ。しばらく一行は外で待っていたが戻って来ない。次の者が勇気を奮って穴へと潜り込む。これも戻って来ない。名指しをされて三人目が穴に入り、それすらも帰って来ないともう誰も名乗りを挙げる者はいなくなった。
「ええい、臆病者たちめ。火鼠はそこにいるというに」
ついに阿倍御主人が立ち上がると、周囲が止めるのも聞かずに穴の中へと潜り込んだ。
穴の中は暗く、幾重にも分岐して、しかも長く続いていた。手にした松明が半分も燃え尽きた頃、阿倍御主人は自分が迷路の中で迷子になっていることに気がついた。戻ろうにも背後の暗闇の中に道しるべはない。
これは困った。果たしてここはどこだ。俺はどちらに進めばよい。心細い思いでとにかく前へ前へと進んでいると、やがて前方に小さな明かりが見えて来た。どうやらこの穴の出口らしい。喜び勇んで飛び出してみると、そこは広い洞窟であった。壁一面が何か光る物で覆われている。
人影があった。
全身赤みがかった大男たちが阿倍御主人に気づくと集まって来た。彼らの額に生えた角に気づいて、阿倍御主人は震えあがった。地の底には鬼が棲むという。そんな話が思い起こされた。
抵抗する間もなく赤鬼たちに捕まると、そのまま洞窟の奥に連れて行かれた。洞窟はひどく大きく、冷え固まった溶岩を組み合わせた石造りの街がその中に広がっていた。奇妙な色合いの植物と思われるものが植わった畑もあり、別の赤鬼や、女性と思われる赤鬼たちが働いていた。
一際大きな建物へと連れて行かれると、その中央に置かれた椅子に座っていたのは、年老いて痩せた普通の人間の老人だった。
「これはこれは、珍しいお客人が迷いこんできたの」
身振りで赤鬼たちを下がらせると、老人は話を始めた。
阿倍御主人が迷いこんだのは地底に広がる赤鬼たちの国であること。極めて稀にだが、地上から迷いこんでくる地上人がいること。そして一番大事なのは、ここより帰る手段が無いこと、などだった。
「帰れないですと、それは困ります。姫が待っているんです。どのようなことでもしますから、地上に返してください」
老人は困ったような顔をした。
「意地悪で言うておるではない。以前はまだ地上に抜ける道が一つだけあったのじゃが、この間の噴火の際に崩れて埋まってしまったのじゃ。ヌシがここに来れたのを見ると、まだ地上につながる道がどこかにあるのじゃろうが、さて、それがどれかと問われてもとんと分からぬ。ヌシが道を覚えておればよいのじゃが?」
阿倍御主人は首を横に振った。目印すらない暗闇の中でどこをどう通ったかなど覚えているわけがない。
「じゃろう。まあ、何ぞ良い知恵が浮かぶまでここでゆるりと過ごすがよい。赤鬼たちは恐ろしそうに見えるが実は気の良い連中じゃ。住めば都とは良く言ったものじゃぞ」
そうは言っても、その都から来た身としては居心地がよいものではない。しかし、では何か他に策があるのかと言えばあるわけもなく、仕方なく阿倍御主人はこの溶岩の宮殿に身を落ち着けた。
そうこうして日々を過ごす内に、周囲のこともだんだんと分かってきた。
この鬼の都には主に赤鬼が棲んでいる。男も女も赤鬼は体が大きく、牙と角を持つわりには穏やかな性格をしていた。頭はあまり良くなく、赤鬼の国の差配はこの老人がすべて行っていた。
老人の補佐をして過ごす内に、阿倍御主人もまた赤鬼たちの敬愛を受ける身となり、何不自由のない暮らしをするようになっていった。老人も過去にこの国に迷いこみ、そのときには帰る道もありはしたが、いつの間にか定住を決意するようになったのだ。
地下の国に暮らすようになって分かったのは、この地下では火鼠はさほど珍しい生き物ではないことであった。赤鬼たちに命じて、あるいは数匹は自分で捕まえて、手にいれた火鼠の皮を剥いだ。じきに人一人がすっぽりと被ることができる大きさの火鼠の皮衣が出来上がったが、たとえそれを使って溶岩が渡れるにしても、やはり地上に戻る手段は無かった。
赤鬼たちの主食はこの地下に生えるキノコに似た植物であった。天井や壁を埋める光キノコの親戚らしく、溶岩の土から何らかの栄養を吸い上げて育つ。赤鬼たちにキノコの栽培を教えて、飢えることのないように食料の管理から住宅を建てる差配まで、やることは色々とあった。赤鬼は愚かで、自由にさせていてはいつ滅ぶかわからない所があった。
たまに小人数で襲ってくる青鬼以外にはさしたる敵はおらず、平和でのどかな暮らしが続いていた。
そんなある日、ふとしたはずみに洞窟の端から匂いが漂って来るのに気がついた。懐かしい匂い。地上の梅の花の匂い。匂いの下をたどると、やがて一つの穴へとたどり着いた。おそらくは地上へと通じている穴。この匂いを辿っていけば地上に出ることができるに違いない。
阿倍御主人の心は踊った。帰れるのだ。地上へ。
だが一度地上に出れば、再びここに戻って来ることはできまい。地下の匂いのする穴なんか、地上では聞いたこともない。最初のときとは逆の状況が生じている。最初は地底から出る術がない。今度は地底へ戻る術がない。
阿倍御主人は前を見て、それから後ろを見た。
赤鬼が一人、走って来ると、老人の危篤を告げた。
今、この洞窟を出れば姫に会える。火鼠の皮衣も手に入れた。きっと輝夜姫は約束通りに妻となってくれるに違いない。だが、しかし、そのことにどれだけの意味があるだろう。
阿倍御主人は右大臣だ。官職名こそ立派だが結局は帝の身辺を警護するだけの使い走りに過ぎない。地上に戻れば自分はまたうだつの上がらぬ下級貴族へ戻ることになる。姫もやがては愛想をつかし自分を捨てるだろう。いやきっと、美しい妻を娶ったとなればあの好色の帝のことだ、何だかだと罪を被せて自分を遠くの島に流し、輝夜姫を手に入れようとするに違いない。
そして老人を失い、いままた自分をも失えば、この気の良い赤鬼たちも滅んでしまうだろう。無計画にキノコを食い尽くして、あるいは青鬼の計略にかかって。
その一方で、ここに残れば、自分は赤鬼たちの王だ。歳を取って死ぬその日まで。
阿倍御主人は外へ通じる穴の前でいつまでもいつまでも迷っていた。
4)燕の子安貝
燕の子安貝が当たった時は実に幸運に思えた。
燕はごく稀に宝貝を産むという。その貝は、不思議な力を持ち、巣の中のヒナの成長を助けるという。その子安貝を手に入れればよいのだ。
これは他の四人の課題に比べれば随分と容易いことに思えた。
早速にして中納言石上麻呂は配下の者を集めて命令を発した。燕の巣を探り子安貝を見つけ出せ。領地の者にもお触れを出した。燕の巣の中に子安貝を探せ。見つけ出したものには莫大な褒美を与える。
ほどなくして多くの者たちが石上麻呂の屋敷を尋ねて来た。
「殿様。ご所望の子安貝です」
ことここに至って、石上麻呂ははたと気がついた。
眼の前に並ぶこの子安貝の数々、いかにして本物と証明するのか。貝は大きさ色形の違いはあれど、どれも普通の貝に見えたからだ。漠然とだが、この世に二つと無き至宝であるからには、暗闇の中で光るとか何とか、ひと目で見て判る違いがあるものだと思いこんでいたのだ。
心の中に浮かんだこの疑問は、そのまま貝を持参した者たちにぶつけられた。お主たち、この貝が本物であることを証明してみせよと。
一刻もしない内に訪れた全員が退散した。最後まで粘っていた者も、結局は何もできぬまま帰る羽目となった。
果たしてこれらの中に本物は混ざっていたのか?
いや、本物かどうかはこの際問題ではない。問題は、輝夜姫がそれを本物と認めるかどうかなのだ。たとえそれが本当に燕が産んだ子安貝であろうとも、ただの子安貝と寸分変わらぬならばそれは意味がないのだ。例えば暗闇の中で燦然と輝くや、あるいはそれが触れた傷を治すなど、普通と異なる所がないといけない。
これは途轍もない難問であった。
だが、だからと言って輝夜姫を諦める気は毛頭なかった。
困ったときは、陰陽師に任せればよい。石上麻呂は陰陽寮を尋ねた。
「さよう。では、貝のことならば、貝の王を尋ねるが良いでしょうな」
陰陽博士安倍公麿は説明した。目の前に金子を積まれればさしもの無口な博士も饒舌となろうというもの。
「中つ国の東の浜の沖に、蜃とよばれる巨大な蛤が生きております。この蜃、ときたま海上に浮き上がり息を吐きますると、これが蜃気楼となりまして海上に幻の都を作り出しまする」
「そこに燕の子安貝があるのじゃな」
石上麻呂ははっしと己の膝を叩いた。ついに解決の緒を掴んだのだ。
「さようでございます。貝の王ならば当然ながら燕の子安貝も臣下に収めておる理屈。恐らくは蜃気楼の中に浮かぶという幻の都の宝物庫の中に、大事に収められておるに違いありませぬや」
そこまで聞けば十分であった。領地に飛んで帰ると旅の手配をして、ただちに出発した。摂津から回船に乗って下関に回り、危険なることこの上ない遣唐船にも躊躇わずに乗り込んだ。中つ国沿岸を南下し、蜃気楼が出るという噂のある浜についたは、出立より六ヶ月後のことであった。
分からぬ言葉ながらも何とか身振り手振りで聞き出した浜に立ち、待つことしばし、海上に靄が立ち込めたと思ったら、またたく間にそれは成長し、見事な都市へと化けた。
蜃気楼である。
その威容に見とれている中、蜃気楼の城郭から一本の道が伸びてきた。それは雲でできているようなどことなく頼りなげな感じがあったが、試しに足を乗せてみると石上麻呂の体の重みを見事に受け止めてみせた。
蜃気楼は時間が経つと消える。そう聞いていたので慌てて幻の道をたどり、蜃気楼の城郭へと登った。城の中はまるで普通の城に見えた。少しだけ色が透き通っているような感じはしたが。
白い肌の背の高い人々が急に周囲に現れると、話しかけてきた。日の本の言葉とも中つ国の言葉とも聞き取れる奇妙な言葉であった。
「ようこそ。稀人。お客人よ。歓迎いたしましょう」
蜃気楼の街に棲む蜃気楼人たちは石上麻呂を街の奥へと案内した。
「待ってくれ。私は輝夜姫との婚礼の祝いとなす燕の子安貝を探してここに来たんだ」
「燕の子安貝ならば宮殿の宝物庫にあります。ここではそれほど貴重なものではありませんので、後ほど差し上げましょう。まずは私たちの歓待をお受けくださいませ。ここでは地上から人が来るのはとても稀なのです」
ここで石上麻呂は大事なことを思い出した。
「燕の子安貝とは一目見て判るものなのか?
宝物としての外見を持っているのか?」
それを聞いて蜃気楼人たちはそよそよと不思議な笑い声を立てた。
「見た目は普通の宝貝です。しかし燕の子安貝は子供の成長を助け、病気を治す力があります。病気の子供に持たせればどんな病気も一晩で治りますので、それが宝物の貝であることが分かります」
石上麻呂は驚いた。なんとそのような判別法であったとは。石上麻呂の気持ちには構わず、蜃気楼人たちは宴の席を設けた。宴会は何時果てるとも知れず続いた。
蜃気楼の都は大きな貝の怪物である蜃が吐き出す気の塊の中に存在する。蜃が長い長い呼吸をするたびに短い時間だけ現世に出現し、すぐにまた消える。消えている間は蜃の体の中に蜃気楼は存在する。つまりその間は下界へ戻ることは叶わない。
蜃気楼の中での生活は長く続いた。蜃がいつ気を吐くかは予測がつかなかったが、それは大概にして石上麻呂が眠っている間だったからだ。
蜃気楼の街では石上麻呂は大事にされた。この街を訪れる客人は少なく、訪れている間に大勢の子を成して貰わねば、街が衰退してしまうからだ。今でさえ蜃気楼人は下界人とは異なる外観になりつつある。このまま後数世代経過すれば、きっと人とは似つかぬものになってしまう可能性があった。
稀人たる石上麻呂の存在は街の存続のための子種としてそれだけ貴重であった。
毎日、不思議な香りのする蜃気楼人の女人たちが石上麻呂の寝室を訪れた。食卓には山海の珍味が並べられ、さらには街の人々の尊敬が捧げられた。日々、石上麻呂を父親とする新しい子が生まれ、蜃気楼の街はそのたびに賑やかになっていった。
その内、十分な数の子供ができたと思われたのか、石上麻呂に燕の子安貝が差し出された。
「今まで貴方を騙していたことを謝ります。できるだけ長くこの街に居て貰うために、お薬で眠っていただいていたのです。実は蜃が気を吐く周期は予測がつくのです。もう間もなくその時が訪れます。できるならばこの街に残っていただきたいのですが、無理に引き止めるのも恩知らずの所業と思い、このように致すことになりました」
なんとそうであったか。いまさら怒る気にもなれず、石上麻呂は燕の子安貝を手に取った。手に入れてみれば何の変哲もないただの貝に見える。女官に案内されていった先には下界へとつながる道が続いていた。あの見覚えのある海岸へと雲の橋が繋がっている。
石上麻呂は地上を見下ろし、そして背後の街を見た。大勢の蜃気楼人が、胸に赤子を抱いて見送りに来ている。すべて石上麻呂の子供たちだ。この子たちとももう会えない。これが今生の別れになるのだろう。女官の説明によると、一度この蜃気楼の街を出た人間は二度と再び戻って来ることはできない。そういう掟なのだと言う。
足下を見下ろし、背後を振り返り、もう一度足下を見下ろした。この道の先には輝夜姫がいる。あの夜の中に美しく輝く姫がいる。
しかし、はたして姫は待ってくれているのか?
もう随分と長い時が経ってしまっている。よもや他の求婚者が先に宝物を手に入れて輝夜姫と婚姻を結んでしまったのではないか。あるいは女狂いで有名な帝が強権と強欲を発動して、五人の求婚者を差し置いて輝夜姫を手に入れているという可能性もある。あるいはあれほどの美しさなのだ。月からお迎えが来て輝夜姫を異界へと連れ去った後ということも、もしかしたらあるのかもしれない。あの現実ばなれした輝夜姫の挙動を思えば、そんなことがあっても不思議ではない。
石上麻呂は踏み出しかけた足を引き戻した。
「私はこの街に住み続けようと思う。日の本の国に帰るのは諦める」
それを聞き、蜃気楼人たちは歓声を上げた。
5)仏の御石の鉢
石作皇子は悩んでいた。
仏の御石の鉢とは仏陀が沙門の僧として使っていた托鉢鉢のことである。輝けるその托鉢鉢は当然ながら天竺の秘宝。見つけるのですら難事だが、国外に持ち出すのはさらに難事。どう考えても無理な話であった。
だが、だからと言って輝夜姫を諦めることができるのかと言えば、それは無理な話であった。外面の美しさに加え、内面の賢さを考え合わせると、この世に彼女に匹敵する女性はいない。その賢さが今回の難題の数々を作りだしたのだが、そのことは今は考えなかった。
どのような形であろうとも、天竺の大きな寺の宝であろう仏の御石の鉢に近づくには、仏法を学ばねばなるまいと石作皇子は結論づけた。見知らぬ異邦人よりは見知らぬ僧侶の方が警戒されないはず。
まずは手近の寺社より始め、思いつく限りの仏教の徒を訪ねた。一通りの教本を読んだ頃に、前より願い出ていた遣唐使船に乗れることになった。そのために本当の狙いは隠して高僧に弟子入りまでした。
苦しい旅は長く続いた。唐の国についたとき、師事していた高僧は病のために亡くなっており、後を継ぐ形で唐の国の大伽藍で仏教を学んだ。
その成果が実って、天竺への大派遣使節の一人として選ばれることができた。
旅の目的地はついに天竺へと繋がったのだ。
砂嵐、盗賊、追剥、国と国との戦争、シヴァ教徒の襲撃。これらすべての苦難を越えて、石作皇子は進んだ。この頃にはすでにその名前は空石僧正へと変わっていた。
ついに天竺へ到着したと教えられたときは歓喜の余りに道の上に座り込むほどであった。
五つの精舎を回った。八つの大寺院を回った。多くの高僧に出会い教えを乞うた。表向きは勤勉なる中つ国の学究の僧の一人として、その実、宝を盗むことを目論む者として。
だが仏の御石の鉢はどこにも無かった。微かな手がかりを探し出して見つけたと思っても、それは一目で偽物だとわかる代物ばかりであり、空石僧正を落胆させた。
聖地を巡礼し御鉢を探し求めるうちに、空石僧正は絶望と諦観から変わっていった。自分の欲望ではなく、今までさんざん学んできた教えに身を委ねたのだ。
すでに輝夜姫の肢体の記憶は曖昧になり、ただ美しい人との感想だけが残っていた。静かな聖地に一人座し、薄闇の中にて瞑想すること七日。周囲でごうごうと渦巻く世界の音を聞いている内に、自分の業がついに見えた。
女人の色香に迷い、無限の地獄を彷徨い続ける亡者。
その先に救いが見えた。
その日、家の表に出た竹取の長者は、見すぼらしい身なりの托鉢僧が門前に佇んでいるのに気づいた。居るぞとも言わずに、ただ静かに軒先に立っているだけの僧に奇妙な感覚を感じながら、竹取長者は米を持ってこさせると僧が差し出している托鉢鉢の中に注ごうとした。
「違いまする」
もう片方の手で托鉢鉢に蓋をすると、托鉢僧は再び托鉢鉢を差し出した。
「御坊、銭の方がようございますかな?」
僧の強欲にやや呆れながら竹取長者は言った。
「違いまする。拙僧の方がこの托鉢鉢を貴方に差し上げるのです」
ふとその托鉢僧の顔を魅入った竹取長者はあっと叫んだ。
「い・・石作皇子さま!」
「拙僧、今は空石と名乗っておりまする」
「今日はどのような御用で」
「姫がご所望の仏の御石の鉢を持ってきました」
空石はそう言うと竹取長者の手の中に托鉢鉢を押し付けた。
「こ、これが仏の御鉢」
「さよう」
竹取長者は手の中の鉢を見つめた。古びた木の鉢である。とてもとても宝の鉢には見えなかった。
「大和国十市郡の山寺にて見つけた物です」
「なんと! 仏の御鉢がそのような所に」
竹取長者の疑問に答えるかのように空石は話しだした。
「すべての身分を捨て仏教に入りたる者を沙門の僧と申します。仏の御鉢とはその沙門が持つ托鉢鉢そのものを示します。すなわち、真の僧が持つものならば、どの托鉢鉢も仏の御石の鉢と呼ぶべきなのです。
山寺に住みたるは一人の沙門。このたび見事に解脱なさり、この托鉢鉢を拙僧が譲り受けました。私はすでに一つ持っておりますゆえに、輝夜姫にお渡ししようと参上した次第」
なんと、そう来たか。竹取長者は身構えた。このような粗末な鉢一つで己の大事な姫を渡せるものか。
「ああ、世の愚物には分らぬ道理なるかや」
空石はそう言うと、竹取長者の手からふたたび托鉢鉢を取り上げ、両手で空中に捧げ持った。
托鉢鉢は光を発し周囲を明るく照らした。その光は柔らかく暖かく、さらに至福の喜びを惜しげもなく振りまいた。いつの間にか周囲の空中に無数の諸天善神が舞い降り、この奇跡を寿ぎ称えた。伎芸天が笛の音を鳴らし、吉祥天が嫋やかな舞いを踊る。
光の中で空石の声だけが語り続ける。
「かって天竺には肝喰と言われた九尾の狐がおりました。仏陀生誕後に天竺を追われ、中つ国に逃れて傾国の妲己となり、各地を彷徨いし後、日の本の国にたどり着き、竹を用いて転生したのです」
空石は托鉢鉢を懐へと納めた。たちまちにして鉢が放っていた光が失せ、周囲にはいつもの日常が戻った。
「貴方の大事とする輝夜の姫をもらい受けようとは申しませぬ。貴方も、また彼女も、まだ業が尽きてはおりませぬ。この色界をいましばらく漂いませ」
それ以上、竹取長者が何を言う間もなく、空石は立ち去った。
エピローグ)
「結局、どの公達も帰っては来なかったねえ」
竹取の長者は嘆息した。一人は帰っては来たが、あれはもう公達ではなかった。
高貴なる御方々のお声がかかったときは有頂天だったのに、姫があんな難題を出すものだから、すべて水の泡と消えてしまった。
広い座敷の中央に鎮座ましました姫はコロコロと笑った。
「私は少しも惜しくありませんよ」
本当にここまで美しい女性は今まで見たことはない。この娘が嫁ぐとすれば、相手はどのような男なのであろう。竹取の長者は本気でそれを知りたいと思った。
空石が語った輝夜姫の正体に関しては敢えて無視することとした。きっと空石めの悔し紛れのデタラメに違いない。こんなに美しい姫の正体が妖怪などとそんなことがあるわけがない。
この間、姫は恐れ多くも帝から手紙を頂戴した。帝からの手紙の内容は誰にも見せずに、姫は長い長い返事をしたたためると、それを帝に送り返した。帝からの連絡はそれで最後となった。
帝にはいったいどのような宝物を要求したのだろうか?
それはもしや日の本の国を根本から揺るがすような代物ではなかったのだろうか。
竹取の長者はそれ以上考えるのを止めた。
恐ろしかったのだ。