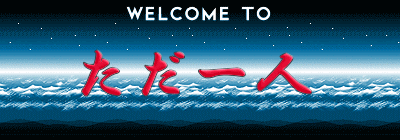
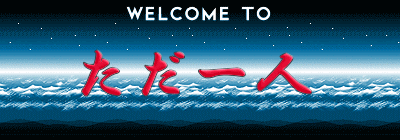
本家絶家の因縁というものがある。
代々長男が若くして死ぬか、どうしようもないダメ人間になり廃嫡する。これを本家絶家の因縁と呼ぶ。これが始まった家はやがて滅ぶ。
うちの家系もそうである。
もともとは平安時代の豪族に端を発し、自分の領地だけを歩いて街道筋まで出ることができたという話である。領地の中を流れる川にも一族の名前がついていたと聞き及ぶ。この川は今も現存する。そこまで権勢を誇っていた一族がこの因縁に取り憑かれ、衰退を見せた。
最初から本家絶家であったわけではなく、江戸時代も終りの頃、マンゾウなる人物が現れたときからそれは始まる。
この家は、古い武士の家系にありがちな長男偏重の風習があった。いわゆる長男教である。
新しい長男は家の家長、つまり父親の横でご馳走を食べ、次男以下は使用人扱いで、実際に使用人と同じものを食べる仕来りであった。長男以外は人に非ず。それを実践するわけだ。今の時代ならまともな感覚なら出来ない所業だが、そもそも平等に扱われる人権という概念自体がここ数十年の平和の産物であるから、当時としては不思議は無かったのだろう。
だが、食い物の恨みは恐ろしい。同じ家に生まれながらにして、ここまでの違いを見せつけられる弟や妹たちの恨みは、やがて因果の悲劇を引き起こす。
マンゾウは長男であったが、素行がひどく悪かったらしく、家長は悩み抜いた末にこれを廃嫡とした。ところがこれ以降、一族の長男はどれもダメ人間が務めるようになった。座敷牢に入れられ、僧籍に入れられ、他家に養子に出され、そして死ぬ。いずれも、次男もしくは三男が家を継ぐ形となった。
家は急速に衰えて行った。
そして遂に、最後の代となった。
やはり長男は愚かであった。そして次男は誰とも結婚することなく子孫は残らない形となり、これで呪いは終わる。そのはずであった。
今度は、甥がおかしくなった。死んだ父は次男で、叔父は三男。本来ならばその甥は呪いにはかからぬはずであった。働き者で優しかった甥は急変し、その家の持っていたかなりの額の財産をたちまちのうちに食いつぶし始めた。
ちょうどそれと重なる事件がある。
我が一族の墓はお寺が持つ墓地の山の中腹にあった。山一つ、こちらの斜面すべて墓が並ぶ場所の中の一角である。
恐ろしく寂れた小さな墓であった。領地内を通る川に一族の名前がつくほどの平安時代からの豪族が没落する。おそらくはその過程で何度も何度も墓を売り飛ばし、そのたびに小さいものに買い換えていった結果がこの無残な有様であった。
その惨状を見るに見かねて、子供三人を抱えた母は欲しいもの一切を諦めてお金を貯め、墓を新調した。この墓は父側の一族の墓であるにも関わらずだ。母は極めて真面目な人であった。生涯の念願であった家を買う頭金にすれば良かったものを、そちらに融通したのだ。
市街を見渡せる山の上にできた新しい霊園に、中規模だが立派な墓を建て直したのである。
このとき、懇意にしていた霊能者を一人頼った。古神道系の先生なので、神道先生と私は呼んでいた。彼女は古い墓から魂抜きを行い、新しい墓に魂入れをした。骨の類はとうの昔に雨水に溶けて消えてしまっていたので、骨の移動は無しであった。古い墓はこのまま十年置き、魂の残香とでも言うべきものが消散した後に、ただの土饅頭に変える習わしらしい。その後、好みにより記念碑を上に置くもよし、放置しておくもよし、そういう話であった。
このことは親戚にも周知徹底していたはずであり、豪華な建墓式もやったので判っていたはずなのだが、父の弟嫁、つまり叔母がそれに手を出した。
「久しぶりにお墓に参ったら、草ぼうぼうで寂れ果てていて、涙が出たんよ」
親戚中に触れ回った。
「だから綺麗な新しいお墓建てたいんよ。お金援助してちょうだい」
筋が通らぬ話ではあったが、親戚たちはしぶしぶお金を出した。
後ほど、何かの機会に故郷に返ったときに、叔母さんに声をかけられた。
「新しいお墓を作ったんよ。百万もかかったんよ」
自慢された。
はて?と思った。たしか母親に聞いた話では親戚全体から集めたお金は合計二百万のはず。言った本人は知らずとも、親戚内で渡すお金の額をお互いに相談したのだから、合計でいくら渡ったかは皆が把握していた。二百万引くことの百万は、百万だ。ではその百万円はどこに?
なるほどこの人らしいや、とは思ったが、そのことを突いてもどうなるわけでもないので、そのまま忘れることにした。醜いものをいつまでも見つめているのは辛いから。
あれか、と思い当たった。
つまり本家の墓を自分の所に移転した段階で、この分家は本家ということになったのだ。そしてマンゾウの呪いはこの家へと移った。本来は受けるべき流れには無かった呪いを、自ら引き入れたことになる。本家筋という立場は移ることが可能なのだ。
今や我が一族が絶えるかどうかは、その家の三男にかかっている。三男坊はもう数十年におよぶ海外赴任で外国に生き、外国に家庭を持ち、その子供たちは日本語を知らない。つまるところ、これならば彼らは一族の枝から生えたものではなく、新しく飛んだ種から芽吹いたものと見なされる可能性がある。
彼らはマンゾウの呪いを免れることはできるのだろうか?
そうであれば良いと、心の底から思う。