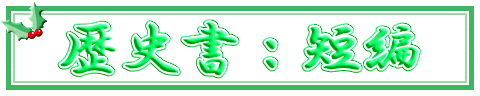
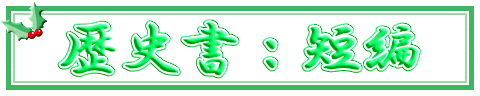
マザークースの歌)十人のインディアン
十人のインディアンが街に出かけ 一人が草を刈って 九人になった
九人のインディアンが街に出かけ 一人が腹を壊して 八人になった
八人のインディアンが街に出かけ 一人が薪を割って 七人になった
七人のインディアンが街に出かけ 一人が転んで 六人になった
六人のインディアンが街に出かけ 一人が蜂に刺されて 五人になった
五人のインディアンが街に出かけ 一人が風邪を引いて 四人になった
四人のインディアンが街に出かけ 一人が熊に出会って 三人になった
三人のインディアンが街に出かけ 一人が車に乗って 二人になった
二人のインディアンが街に出かけ 一人が咳をして 一人になった
一人のインディアンが街に出かけ 一人が眠って そして誰もいなくなった
1)
グスニーオ要塞守備隊の全員を引き連れて村に入るのには、少しばかり決まりの悪いものがあった。村の周囲を囲う形ばかりの柵は熱い日差しの中で誰に修理されることも無く、その古びた惨めな残骸をさらしているばかりである。この村には僅かばかりの軍事的価値も在りはしなかった。何しろ電信どころか水道でさえ、まだ引かれていないほどの小さな村で、井戸を中心にして十数件ばかりの農家が、崩れ掛けた土塀にすがる様にして立っているばかりなのである。
そういうわけで数日ほど前にこの地を通り抜けて行った敵軍も守備兵を残すことさえもせずに、村の井戸から水を補給したぐらいで通り過ぎて行ったものと思えた。今はこのように寂れ果ててはいるが、これでもこの辺りは百年ほど昔には我が国と敵国を繋ぐ主要な道路であり、交易のために道行く人々が朝から晩まで一時も途切れること無く続いていたという話である。その人の列はグスニーオ要塞の前を横切る道を通じて我が国へと続き、人々の足が立てる土埃が常に空を黄色く染めていたと伝えられている。
この村の中央に残る土塀の跡は、かってはここにも小規模な砦の類が存在していたことを示している。それだけの繁栄を誇っていた街道も、山の中をまっすぐに切り開いて作られた遥かに便利で距離も近い新街道の開通と共に凋落の一歩をたどり、この村と同様にグスニーオ要塞そのものも存在意義を失って消滅寸前となっていた。その昔は数千を数えたこともあるグスニーオ要塞守備隊は、今では私が率いるわずか八人ばかりの兵隊と特別要塞軍事顧問と名乗る頑固な老将校が残るばかりで、それすらも、もはや人一人も通らない荒れ果てた旧街道の守りなど不要とばかりに解体の噂がささやかれているほどであった。
敵国の行った電撃戦により戦線はすでに我が国の奥深くへと入り込んでいて、開戦よりこのかたグスニーオ要塞では敵の姿を一兵たりと見ることもなく、我々を残したまま戦場は遥かに遠くに過ぎ去ってしまっていた。まるで津波が海岸を襲うかのような敵の強烈な攻撃に対して一度も有効な反撃を行うことなく、我が軍は敗戦必至の状態にまで追い込まれた。この現状に対して何ら有効な手段を考え付けなかった我が軍の首脳部から、グスニーオ要塞守備隊十人全員が要塞を出て敵の都市の一つでも制圧せよ、との無謀な命令が下されたのが三日前のことであった。そうして少しでも敵を撹乱し反撃の気運をつかもうというのが、その命令の真意であった。そういうわけで私とこの小隊はここにいるのである。そもそもが、僅かに十人ばかりの手勢で都市の制圧など出来るわけが無いことはただの一兵卒に至るまで十分承知していたし、またグスニーオ要塞の守備隊自体が各軍の手におえない兵隊の捨て場と化していた現状からして、装備の劣悪なること、士気の振るわぬこと、まったくひどいものがあった。
一人、老年に差し掛かっている軍事顧問だけが気炎を上げ、彼がグスニーオ要塞に送られてきて以来の、初めてとも言えるこの作戦行動に過大な期待をかけていた。そもそもこの軍事顧問にしてからが元は空軍所属のはずであり、その家柄に釣り合わぬほどの余りの無能さと強情さに手を焼いた空軍が、本来は要塞戦などとはお門違いのはずのこの軍事顧問を、グスニーオ要塞軍事顧問として押し付けて来たものである。
私以下八人の兵隊の誰も彼の意見を取り入れようなどとは露とも思っていない状況であった。陸軍の要塞守備理論を刷新させるとの目的で送り込まれた軍事顧問だが、この惨状とも言える守備隊の有り様を見て初めて、自分が姥捨て山に捨てられたことに気付いた体たらくである。かと言って今更、古巣の空軍に泣きを入れて引き戻して貰うにはそれもプライドが高すぎてできないようだった。毎日を後悔の入り交じった過剰なプライドと共に、自分より優秀な部下を階級に任せて怒鳴り放題に怒鳴り散らしていたという素晴らしき過去の思い出の中に生きている状態であった。
むろんのことグスニーオ要塞で部下を不用意に怒鳴れば、その部下が食事当番の日に、得体の知れない虫の浮いたスープになって己の身に跳ね返って来る。いや、虫ぐらいならばまだマシな方で、ときには履きふるした靴下などが入っていることもある。ここにいるのはいずれも軍規など無視するべきものと心得ている輩ばかりなのである。
そのようなわけで、毎日を焦燥と悔恨の中に過ごして来た軍事顧問に取っては、この作戦行動は千載一遇のチャンスであり、この僅かばかりの手勢によって鬼神もかくやとばかりの働きを見せて軍の首脳部をあっと言わせ、再び空軍の顧問の立場に返り咲くことを夢見ているのは間違い無い。
これが彼がこの小隊の中でただ一人気勢を上げている理由であり、残りの兵隊に取ってはこのお陰で、彼の手柄のためにこれからどんな無茶な命令を下されるのか、と悩みの的でしか無い。部下の一人が私に正直に語ってくれた所では、部下の間ではこの行軍の前に軍事顧問を暗殺しようとの冗談も飛び出したそうであり、それがいつか冗談では無く本気に変わる瞬間が来るのではないかと私は疑っていた。
そんな軍事顧問と荒くれの兵隊達の間に挟まって、これからどんな苦労をさせられるのかと思うと、持病の胃がしくしくきりきりと痛み始め、私はグスニーオ要塞からこれだけは忘れずに持って来た薬を飲んだ。そんな私を軍事顧問は横目でぎろりと睨み、薬などに頼るのは軍人の恥とばかりの意味を込めて、そのまま睨み続けた。それがまた私の胃の痛みを強め、こんなことではいかんなあ、と思いながらもいつもの二倍の量の薬を私は喉に流し込んだ。
恐らくは各地に点在して生き残っているはずの我が軍の他の部隊にも同様の命令が出されているのは間違いが無く、その多くが自分達と同じような立場に置かれているものと考えると、薬の作用にも関らず、私の気分は憂鬱になった。
村の入り口にたたずむ我々の周りを埃っぽい風が舞い、私の背後で兵隊達がぶつぶつと不平を漏らしながら、これも埃まみれの重い軍装を強行軍で傷ついた背中から降ろすのが感じ取れた。
いくら敵の都市を占領せよと命じられたからと言って、このような小さな村を占領しても仕方が無いことは明らかで、それは傍らに立っている軍事顧問にも判っているはずなのに、与えられた命令通りにこの小さな村に対して占領の意志を見せている軍事顧問に対して、私は自分が汗の止まらぬこの暑さから来る微かな殺意を抱いているのを感じた。それは兵士達も同じに違い無く、またその殺意は軍事顧問にだけでは無く、隊長である私にもまた向けられている恐れもあり、できる限り早く彼らの不満を取り除いてやらない限り、やがては険悪な空気が隊を支配するようになるのも明らかであった。
汚れた布で額の汗を拭き拭き、ようやく村人達との相談がまとまった村長が我々の前に出頭した。この戦争が始まる前から、この村はグスニーオ要塞周辺にまだ残っている唯一の村であり、それはグスニーオ要塞で消費する食料や酒の唯一の仕入先であることを意味していた。当然ながら要塞守備隊の隊長として私はこの村長とは顔見知りであり、今は敵国の領土であると宣言されているこの村に対して、あらためて敵として接することにはひどく心苦しいものがあった。
「やあ、あんたか。それに背後の兵隊さんはグスニーオ要塞の守備隊員達だね」汗と埃に塗れた村長は言った。
「こちらの人は誰だね? そうか、以前、あんたが話していた要塞の軍事顧問ってのはこの人かね」
要塞内の人事を民間人に流すことは明らかに軍規違反であり、この一言を取って軍事顧問が私を叱責することは可能であり、またいつもの軍事顧問ならばそうしたであろうが、今は部隊の中でも唯一の味方とも言える私を怒鳴るのはまずいと考えたのか、その村長の言葉はあえて無視し、宙を睨んだままで軍事顧問は怒鳴った。
「これより、この村を我が軍の拠点として接収する。逆らうものは全て銃殺となる。判ったか!」
「判るも何も」そこまで言ってから、村長は私が直立不動で宙を睨んだまま何も言わないのを見て、じっと考え込んだ。そうして軍事顧問が本気であること、私と兵隊達が軍事顧問の命令に逆らえないことを理解した。
「そうか、判った。この村には武器も無いし、兵隊もいない。実を言えば働き手の男達も徴兵されちまった後でね、村に残っているのはわしのようなおいぼれか子供だけだ。誰も手向かいなんかしないから、二人ともわしの家で話し合わんかね。その間、兵隊さん達には村の家の中で適当に休んで貰えばいい」
この村の生活程度ではまともにお茶が飲めるのは村長の家ぐらいのものだ。村長の家の床下には密造酒の倉庫があることは私も知っていて、村長に頼めばそれを私達に振る舞ってくれるぐらいはするだろうけれども、軍事顧問の目の前で昼日中に酒を飲めるわけが無く、私は今は我慢することにした。
「一つだけ覚えておいて貰いたいんだが、あの軍隊のやつらがこの村に来た時にグスニーオ要塞には守備隊がいるのかと尋ねたんだ。わしはあんたとは顔馴染だからね。要塞はとうの昔に滅んで今では誰も住んでいない廃墟だと教えた。住んでいるのは大昔の兵隊の幽霊だけだとね」
それは半分本当である。グスニーオ要塞はもう随分と長い間、何の手入れもされることなく風雨にさらされていたために、今ではそのほとんどが廃墟そのものと化してしまっている。我々はその一部を改修して要塞守備隊の本拠として使っているわけで、守備隊と言っても旧式の要塞砲が一門、かろうじて設置されている程度である。実を言えばこの要塞砲の運用が我が守備隊の機能の全てと言っても過言では無かった。
我々が住んでいるのは比較的に崩壊の進んでいない要塞の南側に当たる部分であり、そこを離れるに従って要塞は次第に崩壊の度を深める。
特に過去に騎士同士の激戦が行われたと伝えられている要塞の北にあたる一角では、奇妙なささやき声や首の無い騎士の亡霊などが頻繁に目撃されるので、荒くれ者ぞろいの守備隊員でさえも滅多に近づくことはしない。以前に一度だけ、私の隣に座っているこの軍事顧問が、視察だと言って我々が止めるのも聞かずに一人で北の塔に出かけて行ったことがあった。みなでこれはいったいどうなることかと心配していたのだが、彼はその日の夕方に真っ青な顔をして帰って来るなり、何も言わずにベッドに潜り込み、そうして三日の間、彼は高熱を出して寝込んだ。この時は結局、軍事顧問に何があったのかは判らずじまいで、自慢話が三度の飯より好きなはずの彼にしては、最後まで沈黙を守り通したただ一つの出来事でもあった。
兵士達の間で要塞の守り神と呼ばれているものは、深夜に歩き回る騎士の幽霊で、その姿自体が目撃されることは滅多に無く、ただ鎧の具足が立てる足音だけが要塞中を巡るというものである。何でもこの騎士は、敵の大群に包囲されたグスニーオ要塞を守るために、援軍が到着するまでただ一人で致命傷を負いながらも、一日近くに渡って戦い抜いたという伝説の持ち主である。そのときに受けた傷による死の間際に、彼は死者となってもなお最後の審判の日が来るまではこのグスニーオ要塞を守り続けて見せると誓ったそうである。
このような観点から見ると、村長の言葉もあながち嘘では無く、我々も守備隊とは言うもののその実は軍隊という組織から見放されたはみ出し者の兵隊ばかりであることを考えると、確かにグスニーオ要塞には兵隊の幽霊だけが住んでいることになる。一方、軍事顧問はそこまで考えは回らなかったらしく、村長に対して実に将校らしい返答をした。
「当然のことだ。要塞と守備隊の秘密を少しでも敵に漏らした者は誰であろうと軍法会議に掛けられて銃殺となる」
「わしが言いたかったのは、わしはあんた達の命の恩人だということじゃ」村長が抗議した。
「恩に着ろと言うのか」鼻息荒く軍事顧問が答えた。
これではまるで村長に喧嘩を売っているのに等しい。いや、軍事顧問に取っては軍隊の長であるという特権を揮うことの出来る良い機会なのであろう。内実の乏しい者ほど、権力にすがりたがるのは理の当然か?
「わしのやったことが気に食わないというならば、それも良い」
少しも状況を理解した様子が無い軍事顧問を見て、村長は説得の方向を変えることにしたらしい。
「この村を占領し、無線で宣言するつもりかね。こんな小さな村が戦利品だ、と。あんたの名前をおまけにつけて。敵の軍隊さえ無視した、こんな寂れた村を見事に奪い取りましたとね」
この村長の言葉にぴくりと軍事顧問の右の目蓋の下が震えた。これは軍事顧問がかんしゃくを起こす前の兆候であることを私は知っている。彼の右手が微かに震えながら、腰のホルスターに向けて動き始めるのを、私は暗い思いで見つめていた。軍事顧問が拳銃を抜くのを止めれば、彼との遺恨が後々まで残るのは確かではあったが、もしそれをやらねば村長が撃ち殺される可能性は非常に高い。この村長も馬鹿な男では決してなく、またそうであればこの私がこれだけ親しく付き合うわけが無く、それ故にこの村長がここまで軍事顧問を挑発するのは、私の守備隊が村に残るのを村長がひどく恐れているからに違い無かった。
一度でも村を占領し返したと無線に流せば、敵軍に取ってはそれがどんなに小さな村だったとしても軍全体の士気に影響しかねない。そうなれば近くの敵軍が見せしめとばかりにこの村に殺到することになるのは必至であり、こんな小さな村ならば砲弾の一発でも当たれば跡形もなく消し飛んでしまうことになる。我々は軍人であるから敵と戦って死ぬのはこれも仕方の無いことではあるが、巻き添えにされる村人としてはたまったものでは無い。出来れば村長がそんな悲惨な運命に陥るのを避けることができるように私は力を貸すつもりであった。
「食料も水もありったけのものを提供する。一晩の宿もだ。明日の朝になったら、もっと戦いようのある街へでかければ良いじゃないか。この惨めな村はこのままそっとしておいてくれんかね」村長は静かに言った。
村長が本音で向き合って話の出来る、実に肝の座った男であることに私は少しばかり感心した。今までは密造酒の魅力に釣られてここを訪れていたのだが、これならばまだ時間のある内にもっと深く人生について語り合っておくべきであったとの僅かな後悔が、私の頭の隅をかすめた。人の真価は逆境で判るものだと、このとき初めて私は知った。
軍事顧問がごく普通のまともな男ならば話はこれで済んでいただろう。確かにこの村には軍事的な価値は皆無だし、また我々がここに居座る理由も無かった。いや、極端な話、この軍事顧問さえいなければ無線の故障を理由にして、グスニーオ要塞に部隊ごと戻っても悪くは無い。どのみちこの戦争が我が国の負けに終わることは目に見えていたし、我々がどうあがこうが戦局を変えられるわけも無かった。だが、プライドだけ高い愚か者というのは、早撃ちの真似をしようとして自分の足の親指を吹き飛ばすことはしても、他人の意見を素直に受け入れることだけはするものでは無い。この臆病者めがと、村長を思い切り怒鳴りつけようと軍事顧問は椅子から立ち上がった。
その時だ。
家の外から恐ろしい悲鳴が聞こえて来て、それに気圧されたのか軍事顧問が吐きかけた言葉を喉の奥に飲み込んだ。何事が起きたのかと慌てた私が村長の家を飛び出したのと、首から赤い鮮血を宙に吹き上げている部下が向かいの家から飛び出したのは、ほぼ同時だった。
驚きながらもその部下を良く見ると、彼の首に赤く錆びた草刈り鎌が引っ掛かっているのが判った。
もう一度良く見て、それが実は非常に鋭利に砥がれた鎌であり、赤く見えるのは部下の血であることに気がついた。
さらにもう一度良く見ると、鎌は兵士の首に引っ掛かっているのでは無く、その刀身半ばまでずっぽりと部下の首に突き刺さっているのが判った。
草刈り鎌が深く刺さっているのにも関らず、これほど大量の血が吹き出す以上、部下の傷は間違いなく致命傷であり、そう私が見立てた通りに、すぐに部下の動きは弱くなりそして動かなくなった。
騒ぎを聞いてそれぞれの家から飛び出して来た他の部下に、死に掛けている男の世話を任せると、私は拳銃を構えて向かいの家の扉を蹴り開けた。そうしておびえた顔で私を見つめている一人の少女を見つけた。少女は無残にも破れた服を体に引き寄せて、部屋の隅にうずくまっている。押さえた手の間からまだ大人になりきっていない小さな乳房が見え、私は事の次第を察した。
「敵はどこだ! 全員、ただちに集合せよ!」
私が飛び出して行った後に、ようやくもう安全と見たのか、村長の家の扉から顔を突き出して軍事顧問が喚いた。それからおそるおそるという感じで私の背後まで来ると、肩越しに部屋の中を覗きこんで軍事顧問は一瞬絶句した。
ここで何が起こったのかが明確になると、問題は後の始末をどうするかだった。死んだのは要塞守備隊の突撃隊員で、この村の少女と話をしている内に劣情をもよおして少女に飛び掛かり、偶然そこにかけてあった草刈り鎌を少女に突き立てられたものだ。普通ならば、たとえ殺そうと狙ってやったとしても、少女の腕で荒くれ者の大男を殺せるものでは無い。おそらくは処女を失う恐怖に駆られた少女が、手にした草刈り鎌を夢中で振り回したのがたまたまうまく当たったという所だろう。もちろん、男の方にも油断があったのだろうし、この状況で少女の罪を問うのは明らかな間違いであった。
言ってみればこの事件のそもそもの責任は、私や軍事顧問にもあるわけである。長きに渡って要塞守備任務という異性と隔離された特殊な状況に置かれていた兵士達を、いきなり女性のいる村、それも兵士を押さえこむ役目をする憲兵や警察というものの存在しない場所に連れて来たのであるから、このような事故の起こることは当然考えてしかるべきであった。部下の中には戦友を殺されて激怒し、この女を直に射殺するべきだ、裁判にかける必要も無いと息まく者もあったが、いやそれは良く無い、少なくとも民間人が関与した以上、略式とは言えきちんとした裁判を開くべきだと私は主張した。軍事顧問はしばらくこの問題を考えた末に、大の男がこのような発言をするのは少しばかり恥ずかしいという様子で少女の銃殺を提案した。しかし、ここで裁判を開けば記録を残さなければならないこと、そうなれば死んだ兵士が強姦をしようとして逆に殺されたこと、それも守備隊の突撃隊員を勤めるような生っ粋の兵士がたった一人の虫も殺せないような少女によって実にた易く殺されたことが記録に残ることを私が指摘するに至って、ようやく思いとどまった。もしそんなことになればそれは我が軍そのものの恥であり、当然ながら事件に関与した軍の関係者全てがこのグスニーオ要塞守備隊からの浮上のチャンスを失うことを意味する。それに加えて、民間人を強姦しようとしたとなれば、我が国の軍規に照らせば間違いなく銃殺となることは明らかで、それならば少女に殺されなくてもどのみちこの隊員の死は避けられないものだったと結論できる。
こうして、軍事上の正式な記録では、突撃隊員は村への行軍の最中に敵の狙撃兵により狙撃を受けて谷底に転落して死亡したことになった。これ以上この村に止まっていては復讐を求める隊員が第二の殺人騒ぎを起こしかねないとして、村長に死んだ部下の埋葬を頼むと我々は次の街へと向かうことにした。
2)
石作りの建物が三十軒ほど。それがその街の全てであった。グスニーオ要塞守備隊の九人で占領するのにはちょうど良い大きさでもあり、それに加えて敵が駐留軍を残すほどの大きさでも無かったのが我々の気に入った所だ。流石にグスニーオ要塞を離れてここまで来ると、自分の縄張りを遠く離れているという不安の上に強行軍の疲労が重なり、軍事顧問でさえも最初の勢いをすっかりと失ってしまっていた。
ここで敵兵に見つかれば僅かばかりの兵隊達では敵の攻撃に対して抵抗しようもなく、また周囲全てこれ敵であるという状況から見て我が部隊が全滅することも十分に有り得るわけで、手柄を立てて再び軍の上層部に返り咲きたいという軍事顧問の欲望もこの厳しい現実の前には萎えてしまうのも無理は無かった。すでに部下の間には長く住み慣れたグスニーオ要塞に返ろうとの意見も、公にこそしてはいないが流れ始めていて、それがじきに表面に噴出してくるのは誰の目にも明らかであり、そのような事態の発生を抑えるためにはここで形ばかりでも占領の真似事をして士気を高めてやる必要があった。
大体がグスニーオ要塞守備隊に放り込まれているような輩は、いずれも荒くれ者で真面目に軍人としての忠義を尽くそうなどということとは無縁の輩であり、ましてや実際に戦場に出て祖国のために命を投げ出そうなどとは決して考えない連中である。
これは無理の無い話で、彼らの大部分は祖国からゴミ同然に扱われて来た貧民階級出身であり、貴族出身の軍事顧問とは生まれも育ちも違うのである。国に恨みこそあれ、恩義など受けたことが無い以上、どうしてその国のために自分の大切な命が捨てられる理由があるものだろうか?
もちろん脱走兵は銃殺が決まりなので、そうおいそれとは隊を抜けて逃げることは出来ないが、上官達が全て戦死したとあればこれはまた別の話となる。部隊の再編成のためとの理由をつけてグスニーオ要塞に帰れば良いのである。ましてや戦場での死因は敵味方どちらの弾が当たったのかも普通ははっきりしないものであるから、これ以上兵隊達の不満が強くなるようならば、これからは自分の背中も自分で良く見張る必要が出て来る。
まあ、最初に襲われるのは間違いなく軍事顧問であろうから、それまでは大丈夫と自分に言い聞かせては見たものの、やはり胃がきりきりと痛みだし、仕方が無しにまた錠剤を二粒ほど自分の口に放りこんだ。この薬は実に良く効く反面、少しばかり習慣性があり、それに加えて強烈な幻覚作用を持っている。決められた服用量をちょっとでも越すとたちまちにして自分の頭の周りを踊り回る小人が見えたり、パイプオルガンを演奏する象が見えたりするようになるので実に宜しくない。元はと言えばそれが原因で、グスニーオ要塞の守備隊長などというあまりありがたくない部署につかされたわけであり、この薬の習慣を断ち切らない限り、私は一生グスニーオ要塞から出られない運命であることも良く判ってはいた。判ってはいるが未だに薬は止めることができない。
一行の中でも比較的に疲れた様子を見せていない部下を二人ほど、斥候として先に街に送り込んで状況を偵察させていたのだが、彼らがようやく戻ると街の状況を説明した。驚くべきことに街には人一人、いや猫一匹残ってはおらず、更に驚くべきことは食事の支度をしたままのテーブルがそのまま放り出されている有り様ということであった。敵兵がいないことには安心したものの、当然人が住んでいるはずの街に人っ子一人いないというのはいくら戦時中とは言え余りにも奇怪な状況なので、我々は一塊になっておそるおそる街中を見回って見た。
確かにテーブルの上には食べ掛けの食事が放り出したままで、今やそのスープ皿の上には赤やら緑やら黄色のカビのジャングルが茂り放題に茂ってしまっている。この様子から見て数日前にこの街に何か恐るべき慌ただしい事態が出来したらしいことは明らかであった。
少なくともそれは食べ掛けの食事を中断したまま街を逃げ出さねばならないような事態で、その正体がはっきりしないことがまた我々の不安を増した。残りの家も見回ってみたがどれも同じような状態で、隊員の中でも迷信深い者がこれは悪魔の仕業に違いないと囁き始めたのを機に、私はわざと隊員達に隊列の解散を命じて、食料の調達を行うように指示した。こういう時には部下に何か仕事を見つけてそれに没頭させるのが一番である。
街の中でも一番立派な家を見つけだすと、私はそこを部隊員の今夜の宿泊所に決めた。そうしてから私と軍事顧問は、何か手掛かりになるものはないかと思って、その家を隅から隅まで調べることにした。恐らくここは町長の家に間違い無く、町長ともあれば街の中で起こったことを記録しているのではないかと思ったからである。
今頃の時期は日が落ちるのが早く、どうやらこの家の主の書斎らしき部屋で、か細いランプの光を頼りに当家の主人の日記らしいものを見つけた。鉄張りのいかめしい日記帳で、貴重な書籍によく見受けられるような鍵付きの本であった。さんざん鍵を探して部屋中をひっくり返した挙げ句に結局鍵は見つからず、それならば何か錠を壊すものを見つけようと階下に降りた時点で、隊員の一人が食事が出来たと伝えに来た。
やはり荒くれ者ぞろいの部隊でもこういう奇怪な状況は恐いのか、全員がこの家の食堂に集まり黙々と料理を片付けた。時折、窓の向こうを風が通り過ぎると、石作りの街路に風の音の木霊が反響するのが何とも言えずぞっとした音となる。たとえて見るならばそれは、髪を振り乱した女が悲鳴を上げながら街路を走り抜けているかのような音で、それが通り過ぎる瞬間に通りかかった家々の扉をがたがた揺するという感じである。これで扉にかんぬきが掛かっていなかったら、夜の闇の中に大きく開いた扉の向こうにいったい何が見えることになるのだろうかと想像すると、私も少しばかり恐くなって来た。いったいどこの誰がこんな陰気な街に住みたがるのだろうと心の中で不思議に思い、そう思ってから誰も住んでいないからこそ陰気なのであって、普段は子供達の笑い声などに満ちた明るい街なのでは無いかなどとも思ったりした。
何事も無く夕食が済み、隊員達がこの家の中に各自自分の寝場所を探すのを待ってから、私は要塞砲の整備員だった男を呼びつけた。この男はあれほど大事にしていた要塞砲から離れる時に、せめて整備道具ぐらいは手放したく無いとの思いから、止せば良いのに重いスパナの類を背嚢の中に詰めて持って来ていた。すでにここは要塞を離れて遠く、この世でただ一つの愛するものから引き離された要塞砲整備員の悲しげな顔を見ている内に、こちらまでつられて悲しくなってしまい、その気分を吹っ切るかのように私は借りた道具を使って頑丈な日記の錠を壊すと、その内容に没頭した。
人の日記を読むことにはタブーを犯す密やかな快感があり、それは軍事顧問も同じなのか私の読んでいる日記をそばからしきりに覗き込もうとしていたが、私は敢えて彼には構わずに日記の先を読み進んだ。風の音に紛れて何か別の音がしたような感じがあったが、それもすぐに街の出来事をつづる文字の流れの中に消え去った。
そうして私はこの街で何が起きたかを知り、大きな叫び声を上げて隊員達を呼んだ。驚きと不信と恐怖の入り交じった顔で、家のあちらこちらから隊員達が飛び出して来た。私を見つめる隊員達を前にして説明する間も惜しく、私は大急ぎで隊員の数を数え上げた。あんまり慌てていたので最初は十人と数えてしまい、いやそんなはずがあるものか、あいつは死んだはずだ、と数えなおすと今度は八人であった。足りない一人の名前を大声で呼ぶと、その隊員は家の便所から青い顔をしてよろめくような足取りで出て来ると我々の前に倒れこんだ。
朝が来る迄にその男は三十七回便所へ通った末に、とうとう最後には一人で立ち上がることも出来なくなり、そのまま垂れ流すだけ垂れ流して死んだ。
この家の主人が残した日記によると、敵の軍隊がこの街を通過した際に、どうやら将兵の多くがここを臨時の休憩所として使用した模様であり、その結果、軍隊が通過した後には大量の糞尿が周囲に巻き散らされる結果となった。これは急速な進軍を続けている軍隊には良くあることで、地面に便所用の穴を掘って始末する暇が無いためである。この街を通り過ぎて行った軍団の規模は二個師団や三個師団という数では無く、振りまかれた汚物の量も並大抵では無かったらしい。日記には更にハエの大量発生が書き記されている。
その結果として引き起こされたのは悪性の伝染病の発生で、どうやらこの街の周囲一帯の畑が腸チフスに汚染されているらしいとの推測がついた。街中の家庭で人々が突然倒れ始め、街ぐるみで協議した結果、医者と病院のある隣の街へ急遽移動することに決まったと日記にはある。この街が無人なのはそのためであり、これが今ここで我々が落ち込んでしまった状況である。
食事係が青い顔で台所に向かうと、まだかまどの上に掛けてあった夕食のスープの残りを蹴り倒した。風向きが変わったのか、それまで気付かなかった畑の悪臭が窓の隙間から吹き込んで来た。これ以上この街に止まれば残りの隊員達もやがて病魔に侵されることになるだろう。この街で手に入れた食料もどれが汚染されているのか判らない以上、全て捨てていかねばならないだろう。
死んだ男をまだ悪臭のする畑の中に埋葬し、彼の銃を形ばかりの墓碑として立てると、残った我々八人は次の街へと向かうことになった。
胃がきりきりと痛んだ。その一瞬、この私まで病気にかかったのかと思い背筋に冷たいものが走ったが、それはいつもの私の持病が出たもので、少しばかりの安堵とともに私は薬瓶を取り上げると、そっと蓋を開けていつもの二倍の量を喉に流し込んだ。
3)
山岳地帯もここまで降りると、流石に人家が多くなってくる。その人家の大部分が山と山の間の僅かばかりの平地にしがみつくように建っている農家である。少しばかり広い場所があったとしても僅かに二、三軒の農家が入り込めばそれでもうその空き地は飽和してしまう。地図によればこの先しばらくは街と呼べるものは無く、それは喜んでいいものなのか、悲しんでいいものなのか判断に迷う所であった。すでにグスニーオ要塞を出た時に比べて部下が二人も減ってしまっているのに、我が部隊ときたらまだ戦果らしい戦果も上げてはいないのである。これが敵との戦闘になった結果の、ある程度の被害を受けての撤退ならば司令部に対する言い訳も立つのだろうが、そうでないところが実に情けない。
こうなればいっそのこと敵に襲われたと嘘をつき、このまま安全なグスニーオ要塞へと逃げ返り、終戦までの日々をのんびりと過ごすというのはどうだろう?
しかしながら、ただでさえ口うるさい軍事顧問がそのような欺瞞を許すわけが無く、彼が平気で部下を売ることも十分予想がついた。では敵の通った跡でも探し出して追いかけて撃ち合いでもすればいいのかと言うと、そうなればそうなったで今では友人とも言える部下達を無意味に死なせることになるわけで、到底、私にはこの案を安易に認めるわけには行かない。
ここで軍事顧問に不慮の事故で死んで貰い、戦闘を放棄して全員で逃げ出したとしたらどうだろう。これはかなり良い案に思えるが、もし万が一その後で我が軍が即時停戦を認めた場合には間違い無く敵前逃亡の罪で全員銃殺となってしまう。我が部隊に対する無茶な作戦を止めるだけの力は無かったものの、こう見えても軍事顧問は軍の中枢に近い所に幾人かの友人がいる。その全てが軍事顧問の味方では無いとしても、ひょっとすればそれらの一部が軍事顧問の真の死因について疑問を抱くかも知れない。我が軍が徹底的に崩壊した後ならともかく、少しでも形が残っている間は軍事法廷を開く意志も銃殺を実行する力も司令部には残っているわけであり、酒を飲むとすぐに口が軽くなる部下を信用して事を起こすだけの勇気は、私にはとても無かった。
試みとして、もし逃げるとすればどこに逃げるべきだろうと考えて見ると、我が部隊の行き先は古巣であるグスニーオ要塞以外に無く、それは司令部の方も良く心得ているに違いない。
グスニーオ要塞はその長い歴史の中で何度かに渡る大補修をされている。元来は崖をくり貫いて造られた堅固で質素な要塞だったものが時代を経るにつれて、その前面に近くの石切り場から切り出された建材を使って新たに城壁や塔が増築されていったものである。こうした人間の手で増築された部分は、最近では人手不足により全く修理されることもなく風雨に痛めつけられ続けた結果、その大部分が崩壊寸前の状態である。一方、崖の内側に当たる部分に関しては丈夫な岩盤をくり貫いたものなのでそれほど風化もひどくは無く、その一部はまだ居室の形を止めている所もある。我々が要塞砲を備え付けて住んでいた所も、そういった比較的にましな部屋の連なる場所であった。ここは元々、王族に近い騎士達が住んでいたらしく、ときたま部屋の奥の亀裂の中から豪華な衣装の慣れの果てといったものが発見されることもあった。
グスニーオ要塞自体は恐ろしく巨大で、その通路は最初から迷路として設計されているために、もし我々のような小隊がその中に隠れれば、この世の果てる時まででも隠れ続けることができるはずではある。しかし残る余生の全てを、幽霊と雑草しか存在しないグスニーオ要塞で送ることになるのは余り好ましいことでは無く、とうとう最後には私はこの考えを放棄するに至った。
行く手への期待とそれを上回る大きな不安を胸に秘めて、私はいつもと変わらぬ顔で指揮を取り続けた。薬の力のお陰で心がひどく鈍感になっているため、何とかそれをやり遂げることができた。もし私にそれだけの度胸と演技力が最初から備わっていれば、そもそも私が薬のお世話になることは無かっただろう。夜が迫り、軍靴の中の足がひどく痛むようになった頃、斥候の一人がようやく一軒の大きな農家を見つけて来たので、そこに一夜の宿をとることに決めた。
元々がこのような人里離れた所で暮らす人々に取っては税金の率が変わりさえしなければ誰が国を治めていようが関心は無く、我々には信じがたいことだが、戦争が行われていることを知らない家も存在する有り様である。
今回、我々が泊まることにした農家もそういう家の一つであった。グスニーオ要塞守備隊の金庫から持ち出した僅かばかりの金の中から泊まり賃としていくらかを農家の主人に払い、我々は裏手の納屋へと案内された。これが軍事顧問の抱いていた血沸き肉踊る戦争風景とはひどく異なることから、軍事顧問は実に渋い顔をして不満を表現していたが、部下達が文句も言わずに納屋の中を整え、特に軍事顧問のために最も寝心地の良さそうな場所を用意したのを見てからはそれ以上のわがままは止めることにしたようである。
行軍の途中で見つけた畑からできるだけできの良さそうな作物を探して手に入れて来ていたので、炊事当番の兵隊は野菜スープを作ることに決め、残りの兵隊達は夕食ができるまでの時間を各自適当に過ごすことにした。軍事顧問は納屋の周囲に見張りを立てることを主張したが、ただでさえ疲れている隊員達にこれ以上の無意味な苦役を与えることも無いと判断し、隊長権限を盾に取って私は軍事顧問の意見を無効とした。
悲鳴はその直後に聞こえて来た。銃を構えて納屋の外に出て見ると、炊事当番の一人が足を押さえて転げ回っており、すでに辺りは血の海というひどい有り様であった。地面に転がって泣き喚く男を皆で強引に押さえ込んで傷を見て見ると、なんと右足が足首のあたりで半ばちぎれかけている状態であった。どうやら夕食の支度に使うための薪を斧で割っていて、誤って自分の足をたたき割ってしまったらしい。
慌てて血止めを施したものの、周囲に巻き散らされた血の量から考えて、この隊員が朝まで持たないことは明らかであった。あらゆる刃物の内でも斧による傷が一番たちが悪いと以前になにかで聞いたことがあるが、それは本当だったようである。輸血をすれば少なくとも命は助かるのだろうが、そのための道具が無い。実を言えば我が隊は消毒用の薬一つでさえも持っていない状態なのである。念のためと思い、農家の主人に医者の居場所を尋ねて見たが、やはりかなり遠くの街まで行かねば医者はいないとの返事が返って来た。重病人を担いで夜の山道を医者のいる街にまで走ったとしても、その衝撃で病人の出血はひどくなり、向こうに着いた頃には全身の血を失って死んでいるに違いなく、となれば後はすべてを病人の運に任せるしかなかった。
医者がいないのはグスニーオ要塞にいたとしても同じことで、そのために以前から何度も軍医を寄越してくれるように軍本部に要請し続けていたのだが、その度に適当な理由をつけられて要請を却下されていた。返す返すもそのときに強引に軍医を要求していればと悔やまれたがもう遅い。それによくよく考えて見れば、はみ出し軍人の吹き溜りとも言えるグスニーオ要塞に貴重な軍医を回してくれるわけも無く、とすればこの男はやはりこうなる運命だったのだなあ、と変な所で感心してしまった。いつも私が飲んでいる精神安定剤を少し飲ませてはみたが、それで傷が治るというものでも無い。
私の手を握ったまま、体が焼けつくような高熱にうわ言をつぶやきながら、その隊員は明け方に亡くなった。彼が息を引き取る寸前に、誰かが納屋の外で何かをつぶやいているのが聞き取れた。