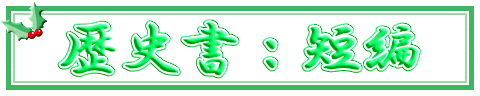
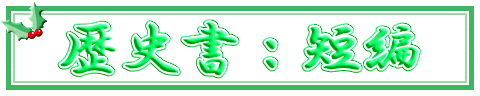
4)
俺達は呪われているんだ、隊員の一人がそう言い出した。いずれ誰かが言い出すに違い無いと予想もしていたし、また自分でもそうでは無いかと思っていたのだが、それでも少しばかりどきりとした。
グスニーオ要塞には昔から一つのジンクスが伝わっている。それはこういうものだ。守備隊が要塞内に止まって戦っている間は決して負けることは無いが、要塞から討って出た部隊は必ず全滅するというものだ。現にグスニーオ要塞の古い戦闘記録を調べて見ると、この言葉通りに要塞から飛び出した、あるいは逃げ出した部隊は必ずと言っていいほど壊滅に近い被害を受けている。グスニーオは不敗の要塞ではあるが、その歴史は決して勝利と栄光に満ちたものばかりでは無いということだ。
要塞からの突撃行動と、現在我々が置かれているような遊撃作戦を同じものと見るのにはそもそも相当な無理があるが、それでもジンクスを額面通りに受け取れば、我々はまさに全滅するべき部隊であり、また実際に次々と部隊員を事故で失っているわけでもあり、このジンクスを迷信とばかりに気軽に笑い飛ばすわけにはいかない状況であった。
困ったことに部下達もこのジンクスのことは良く知っている。最初に要塞を出ることを部下に告げた時にも、このジンクスを理由に上げて反対した者がいたぐらいだ。事ここに至って、部下の間に不穏な空気が流れるのを感じて、私は懐柔策を取ることにした。僅かな期間に立て続けに部下を失ったこともあり、また兵隊達が銃を手に時々奇妙な目つきで軍事顧問を睨んでいることにも気付いていたせいか、軍事顧問は表面上は私の提案に難色を示したものの、最後には私の説得に応じることにした。
そうと話が決まれば、ぐずぐずしていることは無い。重い無線機を背中に担いでただ黙々とここまで運んで来た無線係の兵隊が、無線機を地面に置くとそのアンテナを伸ばした。それを見た生き残りの兵隊達も事態の推移を見ようと周りに集まって来た。今、我々がいるのは山道の真ん中だが、周囲には敵の気配らしきものは無く、これはすでに最前線が遥かに先、恐らくは我が国の首都付近にまで進んでいるはずであることからもむしろ当然と言える状態であり、それゆえに見張りを立てるべきであるとは私は考えなかった。
電波の状態が悪いのか、山の中という位置が悪いのか、なかなか無線はつながらず、いらいらとした気持ちを抑えるために私は薬を幾粒か飲み込んだ。すでに最初の一瓶は空になってしまっていたので、今は二瓶目を飲んでいるところである。手持ちの薬が尽きるまでにグスニーオ要塞に帰ることができるのかどうか、私は少しばかり不安になってきていた。そうこうしている内に無線係の努力が実り、ようやく無線が通じるようになった。さすがに面子というものを面計って軍事顧問は無線に出るのを断ったので、交信が確認されるのを待ってから私は通信兵からマイクを受け取った。ここまでの部隊の経緯を適当に潤色し、三人の部下は敵との戦闘で死んだことにして、私は事態を手短に報告した。いくつかは暗号を使ったが、ほとんどの部分はそのまま話した。どの道、この無線を傍受している敵軍も我が部隊のような小さな部隊のことは気にも止めまい。私は報告の最後を締めくくった。
「聞こえますか。こちらグスニーオ守備隊長。繰り返します。敵と交戦の末、兵三名が死亡。撤退を許可願います」
しばらく無線の上での沈黙が続いた時、何か嫌な予感が私の頭の隅を掠めた。無線機の向こうから電波雑音に混ざって聞こえるのは確かに砲撃の音だ。ということは私の推測通りに、今は首都攻防戦の真っ最中と言うことになる。少しばかり自分達の勇気の無さを恥じる気持ちが起きて来たが、我々がここで何をやったからといって、いまさら戦局が変わるわけも無いという諦めの気分がすぐに沸き上がって来ると罪悪感を消し去ってくれた。
もちろん、そもそもの負け戦の原因はグスニーオ要塞守備隊にあるのでは無く、事がこれほど進むまで有効な手を打たなかった無能な参謀連中にあるわけで、換言すれば我々が自分達を恥じ入る必要はどこにも無いのである。
「聞こえるか。グスニーオ要塞守備隊。これより軍本部からの命令を伝える」
無線機が喋り始めると、続けて幾つかの暗号が流れ出して来た。通信終了を無線機が告げると、通信兵が青い顔で暗号の解読結果を渡して来た。私が隠す間もあればこそ、全員がその紙を覗き込んだ。
暗号の内容は、直ちに全ての兵士を連れて敵の首都に乗り込み、敵軍の最高司令官を暗殺せよとの命令であった。作戦の成功に関り無く、すでに死んだ者を含めて全員に勲章の授与を行うこと、さらにはご丁寧に命令不服従の際には部隊全員を間違いなく即時銃殺に処するとの但し書き付きだ。
「隊長。逃げましょう」
蚊の鳴くような声で部下の一人が言った。こいつも荒くれ者の一人のはずだったが、自分達がどうしようも無く死の縁へと追い込まれていることが判ったためか、日頃の豪胆さもどこかに吹き飛んでしまったらしい。かくいう私も口を開けばきっとこの男のような情けない声が出るに違い無く、そのために返事をするのがためらわれた。
背後に穏やかならぬ気配を感じた。まずいな、と思って軍事顧問の方を振り向くと、すでに彼は拳銃を抜き、我々の方へと銃口を向け終わった後だった。軍事顧問の目は明らかに狂人のそれである。
「貴様達の目論見は判っているぞ!」軍事顧問が怒鳴った。
「軍人として命令に背く事は許さん。卑怯者は一歩前に出ろ。わしがここで直々に引導を渡してやる」
口の端から泡を吹き出した軍事顧問の強烈な興奮に血走った目が全員をぎょろりと睨みつけた。赤い血の線が一筋、その目の端からこぼれ落ちると、拳銃の引き金にかけた彼の指が震え、私には今にも彼が我々を撃ちそうに思えた。
恐いのだ、と私は思った。この人は死ぬのを恐がっている。安全な司令部の中で階級に任せた権威を振りかざして平和な時代を過ごすのならともかく、死がごく身近に、それも前触れも無く訪れるような事態には彼の精神は耐えられないのだと私には判った。だからその反動で、こんな無茶な命令にあくまでも従おうとしている。自分は死をも恐れぬ勇敢な軍人であるという意識にしがみつくことで、精神が崩壊するのを防ごうとしているのだ。
では私はどうかというと、実は彼と同じであり、ただ私の場合には薬という強い味方があったわけで、その点では彼に少しばかり同情を覚えた。私は少し考えた末に、取り敢えずは軍事顧問の言う通りに敵の首都を目掛けて進むことにした。軍事顧問が落ち着くのを待ってから部隊の主導権を取り戻し、何とか自分達が落ち込んだこの事態から脱出する方法を考えだすのだ。
今の状態の軍事顧問では敵と接触したら全員に無謀な突撃行動を命じかねない。もし、そんなことになれば前からの敵の銃撃と、後からの軍事顧問の狂気の銃撃で全員が死ぬことになるだろう。皆が死んだ後で、精神崩壊を起こした軍事顧問はあらゆる物を全身の穴という穴から吹き出しながら敵に向かって命請いをするのでは無いか、という気がした。そのような気がするということは疑いも無く軍事顧問はそうするということで、そうなれば軍事顧問ただ一人だけが捕虜となり生き残って本国に帰ることになる。軍事顧問の狂気のお陰で全員が死に、当の軍事顧問だけが生き残る。そんな理不尽なことがあってたまるものか。私は心密かに彼を部隊から除く決意をした。
部下に荷物をまとめるように言い、敵国の首都に向けての出発を命じると、冷たい口調で全員から承諾の返事が返って来た。この瞬間に私の名は部下の殺人予定リストに載ったわけで、私は参ったなと心の隅では思ったがあえて顔には出さずに、わざと隊列の一番前に立って歩き出した。部下が反乱を起こして私を撃ち、軍事顧問を殺して脱走するとしたら、それは少なくとも夜になってからである。それまでに部隊の中の緊張を緩和し、軍事顧問から銃を取り上げねばならない。拳銃を構えたまま部隊の最後尾をやや離れてついてくる軍事顧問の隙を伺うのは大変だが、機会は必ず訪れるだろう。私はそう自分に信じ込ませると、薬を一握り口の中に放り込んで歩き続けた。
二時間ほど緊張に満ちた行進を続けた後、山道が崩れた。ここの所の雨続きで地盤が緩んでいたらしい。地滑りの衝撃で、長い年月の間ここが自分の居所と決めていた場所を離れた大きな石が一つ、斜面を勢い良く転がり落ちて来ると、悲鳴を上げる通信兵を巻き込んで崖下へと消え去った。通常の兵隊の装備に加えてひどく重い長距離無線機を背中に担いでいたために、警告を聞いた時に可哀想に逃げ遅れてしまったらしい。
後続の落石が無いことを確認してからおそるおそる崖の下を覗きこんで見ると、これが想像を絶するようなすさまじい断崖絶壁で、遥か眼下に潰れた部下の死体と恐らくはばらばらに壊れているに違いない無線機の残骸が見えた。他の部下達も次はわが身とばかりの厳しい顔で崖の下の戦友の死体を覗きこんでいる。その中に軍事顧問の顔を認め、私はそっとその背後に回ると、放心状態の軍事顧問の手から拳銃を取り上げ、残りの武装を手際良く解除した。
幸いなことに軍事顧問は抵抗しなかった。もし抵抗されていれば部下達も自分を押さえることが出来なくなり、恐らくは軍事顧問の殺害という事態にまで至っていただろう。いやそればかりか、彼と一緒に私まで殺されていた可能性が高い。こうして彼がおとなしく捕まってくれたお陰でその危険は回避されたわけであるが、それでも部下の一人が地面の上に座り込んでいる軍事顧問の顔を殴ろうとしたので、私は止めに入った。
けたたましい笑い声がした。笑っているのは軍事顧問で、その目の空ろさからすぐにこれは先程とは別の意味で狂ったなというのが周囲の人間にも判り、それを知って軍事顧問に暴力を振るおうとしていた男も憤懣やるかたないという表情でしぶしぶと拳を下した。グスニーオ要塞守備隊員達はいずれも荒くれ者であり、軍人の風上にも置けないはみ出し者かも知れないが、彼らは少なくとも人間であり人の心を解する者達であった。すぐにかっとなるという悪い癖はあるが、それでも気立ての良い男達であった。
グスニーオ要塞に帰ろう、と私が一言だけ言うと、部下の緊張が目に見えて解けるのが判った。私の決断が一日早ければ二人の部下は死ぬことも無かったのにと悔やまれたがそれも後の祭りで、私は自分の心を無理に抑えこむと薬をもう一錠だけ飲み込んだ。
こうして我々はグスニーオ要塞に向けての長い帰路についた。
5)
一度でも限界を越えて狂気に走ってしまった精神という物はそうた易くは元には戻らないものだと思っていたが、軍事顧問は違った。良く考えて見れば軍事顧問の発狂は、自分の目の前で人が死に、次は自分の番かも知れないという恐怖に対する一時的な逃避行動だったのかも知れない。あるいは部下達の間に膨れ上がる軍事顧問への不満と殺気を感じ取って、怒りの矛先を逸らすためにあえて狂人の振りをしただけなのかも知れない。
どちらにしろ、帰り道で軍事顧問は喚き、騒ぎ、所構わず噛みつき、武器を取り戻そうとして見張り役の部下に格闘をしかけ、そのお返しに部下達に手ひどく殴られ、止せば良いのにそれに対する返礼としてその場に居あわせた全員を罵倒した。私を罵り、部下を罵り、私の家族と先祖に関して罵り、挙げ句の果ては私の架空の性的嗜好に関して罵った。さすがに、この悪口雑言に溜まりかねたのか、止めるのも聞かずに部下達は軍事顧問をロープでぐるぐる巻きに縛り上げるとおまけとして口に猿ぐつわをかませ、二人がかりで担いで運ぶことにした。
人間を担いで運ぶというのは実際にやってみると判るが、担いでいる方よりもむしろ担がれている方が苦痛である。担いでいる方は肩の筋肉にかかる荷重が苦しいわけだが、担がれている方は全身のありとあらゆる場所にそのごつい肩が遠慮も何もなくぶつかることとなる。それも自分の全体重がその上に乗せられているのだから、これは傍から見ているだけでもその痛さが判る。その打撲による痛みにだらだらと油汗を流した軍事顧問が、猿ぐつわを噛みしめながらも目だけで私に懇願するので、結局私は部下を説得して軍事顧問を肩から降ろさせると、元どおりに歩かせることにした。それでも軍事顧問は諦め切れないのか、実にしつこくこちらの腰にぶら下がる拳銃へと視線を向けて来るので、とうとう最後には彼の両手を縛って部隊の前を歩かせることになった。すでに我が守備隊の人数は軍事顧問を入れても六名にまで減少している。これで帰り道に敵の小隊とでも遭遇したら、戦いと言えるものにはならないだろう。斥候一人出していないこちらが、敵の一方的な攻撃を食らって全滅するのは間違い無い。そもそも当初の計画からして、グスニーオ要塞守備隊だけで街を一つ占領しようというのが無理な計画だったわけで、それをさらに警戒厳重な敵の首都に乗り込んで敵の最高司令官を暗殺しろなどとは気違い沙汰以外の何物でも無い。
日も高く登り、丈の低い潅木が生えているだけの、じかに日にさらされる山道は無視できないほど暑くなっていたので、前方に農園が見えて来たのを機会にここで休息を取ることにした。この辺りの農園が栽培しているのは葡萄である。無数の葡萄の葉が棚から垂れていて格好の日除けになるし、またその下に隠れていれば万一敵が道を通りかかっても死角になって見えないだろうと、我々は葡萄棚の下に潜り込んで休むことにした。
農園には人の気配というものが無く、きっとこの辺りでは幾つもの農園を巡回する形で複数の農家が協力して作業をしているのでは無いかと思われた。共同作業の約束をした農家のグループ全員でそれぞれの家の農園を一つずつ巡り、雑草取りや収穫物の刈取を行う方式である。このような場合は全員がなんらかの形で親戚であり、一つの大きな家族であることが多い。とすればこの農園で作業する順番が回って来るまでは、我々は人目を気にすることなくここでのんびりと日を過ごすことができるわけである。グスニーオ要塞へ帰還するのが遅れれば遅れるほど、軍部への言い訳をするのを先伸ばしにすることができるわけで、私にはその方が都合が良かった。
この寂しい農園の光景は、グスニーオ要塞の崩れ掛けた中庭に我々が作った菜園を思い出させた。食料調達の不便さから、働くことを渋る部下達を押しなだめながらようやく作り上げたものだったが、さてそこで出来た野菜と言えばどれもひどく固くて不味いものばかりで私は非常に落胆したものだった。それでもたまに見事なトマトなどが取れることもあり、それなりに我々は期待を込めて時々水をやりに通ったものだった。今となってはあれほど毎日が退屈でひたすらそこからの脱出を願っていたグスニーオ要塞がとても懐かしく、まるで自分が母親の胎内へ戻ろうとしている赤ん坊のように思えた。
いつとも無く、私は眠りに引きずり込まれ、その眠りの中でグスニーオ要塞の中庭へと私は降り立った。足元には小さな黄色い花をつけた名前も知らない雑草が生えていて、その先のモグラに荒らされた菜園の土の真ん中には先の尖った靴のつけた足跡が一つ見て取れた。これは何か古い時代の騎士の金属製のブーツがつけた跡であると、直感的に私は悟った。例の幽霊騎士のものである。彼は時たまこの中庭へと足を踏みいれているようではあるが、まだ目撃される所までは行っていない。カラスが一羽、どこからともなく飛んで来ると、崩れ掛けた中庭の噴水の上に止まり、そいつは私の瞳をじっと覗きこんでから、驚いたことに人間の男の大きな声で何やら喚き上げた。あまりにもその声が大きいので私は自分の両手で耳を覆い、そうして夢から覚めた。
喚き声の主は例によって軍事顧問だ。
「や、くそ。蜂だ。蜂だ。こいつめ、このわしを刺しおった。痛い。痛いぞ。なんてまた痛い蜂だ。
ええい、いまいましい。どうして善良で忠実で勇敢である軍人たるわしばかりがこんな目に遭うのか。
どうせ刺すならば、この卑怯者達が先であろうに。ええい、許せん。皆殺しだ。この世の蜂を全て、皆殺しにしてくれるわ。
ええい、痛くてたまらんぞ。ええい、くそ、蜂め、わしを憎んでおるのか」
再びうとうとと半睡眠状態の心地好さの中に戻りながら、そう言えば何週間前になるのかグスニーオ要塞にまだ我々が居た時も、この軍事顧問は今みたいに蜂にさされたと大騒ぎしていたことを思い出した。中庭に殆ど自生状態で生えている作物の幾つかを手に入れようと足を踏みいれて、どうやらそこにいた蜂の機嫌を損ねたらしかった。してみるとこの軍事顧問は自分でも言っている通り、蜂に憎まれる何かを持っているのかも知れないな、と勝手に納得した。少なくとも私や部下に憎まれていることは知っているはずで、恐らくはそうやって他人に憎まれることで、自分は何か特別な存在でありその類まれな能力ゆえに他人から嫉妬されるのである、と思い込んでいるのだけは間違い無い。
この旅が終わってグスニーオ要塞に戻った後は、このような嫌われ者の性格を持った人物を相手に過ごすことになるのであるから、軍部からの命令に逆らったという負い目を持つ自分は法律的にも人間関係の上でも非常に危険な状態にあるわけであり、下手をすれば部下ともども銃殺されることもありうるぞ、と物騒なことを考えたが、眠りの気持ち良さに負けてそれ以上思い悩むことも無く、再び夢の待つ暗闇の中へと私は引きずり込まれた。
どのぐらい眠っただろうか。何か恐ろしい悪夢の中でうんうんとうなりながら脂汗をだらだらと流した所で、部下に揺り起こされて目が覚めた。日はすでに沈みかけていて、空一面が夕焼けの赤さに染まっており、その赤さがまるで意志あるものかのように、さらなるより激しい赤へと変貌していく様を見ていると、自分は果たしてまだ深い眠りの中にあって夢を見続けているのか、それとも変えようの無い厳しい現実の中の幻想的な一端を見ているのか、どちらとも判別がつかなくなって来た。
そうしている内に、私を起こした部下の真剣な顔が目に止まり、少し離れた所に残りの部下達が集まって人垣を作っているのを見て、私は何かまずい事態が起きたことを悟り、ようやくはっきりと目が覚めた。皆で一体、何を見ているのかと思って部下の肩越しに人垣の中を覗きこんで見ると、なんとそこに横たわっているのは軍事顧問であった。
軍事顧問は縛られた姿のままで世にも恐ろしい形相で宙を睨み、その両手の指はまるで何かをかきむしるかのように鉤状に曲げられて体の前に突き出されていた。誰かがまた猿ぐつわをかました後で、その歯を食いしばったらしく、彼の歯茎から血が僅かに流れ出してそのまま固まっているのが見えた。夕日の赤に染まって巨大に膨れた顔はとても先刻まで生きていた人間とは思えないもので、一瞬、やはり自分は眠っていて、これはひどい悪夢を見ているのだと信じこみそうになった。
隊に入る前は少しばかり医学をかじったことがあるという部下が、軍事顧問の死体を指差すと死因を解説してくれた。
「蜂の毒によるアレルギー性のショックです。ほら軍事顧問が蜂に刺されたと騒いでいたでしょう。アナフラシキーというやつです。
この種の蜂は一度刺されると体内に蜂毒に対する免疫が出来るんです。次に刺された時にはそれが毒と反応して凄まじいアレルギーを引き起こすんです」
軍事顧問の死体の頭がその説明に納得したかのように肯いたように思えた。死体の周囲にいる部下の誰もそれには気付かなかったようであり、私は再び自分が悪夢の中に捕らえられたことを感じ取った。
空は真っ赤に染まり続け、私はいつまでもその中に立ち尽くしていた。
6)
街で聞いた話を総合して見ると、どうやら敵の後衛を務める部隊の大規模な移動が行われているらしく、新街道一帯が移動中の敵兵で埋まっている。ということは我々はグスニーオ要塞への帰り道を完全に塞がれてしまった形になっているわけで、身動きができない状態がここしばらく続いていた。
道々に行き当たった畑から徴収してきた食料も今ではすっかり無くなり、また守備隊の活動資金としてグスニーオ要塞から持って来た僅かな金も当の昔に底をついてしまったために、我々グスニーオ要塞守備隊の生き残りの五人は途方に暮れていた。仕方なしに我々は盗みを行って糊口をしのぐことにしたが、軍隊が駐留していない小さな街に潜り込んでは警察の目を逃れて盗みを行い、街の人々が警戒する頃には次の街に移るというやり方も、正体不明の盗賊団が移動中との噂が広がると監視の目が厳しくなり、そうそううまくはいかなくなって来ていた。
所詮は、我々は兵士であり、盗賊では無かったということである。
こうなれば、いっそ敵に降伏してしまうという手もあるが、敵の目を恐れて途中の人家から盗みだした服にすでに全員着替えてしまっていたのが問題であった。軍服を着ずに敵に捕まれば、それは軍事行動では無くスパイ行為であると判断されかねない。
当然ながら、スパイは敵に捕まれば裁判無しで即時銃殺となる可能性が高いわけで、しかもこの人数ではグスニーオ守備隊の生き残りであるとの言い開きも通用するとは思えない。何分、グスニーオ要塞守備隊との交戦記録は敵には無いわけで、途中で部隊員の半数が次々と事故で死んだなどと説明をしようものならば、たちまちにしてこいつらは嘘をついていると決めつけられてしまうに違い無い。軍服と一緒に身分の判りそうなものも全て捨て去ってしまっていたので、今となっては我々がグスニーオ要塞の守備隊であることは我が軍の本部が保持している写真付きの軍人名簿を見ない限りは誰にも証明できないわけである。
実を言えば私は身分証を一枚だけ、捨てるに忍びずに持ってはいるのだが、そこに写っている自分の顔は、鏡の中に映る自分の顔とは別人に見える有り様で、これを出せば身分を証明するどころかその逆の結果になってしまうのでは無いかと思われた。
こんなことならば軍服を捨てるのでは無かったと思ったものの、それは後の祭りで、そもそも軍服をあのまま着続けていれば今頃は敵との交戦で墓の下に納まることになっていただろうと思い直し、自分を慰めた。
話は変わるが、敵の後衛を務めるはずの部隊がこれほど大規模に動いているからには、どうやらこの辺りに我々と同じように無謀な任務を与えられた我が軍の部隊がいるものと思われた。移動している敵部隊はこれらに対する掃討作戦を行っているわけで、それも軍の大規模な動きから見て、どう少なく見積もっても中隊規模の軍隊が我が方から送り込まれているものと思えた。しかしあれほどの見事な負け戦が、いくら必死の行動とは言え、こういった無謀な作戦一つで逆転するとは思えなかった。皆で長い間に渡って相談した挙げ句に、このまま野垂れ死にするよりはせめてものこと一花咲かせて死にたいと意見が一致したので、それなりに注意して情報を探っていると、どうやらこの先の山岳地帯に我が軍の歩兵部隊の一つが陣取っているのでは無いかと推測できた。
そうと決まれば、善は急げである。ひとたび敵軍の耳にこの情報が入れば、我々が味方の部隊に近づく機会は永遠に消え去ってしまう。我々は疲れた体に鞭打って、問題の山へ向けて足を急がせた。
神経の興奮につれて私の胃はまたしくしくと痛みだし、それを止めるために薬をむさぼり食ったお陰で今度はひどく気分が悪くなって来たが、今の私は贅沢を言っていられる身分では無い。
ちらちらと目の前で踊る妖精や、私をグスニーオ要塞に送り込んで厄介払いをした私の昔の上司の顔を睨んでいる内に、ようやく前方に目的とする山の鞍部が見えて来た。
自分ならばどの辺りに部隊を位置させるだろうと考えて、山の頂上のすぐ下、岩が張り出して天然の要塞になっている部分に当たりをつけた。懐かしのグスニーオ要塞に比べるべくも無いが、要塞防衛戦ならば我が守備隊にはお手のものである。きっとその岩の張り出しに立てこもっているに違い無い歩兵部隊の連中も喜んでくれるだろうと思いながら山を登って行くと、いきなり銃で撃たれた。
私のすぐ後についてきていた部下が恐るべき馬鹿力で私を岩影に引きずり込んでくれたために怪我こそしなかったものの、これにはさすがに驚いた。考えて見ると我々の身のこなしは明らかに兵隊のそれで、いつ戦闘が始まるかとぴりぴりしている彼らに取っては、我々は軍服こそ着ていないものの襲撃に来た敵兵と見えたに違いない。この小さな岩影で大砲の弾が飛んで来るまでぐずぐずしているわけには行かないので、シャツで作った急ごしらえの白旗を岩の間から突き出して、私はおそるおそる岩影から出た。
一団の兵士が坂になった道の曲り角の向こうから降りて来ると、全員で我々を取り囲み、実に手際良く武装解除した。地面に腰を降ろした状態で彼らを観察し、皆が少佐と呼んでいる男がこの部隊のリーダーであると見極めをつけた。やや痩せぎすの厳しい顔つきをした男である。彼は我々を一人づつ綿密に検査した上で全員を自分の前に立たせた。そうしてから、我々をもう一度じろりと一睨みすると言った。
「我々は捕虜は取らない。降伏も認めない。それ故に諸君らを解放することにする。
武器も没収はしない。但し、我々の姿が見える間は弾を装填してはならない。そして、ふもとに着くまでは後を振り返ってはいけない。
再びここに戻ってくるようであれば、仕方が無い。警告無しで撃ち殺すことにする」
静かな、それでいて死を覚悟した声であり、また人の命を奪う者に特有の意志の強さが声の中にこもっていた。少佐が本気でそれを口にしたのであり、また確実にその通りにするであろうことを私は知った。誤解を解こうと私が口を開く前に少佐は、黙っていろとの身振りを一つして話を続けた。
「諸君が持っていた武器は我が軍のグスニーオ要塞守備隊の物だ。あそこの装備は我が軍の中でも最も旧式なのでこの判断に間違いは無い。それを諸君らが持っていたと言うことは、取りも直さず諸君らがグスニーオ要塞守備隊を倒し、戦利品としてそれらの武器を捕獲したということだ。
諸君らがグスニーオ要塞守備隊であるという可能性はこの際、排除する。重要な使命を軍司令部から受けているはずの要塞守備隊がもしこのような所に居るとすれば、それは命令違反を意味するからだ。さらに言うならば、このような場合には見つけ次第に彼らを撃ち殺せとの命令が軍司令部から出ている」
そこまで言ってから少佐は押し黙ると、私の目をじっと覗きこんだ。勿論、少佐には我々がグスニーオ要塞守備隊の生き残りであり、全員の顔に隠しようもなく浮かんでいる疲労とその擦り切れたボロ服から、これまで我々が筆舌に尽くしがたい苦労をしてきたことを知ったに違い無く、それ故にこれは同じ境遇にある我々に対する彼なりの精一杯の同情に違い無かった。
元はと言えば彼の部隊も私の部隊も、このような理不尽な目に会うようなことは何一つしておらず、またどうあっても死なねばならないような状況に我々を追い込んだ責任は、確固たる戦略思想を持たずそれゆえに敵国の侵略を許した軍の参謀連中にあると断言できる。その参謀連中は安全な軍司令部の待避壕の中でのうのうと過ごし、何の罪も無い我々が死を要求されているのはいったいどういう理屈なのであろうか。こう考えると我々が小さい時から教えこまれて来た正義という感覚そのものがあやふやになり、後に残るのは星の巡り合わせが悪かったのだという自嘲だけとなる。
最後の頼みの綱も断たれ、首をうなだれて山を降りて行く部下達を私は絶望とともに見た。別れ際に少佐は自分の胸にぶら下げていた小さな皮袋を取り出し、そうしてそれを私の首に掛けると、振り向きもせずに自分の死に場所と定められた山の小さな要塞へと戻って行った。