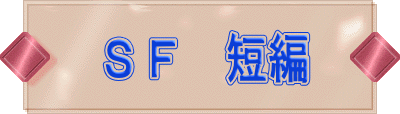
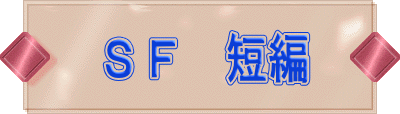
ガトリングガンの咆哮を聞いていると眠くなる。近くで聞くととんでもない騒音だが、バトルボッドの中からだと心地よいBGMだ。
思わず、欠伸が出る。
撃たれる方に取ってはそんなに穏やかではない話だが、そこまで気を使ってはいられない。どのみち照準をつけているのは戦闘AIだ。搭乗者は発射するかどうかを判断するだけ。
三番の報告ランプがつくと、スピーカーからゲンさんのわめき声が流れた。
「えい、クソ! 故障だ。足が動かん。立ち往生だ!」
それに答えて、この隊のメカニック役のナツさんののんびりした声が返る。
「故障じゃねえよ。ゲンさん。ボットの膝のサーボモータが過熱でロックされただけさ。また温度センサの警告無視しただろう。俺が整備しているんだ。故障なんてありえねえよ」
「うるさい。この若造が。こりゃ故障と言ったら故障だ」
「若造、若造って。あんた、八十二歳、俺は八十一歳。一歳若いだけだろ。誤差の内だよ」
「ゲンさん。周囲に煙幕を張って、冷却待ちしろ。そのままだといい的だ」
俺はゲンさんにそう指示を入れると、スイッチを叩いて通信を切り替えた。今頃ゲンさんは一回りも年下の若造がと怒鳴っていることだろう。
「ナツさん。本当に単なる停止だな? 救助しなくていいか?」
ナツさんはざっと手元の情報端末をチェックした。本来の隊長機は俺だが、俺はメカに詳しくないので機器の情報権限はナツさんへ回すように設定してある。ナツさんは端末の数値にざっと目を通してから答えた。
「報告来たぞ。やっぱり過熱によるロックだ。警告音が鳴り響いたはずだが、ゲンさん、耳が遠いからなあ。まったくこの機種は厄介だよ。コストダウンとやらで前の機種よりもヒートパイプが細い。冷却機能に余裕が無いんだ」
その話なら、ナツさんが何度もこぼしていたので流石に覚えている。メーカーの実験室ではうまく動くのだが、実際に戦場に出るとうまく動かないものの一つが冷却系だ。フィルターは砂塵で目詰りするし、ヒートパイプは爆発の衝撃で歪むと本来の性能は発揮できなくなる。一言で言えば、この機体はヤワなのだ。日本軍の本当の敵は財務省という言葉はいつでも真実なのだ。
「ナベさんや。わしゃ、飯食ったかいの?」
今度のはカジさんの声だ。今年九十六歳で、だいぶボケが進んでいる。たまに徘徊もするが、バトルボットにはGPS機能がついていて自動帰還機能もあるから、迷子にはならない。そもそも俺たちの小隊は偵察が任務だ。つまるところ、偵察も徘徊もさほど違いはない。
「みんなあ、飯の支度ができたぞい」今日の食事当番のナカさんからの通信が飛んだ。
ボケているはずのカジさんの機体が真っ先に動いた。最後にゲンさんの機体の冷却中アラート表示が消えて動き出すのを確認してから、俺はバトルボットの向きを変えて帰還を開始した。
アメリカと中国とロシアが揃って崩壊分裂し、インドでカースト革命が起きた後には、全世界的な地域紛争の時代が来た。幸いにして核兵器をぶっ放す馬鹿は居なかったものの、小規模ではあるが終わりの無い地域紛争が地球全域で起きるようになった。敵の敵は変わらずに敵であり、味方の味方はやっぱり敵という状況が続いた。
戦争が長引くに連れて問題となってきたのが兵員不足である。なにせ何をどうやっても戦争が続く限りは最前線の兵は死ぬ。それを律儀に補充していれば、生産人口の減少により、国そのものの存続が危うくなる。かと言って軍隊の規模を減らせば、たちまちにして敵の餌食となる。
その状況の救世主となるべく開発された無人兵器群のAIが容易く暴走することが判り、解決策の模索は最終的に一つの結論へと落ち着いた。
老人兵の採用である。
各国で老人徴兵法が採用され、60歳を越えた老人は一定の確率で抽選され、80歳を越えると問答無用で徴兵されるようになった。
前世紀の戦争では体が弱った老人が戦場に出るのは無理であったが、今はバトルボットと呼ばれる人型戦闘機械が開発されている。人間はバトルボッドの中の揺り籠と呼ばれるナセルに収まり、寝たままでも操縦できるようになっている。
*)
飯の時間は聖域だ。戦争規約に明文化されているわけではないが、お互いに飯の時間は攻撃を手控えることにしている。どのみち老人兵などというものは姥捨て山に捨てられたのと同じものだ。国に捨てられた者が真面目に国のための戦争をやる道理はない。
俺は無指向無線送信機に食事中の信号を流すと、バトルボットを降りた。
バトルボッドの中にあるのは着脱式の操縦席だ。同時に老人兵の自動介護装置でもある。戦場は特殊な空間であるので生活の質などという言葉は無視して徹底的に合理的でかつ冷たい措置を取ることができる。
バトルボットの装甲が開き、中央ナセルがモータ音と共にせり出す。地面に着くとともに、ナセルの保護カバーが開く。
赤い顔のゲンさんがよろよろと這い出した。ゲンさんは威勢は良いが、それなりの歳なので、ゆっくりとしか動けない。
ゲンさんは食事が並べてあるテーブルに何とかたどり着いた。
「こら! カジ。わしの飯に手を出すんじゃない」
カジさんの皿だけ大盛りになっている。惚けているカジさんは胃が破裂する寸前まで食べ続けるからだ。食事を制限するとカジさんは暴れることがある。もちろんカジさんの血液の数値は糖尿病を示しているが、いまさら健康もへったくれもないので無視している。もっとも食事当番のナカさんもその辺りは分かっていて、カジさんの食事にはゼロカロリーの膨張剤をかなり混ぜている。
もうちょっとカジさんのボケが進んだ場合には、バトルボットのナセルの中に固定されたままとなり、口に入れた管から流動食を入れられることになる。介護モードになるとナセルの中には温水が循環するようになり、垂れ流したものはそのまま足の方向へ排出される形になる。この方式だと介護の手間はかからないが、人間そうなってはおしまいだとも俺は密かに思っている。
「ああ、腰が痛い」
食事の皿を受け取りながらゲンさんがぶつぶつ言った。
「そりゃ、シートの角度は自分で調整しないと。こればかりは俺が調節してもどうにもならんしな」ナツさんが指摘した。「それと今度新しい装備が来る。たぶん三日後に換装することになる」
「何が来るんだ。ええっと報告書はどのフォルダに収めたかな」と俺。
「20ミリ高速ライフルだ。レールガンタイプで今までのよりうんと強力なやつ。装填速度は遅いし連続発射制限はあるが、当たれば敵が一発で吹っ飛ぶ」
口の中のものを頬張りながらナツさんが説明した。
「やれやれ。政府のやつら。わしら老人にいったい何を期待しているんだか」
俺はため息をついた。
いまさら老人が戦場のヒーローになってどうする?
次にご紹介さしあげるのは南部戦線の撃墜王ワタナベさんです。今年米寿を迎えました、ってか。
「そう言えばちょっと面白い話を聞いたぞ」とはナカさん。
この分隊の構成人数は五人だが、他の分隊からは離れた戦場孤立点を哨戒している。つまりは人の行き来は滅多にない。そういうわけだから話を聞くと言っても、ナカさんの場合はネットでの違法盗聴のことだ。今の時代は、周囲には無数の無線電波が飛び交い、半分軍事半分民間の複雑怪奇としか言いようがない情報通信網が構築されている。いずれもある程度は暗号化されているのだが、そこはそれ蛇の道は蛇というわけで、アンダーワールドの世界に触れたことがある者ならば、その混沌のスープの中からそれなりの情報を引き出せるものらしい。
皆が食事の手を休めてナカさんを見つめた。ナカさんは得意満面に話し始めた。
「近々、敵の大規模攻勢があるという話だ。うちの軍部の連中はそれに合わせて新装備で迎え撃つつもりらしい」
「それが今度の装備改変というわけかい。手間がかかってしょうがない」ナツさんがこぼした。
「ナツさん、よろしく頼むよ。うちのメカニックはお前さんだけだからな」
「オレは別にバトルボッドの整備士ってわけじゃないんだ。ただの元バイク屋だよ」
「まあそれを言うなら俺たちみんな兵士でもないんだがな」と俺。
軽く相槌を打っておくのは大事だ。雑談のないプロジェクトは失敗するプロジェクトと会社では習ってきた。
「違えねえ。徴兵の赤紙は来たが、別に戦闘訓練なんか受けていないしな。バトルボッドに乗せられてここまで自動歩行で送られて来ただけだしな」ナカさんが自嘲気味に言った。「この中で志願組はナベさんだけか。わざわざ志願するなんてご苦労なこった」
「そりゃまあ、歳を重ねるごとに徴兵される確率は上がるしな。カジさんを見ろよ。九十六にもなって徴兵されちまった。どのみちいつかは徴兵されるなら、その前に志願した方が扱いがいいだろ?」
「扱いがいいって言ってもほんのわずかだぜ」ナカさんが指摘した。
「まあ、本当のことを言うとな。俺は天涯孤独だし、女房子供がいるわけじゃない。生涯を賭けた仕事を持っているわけでもないし、広い持ち家があるわけでもない。だから生きていようが死んでいようが別にどっちでもいいんだってな、そう思ったんだ。とかく老人は生きにくい世の中だから」
喋りながらも俺は頭を掻いた。どうもこの手の話題は苦手だ。
「色々あるんだな」ナツさんがぼそりと洩らした。
まあ人間長く生きているとその色々が増えていく。そしてそのどれもが重く肩にのしかかる。投げ捨てたくなるぐらいに。
ナカさんが食事の皿を片付け始めた。その後は自由時間である。
「ナベさん。悪いけどちょいと整備を手伝ってくれ。ゲンさんのバトルボッドを調整しておきたい」
*)
結局その晩は作業で潰れた。俺とナカさんは整備服を着てゲンさんのバトルボッドに張り付いた。整備服は体の前面だけを覆うタイプの強化服だ。着脱は容易で、色々な作業道具が腕に埋め込まれている。AIアシストもついているので、素人でもバトルボッドの整備ができる優れものだ。
ゲンさんのバトルボッドは足の冷却フィンに敵弾が当たり、放熱機構の半分が壊れていることが分かった。破損したモジュールを作業服の怪力で乱暴に引きはがし、回路接触面を綺麗にしてから新しいパーツに置き換える。バトルボッドはプラモデル並みに簡単な作りだ。
作業が大体終わった所でナカさんが飛んで来た。
「大変だ。先に寝ていたはずのカジさんがいない」
大騒ぎになった。
隊長用のバトルボッドには、公然の秘密だが隊員追跡用のモニタがついている。俺はそれを叩き、探索結果を待った。各人にこっそりと埋め込まれているトランスポンダーが反応し、カジさんの居場所を報告する。
「いたぞ。ゆっくりと移動している。ずいぶんとフラフラしているな」
「深夜の徘徊か。カジさんもずいぶんとボケてきたな」ナカさんがため息をついた。
全員で走った。みんな拳銃だけぶら下げている。それよりも大きな武器は重すぎて腰痛を起こす。バトルボッドを出すのは駄目だ。今の状態のカジさんがバトルボッドを見たら悲鳴を上げて逃げ出してしまう。
GPSが示すカジさんの居場所についた。厄介なことに敵が敷設した地雷原の中だ。カジさんはその中をフラフラと歩いている。
「やばい。やばい。やばい」ナツさんがつぶやいた。
「ここは対戦車地雷、対人地雷、対空地雷、対ボッド地雷がてんこ盛りの場所だ。カジさんに近づけない。というかじきにカジさん地雷踏んで死ぬぞ」
俺はしばらく迷ったが覚悟を決めた。肩につけてある隊長用通信機を叩く。周波数を汎用通信周波数に合わせ、出力を最小にしてから、汎用翻訳機に言葉を流し込む。AIによるかなり荒っぽい翻訳だがこれでも使えないことはない。
「この通信が聞こえるなら返事をしてほしい。こちら日本国陸軍第八師団第三十二偵察小隊隊長ワタナベ。ここの地雷原の管理者と話がしたい」
しばらく繰り返していると小さな雑音とともに応答があった。
「聞こえているぞ。こちらの所属は勘弁願いたい」
「手短に言う。交戦の意思はない。そちらの地雷原にウチの者が迷い込んでいる。彼は痴呆症が進み現在深夜の徘徊を行っている。彼は周囲の状況を全く理解していない。彼を助けに行きたい。もし可能ならば地雷原を眠らせて欲しい。」
しばらく沈黙が落ちた。それからまた通信が繋がった。
「彼の年齢は?」
「九十六歳だ」
「分った。その年齢に敬意を表して君の要請を受けよう。ただし地雷原に入るのは一人だけ。おかしな素振りがあれば、悲惨な結果が生じる」
「了解した。君の配慮に感謝する」
「今、地雷原は眠った。ただし命令が行き届いていない地雷があるかもしれないから、できるだけそっと歩いてくれ」
「わかった」
現代の地雷はすべてスマート地雷だ。命令一つで爆発待機から休止まで自由に設定できる。tだし電波の状況次第で命令が届いていない地雷が必ず残るので、安心はできない。どの種の地雷でも爆発すれば人間一人ぐらいは優にひき肉にできる。
俺は装備を外すと、他のメンバーが止める間もなく地雷原に踏み込んだ。静かに歩いてカジさんに近づく。驚いたカジさんが走って逃げようとするのが一番ヤバイ。
俺に気づいてカジさんが振り向いた。
「ぬしゃあ、誰じゃ」
「料理番です」俺は嘘をついた。「カジさん。ご飯ができていますよ。食べに来てください」
驚くほど素直にカジさんはついてきた。カジさんの死にかけた脳細胞の中で元気なのは食欲だけなのだ。
ようやく地雷原を抜けて装備のところに戻ると、俺は通信を送った。
「ありがとう。無事に彼を回収できた」
「お祝いを申し上げる。現在、地雷原は再び活動状態にある。二度とこの辺りを徘徊しないように注意してくれ」
「了解。重ねて感謝申し上げる」
通信を切る。
ふう。溜めていた息を吐くと共にどっと油汗が噴き出した。本当にヤバイところだった。話がわかる相手でよかった。
「はやくご飯」カジさんが要求した。
「はいはい。こちらだよ」ナカさんが先導した。
ゲンさんは懸命にも黙っていた。ここでゲンさんが怒鳴ってカジさんが走り出したらもう収拾がつかない。
カジさんがバトルボッドを十メートル以上離れたら警報が出るように設定しておこう。今後はこういう事がないようにしないと俺の繊細な心臓が持たない。
*)
しばらくは穏やかな日々が過ぎた。
新武装はすべてのバトルボッドに取り付けられ、その他の細かいバージョンアップも行われた。バトルボッド起動時に索敵モニタに新ウィンドウズの広告が出るようになったのはさすがに腹が立ったが、ナツさんの必死の努力のおかげでじきに出なくなった。
軍部の連中。いくら予算が無いからって広告を取るなんて、いったい何を考えていやがる。まあ俺が悪態をつかなくても、代わりにゲンさんが大声でその経営者の悪口を言ってくれたので少しは溜飲が下がった。
部隊は決められたルートをカメレオンモードで前進する。カジさんの痴呆はひどくなっているので追尾設定にして後ろに引き連れている。本人はバトルボッドのナセルの中で薬が作り出す深い眠りにその身を委ねている。
前方索敵システムに何かがかかった。全員動きを停止して、偽装偵察ボットを送る。これはハチに似せた超小型偵察機だ。
偵察画像が索敵モニタに表示される。下側に小さく一文コマーシャルも出る。ええい!
画面中央に映っているのは敵のバトルボッドだ。あちらも偽装モードで機体全面に3D迷彩がかかっているが、画像処理をかけるとすぐ判る。この点ではまだ我が国の技術の方が上だ。思わず3D迷彩のどこかにコマーシャルが出ていないか目で探ってしまった。こちらの偽装は大丈夫だろうな? ちょっとだけ不安になった。
新武装の二十ミリ高速ライフルを照準する。こいつなら敵の防御を抜いて一撃で破壊できる。俺は照準線を敵に重ねてロックした。
それから通信回線を開く。汎用周波数。最低出力。
「前方の敵兵に告ぐ。キミはこちらの照準に入っている。動けば破壊する用意がある」
しばしの沈黙。
「今から一発だけ警告射撃を行う。キミの前方十センチを狙う。どうか動かないでもらいたい」
照準を調整し、撃った。強烈な衝撃。たしかにこの新兵装は相当ヤバイ。ただし連射能力には難がある。警告を無視して連射しているとあっさりと手の中で半端じゃない大爆発をやってくれると解説に但し書きがついていた。
敵バトルボッドが震えた。すぐ前方を通り過ぎた高速弾の衝撃波が機体を打ったのだろう。
「こちらが狙っていることが理解できたならば、そのまま後ろに向けて前進してくれ。大人しくテリトリーから出ていくならば、こちらからは攻撃しない」
「わかった」返事が届いた。聞き覚えのある声だ。
相手の通信の出力レベルを見る。最低レベルだ。他の地域に聞こえないように配慮しているということはこちらの意図を理解しているということだ。
「変なことは何もしない。このまま出ていく」
その言葉通りに敵バトルボッドはゆっくりと向きを変えると、前へ進み始めた。
「なあ一つ聞かせてくれ」相手が喋った。別にその必要はないがささやき声だ。
「なんだ?」
「オレを撃たないのはこの前の夜の礼かい?」
「そうだ。俺は他人に借りも貸しも作りたくない」
「そうか。わかった」
そのまま相手が索敵範囲を出るまで待ち、パトロールを継続するとその日の報告に異常無しと送っておいた。
俺たちは真面目に戦争していないって?
その通り。
*)
ある日の夕飯時、俺たちは驚くような出来事に遭遇した。
白旗を振りながら、敵軍の兵たちが三人ほど訪れたのである。
実はあれ以来、彼らとは秘匿通信周波数でたまに会話をしていたのだが、とうとう酒を持ってこうして訪れてきたのだ。
向こうも老人兵でそれぞれチャン、リーそしてパオマと名乗っていた。いずれも齢七十というところか。
取り合えず焚火を囲んで酒を酌み交わした。LEDを使ったもっと明るいランタンも装備の中にあるが、この方がずっと雰囲気が出る。
さらに言うならば、彼らとの間で秘密協定を結んである。向こうが偵察に出るときはこちらは陣地に引っ込んでおく。こちらが偵察に出るときは向こうは陣地に引っ込んでおく。それで双方とも誰も死なずにうまくいく。
どのみちどちらも老人兵なのだ。姥捨て山に捨てられてなお命の奪い合いをしなくてはならない道理もない。
そのうち酔っぱらった勢いでナツさんが孫の写真を出してきた。振袖姿の少女が写っている。
「可愛いだろう。今度大学に進学するんだ」
ナツさんは酒に染まった真っ赤な顔で自慢した。
「オレだって持ってるぞ」チャンさんがどこからかスマホを取り出してきた。「ほら見ろ。うちの孫たちとひ孫たちだ」
三枚の写真に合わせて二十人近くの家族が写っていた。
「うちのはこんなだわな。三番目の息子の子供たちだがな」
ナカさんが取り出した写真には、偉丈夫の男が二人写っていた。
「もうどれもおっさんだ。昔は可愛い男の子たちだったのに」
「仕方ない。仕方ない。みんな同じ。みんな同じ」リーが合いの手を入れた。
「ウチはひどいぞ」ゲンさんが怒鳴った。いや、ゲンさんは普通に喋っているつもりなのだが、地声が異様に大きいのだ。
「息子も孫もワシに近寄りゃせん。その代わりにうちの婆さんのところに行く」
「そりゃひどい」皆同情した。
「昔酔って暴れたことがあってな、それ以来ワシゃ嫌われ者よ」
「そりゃ当然だ」皆呆れた。
「ナベさんはどうなんだい」チャンさんが水を向けてきた。
「オレは終生独り者だったからな」
「結婚はしなかったのか」
「しようと思ったこともあったが、相手が事故で死んでしまってね」
「悪いことを聞いてしまったな」
「なに、大したことじゃないさ。みんな、国に家族がいるんだな」
「まあそれでも最後にはみんなここに来るんだけどな」チャンさんが自嘲した。
「ナカさんや。わしゃ飯はまだだでのう」カジさんが割って入った。
「カジさん。あんた今日は六食は食べとるぞ」ナカさんが呆れたように言った。「それより飲め飲め。酒は百薬の長と言うぞ」
カジさんの口に酒ビンを突っ込む。やがて荒い息をしながらカジさんは寝込んだ。
最初は一か月に一回ぐらいの宴会だったが、やがて酒飲みの頻度が上がり、ついには毎日バカ騒ぎをするようになってしまった。
それでも報告書はいつでも「異常なし」の一言で終えた。
*)
やがてその日がやってきた。暗い顔をしてやってきた三人は、話があるんだがと切り出した。
俺もナカさんもこの日が来ることは判っていたので驚かなかった。
「三日後に総攻撃の命令が下った。だからもうここにはこれない」
「そうか。そろそろだと思っていたんだ」とナカさん。「あのな、こっちも教えておくけど、ウチの司令部はそちらの総攻撃を予想して反撃の準備を整えている」
「やっぱりな。どちらの作戦も大規模過ぎて隠せる話じゃないからなあ」パオマが答えた。
「まだどこを攻撃するかの命令は下っていないんだ。だからここに当たるかどうかは判らないが、その時にはお互い手加減は無しにしよう。変に情を絡めると話がややこしくなる」と真剣な顔でチャンが言った。
「わかった。残念だがそうしよう」と俺。
「それとここにきているのは三人だが、ウチの隊は他に二人が寝たきりになっている。バトルボッドは搭乗員の生死に関わらず自動モードで動くからウチは総勢五機で動くことになる」
「ウチも五機だな。カジさんはこのところバドルポッドの中で寝たきりだから、こちらも自動モードだな」
最後の飲み会になり、みんな一気に盛り上がった。
死が近いのだ。それも下手すりゃ友達同士での殺し合いになる。そうとなれば、酒に手加減なんかしていられない。
酒で顔を真っ赤にしてチャンさんが話し始めた。
「昔の話なんだがな。小規模な戦争がいくつも起こり、それに戦闘AIと無人兵器が本格的に投入されたことがあったらしい」
「知ってる。知ってる。スイニョール戦争の時代だな」
「ナカさん良く知ってるなあ」チャンさんが感心した。「で、そのときの戦争でどちらの陣営も無人兵器を戦地に投入したんだ。ところがこれが実に面白くなくてなあ」
「面白くない?」と俺。
「うん、面白くない。無人兵器同士の戦いというのは工業力の衝突でしかない。今日は何機生産しました。その内何機が壊れました。ただそれだけの話が延々と続く。生産に負けた方は頑張って生産力を上げる。結果として戦争はいつまで経っても終わらない」
それを聞くと、ナカさんはどこからか別の酒ビンを取り出すと口に運びながら言った。
「そうなんだよ。大戦初期の頃は戦闘AIだけでバトルボッドを動かしていたらしい。ところがそれだと戦争にならないそうなんだ。単なる工業製品での力比べにしかならない。
いいかい。戦争という行為は相手に痛みを与えるのが目的なんだ。だから戦争の際には人が死んで初めて話は先に進む。んで、各国協議の末に、完全無人化は禁止されあくまでも有人戦闘にしましょうということになった。戦闘AIが暴走し易いなんてタダの言い訳なのさ。
最初の内はバトルボッドに若者を乗せていた。ところがそれだとただでさえ貴重な若者がどんどん死んでいく」
「なるほど。挙句の果ては死んでも国家の懐はそう痛まない老人を乗せるようになったってことか」俺はうんざりしながら嘆いた。
「老人は余っていたからな。ほら、カジさんを見ろよ」
ナカさんはカジさんが収まっているバトルボッドを指さした。
「本当なら老人ホームで介護士を悩ませているのが関の山なのに、こうして駆り出されている。国としては戦地で死んでくれれば万々歳だろうな」
「オレもそうだな」チャンさんがしみじみとした口調で言った。
「オレの家族は口には出さんがね。今回の出征が決まったときはほっとした顔をしていた。オレがもっと歳を取って介護が回ってくるのが本当はイヤだったんだろうな」
今度はナツさんがため息をついた。
「ウチもなかなかだよ。孫からお爺ちゃん頑張ってねと手紙が来たけどな、それに加えて息子の嫁から戦地では給料の使い道がないだろうからこちらに送れといらん伝言がついていた。つまるところ、人が殺される痛みとは言ってもあくまでも手のひらを包丁で切る程度の痛みなんだろうな。そのちょっとした痛みを作りだすためにオレたちはここに送り込まれたわけだ」
「やれやれ、俺たちはゲームの景品扱いか」
世も末だなと全員で笑った。
「その点、俺は家族がいないから誰も傷まないんだな。確かにここに来たのは、もしかしたらあと腐れなく死ねるかもしれないと思って来たんだよ」
皆の手が伸び、俺の背中を優しく叩いた。
「ナベさん。あんたが死んだら俺たちの心が痛む。だからそんなことを言わないでくれ」
不覚にも涙が零れてしまった。
「湿っぽい話は無しだナシ。さあ、飲め飲め。MRE用の純粋エチルアルコールを俺のブレンドで銘酒に作り替えたものだ」
ナカさんが山ほどの酒ビンを取り出してきた。
確かに旨いが無茶苦茶きつい酒だった。それを皆で浴びるように飲んだ。その夜が明けると、チャンさんたちはいつの間にかいなくなってしまっていた。
強烈な二日酔いがようやく治まった三日後、敵の総攻撃が始まった。
*)
反撃の朝、出撃前の整備でカジさんが死んでいることが発見された。ナセルの保護液の中で皺むくれの死体が静かに浮いている。生体信号無し。
「自動モードにして俺たちについてきてもらおう」
俺はそう命じると自分のバトルボッドに乗り込んだ。ナツさんは何か言いたそうにしていたが大人しくバトルボッドに乗った。ゲンさんはここに来て逆に無口になっていた。最後にナカさんが乗って、俺たち小隊は出発した。
偽装状態で森の中に散開する。早期警戒システムに映ったのは敵地雷原の中を抜けて来る敵バトルボッド部隊だ。かなりの数が出ている。
「確固に狙撃」とだけ命令を出しておく。
二十ミリ高速ライフルの出番だ。照準に入る端から打ち抜いた。三機ほど射抜いたところで高温警告表示が出てライフルがフリーズされた。まあ仕方ない。もともとがこういう武器だ。
手持ちの対バトルボッドミサイルを全弾発射し、全隊に後退を命じる。カジさんの機体が前に出すぎて集中砲火を受けそうになったので、その周囲に煙幕弾を叩きこんでから逃げる。
急激な機動に背中が痛いが敢えて無視した。
「あいたあ!」ナカさんの声が通信機から飛び出した。「ギックリ腰じゃ。動けない」
「ナカ・ナセル。介護モード」俺は命令を発した。
今頃ナカさんのナセルの中には人肌の温度の液体が注入されているはずだ。戦闘機動は戦闘AIが行うし、ナカさんがやるべき仕事は腰が痛まないように下手に力まないことだけだ。
撤退する経路に従い予め埋めておいた自動迎撃モジュールを起動していく。無数の散弾、ミサイル、ハイレーザーパルスが飛び交う。突入してきた敵バトルボッドのかなりのものがこの奇襲を受けて混乱している。
チャンさんたちはこの突入部隊に入っているのだろうかと思ったが、どのみち見分ける手段もないので考えないことにした。
全部のバトルボッドが退避壕に飛び込むのを確認してから、俺は収束通信を送った。広域砲撃要請に加えてここの座標をつける。戦術戦闘AIモジュールが俺の判断を裏打ちする。
長くは待たされなかった。空を無数の自律砲弾が埋め尽くし、地表に露出している敵バトルボッドに正確に突き刺さった。一つ一つの爆発は弱いが、集団になるとその攻撃に耐えることのできるものはいない。金属が弾け、内部の人体が沸騰して燃え上がる。本来この種の砲撃は対空専用装備をつけたバトルボッドが対処するのだが、敵軍の中にその種の装備は少なかったようだ。対空専用装備は恐ろしくバカ高い。敵軍にあっても最大の敵は予算ということか。
やがて退避壕の外は轟音と爆音で埋まった。各所に埋設されている監視ボットからの無数の映像が、索敵モニタに次々と投影される。その光景は地獄以外の何物でもない。
外が静かになる。生き残った敵バトルボッドはまだ向かってくる。
「各自退避壕に入ったまま防衛戦闘。これ以上の援護はない。動くものはすべて撃て」
命令を下しながら高速ライフルの銃身を突き出す。照準に入った敵を撃ち、次のは普通のライフルで撃ち、冷却期間が過ぎたらまた高速ライフルで打つ。
その内に弾が尽きたので、高周波ブレードによる接近戦になった。退避壕に近づいた敵機を二つに引き裂き、間髪を入れずにまた退避壕に飛び込む。
そんなことを続けている内に、最後には敵兵の姿が完全に消え、広域放送で敵の撤退が告げられた。
今回の大攻勢は退けられたらしい。
俺たちのキャンプ周辺は砲撃の痕でひどい有様だったが、予め大事なものや予備のパックは地下保存庫に運んでおいた。本来なら保存庫ごとバンカーバスターで吹き飛ばされていてもおかしくはなかったが、ウチの空軍が相当頑張ってくれていたらしい。
かなり損傷のひどいバトルボッドたちがよろよろと集まって来た。
ナツさんのバトルボッドからナセルが解放され、げんなりした様子のナツさんが顔を出した。
「ひでえ戦いだった。全弾撃ち尽くしたぞ」
「ナツさん、お疲れ。こっちも弾は空っぽだ」
「他のはどうだ?」
「あまり期待できないな」
彼らからの通信は当の昔に切れている。カジさんは戦闘前に老衰で死んでいたが他はどうなっていることやら。
小隊長のコマンドを使い、まずゲンさんのボッドから開いていく。
ゲンさんのナセルには大穴が開いていた。その中のゲンさんの頭にも大穴が開いていた。
「ゲンさんは駄目だ。死んでいる。何か文句を言いたそうにしているがな。ナカさんはどうだ?」
「胴体真っ二つ。こりゃあ、ブレードにやられたな。バトルボッドの上半身がくっついているだけでも奇跡だ」
「生きているのは俺とナツさんだけか」
俺は報告書をどうしようか迷った。不思議と悲しさは感じなかった。ここにいるのは老人兵。基本的に死人と同じ。
「なあ、ナツさん。俺は彼らの死亡を隠したい。ここで彼らが死んだと報告すれば、どうせまたすぐに次の老人兵が送られてくるだけだ。同じ死ぬならやっぱり家族の下で死なせてやりたい。俺が死亡報告しなければ次の犠牲者は来なくて済む。戦闘AIを自動モードにしておけば、死体が乗っていてもぜんぜん問題がない」
「そうだな。ナベさん。俺もその案に賛成だ。それにな、退避壕の中で時間があったんで分析プログラムを走らせてみたんだが、敵のバトルボッドもほとんどがAI自律モードの動きをしていた。そうだな、恐らく敵老人兵の八割が最初から死んでいる」
「どちらも考えることは同じか」
「AI自律モードは突撃大好きで生存率は低いんだ。そうでなかったらいくら新兵器があったとしても、これだけの大攻勢を防げるわけ無かったな。幸いオレとナベさんがいれば機体の整備はできるし、それでいいんじゃないか」
「よし分かった。ではナカさんたちのナセルは保存モードにしておこう。いつの日か俺たちが死んですべてがバレたときに、まとめて死体を回収できるようにな」
その後、驚いたことに俺は昇進した。老人兵の死亡率が低いことが評価されたらしい。この地域の哨戒兵は総勢二十名に増員され、不足する機体が中身の老人たちと一緒に送られて来た。
多少難航したものの、新参の老人たちも俺の案に賛成し、結局その内俺は無数の死体を積んだバトルボッドを指揮することになった。
もう老人兵部隊じゃない。死人兵部隊だ。
死んだ老人たちの身内から何かを怪しむようなメールを貰うこともあったが、死んだ老人たちの給料を直接彼らに送るように設定すると誰も文句を言わなくなった。老人兵は生きている間は給料が出るが、死ぬと軍人恩給すらないのだから、家族としては事さらに死を疑っても何の利益もないのが実情なのだろう。
爺さん元気で留守がいい。そんな標語が頭に浮かんで俺はげっそりとした。
俺たちは老人兵。ここは戦場と言う名の姥捨て山。
大概のヤツは操縦ナセルの中で大人しく二度と目覚めない眠りを貪っている。
機械たちは自分で勝手に戦い、本国では勘違いした奴らがお爺ちゃん頑張ってねなどと叫んでいる。
まったく誰だよ。こんなバカな戦争を考えたヤツらは。