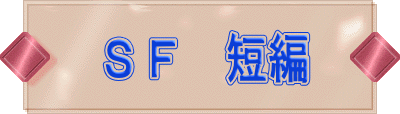
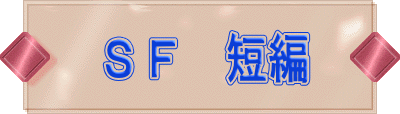
最後のチップを置いた番号は無情にも外れた。一年前から始まった不運のこれが最後の一つだ。
俺はルーレットのテーブルから立ち上がった。
絶好調だったとき、一つの口座を作った。それは俺がギャンブルから引退した後のための資金を貯め込むもので、結構大きな額が貯まっていた。いつの日にか来るだろう俺のツキが枯渇したときに、それだけは持ったままこの世界を去ろうと思っていた。
最高級の車が売られ、そこそこに豪華だった邸宅が競売にかけられ、惚れぬいていた女に逃げられ、すべてのギャンブル用の口座が空になったとき、その決意はあっさりと崩れた。
これを使ってもう一度返り咲く。その決断を当時の俺は密かに誇りに思ったものさ。もちろん最後の口座もあっという間に空になり、俺はひどく後悔することになった。つまり俺は引き際を間違えたのだ。
後はもうご想像の通りだ。あらゆる家財道具を売り、残っていた最後の腕時計を売り、女がたった一つだけ俺に残していった指輪を売った。
ポーカーは文無しの俺の相手をしてくれる奴らがいなくなったので、もっぱらルーレットに張り付いた。
着ていたオーダーメイドのスーツは売って、古着に着替えた。
そこまでして作った最後の資金がたった今融けた。
後は、そう、まだ内臓がある。腎臓と角膜は一つづつ売れる。肺は買ってくれるヤツがいない。心臓はもうすでにギャンブルという質に入っている。
俺は自嘲の笑みを浮かべた。よくもまあここまで堕ちたものだ。
カジノから出たところで声を掛けられた。
そうして今、俺はここにいる。エリア51。いったいこれは何の冗談だ。
スカウトなのだと俺を拉致した連中は説明した。スカウトの割には借金取りと勘違いした俺に逃げる暇を与えてはくれなかったがな。何しろ問答無用にテーザー銃を撃ちこんできたぐらいだ。
連れて行かれた先の軍事基地のブリーフィングルームは大勢の人間で賑わっていた。その中に俺は顔見知りを何人も見つけた。いずれも賭け事で食っている連中だ。
ポーカーのチャンピオンであるアリ・ハルマン。
賭博なら何でもござれ、最年長と言われるジャック老。
世界中のカジノに出没する大金持ちのザハン・トールマン。
賭けビリヤード専門のマッカート。
いずれも一癖も二癖もある連中で、最近では遠くから俺の顔を見ると避けるようになった連中だ。理由はもちろん近づくと不運が遷るから。
軍服を来た男が部屋に入って来るとプレゼン台を叩いて注目を集めた。
「みな聞け。私はアンドレア宇宙軍大将だ」
宇宙軍といえば比較的最近独立した新しい軍事部門だ。
「私はいま世界中の人々、政府、国際機関を代表して話している。これから聞かされる話は機密に属し、この話を聞いたものは一定期間の拘束を余儀なくされることを了承して頂きたい」
「俺は聞きたくないぞ。ここから出してくれ」聴衆の一人が怒鳴った。
「却下する。ここにいる諸君はこれから私がする話を聞く義務があるし、他の選択肢を与えることはない」
聴衆からブーイングが上がったが、アンドレア将軍が拳銃を抜いて一発撃つと静かになった。天井から砕けた天井板の欠片が落ちる。鍛え抜かれた軍人のみが成せる、実に正確で揺るぎない射撃だ。
「ご清聴に感謝する。さて、三十年前のことだ。スニア博士という人があるプログラムを開発した。そのプログラムは世界中の情報を統合し、これから世界がどうなるのかを予測するための、自己進化型の未来予測システムであった」
博士が作り上げたこのシステムは折からのコンピュータ技術の進歩に合わせて精度を増し、やがて世界中の未来を恐ろしく正確に予言するようになった。もちろん大地震の発生などの突発的自然現象の予測は無理だが、人間世界の経済、政治体制の移行などは完全に予測と一致していた。
だが機械の能力が上がるにつれ、予測される未来は遥かに先までもが提示されるようになった。最終的に提示されたのは『人類の破滅』であった。
予測を分析した結果、一番大きな問題は資源の枯渇、次に致命的な疫病の流行、さらには政治の混乱と予想される二度の世界大戦。最終的にこれらはすべて人類文明が限界点に達した証拠なのだと結論が出た。実際のところどんな文明種族でも同じ壁にぶつかるのではないかと結論づけられていた。
その限界点は百年後。百年後にあらゆる災厄と混乱が噴出して人類文明は消滅する。人口は激減し、地球全体で十万人も生き残ればよい方だと演算された。そして資源を使い尽くした以上、もう二度と文明が発展することはないとも。これは事実上の人類の死刑宣告であった。
会場が静まり返った。
「質問いいかね?」
ジャグリング・ポールと呼ばれるギャンブラーが手を挙げた。ジャグリングが趣味という変わった男で、天才的数学者だと聞いたことがある。その数学能力を使って正確な確率計算でギャンブルを進めるのが彼のスタイルだ。
「未来がそこまで正確に予測できるなら未来の修正はできないのかね?」
「多少の修正はできる。そのために開発されたシステムだからな。実際にそれである国の政治体制を崩壊させることもできた」
べろりとアンドレア将軍は暴露した。それはここでの会話が絶対に外に漏れることがないことを確信している証拠でもあった。
「だがそれでもほんのわずか未来予測を変えられるのが関の山だ。未来に対する様々な対策案が講じられたが、どれもこの破滅の予言を覆すことはできなかった」
アンドレア将軍は続きを話し始めた。
ここでもう一つの発見が我々のものになった。新規に打ち上げた天体観測衛星がバースト通信を受信したのだ。発信元は宇宙の彼方。
調査の結果、ペルセウス腕にある種の星間文明があるのではないかと推論がついた。更なる調査の結果、それは恒星二百個の領域にも渡る巨大文明であることが判明した。
「我々はメッセージの内容を解読した結果、それがある種の超空間航法について述べているのではないかと考えた」
「それが私たちに何の関係が?」とジャグリング・ポール。
「彼らは募集しているのだ。新たに自分たちの庇護下に入る文明を。そのために超空間航法の秘密を洩らし、ある座標を提示している。むろんこれがある種の罠で、未熟な星間文明を見つけ出し攻撃することが目的ということもある。だが我々人類にはもう後がないのだ。ここで何らかの膨大な技術的支援が無ければ百年後には人類文明は崩壊する」
アンドレア将軍が何かを操作すると壁に映像が映し出された。
「我々はあらゆる資源を投入して宇宙艇を二十隻作った。どれも超光速航行システムを搭載している。一隻につき乗員は三人が乗れる」
俺たちは画像に魅入った。宇宙艇はどこかのSFに出てくるような流線形ではなく、楕円形をしている。半分が半透明な素材で、半分が銀色の素材で覆われている。
「多くの資金と人命を消費した。これがその結晶だ。その結果、人類文明の終焉は十年ほど縮まったが、どのみち後がないのだから構わないと我々は考えた」
「どうして二十隻も?」
ジャグリング・ポールは引かない。さすがに数学者だけはある。
「あらゆる実験と研究の結果にもよらず、超光速航行は不安定だ。一度の超空間ジャンプで半数は脱落する」
「脱落?」
「つまり消えるのだ。超空間から出てこない。あるいは出てきたとしても計算外の見つからないような場所に出ているものと思える。ジャンプの成功率五十%。これが我々の技術の限界だ」
部屋が静まり返った。それにはまったく注意を払わないでジャグリング・ポールは質問を続けた。
「その星間文明にコンタクトできる位置にたどり着くまで何度のジャンプが必要なのだね?」
「十回だ」アンドレア将軍は言い淀みもしなかった。
今度こそ本当に静まり返った。しばらく経って絶句していたジャグリング・ポールが示唆した。
「二十隻飛んだ中で一隻でも到着できる確率は二%程度ということになるな」
アンドレア将軍はその言葉に頷いてみせた。
「超空間航法は完全なギャンブルだ。何を改良してもこれ以上成功率は上がらない。
だが実験中に奇妙な性質が観測された。ジャンプ成功率はジャンプ装置のトリガを引く人間の運不運に大きく左右されるのだ。
それがどういうメカニズムで発動するのかは分からないが、その事実だけで我々には十分だった。
その現象を元として、現存するギャンブラーの中で一番運が良い連中を搭乗させ、超空間ジャンプのトリガーを引かせるという案が浮上したのだ」
会場が騒めいた。
「静かにしろ!」アンドレア将軍が怒鳴った。「諸君には必ず協力してもらう。断れば機密保持のために一生涯の期間を軍刑務所の独房で過ごしてもらう。参加してなおかつ任務を成功させた暁には莫大な賞金が与えられる」
将軍はその金額を口にした。俺が耳を疑ったぐらい確かに莫大な金額だ。
十回だけ、勝率五割のギャンブルをやればいい。その内一回でも負ければ命を失うという条件つきで。
「どうして今なんだ。もっと技術レベルが上がってから」そこまで言ってからジャグリング・ポールは自分の額を叩いた。「ああ、そうか。資源を使い尽くした後で技術流入があっても無駄ということか。未来を変える分岐点は今しかないのか」
「そういうことだ」とアンドレア将軍。
「あのう」誰かが手を挙げた。驚いたことにそれは俺だった。「どうして俺が。俺はいま物凄く不幸のどん底でどんなギャンブルでも負けるのだが」
それに答えたのは富豪ギャンブラーのザハン・トールマンだ。恰幅のよい紳士で彼のギャンブルの種銭は底が知れないと言われている。
「すまん。私が推薦したんだ。ほら、ギャンブルってのはちょっとしたことで運が天井からドン底までくるくると変化するだろう。だから運の良い人間たちだけではなく、ひどく運が悪い人間も選ぶべきだって私が提唱したんだ。たまたまそれが君だっただけで。すまん。他意は無いんだ。もちろん君には断る権利がある」
「それで俺がもし断ったら?」
「むろん独房行きだ。例外はない」アンドレア将軍が断言した。
俺は席に座りなおした。確かによくよく考えてみれば俺にはもう何も失うものはない。俺と一緒に飛ぶ乗組員には気の毒だが。
「以上が私が話してよいすべてだ。技術や扱いについての詳細は後程紹介されるコンパニオンたちに聞いてくれ。
さて、全員志願してくれたとみてよいのかな?
自分は軍刑務所の独房の中の方がよいと思うものは今言ってくれ。言っておくがそこでの生活は退屈なだけでそれほど悪いものではないぞ」
ひどい冗談だ。だが誰も手を挙げなかった。ギャンブラーだって命は惜しい。だが勝っているときのギャンブラーというものは、自分だけは何があっても最後には勝ち切って終わると信じている間抜けな生物なのだ。
こうして俺たちの命賭けのギャンブルは始まった。
*)
その日から俺たちは長く厳しい訓練を受けた。
・・とは言わない。出発の日まではわずかに三日しかなかったからだ。宇宙船の準備と乗組員たちの訓練はとうの昔に終わっていて、後は俺たちギャンブラーの訓練だけという話だった。
ギャンブラーがやることはジャンプボタンを押すだけなので、特に訓練は要らない。その代わりにやってはいけないことを片っ端から頭に叩き込まれた。
空調システムのボタンに触ること。これはやってはいけない。
操縦機器に触れること。これはやってはいけない。
エアロックの周りで遊ぶこと。これもやってはいけない。
無重力下でコーヒーを噴き出すこと。知らない配線配管を踏んづけること。まるで押してくれと言わんばかりに明滅する正体不明のボタンを押すこと。あんなこと。こんなこと。これらは全部やってはいけない。
もう頭にきて、それなら何をやっていいのかと訊いてみたら、初めて教官は押し黙った。結局、俺たちがやっていいことは何もないってことだ。ジャンプボタンを押すこと以外は。
夜は皆でレクリエーションルームに集まり雑談をした。
軍の強制的なやり方にもっと反発するかと思ったが、皆驚くほど協力的だった。おそらくは楽観視しているのだ。ここに居るのは俺を除いていずれも絶好調のギャンブラーたちだ。生き残る確率はわずかでも、それをうまく掴むのは自分だと心の底では信じている。この地獄から帰って来たときに貰える莫大な協力金の使い道で頭がいっぱいなのだ。
そんな中、富豪ギャンブラーのトールマンが俺に近づいて来た。他のギャンブラーは運が落ちるからと俺の傍に近寄ろうともしないのに。
「君に一言だけ言っておきたくてね」トールマンは鼻を掻きながら言った。「ここにいる皆は徴募兵だが、私だけは志願兵でね。軍から最初に相談をされたのは私なのだよ。他のギャンブラーを名簿に載せるのも手伝った」
「そいつは驚きだ。で、どうして俺の名前がその名簿に?」
「君には悪いと思っているんだよ。ほら、こういった運の強い者たちが競っている中にな、運の悪い者を放り込むとどうなるのか。その場の悪運のすべてがその運の悪い者に集中する。つまりは悪運に対して拭き取り用のスポンジのような働きをするわけだ」
しばらく考えた。この場でこいつを殴って良いものかどうかを。
「そういうわけでよろしく頼むよ」
俺の殺気を感じ取ったのか、それだけ言うとトールマンはそそくさと消えた。
何がよろしく頼むだ。宇宙船が飛び立つ前にこいつだけは殺そうと心に決めた。どこかで拳銃を手に入れねば。
なに、そう考えただけで本気じゃないさ。
次の昼からは自分が乗る宇宙船のクルーに引き合わされた。一機の宇宙船に正規の乗組員は二人。俺の場合はパターソン船長とブエン副長だ。パターソン船長は短いあご髭を生やした精悍そうな筋肉質の三十台の男で、それに比べてブエン副長は小柄なベトナム人の男だ。
「よろしく頼むぞ」とパターソン船長。彼は快活で陽気な性格だ。
「隠し事なしで言う。うちは貧乏くじを引いたと考えている」
パターソン船長はにこやかな顔で冷たい氷のようなセリフを吐いた。
「まず機体番号が不吉な十三番だ。当局もこれは気にしたらしく欠番にしようとの声も上がったがな。結局そのままになった。それとキミだ。キミは今一番ついていないギャンブラーという話だが」
「その通りだ」
隠しても仕方がない。それに俺の運にかかっているのは彼らの命だ。
「ちょっと試してみてもいいかな?」
「何を?」
単純なゲームをパターソン船長としてみた。トランプのカードをそれぞれ一枚引き、その数字で勝負するというものだ。完全に運任せのゲームで、賭け金は一回一ドル。
十回勝負し、俺は十回とも負けた。自分でもここまで運が落ち込んでいることに唖然とした。
「これではジャンプボタンは私が押した方がよさそうだな」
「そうしてくれ。俺は宇宙船の隅っこで大人しく座っているよ」
話はそう決まった。十ドルはきっちりと支払ったよ。俺は借金でギャンブルはしない主義でね。
夜は用意されたラウンジでのんびりと過ごした。もっとも俺は仲間には入れて貰えなかったが。とかくギャンブラーというものはツキにはうるさい。不運に見舞われている者には触られるどころか言葉を交わすのもタブーだ。
グループの中心にいるのは富豪ギャンブラーのザハン・トールマンとポーカーチャンピオンのアリ・ハルマンだ。この二人は知名度が抜群なので不思議はなかった。
異彩を放っているのが通称ジーザス。こいつは風貌がどこかの救世主にそっくりだ。ギャンブルのスタイルもそれに合わせて勘に任せたもので、しかもそれが実際に良く当たる。一部のファンから熱狂的な支持を受けている謎の男だ。
ジェーン・タイロンはこのメンバーの中で唯一の女性だ。髪は短めのブロンド、年齢は三十五ぐらいに見えるが詳しいことは判らない。いつも素気ない化粧でカジノテーブルに座っているという印象だ。
他にも癖のある奴らがずらりと揃っている。これを全部どこかのカジノから拉致してきたとすれば今頃はどこのカジノも噂話で持ち切りだろう。
三日間は特に何ということもなく過ぎたが、その間にいくつかの事件が起きた。
ジーザスは自分が乗る船体の番号に「1」という文字を描き加えた。
元の機体番号と合わせて、これで「111」になる。つまりは聖なる番号トライユーン「三位一体」だ。なんと芝居がかっていること。いや、それともジーザスは本気で自分を神と考えているのか。まあ確かに十戒の中には、汝賭け事をするなかれ、は入っていないからな。
9番艇に乗るはずだったギャンブラーはこの三日の間に心臓麻痺で死んだ。これには軍当局も慌てたようだったが、今さらどうにもならないので9番艇はギャンブラー無しで飛ぶことになった。俺を9番艇に移籍するという話も持ち上がったが9番艇の乗組員たちに断られた。顔には出さなかったが俺は深く傷ついた。
止せばいいのに乗組員たちは6番艇担当のニコ・S・ハイネにカードで挑戦し、有り金すべてを持っていかれた。当然と言えば当然だ。ニコはトランプの魔術師と呼ばれるほどの凄腕だ。監視カメラ以外ではニコのすり替えを見破ることはできない。
そうこうしている内に出発の期日が来た。
*)
超空間航行艇、略してHSSは楕円球体の形をしている。前半分は居住空間、後ろ半分は跳躍用のメカニズムで埋まっている。こいつは超空間ジャンプを行うためのものなので普通の宇宙船に見られるロケットエンジンの類はついていない。せいぜいが姿勢制御用のミニロケットぐらいのものだ。居住空間は結構広いが、これは乗員のためというよりは単に駆動部が大きいためそれに引きずられて大きくなっただけだ。
俺はパターソン船長とブエン副長の後をついて宇宙艇に乗り込んだ。二人は俺をこのまま置いてけぼりにしたがっていたし、俺もそうして欲しかったが、軍上層部はそうは考えなかった。
パターソン船長がジャンプボタンの前に座り、ブエン副長が操縦席に、そして俺が副長席に座った。ブエン副長はシートベルトで俺をきつく固定した。
「いいか、何があっても何にも触るな。お前が触っていいのは自分のナニだけだ」
「そんな言い方していると石鹸で口を洗われちまうぞ」
「ブエン。くだらん冗談を言うな。俺たちはこれから長い間一緒なんだぞ」パターソン船長が割って入った。
「はいはい」ブエン副長はそれだけ返すと計器類のチェックに入った。
「オールグリーン。異常なし」
操縦席のスイッチを押す。スクリーン上に表示された二十の絵の一つが明るく光った。操縦席から見える外の光景に残りの乗組員たちが次々と宇宙艇に搭乗する姿が見えた。
ジーザスが11番艇の外に描かれたトライユーンの数字にキスをすると、彼の乗組員たちの上に何かの祝福の儀式をしてから乗り組む。
おやおや、教祖さまはもうファンを獲得したらしい。
二十の輝点がすべて明るく輝く。準備はすべて整った。
スピーカーから号令が轟いた。
「ジャンプ・イン!」
パターソン船長が復唱し、それから勢いよくジャンプボタンを叩き込んだ。
外の光景が瞬時に黒に切り替わった。次の瞬間には宇宙艇は星空の中に浮かんでいた。もっとも俺は外を見る余裕はなく、まるでジェットコースターで滑り落ちているかのような強烈な下腹の感覚に耐えていた。いきなりの無重力状態だ。訓練されていない体は落下しているものと勘違いする。
パターソン船長が怒鳴った。
「しばらく我慢しろ。チェックが終わったら艇に回転をかける。いいか、吐くなよ。吐くと大変なことになる」
「判ったから早くしてくれ」俺はそこまで言うのが精一杯。
「1番確認、2番確認、3から8番まで確認、10から13番まで確認、15、17,19番確認」
ブエン副長が読み上げる。そこでしばらく間が空いた。
「20番来ました」
それで最後だった。
「ジャンプ成功したのは十六隻か」とパターソン船長。「残りは死んだかそれとも」
そこで彼の言葉は尽きた。
「きっと到着したのは天国ですよ」ブエン副長が相槌を入れた。
「そう願いたいものだ」
俺は何か気の利いたことを言おうとして、それから止めた。四隻の船が消え去っている。ギャンブラー同士は単なる顔見知りのケースが多いが、彼ら乗組員たちはお互いに友人だったのだ。その喪失感は計り知れないものだろう。
その夜、ディスカッションが行われた。
一回目のジャンプの成功率は八十%だ。本来の成功率は五十%が限界という話なのでギャンブラーの起用は成功だったという結論に落ち着いた。
消滅した艇についても議論は行われた。
9番艇は搭乗前にギャンブラーが心臓麻痺で死んだ艇だ。何かを暗示していたのだろうか。
14番艇はコンピュータ技術者のディビット・イーロック。副業でギャンブラーをやっている男で凄腕のメカニック、つまりイカサマ師だ。運に関係ないギャンブルをする人間がどうしてこの作戦に選ばれたのかは謎だ。もしかしたら俺と同じ理由でトールマンに選ばれたのかもしれない。
16番艇はハンサムなウィーリー。ギャンブルの腕というよりはカジノを訪れる欲求不満の女性客を落とすことを専門としていた男だ。
そして18番艇はニコル・ティールセン。本業はレーサーでギャンブルはただただスリルを求めてやっている破滅型の思考をしていたヤツだった。
彼らすべてが虚空の闇の中に消えた。超空間から出てこなかった艇がどうなるのかは追跡する手段がないのでまったくの不明だ。どこかの太陽の中に飛び出たのかもしれないし、あるいは超空間を未だに漂っているのかもしれない。そこで食料と酸素が尽きるまで耐え続けるのだ。
あまりにもぞっとしない死にざま。医薬品の棚にドクロマークのついたビンが混ざっている理由を俺は理解した。
*)
俺たちはそこで一週間の待機に入った。その期間を利用して宇宙艇の後部では小型原子炉が全力でエネルギーを作り蓄電器に蓄えている。一回の超空間ジャンプで蓄電器はほぼ空になってしまうので、ジャンプのたびに一週間の待機期間が必要になる。その間、宇宙艇は孔雀の羽のように放熱フィンを広げて、原子炉が生み出した熱を宇宙空間に捨てている。
宇宙艇にはゆっくりとした回転がかけられ、地球の重力の二割程度の重さを作りだしている。正確には重力ではなく遠心力だそうだが、細かいことはどうでもいい。お陰で俺はようやく吐き気から解放された。窓の外でぐるぐる回っている星のことはできるだけ考えないようにする。もっとも船外モニタは補正されているので、回って見えるのは直接観測窓だけだが。
宇宙艇は周囲を観測し、パルサーを見つけ出すと銀河系の中での自分の位置を算出した。パルサーってのは規則正しく電波を発射し続ける天体だ。その周波数は正確で揺るぎない上にパルサー毎に異なっている。だから宇宙空間では灯台として使うことができる。
宇宙艇の観測装置はすべて自動で動き、パルサーを見つけるとその位置関係から自分の位置を算出するようになっている。超空間ジャンプのたびに星空の形はすこしずつ変わるので、こうしないと宇宙の中で迷子になってしまう。
まあ、これらはすべてブエン副長の説明の受け売りだがな。
「一回のジャンプで計算通りに二百光年を飛んでいる」暇ができたブエン副長が説明してくれた。「これを後九回繰り返せば目的地だ」
俺は船外を見た。煌めく星々、その間を支配する漆黒の闇。他の宇宙艇は肉眼では見えない。一応小さなパイロットランプの灯りはついているし、操縦席からも光は漏れているはずだが、相当に注意しないとその存在には気が付かない。
俺たちは何てちっぽけな存在なんだ。しみじみとそう思った。
時間があったので皆と色々と話しあった。他の宇宙艇の連中も含めての映像通信機を使った大セッションだ。
「向こうに行くのはいいが彼らは本当に助けてくれるのかな」
そう言ったのは3番艇のギャンブラーのファドだ。彼には特にあだ名はついていない。最近急にのし上がってきた人物で、他のギャンブラーからは強運だけの男とみなされている。つまりはやがて運を使い果たして消えていく類の人物だ。ギャンブラーに運は必須の属性だが、不運の時期をやり過ごすだけのテクニックも必要になる。彼にはそれが欠けている。
「助けてくれると思う。私の推論では」と数学者のジャグリング・ポール。
「わざわざ超空間ジャンプの情報を明かすのがその証拠だ。自力で超空間ジャンプ機構を作り上げ、危険を顧みずにやってくる。そんな種族を求めているんだ。単に新しく隆興した技術文明を見つけて処分しようという意図ならもっと効率のよいやり方がある」
「わからないぞ。単にそうやって遊んでいるだけかもしれぬ」この中で最年長のジャック老が混ぜ返した。
現役のギャンブラーに高齢者は稀だ。ギャンブルに必要な高度の集中力が老人には支払えないからだ。ジャック老は相当な高齢にも関わらず未だ引退していないことでも周囲から一種の敬意を持って扱われている。
「しかしいずれにしても俺たち人類には後はない」アルト・ドアル・Jrが続けた。
彼は闘犬ブリーダであり、また自分でも闘犬ギャンブルにどっぷりと嵌っている。やれやれ、軍の連中ときたら手あたり次第に候補者を集めたようだ。
ジャンプから三日後、死んだ連中の慰霊祭が行われた。
ジャンプ船での死は派手な爆発も何もなく、ただ超空間から現れないだけだから死の実感が乏しい。もしかしたら到着しなかったのは、死んだのではなく何らかの故障によりジャンプしなかっただけなのかもしれない。だから来なかった連中と死が結びつきにくい。それでも時間が経つと死の実感がわくものだ。その結果がこの慰霊祭だ。
乗組員の一人が紙を使って作った花束を宇宙空間に投げ、俺たちは各宇宙艇の操縦席で黙祷をした。ギャンブラーのジーザスが祈りの言葉を唱え、彼らの魂を祝福した。
超空間にまでこの祈りが届けばいいのだが。
残りの期間はトールマン主催での大ギャンブル大会だ。といっても宇宙艇の間を行き来するのは大変に面倒なので映像通信でのギャンブルだ。トールマンがディーラーをやり、他の艇の連中が賭ける。俺は参加しなかったがパターソン船長たちも参加した。その結果、パターソン船長は冷徹で合理的な判断をすることが判ったし、ブエン副長はとうてい勝ち目のない勝負にも果敢に挑戦することが判った。
賭け金はミッション成功時の報酬から払うことになっていた。だから彼らが賭けた金額ときたら、まるで現実感の無い額になっていた。生涯賃金を遥かに越える金額がポンポンと飛び交うのだ。傍で見ていても現実感の無さに思わず笑ってしまった。
本当にギャンブラーってのは愛するべきクズどもだ。
*)
いよいよ二回目のジャンプの日がやってきた。
今度もパターソン船長がジャンプボタンの席に座った。心無しか顔色が悪い。緊張のせいか額に汗が浮いている。
タイムアップ。機械音声が叫んだ。
「ジャンプ!」
俺は副長席でモニタを睨んでいた。まず最初に消えた光点は11番艇ジーザスの船だ。続いて二番目三番目が飛ぶ。
パターソン船長は強く奥歯を噛みしめると、ボタンを叩き込んだ。
キャノピーの外の光景が瞬いた。星空が映っているのは変わらないが、一瞬で星の配置が切り替わったせいだ。
ブエン副長がモニタの報告を読み上げる。
「1番確認、4、5、7番確認。あ、いま6番来ました。11、12番確認」しばらく間が空いた。「17、19番確認」
沈黙があった。
「終わりか?」とパターソン船長。その肩ががっくりと落ちる。
「20番来ました」ブエン副長が最後の報告をした。「総勢十一隻来ています」
「ここまでで半分脱落か」椅子に深く腰掛けてパターソン船長がつぶやく。「予想よりは遥かに良い、しかし希望よりは遥かに厳しい。後八回ある」
そこから先は俺たちは無言だった。
ポーカーのチャンピオンのアリ・ハルマンは二回目のジャンプを生き延びることができなかった。彼は富豪ギャンブラーのトールマンと袂を分かつグループのリーダーだったからギャンブラーたちもひどく静かになってしまった。
最年長のジャック老も無敵のディーラーのハン・ホフマンも消えた。
今回も三日目に慰霊祭が行われ、その後ジーザスの下に大勢の人間が詰めかけた。その中には慣れない宇宙服を無理して着込んだギャンブラーたちも混ざっていた。ここまで来て初めて、このギャンブル航行の恐ろしさが実感できたわけだ。
苦しいときの神頼みとは言うが、それを笑えないだけの切実さがそこにはあった。驚くべきことにパターソン船長の姿もその中にあった。
船内時間の深夜に行われるギャンブル大会で、初めてこのまま地球に帰ろうと主張する者が現れた。それならジャンプは後二回で済む。生き残る確率は前に進むよりは存外に高い。だが実際にはそれは無理であることが指摘された。軍当局はそういうことができないように、最初から引き返せないようにシステムを構築していたからだ。
遠い宇宙空間にいる「彼ら」に出会って地球に送り届けて貰う以外に地球への帰還の方法はないのだ。