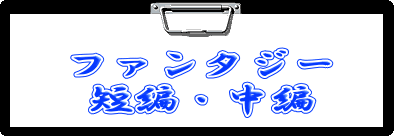
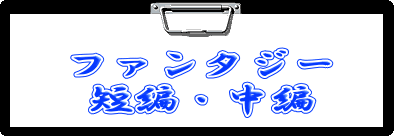
1)
豪華な調度で整えられた部屋の中でニューヨークの吸血鬼の女ボスであるリビアは長い黒髪を揺らしながらうんと大きく背伸びをした。
見事にバランスの取れた体形を基とした滑らかな姿態。透き通るようなやや青みが見て取れる真っ白な肌。完全な形の顎に続く滑らかな白く細い首が蠱惑的に強調される。その肌に触れることができる喜びを男なら誰でも夢見ることだろう。女ならなおさらだ。ただしその望みはこの肌を剥ぎ取って自分のものと入れ替えることができたらなというものだ。
リビアの動きにつれて、その首に巻かれた美しい宝石のネックレスがその妖しげな輝きを強める。中央に大きな名も知れぬ八十一面体にカットされた宝石。その周囲を彩る七つのそれぞれ異なる宝石たち。それらはまるで自ら発光しているかのように見える。魔力の渦に包まれてまるで意思あるものかのように次々と色を変え、主人の姿をさらなる輝きで飾る。
美の化身たる彼女の体はこの世で最も貴重な売り物である。だからその体を買うことは可能だ。
その金額は一晩につき一億ドル。
だがそれでも夢のような一夜のためにその金額を喜んで払う者は多い。それと同時に購入者は己の血の一部も捧げることになる。その代価の意味も知らずに。
豪華なソファに寝そべっているリビアの前で、床に頭を擦り付けている男がいた。そんな姿では着ている高価なビジネススーツが台無しだ。
リビアの横にはボディガードが二人立っていて油断無く機関銃を構えている。プロだけに目の前で這いつくばっている男に対しては何の感情も見せない。それに装填されている弾は普通のものではない。銀の弾丸から聖水を仕込んだガラスの弾丸まであらゆるものが入っている。どんな魔物に襲撃されてもそれなりに戦えるようにだ。
這いつくばっている男に向けて、ほとほとウンザリしたという口調でリビアが口を開く。口紅を塗ったわけでもないのに常に真っ赤に染まった唇が淫らに踊る。
「モーリス。いい加減にしつこいわよ。貴方は今月分の上納金を払っていない。だから吸血侍従契約はお終い。ここには貴方の席はないの」
モーリスと呼ばれた男が顔を上げた。かなり年配の老人に見えた。
「お願いです。リビア様。私の財団は破滅したのです。もう差し上げるお金はないのです」
「では私たちの契約も終わり。もともと私の派閥と貴方とはそういう関係だったでしょ?」
リビアは冷たい声で返した。
「そんな。これだけの長きに渡って忠誠を尽くして来たのに」モーリスは抗議する。
「その代わりに貴方には不老長寿を上げたわ。さあ、お行きなさい。モーリス。ひどい顔よ。分かっていると思うけど貴方の時間は尽きかけている。残された時間を大事にしなさい」
「だからこそ。リビア様。お願いです。血の膏薬をください」
「ダメよ。もう貴方の席に次ぎに座る人間は決まっているの。バートラム卿よ」
それを聞いてモーリスの顔が歪んだ。
「あ・・あの成金。あんな俗物!」
「それでも彼は入札であなたの席に千億ドルの値を付けたのよ。大事な空席を空けておくわけにはいかないの」
「お願いです。主よ」
「しつこい」
リビアの頬に怒りの赤みが差した。
この瞬間モーリスの命は天秤の上に載せられていた。半吸血鬼とは言えモーリスはリビアの子に当たる。吸血鬼社会では子殺しは禁止されているわけではないが、それでも眉を顰められる行為だ。ただその慣習だけがリビアの怒りからモーリスを守っている。
部屋の奥のドアが開き、ボディガードの一人が入って来た。
「女王様。ハインズ様からお電話が来ております。秘匿回線なのでこちらに回せません」
「後にしてって言っておいて」リビアが振り向きもせずに答える。
「それが火急の用との事です」
リビアは考えを変えた。
「いいわ。すぐに出ると答えておいて」
渡りに船だ。この鬱陶しい状況を終わりにできる。
ネックレスを首から外すと、ソファの横の扉を開きそこに納める。それは金庫に見えない金庫だ。ネックレスが収容されると金庫は自動的に閉じロックがかかった。これで特殊合金製の金庫はパスワードが入力されない限り開かなくなる。
リビアはまるで重力を感じないかのように軽やかに立ち上がると薄いガウンを靡かせながら謁見室を出た。
背後でモーリスが伏せていた顔を上げた。その眼がぎらりと光る。
長い電話が終わり、リビアが謁見室に戻って来ると、部屋に残っていたボディガード二人が床に倒れていた。モーリスの姿は無い。
ガスの匂いを嗅ぎ、リビアがその整った眉を顰める。麻酔ガスと判断する。吸血鬼は薬物に強い抵抗力があるのでこの程度は問題がない。
はっと気づき、ソファの金庫を開ける。
そこが空っぽであることを知り、彼女は咆哮した。
女王の叫びを受け、奥の間にいた配下の吸血鬼たちが飛びこんでくる。
リビアの手がテーブルの上の通話機を叩く。
「モーリスはどこ!?」
全フロアを統括する監視室から返事が戻る。
「モーリス様なら10分前にお帰りになられました」
「どうして止めなかったの!」
「マダムからのご命令が無かったからです」
「モーリスが盗むところを見ていたでしょ」リビアは言った。その音声には普段彼女が絶対に見せないものが含まれていた。
震える声で監視室からの抗議が返る。
「失礼ですがマダム。謁見室には現在監視禁止命令が出ています。これは他ならぬマダムご自身の指示です。モーリスに死告げる姿を誰にも見せたくないとの意向でした」
それを聞いて再びリビアが咆哮した。吸血鬼にだけ聞こえる超音波の命令がビル中に満ちる。
フラット内に居るすべての人間の運命がこの時点で決定した。
2)
その日は朝から騒がしい日だった。
まず対策局の魔術部門で爆発があった。
原因はご想像通りに新入りの魔導士のアーダラクだ。
前回の事件以来、彼は特例で対策局魔術部門に所属することになった。最初は大昏睡事件の犯人として冷たい目で見られていたが、その恐るべき魔術の腕でたちまちにして対策局所属の魔導士たちの心をつかみ取った。つまり全員を弟子にしてしまったのだ。
最初の頃はバチカンの裏古文書庫に入り浸っていたが、やがてそこにある禁書以外のあらゆる文書を読みつくしてしまったらしく、ふたたび新しい魔術の実験に戻った。
その結果が朝の爆発だ。幸い人死には出なかったが召喚されて暴走した魔獣たちが対策局のあらゆるオフィスを駆けまわった。その狩り出しに対策局の全員が動員される羽目になった。
ここまではまだ神学生たちのよい訓練になったから、終わりよければすべて良しとも言える。
魔獣の暴走の中で一番まずかったのは大型魔獣の一体が共用オフィスに飛び込んだことだ。そいつはアナンシ司教の大理石テーブルの上のゲーム盤に突っ込んでしまった。
アナンシ司教の本物の怒号を皆は初めて聞いた。
それでもオフィスの窓はヒビが入るだけで済んだ。ロケット弾でも破壊できない最高グレードの防弾ガラスという謳い文句は嘘ではなかったと証明されたことになる。
こういったわけで部屋中に飛び散ったゲームの駒をすべて回収するまで共用オフィスへの立ち入りは禁止された。
アナンシ司教はこう宣言したのだ。ガラスの駒を踏みつけて壊した者は、私がそいつを直々に壊すと。こうなるともう誰も怖くて部屋に足を踏み入れることができない。
不思議なことに魔獣の死体はどこにも見つからなかった。きっとアナンシ司教に食べられてしまったのだと皆は結論した。
次に来るのはアーダラクの監督官である私が呼び出されて説教されることだと予想して、私は自分のオフィスに閉じこもった。
そこで神へ祈りを捧げる真似事をしていると窓を何者かがノックした。
悪意がある者は対策局周辺の保護結界を越えることはできないが、あの腐った魔神の例もある。警戒は怠れない。
恐る恐る窓を開けると、外に居たのは人間の子供ほどのサイズの小さな天使で、一般に智天使ケルビムと呼ばれている存在だ。そいつは小さな翼をはためかせて宙に浮いている。
ケルビムは普通に人が想像するような子供の天使ではなく、体が小さいだけで性器もちゃんと大人に遜色ないものがついている。当然というかそれはきちんと服を着ている。やはり白を基調とした天国の最新モードだ。
この天使一体で人間の軍隊の最新装備一個小隊に匹敵する力があると聞けば驚くだろうか?
「やあ、君はどこの子かな?」私は訊いた。
基本的にケルビムは上位天使のお遣いが仕事だ。
「アリエル様配下のボルマンと言います」
それは自己紹介した。
「アリエル?」彼が私に伝言とは珍しい。何事も控えめな大天使なのだ。
「いえ、あのお方の遣いではありません。今回はマドウフ・ベイル様に依頼されたのです」
光の精霊マドウフ・ベイル。
なるほど、精霊たちは召喚されない限り天界都市からは出て来たがらないので、手近にいたケルビムにお遣いを頼んだということか。
「これです」
ケルビムはどこからか大きな写真本を出して来た。なんとそれは高級家具カタログだ。
それも一般的なカタログではなく、セレブたち専用の目の玉が飛び出るほど高い家具が並んでいるものだ。一般人はこの本を見ることもできない。極めて限られた数だけが出版されているカタログだ。
「マドウフ・ベイル様はこの本にしおりを挟んでおりました。そのページに伝言が書き込んであるそうです」
賢明にもケルビムは中を覗かなかったようだ。本来の職務以外のことに深入りしないのは褒めるべき性質だ。
「分かった。ご苦労様。他になにか無ければ帰っていいよ」
あまり長い間天使と話をしていると必ず誰かが目撃してしまう。要らぬ危険は冒すものではない。
一礼してケルビムが消えると私はカタログを開いた。
天使たちはこういった地上のアイテムをたまに天界に持ち帰る。彼らの仕事の大部分は地上界の監視だからだ。マドウフ・ベイルはそういった鹵獲品の一つに目を止めたのだろう。
本に挟まれていたしおりは光でできた木の葉っぱだった。輝く葉脈でできており、とても綺麗だ。しばらく眺めた後に私はそれを捨てずに神父服のポケットにしまった。芸術作品にはそれなりの敬意を表するべきだからだ。
しおりが挟まれていたページにはアンティーク家具が並んでいる。本物の骨とう品ではなく、それらに似せて現代の技術で精巧に作り上げた品だ。値段は要相談となっていたが、だいたいの金額は分かるようになっていて、それが一つで百万ドルを超えているのを知り私は絶句した。
まあ絶滅危惧種の樹木を始め、今では入手困難な材料をふんだんに使っていればそれも不思議はない。
ページの余白に文字が書き込まれていた。
しばらくその見慣れぬ文字を眺めていて、それが古代アラム語であることを思い出した。キリストの時代に使われていた古代文字だ。
しばらく集中して頭の中の『忘れじの花』の魔法を探す。ダークの時代に魔導士アーダラクが私の頭の中に組み込んだものだ。この魔法はいくつにも分けた記憶領域を別々に使えるようにしたもので、発狂することなく大量の記憶を保持できるようにしたものだ。
アーダラクは物覚えが悪い魔王というイメージを嫌ったのだ。
記憶が蘇るにつれて意味のない記号の羅列が目の前で変化し、意味のある単語へと変化する。
その内容はこうだ。
『ダーク。我が友よ。頼みがある。印をつけた家具を私宛に送ってくれないか』
おい。思わず独り言を言ってしまった。
まったく、都合が良いときは友達扱いか。だいたい精霊が家具をどうするというのだ。きっと私なんかには想像もできないような用途に使うのだろう。
おまけにクレジットカードの番号も書いていない。ということは代金は私持ちということか。だがまあ仕方がない。大概の精霊が世事に疎いのは当たり前だからだ。
幸いダークの時代にやった裏の仕事の代金がケスマイ島の秘密口座に使われることもなく残っている。
私はその内の一つを選び、電話で注文を出しておいた。
たしかこの口座は某国の政府議員の一人を暗殺したときに作ったものだ。警戒は厳重でおまけに魔物の一匹を人間に偽装させて護衛につけていた。だがダークの配下にとっては赤子の手をひねるよりも簡単な仕事だったのを覚えている。
神よ。ダークとその配下の魂を許したまえ。
家具は指定の場所に届けてもらえれば、後は深夜の内に天使たちが天界に運ぶだろう。精霊と天使はお互いに干渉はしないが、そう仲が悪いわけではない。
さて一段落がついたとコーヒーを入れていると外の廊下に二人分の足音がした。
ドアにノックがあり、返事をするとアンディがドアの影から顔を見せた。
「あの。マスター」
「何だ?」
天使が去った後で良かった。アンディたちに目撃されたらまた何か厄介なことになる。
「あのその」
アンディは隠していた右手を差し出した。その手は毛むくじゃらだ。
ああ、と理解した。
「その、魔法薬学の講義に出ていたのですが、そこに魔獣たちがなだれ込んできて」
アーダラクが呼び出したヤツだ。子供たちのいる講堂にまで侵入したのか。よく人死にが出なかったものだ。
「それで実験中の薬液がひっくり返って」
毛生え薬は合成が簡単なので魔法薬学の講義によく使われる。雪男の肝臓と水棲馬のタテガミの入手が難しいだけの単純な薬剤だ。
これを浴びた部分にはたちまちにして毛が生える。
「心配しなくても良い。一週間もすればすべて抜け落ちて元通りになる」
そうなのだ。この薬効の短さから結局は商品化できなかった代物だ。そうでなければ対策局の良い資金源になっただろうに。
「それがその」アンディは言い淀んだが、意を決してドアの脇に隠れていた人物を引っ張り出した。
全身毛むくじゃらの尼僧服の人間がそこに居た。見た目は雪男そっくりだ。
「まさかエマか!?」
毛むくじゃらの人物はわあっと泣き始めた。
「まともに頭から薬液を被ったんです」とアンディが後を続けた。
勘弁してくれ。こういうときは何と言って慰めればよい?
「取り合えず。アンディ」
「はい」
「彼女を浴室に連れていけ。それと安全カミソリと脱毛クリームを山ほど買ってきなさい」
実はそれはあまり効果がない。魔法の薬液の効果が切れるまでは、剃る端から次の毛が生えてくるのだ。
だが気休めでも何もやらぬよりはマシだ。そのうちにエマも諦めがつくだろう。
最期に被服部のマグダラ尼僧が無表情な顔で私の部屋を訪れた。マグダラ尼僧は取った歳月の分をすべて不愛想な皺だらけの顔に変えてきたような人物だ。
その手にしたトレイの上には綺麗に畳んだ私の神父服が載っていた。
彼女はそれを私の目の前で広げるとこう言った。
「取れないのですよ」
彼女はその老齢に合ったこれも皺だらけの手で神父服の表面を撫でた。
キラキラ光る何かがそこから舞い散った。
「これはいったい何ですか? ファーマソンさん」
声に抑揚は無かったが、それが彼女が激怒しているときの声だと私は知っていた。
「うっかりと他のものと一緒に洗濯したら、大変なことになってしまいましたの」
それは私のミスというよりご自分の専門領域に対する貴方のミスでは、と言いそうになって慌てて言葉を飲み込んだ。もう嫌な予感しかしない。
そこまで来てその光の粉の正体に気がついた。
天界で光の精霊マドウフ・ベイルが私に吹きかけた力の名残だ。人間の魔術では真似することさえできない純粋な魔力のきらめきだ。
「それは時間が経てば消えるはずです」かろうじてそれだけ言った。
彼女の眉が大きく上がった。これが彼女の攻撃モードの表情だ。
「確かですね? 神父。ただの言い訳ではないでしょうね?」
「本当です」
強烈な魔力の残滓は冷たい荒野の中の焚火だ。やがては散逸して消える。ただしその前に虫を引き寄せる誘蛾灯のように周囲のあらゆる霊を引き寄せてしまうが。
そのことは敢えて説明しなかった。
奇跡的にスマホからメールの着信音が鳴り、私は天の助けとばかりに飛びついた。
驚いたことに夜の吸血鬼女王リビアからのものだ。例によって短い一言。
「手を貸して」
その場で対策局を飛び出した。
3)
ニューヨークまでは旅客機で一本だ。時間はわずかに六時間しかかからない。
急ぎではないようだったので着いた日はバーで酒を飲み、因縁をつけてきた相手と軽く喧嘩をして、次の日は一日ぐっすり眠ってから夜にはすっきりした顔でリビアのフラットを訪ねた。
リビアはちょうど起きたところだ。八十一階の防弾ガラスの向こうに見える外の夜景が綺麗だ。
前回の悪魔たちの襲撃の痕跡は綺麗さっぱりと消えていた。それと警備員の顔ぶれがすべて入れ替わっている。
「やあ、リビア」私は挨拶した。
「いらっしゃい。ダーク」とリビアが答える。
リビアはいつも綺麗だ。高位吸血鬼は食事を選ぶ。その時代の美男美女の血を好んで飲むのだ。それを繰り返している内に、吸血鬼の容貌も犠牲者の資質を取り入れて美男美女に変化する。これは魔法生理学とでも呼ぶべきものだろう。こうして吸血鬼は時代毎に変化する美の基準にいつも追いつく。
「まだ警備の者は人間だけか。たまには人狼でも雇ったらどうだ? 吸血鬼の護衛には最適だぞ」
私の勧めにリビアはふふっと笑った。素晴らしい笑み。それを手に入れるためなら資産のすべてを投げ出す者も多い。
「あら。そのポストはあなたが職を探しに来たときのためにわざわざ空けているのよ」
それに対して私は片方の眉を上げて見せた。
「それは是非ともアナンシ司教に聞かせたいものだな。ヘッドハントがかかっていると知ればもっと私の扱いも良くなるだろうに」
それを聞いてリビアはまたもやほほ笑んだ。傾国の美女の微笑み。背後に毒を塗ったナイフを隠した者の笑み。
「いいわよ」
細く美しい手を伸ばすと電話機を取り上げた。美しく磨き上げた貝殻が全面に張り付けられている特注の電話機だ。
その指が『嫌な山脈』と表示されたボタンを押す前に、私は止めた。
アナンシ司教は今ゲーム盤の件で気が狂ったようになっている。わざわざ火に油を注ぐ必要はない。
しかし彼女はいったいどうやってアナンシ司教直通の電話番号を手に入れたんだ。いや、吸血鬼なんだ。どんな手段でも使うことができる。
「それより、リビア。私に何か用か?」
「お願いがあるの」
リビアはソファから身を起こした。黒く長い髪が水のように体を流れ落ちる。体を覆っている薄い絹の服の隙間からその真っ白な肌がときどき覗く。胸の完璧なる曲線がその存在を主張する。
思わずごくりと唾を飲んでしまったのは失敗だった。
悪戯な表情がリビアに浮かんだ。
「あら、ダーク。あたしはいつでも良いわよ」
もちろん、誘惑に乗るつもりはない。リビアが好きなのはかっての血と暴虐に満ちたダークなのだ。そして私は再びダークに戻るつもりはない。
私は十字を切って見せてから言った。
「父と子と精霊の御名において、この女性の誘惑から我を救いたまえ。アーメン」
ふんとリビアは鼻を鳴らした。まるで優しいベルであるかのような音。
「あら、言ったこと無かったかしら。あたし、救世主に会ったことがあるの」
初耳だ。考えてみればリビアは古い血を引く吸血鬼の女王だから不思議もない。彼女は二千年前にも生きていた。吸血鬼は加齢とは無縁なのでつい失念するがそれほどの歳だ。人狼も同じく長命種族だが、歳だけは極めてゆっくりと取る。
「じっくりと話してあげようか?」リビアは話を続けた。
父たる神が存在しないとしたら、その子たる救世主はいったい何者なのだろう?
疑問は尽きなかったが、ここで詳しく話を聞くのは間違いだと直感が告げた。彼女がその気になれば抵抗できる自信は私にはない。
「それよりも何の用か言ってくれ」
「そうね。そちらが先ね」
彼女はうんと背伸びをした。どんな動作をしても彼女は美しい。
「あたしのお大事のお宝が盗まれたの」
そいつは驚きだ。リビアから何かを盗める者がいるとは。
「魔導具よ。それも古い古い魔導具。お婆様から譲られたものなの」
嫌な感じがした。
リビアの年齢が数千歳ならば、その彼女の祖母ともなれば数万歳となる。
人類文明が始まりかけた時代に魔導具があるとすれば、それは古代魔導時代、つまり伝説の前人類の時代に作られた魔導具ということになる。
そういった魔導具は現代の魔導士では到底たどり着けないレベルのものが多い。我々人狼や吸血鬼が魔法創造された時代の技術なのだ。
リビアが盗まれた魔導具も当然普通のものではあり得ない。古代魔導具。それは怪物のような力を秘めた本物の災厄だ。
私は一度だけそれを使ったことがある。あの時はあのまま世界が崩れ去るかと思った。
「そいつはいったいどんな魔導具なんだ?」
「ネックレスの形をしているの。カットした宝石をいくつも連ねたもので、破壊は不可能。一度も使ったことがないのでどんな機能かは判らないわ。でも野放しにはできない」
事態の重大さに頭がくらくらする。それにこれは対策局に報せるわけにはいかない。
古代魔導具は第一級の禁制品だ。こういったものの所持がバレれば非常に厄介なことになる。下手に使えば世界を揺るがしかねないからだ。
頭がくらくらする。私は来客用の椅子に座り込んだ。
「で、リビア。盗んだ者に心当たりは?」
「あるわ。モーリスという男よ。吸血侍従の一人」
吸血侍従とは各吸血鬼派閥が抱えている人間のスポンサーたちのことだ。
永遠の命と引き換えに毎年一定の金額を吸血鬼派閥に提供するという仕組みになっている。吸血侍従は完全な吸血鬼とは異なり、増殖能力はない。毎月吸血鬼ボスの劣化処理した血液を貰って飲むことで、不老と健康と若さを維持できる。リビアの派閥では膏薬の形で提供していたと覚えている。赤い軟膏で、これを肌に摺りこむという形で服用する。
対策局は吸血鬼の数を厳しく制限している。これには対策局だけではなく、あらゆる魔物の派閥が協力している。魔物は多かれ少なかれ人類全体に寄生していて、人間の血や肉や技術製品に依存しているのだ。だから一つの種族が人間を独占して支配することは許されない。
結果として吸血侍従の席にも厳しい制限が生じる。リビアの派閥では十ほど席があったはずだ。これを勝手に増やすことはできない。
だからその席は非常な高額で売り買いされる。吸血派閥の最大の収入源と言ってよい。
「モーリスの財団はこの間の株の暴落で破綻したの。毎月の上納金が払えないとなったので、吸血侍従の席を追われることになったの」
吸血侍従がその座を追われるということは不老サービスが得られなくなるということだ。ボスの血が貰えなくなれば、吸血侍従はたちまちにして本来の年齢に戻ることになる。つまりは死だ。
眉をひそめながら彼女は続けた。
リビアも冷徹ではあるがまったくの冷酷というわけではない。吸血侍従の座を失うということが死の宣告だとは分かっているが、だからと言って血を分け続けるわけにもいかない。吸血侍従の席は吸血派閥が生きていくための重要な商品である。巨額な商品を遊ばせておくわけにはいかない。
「ボディガードの一人が買収されていたのに気付いたときはすでにネックレスが盗まれた後だったの。当然そのときにはモーリスは姿を消した後よ」
なるほど、その魔導具を取り戻してほしいということか。
確かにこの仕事はその性質からして普通の探偵にも賞金稼ぎにも魔物にも頼むことはできない。古代魔導具が盗まれたなど公にすればその時点で、世界中の怪奇機関が争奪戦を始めかねない。古代魔導具にはそれだけの魅力がある。
迂闊にもリビアは他人が見ている前で金庫にパスワードを打ち込んだことがあり、そのときにボディガードの一人が番号を覚えてしまったのだ。
吸血鬼や人狼などの長命種族は精神的成長が人間に比べてひどく遅い。リビアはこの中の誰よりも歳を取っているが、生き方に甘い所がある。でなければそんなミスはしなかっただろう。
「それでそのモーリスという男についての情報は?」
「一通りのものはあるわ。ウチの吸血侍従だったのだから。でも現在の居場所は不明。影も形もないのよ」
それはそうだろう。相手は吸血鬼について熟知している。
吸血侍従は半吸血鬼だ。不老長寿ではあるが、それ以外は通常の人間に近い。
つまりそのモーリスという男は夜はどこかの物置の中に隠れていて、昼だけ行動している。吸血鬼が探しそうなところにも近づかないし、もちろん酒場にも顔を出したりはしない。
夜の女王リビアからお大事の魔導具を盗み出すぐらいだ。馬鹿ではない。
このニューヨークのどこかに、人類の核兵器に匹敵する魔導具を持った男が隠れている。何としてもそれを取り返さなくてはいけない。
こうして人狼神父から人狼探偵になった私はリビアのフラットを出た。