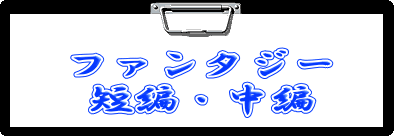
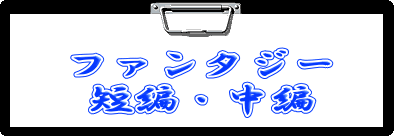
1)
私はバチカン特殊事例対策局の指示でファーマソン神父の名前のスマホは持たされている。だが実を言えばスマホがあまり好きではない。だからいつも電源を切っている。映画館に映画を見に行ったときにマナーとして電源を落として、そのまま電源を入れるのを忘れていたと言う風を装う。
それにスマホで話をしている神父の姿なんてあまり見た目が良いものではないだろう?
知らない一般人が見たら神父がスマホで神様と会話をしているように誤解されてしまう。
まあそういうわけで私のスマホはいつも電源を切っている。そうしておけばアナンシ司教からの呼び出しの電話を受けなくて済む。
だが不思議なことにアナンシ司教からの電話は掛かって来る。なぜかそのときだけ偶然スマホの電源が入っているのだ。例えばアンディに用事があって電話を掛けた直後などに掛かって来る。ひどいときは何かの拍子にポケットの中のスマホをぶつけてしまい、気がつくとそれで電源が入っていたりする。そしてその瞬間にアナンシ司教からの電話が掛かって来る。
くそ。彼の魂に呪いあれ。
きっと彼は何らかの魔術的手段を使っているのだとは思うのだが、私の知る限りの魔術防御を使っても防げないところを見ると、実はすべて単なる偶然が成せる技という可能性もある。
あるいはアナンシ司教は1分間に1回の割で常に私に呼び出しの電話をかけているかだ。
ああ、うんざりする。
だがそれでもアナンシ司教からの呼び出しを無視するのは得策とは言えない。彼を無視した者には常に恐ろしい報復が待っているからだ。
しぶしぶという様子を全面に押し出して私は対策局のオフィスの扉を押し開けた。
広い共同オフィスの中央にまるでエベレストの山のようにアナンシ司教の巨体が聳えている。その前に置かれている大きな大理石のテーブルの上には何かの駒が並べられている。
その中でも一番安物の青ガラスで出来た駒はそれぞれ対策局のメンバーを示している。赤のガラスの駒は対戦相手の駒だ。それ以外の駒ももちろんあり、それらはすべて何らかの宝石でできている。
それらの駒が実際には何を表すのかはアナンシ司教以外は誰も知らない。
アナンシ司教はその駒を使ってどこかの誰かと何か複雑なゲームをしているに違いないと対策局のメンバーは噂している。だがその真偽は誰も知らない。
そもそもアナンシ司教のような存在が他にもう一人居ると考えるだけで空恐ろしいことであり、それを考えると夜に寝られなくなりそうだ。
「来たか」遅いぞという含みを持たせた声色でアナンシ司教が声をかける。
「人蛙族と蛙人族の縄張り争いの仲裁をしていたんですよ。司教もご存じでしょう? あの例の呪われた聖なる溜め池に関する拗れに拗れた案件」
「解決したのか?」
「いえ、でもすぐに解決するでしょう。蛇人族に仲裁に入って貰うことにしたんです」
「血が流れるのは無しだぞ?」
「その前に妥協点を見つけるでしょう。どちらも蛇人族に食われたくはないでしょうから」
私はその想像に思わずにやりとしてしまった。
「両者が妥協する前に蛇人族が空腹に負けた場合はどうなる?」
「その場合は縄張り争いの仲裁の問題が蛇人空腹殺蛙事件の捜査に切り替わるだけです。そちらの場合は犯人が明白なのですぐに事件は解決します」
この完璧な論理に我ながら惚れ惚れした。もっともこれはファーマソン神父のやり方ではない。発案は私の中のダークだ。いつもなら奴の言葉には耳を傾けないのだが、きっとその時には私は酔っていたのだろう。なにぶん人蛙族も蛙人族も人の話を聞こうとはせず、相当私を苛つかせていたというのも背景にある。
喚きさえすれば自分たちの思い通りになると考えているような連中は死ねば良いというのは私とダークの共通の意見だ。ただその筋道が二人の間では少しだけ異なるだけに過ぎない。
しばらくの間アナンシ司教は自分の目頭を抑えていた。それから何か悪い考えを振り払うかのように頭を振って、立ち直った。それから本題の質問に入った。蛙たちの問題は諦めることにしたようだ。
「ファーマソン。一週間前にはどこに居た?」
一週間前? ええと。私は記憶を探った。
「アストリアの裏神学学会に出席していました。ほら、不良天使たちが悪魔の若者たちを嬲り殺しにした事件を例に取っての懺悔の効用に関しての発表があったので。オブザーバーに呼ばれたんです」
「大盛況だったか?」
「大盛況でしたよ。もう少しで悪魔側の聴衆たちによる大暴動に発展する所でした」
「ああ、それ以上は言うな。よし、それに出演していたならば問題はない」
アナンシ司教は手元の別の資料を捲った。
「三日前は?」
それなら良く覚えている。エマが暴走して四人ほど重傷者が出たからだ。
「子供たちの戦闘訓練をしていました」
子供たちとは対策局にスカウトされてきた若者たちのことだ。それが普段エマに勝てない事を根に持ってかなり汚い手段を持ってエマをやり込めようとしたのだ。
怒り狂ったエマが獣化を引き起こして大惨事になる前に私が止めに入ったのだ。
満月の時期に未熟な狼娘を怒らせることほど馬鹿なことはない。暴走すると破壊衝動を自分でも制御できなくなるのが人狼というもの。
私の返事を聞いてアナンシ司教の目が細くなった。
「それではアリバイにならないな。子供たちはみなお前のファンだからな。頼めばどんな証言でもするだろう。そのとき他に誰かいなかったか?」
「途中で清掃員のジャブゼスが見学に来たような」
ジャブゼスは対策局全体を一人で掃除している古株の清掃員だ。対策局の範囲は広い。たった一人で彼がどうやってこの偉業を達成しているのかは誰にも分からない。
「裏を取ってもいいか?」
「もちろん」
アナンシ司教はその底知れぬ深さを持った瞳でじっと私を見た。その瞳に見つめられると背中がムズムズする。それはファーマソンだけでなく、私の中のダークも同じだ。深淵に覗かれるという表現がピッタリくるのがこれだ。
アナンシ司教の正体は私にも分からない。天界の天使たちも魔界の悪魔たちもそのことについてはまったく何の情報も掴めていないのだから、尋常ではない。だが他人の秘密を掘り下げる者は長生きはできない。特にここ、対策局では。
「では無罪放免だ。ファーマソン」
何という事だ。この私の誠心誠意ある言葉よりも一介の清掃員の方が信用があるとは。この世はどこか狂っている。
「何が何やら分かりませんが、これで用事は終わりですか?」
「いや、本当の用事はこれだ」
アナンシ司教は新聞を投げて寄越した。異国の新聞だ。
「訃報欄だ。上から三番目」
現代でも訃報を新聞に載せる人間がいるなんて思わなかった。新聞の日付は二週間前だ。言われた欄を覗くと、英語とスペイン語で同じことが書いてあった。
バー・ザー・ランの死亡通知。葬儀のお知らせ。告知された葬儀の日取りは一週間前。
懐かしい名前だ。だがそれはトラブルを予感させる名前でもあった。
2)
私は飛行機が嫌いというわけではない。ただ対策局所有のあの狂った超音速戦闘機が嫌いなだけだ。
そういうわけで一人で旅客機のチケットを取ると、まだ朝暗い内に大教会の寄宿舎を抜け出した。
アンディとエマが私について行こうと出口を見張っているのは分かっていたので、屋上から出て宙を跳んだ。
大教会の周りには厳重な魔術結界が形成されているし、それ以前に神聖な場なので邪な者は基本的に出入りできない。だから通常の出入り口以外を通り抜けるのは至難の技なのだが、何事にも例外はあり、私のような特殊な免疫を持っている者はそれを素通りできる。
エマはまだ新米の狼娘なので、私がその気になればその鋭敏な耳と鼻を誤魔化すことは容易い。本人はまだ自分の未熟さには気づいていないようだが、おいおいとそれは教育していくつもりだ。そうでないと彼女は一年以内に死ぬことになるだろう。
今回の出張には何を言われても彼らを連れて行くわけにはいかない。これはダークの時代に関する物事なのだ。これ以上私の暗い過去に彼らを巻き込むつもりはない。
あの闇大戦と一言で表現される時代については特にだ。あらゆる憎悪と悪意と欲望を地獄の大釜で煮込んだような有様だった。それを知るだけで魂が汚れるかも知れないものに、子供たちを巻き込むなんてもっての他だ。
旅客機の座席に腰を落ち着けてから目を閉じる。一応偽名は使っているが、それでも周囲の匂いを確かめる。もし魔術や魔物の臭いがするようなら搭乗は取りやめるつもりだった。今でも私を殺そうと狙う者は数多いし、それらの中には無関係の乗客たちを巻き込むことに一切躊躇しない者も多い。
バー・ザー・ランもかってはそうした敵の一人だった。
彼は反ダーク派の頭領の一人であり、専門は呪術だった。
恐ろしく強力で、恐ろしく厄介で、恐ろしく複雑な魔術の代表である。
ダークの部下のかなりの数がバー・ザー・ランの呪術で殺されたし、バー・ザー・ランの呪術家族の大半がダークの手の者に殺されていた。血で血を洗う抗争とはまさにこの事だった。
そんな彼はある日、いきなり姿を消した。あらゆる公の場に出なくなり、呪術の依頼もすべて断るようになった。ダークはこれを何かの罠かと勘繰ってはいたが、結局それ以上は何も起きないので、やがてこの敵のことは忘れてしまった。なにぶん当時のダークには十本の指では数えきれないほどの強敵が他にもいたからだ。
舞台から降りてしまった敵にいつまでもかまけている暇はダークにはなかった。
その彼が死んだ。今さら彼の遺族を訪ねて何がどうなるというものではないのだが、アナンシ司教が行けというからには何かまずいことが進行中なのだろうと思った。
それも大災厄級にまずいことが。
対策局のデータベースに載ったバー・ザー・ランの情報は彼が入院していた病院の情報だけだった。今回の訃報欄に掲載されていた情報から対策局の支局が新たに探り出したものだ。
それによると彼は長い間昏睡して入院していたらしい。
これがかっての大呪術師の成れの果てとはと切なくなってしまった。往時は弟子を百人近くも抱えた呪術界の大スターだった男だ。政界の大物の中でも有名な者が彼に呪い殺されているのは闇の世界では有名な話だ。
こういった政治上の大物は政治力だけではなく、魔術的にもブレーンを持ち、自身に魔術防御をかけているケースが多い。だからその防御を掻い潜って相手を呪い殺すというのは極めて難しい。そういった連中を相手に次々と呪殺を成功させているのだから、バー・ザー・ランはまさに大呪術師の称号を受けるに相応しい男だったわけだ。
病院に当たり、遺体を引き取ったのはバー・ザー・ランの孫娘の一人であったことは突き止めた。病院にも守秘義務はあるが神父服とバチカンの威光は偉大だ。それほど苦労することなく情報を引き出すことができた。この孫娘自体は呪術には関係しないごく普通の女性だ。夫を交通事故で亡くした後は、田舎に引きこもって静かに暮らしている。
孫娘と言っても彼の呪術家族は大所帯で、妻だけでも四十人はいたから孫の数も二百人は下らないはずだ。そのいずれもが呪術に多かれ少なかれ関わっていたに違いない。
その内の一人だけが今や普通の人間としてひっそりと生き延びているのか。
栄枯盛衰世の習いとは言うが、実に、その、感慨深い。
特にその四十人の妻たちを皆殺しにしたのがかっての自分だったと思うと、罪悪感で胸が痛む。もっともどの妻たちもいずれ劣らぬ殺人鬼たちではあったが、それで罪悪感が多少なりとも楽になることはない。
孫娘の家は美しい花を咲かす鉢植えに囲まれた小さな家だった。こじんまりとしていて、表通りからは陰になっているせいか玄関は直接には見えない。ちょっと窓から中を覗いてみたいなと思わせるが、この完璧な静謐を壊すのが怖くて足を踏み入れるのは躊躇ってしまう。そんな隠れ家的な家だ。
敷石にラクガキのような印が刻まれている。どこかのいたずら坊主が釘で敷石を引っかいたような微かな傷跡。
魔術の刻印。隠れ家の印。これが正しく働く限り、この家を魔術的手段で見つけ出すのはほぼ不可能に近い。書類に書かれた住所から辿ることでしか、ここには行きつけない。いや、それですら普通の一般人では道に迷って永久にたどり着けない可能性もある。
素人の技ではない。私は心の警戒レベルを一段階上げた。呪術師は死んでもなお呪術師なのだ。
バー・ザー・ランが本当は生きていて、ダークへの復讐を再開したという可能性もちらりとは考えた。
*
「お茶のお替わりはいかがです。ええと」彼女は微笑んだ。
「ファーマソン神父です」私は答えた。
「ああ、御免なさい。最近は歳を取ったせいか物覚えが悪くて」
「気にしないでください」私も微笑んだ。
バー・ザー・ランの孫娘は人の好い叔母さんだった。白髪が目立ち始めた髪を束ねて結い上げてある。背はそれほど高くなく、老齢を重ねると痩せていくタイプと見た。
「本当にうれしいですわ。最近では滅多に誰も訪ねて来なくなって」
それはそうだろう。敷石の魔術のおかげで、招かれない限りはこの家には誰も近づけない。
バー・ザー・ランは半人半悪魔だった。彼の大勢いた妻たちのほとんどは人間だったように覚えているから彼女はほぼほぼ人間のワンエイスということになる。つまり八分の一の血が悪魔ということだ。バー・ザー・ランのケースは特殊だったが、通常悪魔の血は姿形ではなく精神構造に強い影響を持つ。きっと彼女の場合はときおり残酷なことを考えている自分に気が付いて嫌気が差すぐらいのものだろう。
善人と悪魔の血はそりが合わないものなのだ。
沸騰するポットから茶葉へとお湯を注ぎながら、歌うかのように彼女は言った。
「本当に祖父の知り合いが訊ねてくるのは稀なんですよ。祖父はあまり人付き合いのよい方では無かったし、何より昏睡に入ってからは病院のベッドに寝た切りでしたから」
「どのぐらいになりましたっけ。十年?」
「ほぼ二十年ですわ。先週死ぬまでは一度も昏睡から覚めずに」
二十年か。恐らくは呪術の反作用だ。強い呪いを相手がそれ以上強く反射したりするとこうなる。それほど長く眠り続けるとはいったい何をしたのだろう。
幸い彼女は二十年前の祖父の知り合いなら目の前にいる人間と歳が合わないことには気づかなかった。成人した人狼は加齢が止まるのだ。
「お爺様には誰も見舞いには来なかった?」
「ええ、この二十年に二度ぐらいかしら。お母さまに聞かされた話ではお爺様は何か後ろ暗いことに手を染めていたと言うんです。だからきっと友達と言える人は誰もいなかったのではないかと。あら、あたしったら何を話しているのかしら」
「いえいえ、何でも話してくださって結構ですよ。職業柄懺悔にはなれておりますので」
それを聞いてふふっと彼女は微笑んだ。本当に善良なるおばちゃんの顔だ。神よ。彼女の魂に祝福あれ。
「そう言えば、お母さまはどちらに」
「奥の間で寝ています。母ももう相当な高齢で最近はいつも寝てばかりいるんです」
彼女の母親となるとバー・ザー・ランの娘という可能性もある。それならばもっと詳しいことを聞けたかもしれない。残念だがこれはそこまで立ち入るべき話でもあるまい。
「そうですか。お会いしたかったのに残念です」
私は席を立ちあがった。
「そろそろ行かなくては。懐かしい会話を有難うございます。どうかお気を落とさぬように」
「ありがとうございます。神父さま。どうか祖父の魂に平穏を祈ってください」
「もちろんです。では」
私は踵を返した。
そのとき背後の扉がきしみを上げて開くと、しわがれ声が聞こえた。
「そこまでだ。神父さん。動くんじゃないよ」
動くなとは言われたが振り返るぐらいはいいだろ?
私はゆっくりと振り返った。
ドア枠に持たれかけるようにして、やせ細った老婆が一人、ショットガンを私に向けていた。白髪は乱れ、まさに鬼婆の姿そのものだ。
バー・ザー・ランの獰猛なる娘たちの筆頭、カーリーその人だ。
「声を聞いたときはもしやと思ったけど、やっぱりあんたかい。ダーク。神父の恰好をすればあたしを欺けるとでも思ったのかい」
「失礼な。聖なる勤めを愚弄するとは」とりあえず言い返してみた。
「ふん、いいかい、良くお聞き。この銃には銀の散弾を詰めてある。まともに食らえばあんたでもただじゃ済まないよ」
まともに食らえばの話だ。今まで誰にもできなかったことがこの老婆に出来たならばの話だ。
「まあ、待ちな。カーリー婆さん。私はここに喧嘩をしに来たんじゃない」
「お母さん。いったい」と娘さん。彼女はこの成り行きに目を白黒させている。
「ふん、どうだか」そう言いながらも引き金は引かない。確実に私を仕留められるかどうか自信がないのだろう。もし銀の散弾を詰めたショットガン程度でダークが倒せるものなら、当の昔に誰かがやっている。
私の頭の中のダークはいくつもの可能性を考えたが、その大部分が部屋中を血まみれにする結果に終わるものなので、私は慌ててそれらを心の中から消した。
何よりもここにある格調高い上等のソファーを血で汚したくはない。
「一つ取引を申し出たい」
それを聞いてカーリー婆の目の瞳孔がわずかに広がった。興味を惹いた印だ。
「何だい。早くお言い。あたしの指が引き金を引きたいって泣き叫んでいるよ」
「これから私とあなたの間で魔法のギースをかける。こちらの提案はあなたが私の質問に正直に答えること。その代価として今日より一年間、私はあなたとあなたの娘に攻撃はしない。受け入れるかね?」
ギースは魔法の誓約だ。ギースを司る亜神に誓いを捧げるとそれを各実に執行してくれるという古きそして強力な魔法だ。
私はギースを良く使うが本来はこう簡単に使って良いものではない。ギースの内容は誓約者を縛るので多くのギースを使えば使うほど使用者は自由な人生を送るのが困難になっていく。また強いギースを使うとその分多くの生命力を先払いで支払うことになる。ギースの内容によっては誓った瞬間に使用者が枯れ果てて死ぬこともある。それなりに注意が必要な魔法なのだ。
「怪しいね。それにその取引じゃ不満だ。この場の主導権はあたしが握っているんだよ」
カーリー婆はショットガンを振って見せた。
優れた武道者は戦いの最中には意識して瞬きを止める。瞬きの瞬間に攻撃を仕掛けてくる猛者がいるからだ。
ちょうど今のように。
カーリー婆はショットガンの銃口に合わせて自分の視線を揺らした。
その隙を捉えて私は瞬時に位置を変え、カーリー婆の横に立ち、ショットガンを掴むと天井に向けた。
そのどの一つの動きさえ、彼女には見えなかっただろう。戦いの最中に視線を外すとはそういうことだ。
「さて、これでこの場の主導権は私に移ったわけだ。ミス・カーリー。取引を受け入れるかね?」
一瞬にして立場が逆転したことに頭が追い付かず、カーリー婆はごくりとツバを飲み込んだ。隣で叔母さんが大きく目を開いてこの一連の流れを見ている。賢いことに彼女は叫ばなかったし身動きもしなかった。
ようやくカーリー婆が口を開いた。
「あんた、本当にあのダークかい?」
「色々あってね。今はダークじゃない。前の生き方は捨てたんだ」私は微笑んだ。
実際にはそんな言葉で説明しきれるような軽いものでは無かったが。
老婆は抗ってが万力のような私の腕に掴まれたショットガンはピクリともしない。一瞬躊躇った後に、彼女の顔に諦めが浮かんだ。
「受け入れるよ。あたしはあんたの質問に正直に答える。あんたはあたしたちに危害を加えない」
反射的に応えそうになり、危ういところで思いとどまった。これにハイと答えれば、彼女たちに永遠の免責を与えることになる。そうなれば彼女たちはいつでも自由に私を攻撃できることになる。これがギースの怖い所だ。
私は正しく言い換えた。
「私ファーマソン神父の提案はバー・ザー・ランの長女たるカーリーが私の質問に正直に答えること。その代価として私は今日より一年間、あなたとここにいるあなたの娘に攻撃はしない。これを持ってわが契約となす」
魔法のギースの帳が降り、魔術が成立した。
これで彼女たちは嘘はつけなくなる。元より私は彼女たちを傷つけるつもりはないので、私に損はない。
*
叔母さんはすっかりと冷めたお茶を入れ直してくれた。
二人して私の真向かいに座る。銀の散弾の入ったショットガンはそのまま彼女の手に握らせておいたが、もちろん彼女はもうそれを使うつもりはない。
ギースの誓約の解釈と結果は複雑だ。この取引では一見私からの攻撃は禁止され向こうからの攻撃だけが許されるように見える。だが彼女がショットガンを撃つという行為自体が私の質問を遮る可能性がある以上、彼女の行為もまたギースに触れることになる。それは彼女もよく承知している。なにせかっての大呪術師の娘たちで結成された呪術戦闘部隊の長だったのだから。
「まず最初に教えてくれ」私は口火を切った。「彼はどうして昏睡状態になった。いったいどんな仕事を請け負ったんだ?」
「あれ、まあ、呆れた」手の中のカップの湯気を吸っていたカーリー婆は心底驚いたという風に顔を上げた。
「知らなかったのかい。うちのが受けたのはあんたの呪殺だよ。でも殺すのは無理だったね。あんたには山ほどの魔術の守りがついていたから。だから方向を変えて、あんたの封印を行った」
私も驚いた。
「封印? ということは本当は私が昏睡するはずだったのか?」
「ああ、そりゃ凄い魔術儀式だったよ。弟子を二十人ほど生贄にして悪魔のシャビラブ・ヘルターを召喚したのさ。あたしも施術師として加わっていたからね。よく覚えている。総勢百人で魔法陣を組んで三日かけて召喚したんだ。美しかったね。あの悪魔は」
キリスト教では神に属さない存在はすべて悪魔に分類する。だが現実はそこまで単純ではない。
シャビラブ・ヘルターは人類の神話体系には存在しない独自の神だ。恐らくは暗い洞窟に棲む異種族が崇拝していた神の成れの果てだろう。その実体は地球のどこかの深い過去の中にいて、呼び出すのも至難の技なら制御するのも至難の技という実に厄介な魔神だ。その代わりその力は通常の魔術体系とは直交する位置に作用し、大概の魔導士の魔術防御をまるでただの霧のカーテンかのように通り抜けることができる。
シャビラブ・ヘルターを正しく表現すると異教の魔神ということになるのだろうが、その実それは正しくない。それはまた何か別のものだ。
だがその召喚の代金は凄まじいの一言に尽きる。現にバー・ザー・ランは高位の弟子のほとんどをこのたった一回の魔術儀式で支払ってしまっている。
カーリー婆はため息をついた。
「まったく。それで父は昏睡したんだよ。あんたを眠らせ続けるために。正当なる代価ってやつさ。ところがあんたと来たらピンピンしている上にウチのロクデナシ親父はいつまで経っても目を覚まさない。こっちも色々手を打ったが、どうにもならなかった」
なるほど。それで合点が入った。二十年前、まだ私がダークだった頃、影武者を何人か抱えていた。その一人がいきなり昏睡を起こし、あらゆる魔法の治療も功を奏しなかった。
だがダークにしては珍しくその部下は殺さなかった。使えなくなった部下はすぐに処分するのがダークのやり方だが、その謎の昏睡に疑問を感じたのだ。その通り、もし昏睡した部下を殺していれば、その場で術をかけた者は解放されていただろう。
ダークはその代わりに墓地を一つ用意し、その下に昏睡した部下を丸ごと埋めたのだ。そしてその墓に罠を仕掛け、死んだのが本物のダークかどうかを調べに来た者を殺そうと画策した。
だが罠にかかるものは誰も出ず、昏睡した影武者もいつかは復活するかと思ったが、やがてダークはそのままその事を忘れてしまった。しょせんはただの影武者の一人だったからだ。
そう本当に忘れていた。
今の今まで。
バー・ザー・ランの呪術は正しく働いていた。ただその標的を魔法が間違っただけだ。そしてその術の関係が正しく働いていたために、その術は誰にも解くことができなかったのだ。ひとえにバー・ザー・ランの魔力の強さゆえに。
何と言う皮肉と偶然。もし本物のダークがその術にかかり昏睡していれば、遠からず眠ったままのダークは誰かに殺されていただろう。そしてダークが死ねば、術者の術も解け、バー・ザー・ランは昏睡から目覚めることになっただろう。
実際にはターゲットは眠り続け、バー・ザー・ランも眠り続けたということか。
バー・ザー・ランが昏睡に落ちたことは長い間秘密にされた。だから両者の関係に気づかなかった。もし気づいていたならばダークは何らかの手を打っただろうか?
それは怪しいものだ。ダークはそこまで配下のことを気に掛ける男ではなかった。
そして時が満ち、バー・ザー・ランは死に、この茶番劇にも幕が降りた。
実にひどい結末だ。胸が悪くなる。
「婆さん。いや、カーリーさん。その呪術の依頼者が誰かは教えて貰えないかね?」
カーリー婆さんはにっこりと笑った。まるでこの答えを言うのがたまらなく嬉しいとでも言うかのように。
「そいつは駄目さ。依頼者の名前は伏せるようにあたしには命のギースがかかっている。あんたがそれを知ることはできないよ」
彼女は私とのギースで質問には正確に答えないといけないが、それより古いギースによりこの質問に答えることはできない。
両者を満たす答えはただ一つ。私が答えるように強要すればカーリー婆さんはそれを答えようとして即死する。それで二つのギースは正確に守られることになる。
証明終わり。
となればここにはもう私ができることは何もない。
私はお茶の礼を言い、その家を後にした。
自分たちがまだ生きていることが信じられないかのようにカーリー老婆は私が去る姿をじっと見つめていた。怪物は去ったのだ。
3)
対策局にある自室に戻るとさっそくに出張報告書を書き上げる。バー・ザー・ランの家族の近況とその死の状況などだ。
調査結果はどれもシロ。怪しげな動きはカケラもない。そう書いておいた。事実だから問題はあるまい。ダークと呪殺に関する事項はわざわざ報告することはない。
最後に旅費を計算し、途中で立ち寄ってトラック一杯分食ったステーキの代金も付け加えて請求する。これぐらいは役得というものだ。
アナンシ司教は口うるさい男だが、必要と思われる経費はケチったりはしない。人狼の食費は大事な経費で、これを節約しようとする試みは大概が悲惨な結末を迎えることは彼も良く知っている。
空腹状態の人狼は実に簡単に理性を失うものなのだ。周囲にごまんといる人間が美味しそうな肉に見えるようになるまでにさほど時間はかからない。
提出前にスマホの電源を入れると、珍しくもメールが一通届いていた。差出人の名前を見て目を剥いた。
この人物からメールを貰うのは初めてだ。滅多にないことなのですぐにメールを開いてみる。
ニューヨークの吸血鬼の女王リビアからのメールにはただ一言だけ書いてあった。
『電話して』
もちろん緊急だ。それ以外にリビアが私にメールを送る理由がない。
その場で電話すると、コール一回でリビアが出た。
「遅いわ」
リビアが人を責めるような口調で話すことも滅多にない。だから単刀直入に尋ねた。
「何が起きた?」
「バールバナ」
それだけ言ってからリビアは電話を切った。慌ててかけ直してももう繋がらなかった。
私は対策局専用の超音速ジェット戦闘機が大嫌いだ。それは巨大なエンジンの化け物で、試作として一機だけが製造された。ところが対策局所属の怪物の一人以外には誰も使えなかったために対策局専用になったという経緯があるいわくつきの機体だ。
この戦闘機の通常巡航速度はマッハ5だが、アフターバーナーを使うとマッハ7になる。飛行中は角度を一度変針するだけで10G近い加速度がかかる代物だ。大量の燃料を消費して地球一周も可能だが、そのコストは莫大なものになるので誰もやらない。
狼男の私が本気で動くとこの体にはそれどころでないGがかかるが、自分で動く分には気にならないものだ。だが乗客という立場で縦横無尽に強烈なGがかかるとたまらない。その強烈さはとてもこの繊細な胃袋が耐えられるものではない。
パイロットは岩人間だ。いわゆるガーゴイルと呼ばれる種族の一人で闇レッドデータブックの中では絶滅危惧種に指定されている。
体のほとんどが生きている岩とでも言えるもので、彼はかなりのGでも気絶せずに耐えることができる。しかも彼には胃袋と言えるものはない。有り体に言えば内臓が元より無いのだ。
操縦は彼に任せて、私は太いベルトで座席に体を縛り、太い注射器で麻酔薬を自分に打ち込んだ。
象でも一年間は眠り続ける薬の分量だったが、五分後には体が解毒して目が覚めてしまい。その後はいつものように拷問の時間となった。
諦めて行程のほとんどは目を瞑って過ごした。
バールバナ。その名前が頭の中をぐるぐると巡る。絶対に聞きたくはなかった言葉だ。それはトラブルを、それも極大級のトラブルを予感させる言葉なのだ。
ダークが天界への襲撃の準備をしていたときの話だ。
闇に属するあらゆる組織がダークの下に貢ぎ物を持って来た。
あらゆる種類の魔道具、そしてあらゆる種類の魔導書。ただのガラクタから一度作動すれば大きな街一つが炎の中に消え去るものまであらゆる種類があった。
それらは貢ぎ物という名前の悪意の塊りだった。
使用者の命を確実に奪ってしまったり、動き始めると止まらなかったり、攻撃の対象を選ばなかったりと、危なくてまともに使えないものばかりだった。
天界との闘いを助けるなどとは言っても闇の組織たちの考え方は様々だった。
単に天界への意趣返しを狙うもの。
他の闇の組織をうまく潰し合わせようとするもの。
単純に思い上がったダークがひどい目に遭うことを期待するもの。
そういった集大成がそれらの贈り物であった。
だがダークはまったくの馬鹿というわけではなかった。これらの贈り物を安易には使わず、配下の魔導士たちに調べさせたのだ。そしてその特性をすべて露わにした。時には配下の命を躊躇わずに犠牲にして、その秘密を一つ一つ暴いていったのだ。
そしてそれらを五つの危険度に分類し、それぞれを闇の保管庫に納めた。
闇の保管庫には使い魔の番人が置かれ、ダーク以外の何者をも闇の保管庫に触れなくした。
その内の危険度で三番目に分類される闇の保管庫の名前がバールバナなのだ。ダークと親しかった連中以外の誰も知らない名前だ。
その保管庫のアイテムの一つでも、街一つを滅ぼすには十分な威力がある。
それに今、誰かが触れようとしている。
挨拶もせずに吸血鬼女王のリビアが棲む高層マンション八十一階のフロアを押し通った。
サブマシンガンを持った護衛たちが血相を変えて隠れ場所から飛び出して来たが無視してその横を通り抜けた。彼らには私の動きが見えなかっただろう。
しょせんは人間だ。リビアはいつになったら護衛の人狼を雇うのだろう?
一陣の突風となり美術品が並ぶ廊下を走る。ミケランジェロの未発表の彫像の横を通り、ヒエロニムス・ボスの隠れた名作を横目で見ながらリビアの居室の扉を押し開ける。鍵は掛かっていたが扉の内側のボルトが呆気なく折れて開いた。この程度のバリケードでは本気になった狼男は止められない。
特に私は。
大きくて高価で豪華なソファの上にリビアは体を横たえていた。
夜の女王、ニュヨークの吸血鬼たちの支配者であるリビア。昼でも起きていられるきわめて高位の吸血鬼の一人。古き古き血の持ち主。
彼女が人間であったときにどの民族であったかはもう分からない。齢が五百年を越えた吸血鬼は例外なく肌の色を失って透き通るように白くなる。全身の骨格や肉のつきかたさえも少しづつ変化し、最終的にその時代の美形とされる姿へと変じる。
この変貌のプロセスが生理学的なものなのか遺伝子的なものなのか、それとも魔法学的なものなのかはいまだ解明されていない。
ただ彼女の髪が黒色をしていることだけは元のままだと思う。
リビアの肢体を包む薄い絹のガウンは幾重にも分かれてその体の周囲に広がっている。下着をつけていないのがそのガウンを透かして見てとれる。髪と眉毛以外はまったくの無毛だ。美しい乳房の先がガウンを押し上げている。
彼女は恥ずかしがらなかったし、私もそうだ。昔さんざん見た体だ。何十年経っても少しも衰えていない。老いぬ体は吸血鬼の特権だ。
背後からボディガードが飛び込んで来ると、私とリビアの姿を見て一瞬固まった。ボディガードとしては侵入者を見ないといけないのに、リビアの姿から目が離せず困惑している。
吸血鬼の持つ魅了の魔力。その効果の半分は美しい肉体が引き起こす欲情という生物学的効果で作られている。
彼女が手を振ると、ボディガードはようやく納得してリビアから視線を引きはがすと外に出て行った。ここではボスの命令は絶対だ。それがリビアの魅力のためなのか、命令に逆らえば容赦ない死が与えられるためなのかは分からない。
「やあ、リビア」客としての礼儀として私が先に声をかけた。
「いらっしゃい。ダーク」
「私はファーマソンだ。ダークは死んだ」いったい何度このセリフを言ったことか。
「嘘ばっかり」リビアは嫣然と微笑んだ。
その微笑みを得るためなら全財産を差し出す者も多い。
その片手が上がると私を招いた。白というよりは透き通った青白い色の華奢な手が伸びる。その薄い青の瞳が煌めき、そこだけ赤い唇がわずかに開く。
その口の中に伸びる長い牙はうまく隠している。
その優雅な動作に合わせて微かな魔力の匂いがした。甘く蕩けるような、欲情の期待を込めたものだ。
魅了の魔法。それは少しも危険を感じさせない。だが一度かかれば自我を支配され、奴隷と化す。それほどの致命的な魔法なのに警戒する者は少ない。
随分昔にダークが自分の魂に埋め込んだ魔術式が反応し、蠱惑の霧が晴れる。代わりに創り出されたのは強烈な嫌悪感。もし今ここにいたのがダークならリビアを殺そうとしていただろう。つまるところダークは自分以外の誰も信用などしていなかったのだ。
私は屈んでその手に軽くキスをすると、背を伸ばして着ている神父服を強調した。
「ビジネスの話に移ろう」できるだけ冷たく聞こえるように言い放つ。
「あら、ダーク。つれないのね」
「今はファーマソンだ」厳しい声で言う。私は今は彼女の恋人ではないし、またそれに戻る気はない。
「それと二度とやらないでくれ。どこまで抑えられるか自信がない」
次はリビアを殺してしまうかもしれない。もちろんリビアほどの古く強力な吸血鬼を殺すのは狼男の力を持ってしても至難の技だ。
リビアは私の言葉を逆に取り、自分の魅力に自信を得て微笑んだ。
この私の中に埋め込んである防御反応のことはリビアにも教えたことはない。いくつもの秘密を持つことで今まで何度も私は危機を乗り越えてきたのだ。
「あら、ダーク。あたしはいつでもいいのよ」
なんというセリフだ。罪深き者よ。汝の名は女なり。私は嘆息した。
「悪いがその余裕はない。今の私の頭の中はバールバナで一杯だ」
「嘘ばっかり。本当はあのエマとかいう小娘のことで一杯何でしょう」
「いったいどうしてそんなことを思うのか」私は呆れた。
「彼女は私の直系、それも最初に作った人狼なんだぞ。言わば私に取っては娘に相当する。そんな感情はない」
それに答えてリビアは断言した。
「嘘ばっかり」
うん、これは駄目だ。私が何を言っても信じてもらえない。齢数千歳なのに、それでもリビアは女性の本性を維持している。大したものだ。
数千歳? リビアの言によるとかって救世主を誘惑したことがあるそうだ。当時はリビアという名前では無かったらしいが。
彼女がキリスト教の信者になったのはその頃らしい。
さて、何か忘れていないか?
そうだ。大事なのはバールバナだ。その言葉がリビアの口からどうして出て来たかだ。
「ちょっと長い話になるわよ。座ったらどう?」
彼女はソファの横の椅子を示した。見事な彫刻が施されたアンティークの椅子だ。恐らくは彼女の趣味である芸術家の青田買いで手にいれた、どこかの有名芸術家の未発表作品だ。
これに座るなんてとんでもない。それこそ芸術に対する冒涜だ。私は立ったままでいることにした。
「あのね。あたし、この二週間、ダークと暮らしていたの」
なんだって?
ある日、彼女のフラットをダークが訊ねて来た。
それは本当にダークだった。かってのダークその人だった。姿形も態度も言葉使いも。
恋人に会いに来たのだとダークは言った。そして彼を止めようとしたボディガードを殺しかけた。
リビアが介入しなけば大変なことになっていただろう。
しばらくの間、そのダークは彼女とここで暮らしていた。
「偽物だとは気づいていたんだろ?」
「もちろんよ」
「では、どうして?」
「好きだから。ダークを。愛しているから。ダークを。でもあなたはダークを辞めたし、あたしはダークが欲しかった。だから偽物でも興味を惹かれた」
そう言うとリビアは私の反応を探るかのように悪戯っぽく目を覗き込んできた。
なんということだ。これほどの年月が経ってからリビアの告白を聞かされるとは。
「ダーク。あなた、あたしがどうして天界への挑戦などという暴挙に手を貸したと思うの?」
「それは君たち吸血鬼の悲願だから。そうではなかったのか?」
「ダークは賢かったけど、同時に馬鹿だったのよね。吸血鬼はみな現状に満足しているわよ。だから武闘派を穏健派が抑えていられる。誰も世界のトップに立ちたいなんて考えていない。今でも不死を求める人間たちの血でプールを十分に満たすことができるのに、それ以上を求めて不安定な玉座に座りたがると思うの?」
本当に馬鹿だ。ダークは。すぐ近くにあった愛にすら気づかないほどに。
そして今やダークはファーマソンになり、その愛を手にいれる機会すら失ってしまった。
私は頭を切り替えることにした。
「その偽ダークはどんな奴だったんだ?」
「だからダークにそっくりだって。鋭くて、すぐ熱くなって、すぐ冷めて、賢くて、そして残酷。いつも身に纏っている他人の血の匂いも同じ。殺しを躊躇わない冷酷さも同じ。
楽しかったわよ。昔のダークが戻って来たみたいで」
リビアは本当に楽しそうに笑った。彼女は昔からこういう笑い方をする人だったか?
ダークは今まで彼女のいったい何を見てきたのだろう。
「どこもかしこもあなたとそっくり。裸の背中のアザも同じ。女の愛し方もあなたとそっくりだったわ」
その言葉の内容はちょっと衝撃だったが、リビアならありそうだとも思った。吸血鬼には貞操観念はない。基本的にフリーセックスが彼らの生き方だ。
ここまで聞くとその偽物の正体はただ一つだけ、思い当たった。
「彼はしばらくあちらこちらに出かけていたみたいだけどね。数日前にバールバナに行くと言って出て行ったの。この名前、例のアレよね?」
「そうだ。私は今、とんでもないトラブルの中にいるようだ」
「私たち、よね?」
「私、だ。君は関係ない。できればしばらく別の隠れ家に移って欲しい。もし奴が闇の番人にダークと認められたら恐ろしいことになる」
その昔、神に触れ、ダークはファーマソン神父に変化した。それ以来何度か闇の保管庫に行ってみたことがあるが、闇の番人は保管庫を開けてくれなかった。
それぐらい私は変化した。闇の番人は私をダークとは認めなかった。まあもともとそれら保管庫の中身にはもう興味を失っていたんで、これ幸いと忘れることにした。一度使えば所有者の命を吸い取るような魔道具などこの世に出ない方が良い。
だがもしかしたら保管庫の番人たちはその偽ダークをダークと認めてしまうかもしれない。
問題があるのは魔道具だけではない。質の悪い魔導書がいくつか世に出るだけで戦争が始まる可能性がある。あれらはたいがいが自我を持ち、しかもそれは悪意の側に傾いていることがほとんどだ。それらの魔導書は所有者に力を与え、ついでに自分たちの楽しみのために所有者を操ることまでする。魔導書に取り憑かれた魔導士が世界を征服しようとして騒ぎを起こすことは今でもときどき起こることだ。
うん、今回のこれは十分な災厄だ。
私はリビアのフラットを出ると、偽名でスポーツカーを借り、時速二百キロでかっとばした。
例によってアナンシ司教から呼び出しの電話がかかってきたが今度ばかりは無視した。バールバナと闇の保管庫のことをアナンシ司教だけには知られてはならない。そんなことになれば単純に世界が滅ぶことよりもまずいことが始まる。