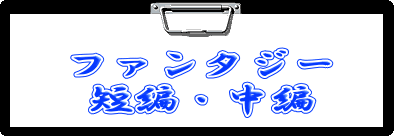
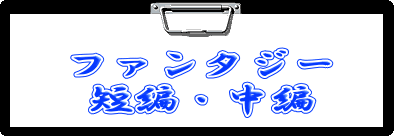
4)
パトカーを三回振り切ったお陰で指名手配されたことが予想されるので、行き着いた街で新しいレンタカーを借りた。
四輪駆動のごつい車だ。これから行く所には道路はない。バチカン支給のカードは使わずに、現金ですべて支払う。レンタル保証金はとんでもない値段になったが、黙って支払う。
カードは使うことはできない。バチカンをバールバナに案内するようなことはしたくないからだ。
ダークの時代に作っておいた秘密口座は今でも有効だ。その中には目を剥くような金額が眠っているのだがどれも例外なくダークが悪事で稼いだ金なのであまり触りたくはない。しかしこの場合だけは例外だ。
闇の保管庫のことは私だけが知っておくべき秘密と考えている。権力を持つ組織がその中のアイテムを知れば絶対に欲しがるし、それを持てば絶対に使いたくなる。そして一度使えばもう止められなくなる。それは保管のためというよりは封印のための場だと私は捉えていた。ただ単に戦争をしたいだけなら、もっと便利で使いやすい道具はある。
そう考えるとダークは凶暴な男であったが、賢い男でもあったと分かる。少なくともこの罠にはかからなかったのだから。
山中深く行ける所まで車を飛ばし、周囲に人気の無い場所を見つけて車を停めると、後は夜を待った。
人狼は満月の夜の大気に満ちた魔力を吸収して狼へと変身する。今日は半月だが、それでも私にはちょっとしたギミックを使っての獣化が可能だ。
神父服を脱ぎ、皺にならないように綺麗に畳んでおく。心の中に満月を浮かべ、周囲から魔力を取り込む。変身に足りない分は私の体の中奥深くに埋められた魔石から取り出す。
これはダークが自分自身に埋めたものだ。
天界との大戦を狙っていたダークは満月の晩しか獣化できないという人狼の欠点を放置しておく気はなかった。配下の魔導士たちと相談した結果、満月の晩に吸収した魔力を貯めておけるようにしたのだ。このお陰で月が出ていなくても一回か二回は変身することはできる。
全身の肉が融け、骨が歪む。苦痛と快感の間の中で変形が始まり、やがてそこには一匹の狼が生れた。
監視衛星が空の上でこの周囲を見ているかも知れないが、闇の中なら四つ足で走る私を赤外線で見ても大型の四足獣としか見えない。そのはずだ。
沖天の半月の明かりでも狼には十分だ。闇に紛れて木々の間を抜け、荒野を駆ける。驚いて飛び出して来たネズミの尻尾をわざと踏んで通り過ぎる。
不注意だぞ、お前。
こうして人の姿を捨て、疾走することの何と気持ちが良いことか。
冷たい風は気持ちが良い。
足下で撥ねる水たまりは気持ちが良い。
草の匂い、岩の感触、それらの間に息づく生き物たちの密やかな呼吸。夜間の捕食者の接近に怯えた匂いを微かに漏らしている。
古い血に問うてみたい。どうして俺たちは狼であることを捨てて人に成ったのか。
ただ今を生きる喜びを捨てて、どうして文明など持ったのか?
狼であることで十分ではないか。それですべてが満ちているのに。
月の光の下での俺たちの王国をどうして投げ捨ててしまったのか。
俺の夢想を断ち切ったのは、前方に現れた大岩の上に座っている存在だった。
それは光り輝いていた。
まるで白亜の崖から切り出して来た彫像かのような、一点の隙も無い完璧な顔。
すらりと伸びた指。黄金比を体現したような見事な体。
しかも全裸だ。その全身が光を発している。髪は炎の赤。まるでそれ自体が燃えているかのように揺れ輝きときおり何よりも深い闇がその炎の中を縞のように横切る。瞳の中央は金色に輝いている
これでもし翼があったら天使族だと判断しただろう。
私は立ち止まって身構えた。本物の狼ではないので唸りはしない。
もちろん、これは人間ではない。そして私が知る如何なる魔物でもない。この世の存在ですらない。
深い深い場所から湧き上がるガスの泡を思わせる声で、それは言った。
「やあ、ダーク」
私は人語を使うために顎の構造を少し変える。並みの人狼にはできない技だ。
「やあ、見知らぬ異邦人よ。知り合いだったかな?」
強烈な魔力の振動。例えるなら一杯に水を貯めたダムの出水口の前に立っている感覚。大気の中に何か危険なものが満ちている。
「知り合いではない」それは言った。「だがまったくの無関係というわけでもない」
「お名前を聞かせてもらえるかな?」
この感じは何だ?
この嫌な感じ。胸の中を満たすこの焦燥感。
その違和感の正体を探って、私は驚愕した。
それは私の中のダークが感じている強い恐怖だった。
「ああ、失礼した。私はデウゼロ・アン・バラマス・イフ・デ・オリオンと呼ばれている。君たちの間では別の名前の方が知られているだろう。シャビラブ・ヘルターだ」
シャビラブ・ヘルター。太古の異教の魔神。美しき災厄。すべてを食らうモノ。
私は意図せずに一歩後ずさった。この美しき魔神が放っている異様さは今まで感じたことが無いものだったからだ。
「誰もお前を召喚していないぞ。異界に棲む者は召喚されない限りこちらに来られないルールだ」
ザ・ルール。
世界を統べる最強の法則。あらゆる魔法の上にあり、あらゆる科学の上にあるもの。その昔のダークは『ザ・ルール』は神が創造したものだと思っていた。だが今やそれは違うと知っている。神よりも上にあるものなのだ。
誰が創ったルールかは知らないがこの太古のルールは今も有効だ。
ザ・ルールには何種類かあり、その一つが異界召喚に関するルールだ。これが無ければ当の昔に無数の魔神たちの侵攻によりこの世界は滅ぼされていただろう。
魔導士たちが結論づけた異界召喚に関するルールは正確にはこういうものだ。
『召喚には生贄が必要であり、その命の価値により異界の存在がこちらに留まることができる日数が制限される。その際の1日は24時間もしくはバルシャンの蝋燭が燃焼する期間として定義される』
シャビラブ・ヘルターは私の問に微かに笑ってみせた。口の端が少しだけ上がる。それだけで冷たい感じが消え、親しみやすさを感じさせる。
もちろん最後まで計算され尽くした表情の変化だ。そもそも魔神の本体が人間の姿をしていることはあり得ない。その必要がないからだ。
「召喚ならされたよ。最近、私の名前を唱えたものがいてね」
それは今度はにっこりとほほ笑んだ。
「差し出された生贄はわずかに二人。だからあまり長居はできないんだ」
背筋を怖気が走った。
最近それの名前を口にしたのは私が知る限りただ一人。とすると生贄にされた二人とは。
カーリーは仕方がない。今までにその手にかけた人間の数は千を越える。だが、あの人の好い孫娘は可哀そうだ。その事実に心が痛んだ。
「あれは召喚のための詠唱ではない。話の中でお前の名前が出ただけだ」
シャビラブ・ヘルターは指を一本私の前で振ってみせた。
「私を呼び出すにはそれだけで十分ではないかね?」
あり得ない。これは明らかにルールの拡大解釈だ。
だがそれだけでこちらに出現できるということは、ルールの解釈を捻じ曲げるだけの力がこの魔神にはあるということだ。三大悪魔ですらできぬことをこの存在は容易くやって見せた。
それの名前を口に出すだけでも命に係る。それを話題にするだけでも召喚の儀式と受け取られる。
沈黙せよ。ただ恐れよ。そは災厄なり。
「魔神が私に何の用だ?」かろうじてそれだけ言った。
「ああ、そう警戒するな。なに、大した用ではない。ちょっとした挨拶だ」
「やり残した仕事を片付けにか?」
影武者を昏睡させたのはこの魔神だ。そしてその昏睡は術師が死亡したことにより二週間前に解けている。シャビラブ・ヘルターはそこで改めて自分の間違いに気づき、その仕事を完遂させる気になったのだろうか。
「あの仕事はすでに終わったものだ。私は召喚者が示した場所に居た召喚者が見せた写真の男に力を振るった。召喚者がターゲットを間違えたのは私のせいではないし、私がフォローするべき事柄でもない」
私の表情から何を考えているかに気づいたのか、それとも私の考えを読んだのか? シャビラブ・ヘルターは私の頭の中の疑問に正確に答えてみせた。
「では何の用だ?」
ああ、質問してばかりだ。分からないことだらけだからか。
「暇でね」シャビラブ・ヘルターは欠伸の真似をして見せた。
矛盾するようだが、魔神はこんな動き一つ取っても優雅だ。
「闇大戦の間ずっと君を見ていた。君はとても興味深い。とても面白い」
それから一言だけ付け加えた。
「玩具にするにはもってこいだ」
胸の中で何かの火が灯った。自分を玩具にすると言われてダークが激怒したのだ。
「ははは、怒ったか。そうでなくては。ではまた会おうぞ。我が善きウルフよ」
シャビラブ・ヘルターは立ち上がり、その瞬間に何の痕跡も残さずに消えた。
強制的に生贄にされた二人の魂に祈りを捧げた。
せめてその魂だけはシャビラブ・ヘルターの手を逃れ、主の御許に行けますように。アーメン。
残念ながら主の玉座には誰も座ってはいないのだが。
5)
岩山の中腹の張り出した岩棚の下がバールバナの入口だ。ここはちょっとした洞窟になっていてその先はただの突き当りになっている。
バールバナへの扉は物理的に存在しているわけではない。それは一種の空間の穴と言って良いと思う。それを作った魔導士に詳しい話を聞いたはずなのだがよく思い出せない。
この扉が開くのは一日につき二時間だけと決まっている。その瞬間を洞窟の暗闇の中でひたすらに待つ。狼男の暗視能力ならばこの暗闇の中でも十分に見える。
今の私を外から見れば、赤い目だけが闇の中に浮かんでいる化け物に見えることだろう。
やがて洞窟の奥の暗闇が一際と深くなった。星辰の位置が整い、闇の保管庫との門が開いたのだ。
その中から何ものかの視線が私に注がれた。それは言葉を発した。暗闇の中の一番濃い所にいるのでその姿は見えない。
「ダークに似た者よ。懲りずにまた来たのか」
「またとはどういうことだ? 私がここに来るのは数十年ぶりだぞ」
「昨日来たではないか」
その言葉と共に何かが投げつけられた。それは乾いた音を立てて床に転がった。さらに暗視能力をブーストしその細部を見分ける。
木の盾の残骸だ。表面にいくつかの魔石が埋め込んである。
魔道具、守りの盾バンジュラム。いや、その残骸だ。
かってダークがあいつに持たせた魔道具の一つだ。
「昨日はこれを身代わりにして逃げたようだが今回はそうはいかんぞ」
「手順に従っていない」私は指摘した。
「何だと?」姿なきモノは動揺した。
「手順だ。何度も教えただろ」
闇の番人というのは基本は使い魔だ。
元々彼らは人間であった。魔術でその自我を奪い、最低限の知性を残して人間らしさをすべてはぎ取っる。それから魔術儀式で存在自体の位相を変えて使い魔に仕立て上げたものが彼らだ。
闇の番人はようやく自分が受けた訓練を思い出したようだ。
「合言葉を言え」
そうだ。それが正しい手順だ。
私はこほんと一つ咳をしてから歌い出した。
「夜の静寂の中にて 我は願う 闇の王 鴉の主よ
憎き昼の落とす影にて 我は願う 永遠に続く冬を
黄昏の淡き揺らめきにて 我は願う 血と叫びの供物を
黎明の消えゆく断末魔にて 我は願う 汝の破滅を糧として」
もちろん闇の保管庫ごとに合言葉は異なる。これはバールバナのためのものだ。言葉のつながりの中にちょっとした魔術を組み込んであり、透視や読心の魔術でも読み取れないようにしてある。
ごくりとツバを飲む音がした。闇の番人には喉なんか無いのに。
「ご主人さま。いや、しかし、違う。姿形はそのもので、合言葉も合っている。だが精神が違う」
「混乱しなくてよい。別に保管庫を開けとは言わない。だが一つ教えろ」
「何でございましょうか」いきなり闇の番人の口調が丁寧になった。
「昨日来た男についてだ。何をした?」
「その男はダーク様にそっくりでした。姿形だけでなく心の中まで。しかし合言葉を言えませんでした。私が保管庫を開くことを拒否するといきなり襲ってきました。ですので私に与えられていた力で反撃したのです。男はその魔道具を身代わりとして逃げのびたのです」
守りの盾バンジュラムは中級のガラクタ魔道具だ。防御に特化した魔道具で物理魔法問わずにかなりの攻撃を受け止めることができる。それだけなら使える魔道具なのだが、攻撃を受け止めたときに本来所有者が受けるはずであった苦痛をそのまま味わわせるという謎の特性を持っている。つまり槍を受け止めるとその槍に刺されたのと同等の痛みを与えてくれる。
どこの馬鹿だ? こんな魔道具を作るのは。
たぶん頭のイカレた魔導士でしかも相当のサディストに違いない。この盾を持った者は死にたくなければ死ぬような痛みに延々と耐え続けることを要求されるのだ。
それでもこの盾は本来なら死を招く闇の番人の一撃を受け止めてみせた。ガラクタなりに見事に役割を果たしてみせたということか。
偽ダークは全身を満たす激痛に叫びながら逃げ出したらしい。
「ありがとう。ご苦労だった」
聞くべきことを聞き終わったので私は闇の番人に礼を言うと踵を返した。
「ご主人さま。私はどうすれば?」背後から闇の番人が訊ねた。
「そのまま保管庫はずっと封印しておけ。誰にも開けてはならぬ」
「このままずっとですか?」声に悲哀が籠っている。
以前に誰かがここを訪れてから何十年も経過している。次に人が訪れるのはまたもや何十年も先になるだろう。ひょっとしたら何百年かも知れない。その間ずっと、闇の番人は異空間で一人切りで過ごす羽目になる。
「それがお前の役目だ」
私は冷たく答えた。それ以外に答えようがないからだ。彼を解放することはできない。そして闇の保管庫は今後も誰にも触られないままが良い。
許せ。闇の番人よ。
*
来た道を逆に辿り、使った経路を逆に使い、ようやくニューヨークに戻って来た。
リビアの棲む高層ビルが見えてきたとき、異変に気がついた。ビルの最上階から炎が立ち上っている。
狼男の視力で火事の位置を確認する。
燃えているのは恐らく対空ミサイル発射機が設置されていた部屋だ。襲撃に当たって空対地ミサイルでも撃ち込まれたに違いない。屋上のヘリポートの端からヘリのローターの一部が覗いている。となると侵入は空から行われたのか。
エレベータを待つなどと悠長なことはしなかった。小さく呪文を唱え、体と魂の境目にあるこの世でないどこかを開く。緊急時の魔力溜めから全身に弾けんばかりの力が流れ込み逆巻き溢れ出す。
胸の奥に湧き上がってくる周囲の消防隊や見物人を見境なく殺戮したいという欲望を無理に抑え込むと、高層ビルの外壁に鋼鉄と化した指を食いこませそのまま垂直に登攀する。滅多に出さない本気モードだ。普通の人間の眼には黒い影が上に飛んだとしか見えなかっただろう。
八十階分を両腕の力だけで瞬く間に登り切り、リビアが棲むフラットの窓を破る。防弾ガラスだが気にしなかった。フルパワーの狼男の拳を受け止められる防弾ガラスなどこの世に存在しない。それには魔術防御も懸けられていたがどちらにしろ結果は同じ。
バラバラに砕けたガラスと一緒に部屋に飛び込む。
この部屋の中にいた何人かの男たちが反射的に手にしたマシンガンをこちらに向けた頃にはもうその背後に立っていた。
匂いで分かる。悪魔族だ。ならば手加減の必要はない。
二人の首は簡単に折れた。三人目はこの小隊のリーダーだったらしく、防御の呪文がかかっていた。私のおよそ十トンの握力にこの男の首の骨は抵抗して見せた。
もっとエレガントな戦い方もあったが急いでいたので力づくにした。呪文を唱えて私の体に組み込まれた次の魔術を発動させる。
かって魔道具と一緒に貢がれた魔導書の中に記述されていた術式だ。体に直接組み込むと普段よりも強い力が出せるが反動としてあっと言う間に体力を使い果たして枯れ果てて死ぬ。そういう役に立たない自爆型魔術だ。
生命力の塊りである狼男ならばこの欠点も何の問題もない。衰えた体は次の満月になればまた再生する。
私の手の中で悪魔の頭蓋骨がまるで脆いクッキーであるかのように細かく砕ける。
そのまま壁に突進して大穴を開けて廊下に出る。廊下の左右に並ぶ芸術作品がひどい有様になっているのを見て少しだけ心が痛んだ。
その中に以前私が描いたリビアの似顔絵が入っていることに気づいて悲しくなった。それをやった奴はすぐに支払いをすることになるだろう。
廊下を暴風の如くに駆け抜け、ドアをたたき壊して中に飛び込む。
まるで何事もないかのようにリビアがソファに寝そべっていた。その周囲にボディガードたちが何人か立って、必死の形相で銃を撃ちまくっている。彼らを取り囲んでいるのは悪魔たちの部隊だ。悪魔たちの周囲では防御の呪文で弾丸が火花を散らしながら弾かれている。これではリビアの側に分がない。
目の前でボディガードの一人が頭を撃ち抜かれて倒れる。
リビアの周囲にはボディガードたちの体がいくつも転がっている。生きている者は一人もいない。彼らは死ぬまでただひたすらリビアのために戦い続けているということだ。なんという忠誠心。いや、魅了の魔法の結果なのか。
「あら、ダーク」私の姿を見てリビアが言った。
それを聞いて悪魔たちの体がびくりと震え、全員が一斉に私に銃を向けた。
彼らの銃から銃弾が吐き出されたときにはすでに私はフラットの高く作ってある天井まで飛び上がっていた。
銀の弾丸だ。狼男を殺すための装備だ。
殺せるさ。もしもそれが私に当たりさえすれば、の話だが。
悪魔たちの背後に降り立つ瞬間に、伸ばした爪でその体を引き裂く。
ボディアーマー程度では私の獣化した爪は防げない。
普通の防御魔術程度では私の強化魔術は防げない。
存分に暴れた。ダークの好みのやり方で。
腕の一振り毎に悪魔の首が千切れ、蹴りの一つ毎に悪魔の胴体が分断される。飛んでくる銀の銃弾は鋼鉄より硬い爪の先で正確に貫き弾いた。サブマシンガンは射出速度が遅いのに加えて、今の私に取って銃弾は空中に止まったハエだ。
引き裂き、潰し、噛み千切り、貫く。いつしか私は大声で笑っていた。
人狼の抑えがたい本能。殺戮の愉悦。ファーマソン神父になっても消せなかったもの。血と肉への渇望。
たちまちにして一匹を除く全員が血の海に沈んだ。
最後の一匹だけは、両腕を引きちぎるだけに止めておいた。悪魔族はこの程度では死なない。
そこまで来てようやくここに来た目的を思い出した。
「リビア、無事か?」
「かすり傷一つないわ」リビアは嫣然と微笑む。「でもせっかくのペルシャ絨毯は台無し」
足下の血で濡れた絨毯を指さす。悪戯っぽく呟く。
「クリーニングに出したらちゃんと落ちるかしら」
やれやれだ。心配して損をした。吸血鬼の女ボス、夜の女王のリビアを心配することほど無駄なことはない。私よりもずっと年上なんだ。この人、いや、吸血鬼は。
大体血がぐっしょりと染みこんだ絨毯をクリーニングしてくれる洗濯屋が存在するだろうか。こんな代物を渡されたら、大概の人間なら腰を抜かして警察に駆け込む。
生き残った悪魔の頭を掴んで空中に持ち上げる。
「どうしてリビアを襲った」
「馬鹿野郎。ダーク。俺たちはお前を殺しに来たんだ」
「私を? 私がお前たちに何かしたか?」
悪魔は喚き散らした。あらゆる呪いの言葉と呪文をまぜこぜにして。聞いてはいられないので、その口に拳を突っ込んで歯を全部叩き折った。魔術が発動している間は私の体は鋼鉄よりも硬い。
いきなり静かになった。
「何があった?」
「お前が俺たちの巣を襲ったんだろう。いきなり現れたと思ったら兵を貸せと命令してきて、断ったら女子供も含めて皆殺しだ。お前を殺してその首を犠牲者に捧げないと俺たちの怒りは収まらない」
「何のことだ。それはいつの事だ」
「十日前だよ。忘れたのか」
ああ、それでアナンシ司教が私のアリバイを確かめていたのか。
偽ダークはあちらこちらの闇の組織を襲っているのだ。それも結構派手に。
実に迷惑なことだ。
なるほど彼の言っていることは本当だ。悪魔たちが持っている武器は対狼男用の銀の武器だけで対吸血鬼用の武器がない。白木の杭もなければ十字架も聖水も、最近どこかの闇メーカーが開発したブラニウム剤もない。
リビアはニューヨークの吸血鬼のボスというだけではなく吸血鬼五大派閥の一つ『血の盟約』の大長老だ。例え悪魔の部族とは言えそうそう気安く対峙できる相手ではない。
偽ダークを匿っていたのはリビアの行為だからその住処に襲撃を掛けられるまではリビアは飲み込まねばならない。だがリビアそのものには傷一つつけないことで敵対はしない。そう悪魔たちは考えたのだ。
そしてリビアもそれを分かっているからこそ慌ててもいないし怒ってもいない。ボディガードたちが職業上の義務で命を懸けるのを横からただ眺めているだけにとどめ、自ら悪魔たちには手出しをしていないことでそれを示している。
人間とは違って魔族たちはかなり高度な戦略戦術感を持っているのには感心する。
しかし考えてみればこれもやはり私の問題だ。この惨劇はすべて私がダークであった頃の遠い残響なのだ。
私は悪魔の首を掴んで宙に持ち上げた。すでにその肩からの出血は止まっている。ドブの匂いのする嫌な血だ。
「いいか、良く聞け。そして他のヤツラにも伝えろ。偽ダークが動き回っている。そして今の私は対策局のファーマソン神父だ。ダークではない」
「偽ダーク? 誰がそんなことを信じるか」
私はギースの印を結んだ。これが一番手っ取り早い。
「誓おう。今より三十秒、私は真実を話すと」
魔法の帳が被せられるこの感じ。それは悪魔にも感じ取れた。彼らはそもそも魔法種族なのだから当然だ。
じっと悪魔の目を覗き込む。
「さあ質問しろ」
悪魔は躊躇った。それから意を決して訊ねた。
「俺たちを襲ったのは偽ダークか?」
「そうだ」
「十日前の俺たちへの襲撃にはお前は関わってはいない?」
「そうだ」
「だがここにはその偽ダークがいたぞ?」
私はリビアに視線を向けた。リビアは舌を出してみせた。そこだけ赤い唇からピンク色の濡れた舌がちろりと覗く。実に煽情的な光景だ。それを見て私に首を掴まれて宙づりになったままの悪魔の股間が敏感に反応するのが分かった。周囲のすべてを感知する狼男の能力が嫌になる瞬間だ。
両腕を千切られて半死人状態の悪魔ですらリビアの性的な魅力には逆らえない。彼女が本気になったらいったいどんなことができるのだろうとちょっと怖くなった。
少し躊躇ったがようやくリビアは答えた。
「昨日、彼はここに帰って来たの」
「今はどこに?」
「知らない。またぶらりと出て行ったの。その人たち何日か前から辺りをウロウロしていたから、たぶん狙われているのに気がついたのよ」
やれやれ。悪魔という種族はどこか詰めが甘い。そしてリビアは今日の襲撃をあらかじめ予想していた。予想していてなお、この惨劇を楽しもうとしたのだと私には分かった。
彼女の血は私よりも古い。賢くて、敏くて、おまけに残虐。血が流れることが大好き。例えそれが味方の血であっても、血ならばすべてウェルカムなのだ。
ああ、リビアよ。汝の名は死が賛美するところ。まさにダークの好みだ。
だが今の私はファーマソンだ。ダークじゃない。
悪魔は私の目を覗き込んで言った。
「お前はその偽ダークを知っているのか?」
残念。私の頭の中で数えていた三十秒がたった今過ぎだ。ギースの効果範囲は今終わった。これでもう誓約には縛られない。この悪魔がそれに気づくほど賢くなければよいが。
「知らない。昔の私は有名人だったからな。成りすましはいくらでも出てくるさ」
さらりと嘘が出た。これもファーマソン神父になってから覚えた技だ。ダークの時代にはそもそも嘘をつく必要がなかったから。嘘は弱いものが使えるたった一つの手段である。
私は悪魔から手を離した。
「さあ、もう用は済んだだろう。お前はもう帰れ」
ケツを軽く蹴って両腕の無い悪魔を部屋から追い出した。階下は消防隊で一杯だろうが、きっと彼らは最上階に上るための階段が無いことに慌てていることだろう。
悪魔がいなくなって彼らが使っていた襲撃魔術の効果が消え、遅ればせながら働いたスプリンクラーが各部屋の火を消していく。
周囲はひどい有様だ。悪魔の死体だけではなくリビアのボディガードたちの死体も転がっている。
そしてリビアは最初から最後までソファーの上でその姿勢を崩していない。
私はリビアのソファーの横に椅子を持って来て座った。血だまりは慎重に避ける。神父服を血で汚したら、また被服部から苦情のメールがアナンシ司教の下に届いてしまう。
私はと言えば、あれだけ暴れても返り血は一滴も浴びていない。これもファーマソンになってから覚えた技だ。たいしたものだろ?
「しかし、あいつ。偽ダークはいったい何がしたいんだ? 悪魔の巣を襲うなんてマトモじゃない」
「彼の名前は忘れてしまったの?」リビアが非難が籠った口調で言った。
「忘れたんじゃない。最初から覚えなかった」
ダークはあいつを影武者一号の意味を込めて、ダーク・ワンと呼んでいた。
「ひどい」
「まったくだ」とこれは心の底からの感想。ダークは本当に人非ざる人だ。いや、狼男という意味ではなくて。
「本当に彼の動機が判らないの? ダーク」
「私はダークじゃない。ファーマソンだ。間違えるな」
「あら? さっきは血に塗れたかってのダークだったわよ」
「見間違いだよ。もちろん」私は断言した。
「ええそうね。そういうことにしておきましょう。ダーク。彼はね、記憶が混乱しているの。自分を本物のダークだと思いこんでいるのよ。だから昔のダークがやりそうなことをしているだけ。悪魔を配下にして、天界との闘いの準備を進める」
私はショックを受けた。バー・ザー・ランの呪術はあいつを昏睡させただけではなく精神にもダメージを与えていたのか。
あいつがそこまで影武者の役に入れ込んでいなければ、バー・ザー・ランの偵察部隊の目を誤魔化すことはできなかっただろう。
奴はシェイプシフター。擬態生物だ。一般にはドッペルゲンガーと呼ばれる存在で、対象の姿形に留まらずあらゆる動作や思考までをコピーすることができる。だがそれでも人狼の能力まではコピーできない。それだけが救いだ。
厄介なのは影武者の役を完璧にするためにあいつに与えた中級魔道具の数々を、ヤツがまだ持っているということだ。使い方によってはそれだけで街の一つや二つは優に消すことができる。
止めなくては。ここにも私の過去の罪が横たわっているのだから。
私は立ち上がった。神父服の裾の皺をはたいて伸ばす。
「さて、リビアはこれからどうする?」
「しばらくは別荘で過ごすわ。このフラットの防備が甘いことも分かったし」
「そうだな。それがいい」
リビアの派閥には何人も大金持ちのスポンサーがついている。この破壊されたフラットもすぐに直されるだろう。
「あなたはどうするの?」
「心当たりがあってね」
リビアに一つウインクすると私は破壊されたフラットを出た。エレベーターは止まっているので、今度も垂直の壁を伝って降りた。
6)
追い込まれた人間は、いや、人間でなくても、脅かされた生き物は自分が慣れ親しんだ住処に戻るのが常というもの。
この場合はニュージャージのアトランティックシティの郊外にある墓地がそれだ。
当時のダークはやはりリビアのフラットに入り浸っていたので、活動の痕跡のほぼすべてがニュヨーク周辺に集中している。
悪徳の街は悪党や魔物に取っては住み心地が良いのだ。
その墓地の一番奥にある一番大きな区画が昏睡したダーク・ワンを埋めた所だ。
大きなコンクリ作りの玄室で、中央に棺。その周囲に副葬品を並べるという古式ゆかしい造りだ。副葬品の周りに張り巡らされた魔術の罠も含めてすべてダークの趣味に合わせてある。
本物のダークが死んだと思わせることで術者を炙り出すつもりだったのだが、その肝心の術者が昏睡しているのだから誰も来ないわけだ。そういうわけでダークの当ては外れて今に至る。
つまりダークは冷酷にもこの影武者のことはあっさりと忘れたのだ。
花束を持って墓を訪れる。しばらくその前で祈りを捧げる振りをした後に、周囲の人影が消えた瞬間を見計らって墓の扉の中に滑り込む。
湿ったカビの匂い。顔にかかる蜘蛛の巣。蜘蛛ってやつはどんなに密閉した所にもいつの間にか入り込むという魔法の力を持っている。
玄室の中は暗いが広い、そこに安置された棺の上にそいつは座っていた。そいつの身じろぎと共に周囲で明かりが灯る。
奴の手の中にあるのは魔道具コンジャラ。いわゆる魔法の杖で、ドラゴンと同等の火炎のブレスを噴き出すガラクタ魔道具だ。
「待っていたぞ。これが罠だとは考えなかったのか?」
不敵な笑みを偽ダークは浮かべた。
そうだ。そうだ。昔の私はこんな歪んだ笑い方をしていた。今の私のように青空の下で高らかに笑うなんてことはダークには逆立ちしてもできない。
そしてその笑いを続けるためにも、私はこの過去からの呼び声を解決しないといけないのだ。
「ああ、ドッペルゲンガー。無駄な戦いはしなくて良いんだ。お前はダークではないし、私もダークではないのだから」
「何を言っている?」
「その杖は小さな炎も出せる。少しだけそれで灯りを作って私の顔を見るがよい」
偽ダークは躊躇った。だが私の言葉に興味を惹かれたのか、杖を振ると炎を噴き出させた。
私の顔を炎が舐める。まったく人の言うことを聞かない奴だ。少しだけと言ったのに。
私の顔の皮膚が焦げたがすぐに再生するので問題はない。彼の失礼は忘れてやろう。ダークはともかく、ファーマソンは寛大なのだ。
私の顔を見て偽ダークの目が見開かれた。
「お前は何者だ。どこかで見た顔だぞ」
「鏡を見てみるがいい。副葬品の中にあるはずだぞ」
「お前は俺だ。どういうことだ」
「いや、俺はお前じゃないし、お前は俺でもない。ドッペルゲンガー。さあ、擬態を解いて元の姿に戻るがよい」
「お前は何を言っているんだ!?」
「お前はバー・ザー・ランの呪術を受けて脳にダメージが残っているのだ。お前はドッペルゲンガー。昔のダークに化けたシェイプシフターだ」
偽ダークが呻いた。その頭の中で何かの記憶が葛藤を始めたらしい。自分で自分の顔を掻きむしる。
「嘘だ。嘘だ。お前は嘘をついている」
「嘘はついていない。何ならギースをかけようか?」
そのとき、背後で爆発音とともに墓所の扉が吹き飛ばされた。素速くステップを踏み、偽ダークの横に位置を取る。
迂闊だった。偽ダークの説得に注意を注ぎ過ぎて外の気配を聞いていなかった。
悪魔たちの部隊が飛び込んで来た。被っている戦闘帽に特徴的なマーク。この間リビアを襲った連中とはまた別の部族だ。
やれやれ偽ダーク。いったいいくつの悪魔を襲ったんだ?
そしてよりにもよって何で悪魔マークス族を選んだんだ。彼らは闇大戦の前は熱心なダーク擁護派で貴重な戦力の供給源であった。そして闇大戦の後はダークを仇敵として付け狙うようになった部族だ。
ああ、偽ダークの頭の中の勢力地図は、まだ闇大戦の前のものなのか。
それは偽ダークもさぞやびっくりしただろう。味方と信じて訊ねてみればいきなり襲われたのだから。
「殺せ! 殺せ!」悪魔の一人が悪魔語の方言で叫ぶ。「動いている者は皆殺せ」
動かなければ見逃して貰えるのかな、と心の隅で思ったのは秘密だ。
「ようこそ。我が家へ」偽ダークが言った。
「そいつだ!」リーダーらしき男が叫ぶ。そこで私に気づいて動きが一瞬止まった。神父服が目に留まったのだろう。
「そいつも殺せ!」そう続けた。
私の頭の中でその悪魔にタグがつく。それはとても短い言葉だ。『敵』
私の中の本物のダークの反応だ。
偽ダークがコンジャラの杖を持ち上げた。それを見て私は彼の背後の棺の後ろへと跳んだ。
この魔道具は杖の前方にドラゴン・ブレス並みの炎を噴き出す。それだけ聞けば役に立つ魔道具に聞こえる。だが私に貢がれた魔道具はどれも使いようのないガラクタだったことを思い出して欲しい。
コンジャラの杖から爆発にも似た炎が噴き出した。炎は墓室の中一杯を隙間なく埋め、武器を構えた悪魔たちをすべて焼き尽くしながら墓室の外へと噴き出した。
それはきっとニューヨークからでも見えたに違いないほどの凄まじい炎だった。ドラゴンに匹敵する炎。耐火耐爆耐衝撃を誇るドラゴンの鱗を持つモノだけが使える炎。
墓室の壁が照り返しで焼け、それは杖の後ろにいた偽ダークとこの私も同じだった。
私の髪の毛が瞬時に焼け落ち、顔の皮膚が黒く炭化する。神父服は特殊な難燃性の素材でできているので燃え上らない。だがその下の肌は流石に熱い。
だがいずれも問題はない。私の怪我はもう治り始めている。黒く焦げた皮膚が次々に剥がれ落ちて新生する。
これが魔道具コンジャラの問題点だ。その炎は見境がなく、使用者まで焼けてしまう。絶対に部屋の中で使って良い魔道具ではない。
それは偽ダークも同じで、全身から煙が上がっていた。
所詮は偽物だ。狼男の治癒力は彼にはない。
守りの盾バンジュラムがあればここまで被害は大きくなかっただろうが、それは闇の番人に破壊されてしまっている。
「おい。お前はシェイプシフターだ。焼けた皮膚を変形させて一か所に集めるんだ」
私は彼の耳元で怒鳴った。ドッペルゲンガーは体のパーツをかなり自由に操ることができる。そのため一度に体の大部分を失わない限りはそうそう簡単には死なない。
だが何も起きない。彼は自分がドッペルゲンガーであることを忘れているのだ。それどころか人狼たる自分の火傷が何故治癒しないのかと狼狽している。
すぐに生き残った他の悪魔たちが墓室に飛び込んで来た。こいつらは何等かの魔道具か魔術で炎を防御したに違いない。どちらも高価なので下っ端には使わせて貰えないのが哀れだ。
偽ダークは焼け焦げた顔を上げた。目は焼けているが耳はまだ聞こえる。気配を察したのだろう。
その手が動き、懐から新しい魔道具を取り出すと投げた。
魔道具チャムラム・バイタル。短剣の魔道具だ。それは宙を飛ぶと、飛び込んで来た悪魔たちを切り裂きながら飛び回った。
強力な魔力をその刃に凝集させ、魔術の防御を切り裂いて悪魔の首を貫く。一人殺すとその生命力をすべて吸い尽くし、次の攻撃へと移る。生きている者が存在する限り、このサイクルは延々と続く。
一度放てば使用者以外は敵味方の区別なく殺してしまう魔剣。
これほど役に立たない道具はない。オーバーキルの代名詞みたいな魔道具だ。
さきほど悪魔が叫んだ『動くものは皆殺せ』というセリフをそのまま短剣に仕上げたものと言える。
私は身構えた。瞬く間に墓室内の敵をすべて殺し尽くした後、チャムラム・バイタルはその軌道を私に定めた。真っすぐに私の胸目掛けて飛んでくる。
意識することもなく私は腰の後ろから二本の短剣を抜いた。一本は特殊鋼材の鋭いナイフ。もう一本は刃に銀を流してある対人狼用のナイフだ。
チャムラム・バイタルがこちらの鋼鉄の短剣にぶつかり火花を散らした瞬間を狙って私はその魔道具に噛みついた。
鉄の板でもかみ砕ける狼男の顎に挟まれてチャムラム・バイタルの動きが止まる。舌の上でその刃がぴりぴりと辛く感じる。
私の生命力が吸えるものならやってみるが良い。その手の攻撃に対する対処はダークの時代に体に組み込んである。役立たずの魔導書の一冊から取り込んだ魔術でだ。
その魔術の副作用は体の魔力構造を改造している間に被験者が即死しかねないほどの麻酔も効かない苦痛が生じることだ。術が完成するまでに二十四時間かかる。それに耐えられる生き物はこの世にいない。
人狼以外には。
私は自分の延髄を破壊して子飼いの魔導士に命じて術をかけさせたのだ。これなら魔法の痛みを感じることはできない。あくまでも首筋に埋まるナイフの痛みだけだ。そして術が終わればナイフは抜かれて延髄は治癒し、私は生き返ることになった。
闇大戦の直前のダークはそんな無茶苦茶なことを繰り返していたのだ。まさに狂っている。
昔のことを思い出しながら、私はチャムラム・バイタルの急所、柄に埋め込まれている魔石を銀のナイフで叩いた。
呆気なくそれは砕け、チャムラム・バイタルの動きは止まった。ただの死んだ魔道具として床に転がる。
「さあ次は何だ?」
後はどんな魔道具を彼に与えていただろうかと考えながら私は尋ねた。
それに応えたのは偽ダークではなかった。墓室の外の悪魔の残党が携行ロケット砲を撃ち込んで来たのだ。
私は高速モードへと滑り込んだ。空中を飛んでくる殺気の塊りに手を伸ばして掴む。そのままぐるりと体を回し、ロケット弾を墓室の外へ放り出す。
爆発。そして誘爆と思われる新しい爆発が二回ほど。
それで終わりだ。外が静かになった。しかしこれはまずい。じきに警察や消防隊が血相を変えてここに集まってくるだろう。
棺の上に横たわった偽ダークは死にかけていた。体の前面が丸ごと焼けたままだ。死んだ組織を一か所に集めて切り離せば問題はないのだが、まだ自分がシェイプシフターだと思いだしていないのだ。
私が彼の方に一歩足を踏み出した瞬間にそれは起った。
墓室の床に転がっていた黒焦げ悪魔の一人はまだ生きていたようだ。そいつがサブマシンガンの銃口を上げると撃ったのだ。
最悪なことに私は高速モードを解いた直後だった。高速モードは一度解くと次に入るまでに数秒のインターバルが要る。
止められなかった。数発の弾丸が偽ダークの体を貫いた。
反射的に銀のナイフを投げ、その悪魔の心臓を貫いて殺す。
偽ダークに駆け寄った。
「銀だ」偽ダークの口から呟きと血が溢れ出した。「俺の心臓が」
「馬鹿野郎」思わず怒鳴ってしまった。「お前はドッペルゲンガーだ。さっさと俺の姿の変身を解いて、焼けた皮膚を切り離せ。銀の弾丸はお前には効かない。破れた心臓もそのまま切り離して新しい心臓を作れ」
無茶を言っているのではない。シエィプシフターは肉体形成のプロだ。治癒はしないが古い部分を捨て、新しく作った部分だけでやっていける。
「俺は・・俺はダークだ。ああ、俺の心臓・・」
くそっ。バー・ザー・ランの奴。いったいどんな呪術でこいつの頭を壊したんだ。
こいつ。こいつ。そう言えばこいつの名前は何だ。ダーク・ワン。ダークの影武者。
確かアラバ・・、そうアラバムとかそんな名前だ。
名前だ。完全な名前。いま必要なのはそれだ。シプシフターは擬態中でも本当の名前を呼ばれれば反射的に擬態を解く。そんなことを聞かされたことがある。あろうことか目の前のこの男から。
私は自分の記憶に集中した。神に触れられて以来、自分の内面に潜る術を覚えた。無数の他人の意識と経験を流し込まれて破綻しかけていた自我を保つためには、自分の内側を探って、そこに本物の自分を見つけるしかなかったのだから。そこで見つけたのが今までダークの内側で静かに登場を待っていたファーマソン神父だった。
記憶の底の底までを探って、ようやく一つの名前が見つかった。
「ドッペルゲンガーのアラバム・バルカス。しっかりしろ。自分を思い出せ。偽の記憶は捨てろ。お前はダークじゃない」
その先の言葉は私の内面深くから浮かびあがって来た。
「俺がダークだ。その名前を私に返せ。ダーク・ワンたるアラバム・バルカスよ。これを汝に命ずる。ダークはただ我一人なり」
バルカスの目に光が戻った。今までどこか遠くを見ているようだった目の焦点がはっきりと私の顔に合った。
自分の頭から何かを排出するかのように頭を振り、そして改めて私を見た。
「おお・・」その唇から声が漏れた。「ダーク様。我が魔王よ」
「話は後だ。早く体を作り直せ」
私は指摘した。
「それから恥ずかしいから二度とその呼び名を使うな」
自分の顔が恥ずかしさで耳まで真っ赤になっていることは感じていた。
*
アナンシ司教は私の報告を受け、アラバム・バルカスの対策局入りをあっさりと認めた。
シェイプシフターはレア・モンスターだ。特に彼のように訓練を受けている者は。アナンシ司教は表情には出さなかったが内心飛び上がるほど喜んでいたはずだ。彼はトリッキーな駒ではあるが、使い方によってはアナンシ司教がやっている複雑なゲームでの切り札となるものを手に入れたのだ。
アナンシ司教はさっそく彼を表す駒を彫り上げた。それは青ガラスで出来ていて、仮面の形をしていた。
彼の目の前の大理石のテーブル、そこの盤の外に見慣れぬ駒が一つ増えていることに私は気づいた。
どうしてアナンシ司教がそれの出現を知ったのかは分からない。だがその駒が何を意味するのかは一目で判った。ダイヤモンドで作られた白く輝くキラキラした大きな駒。
そのことは敢えて訪ねはしなかった。あの異教の神にまた召喚の言葉と取られては堪らない。
ダイヤモンドの駒は何か一言では形状しがたい形をしていた。