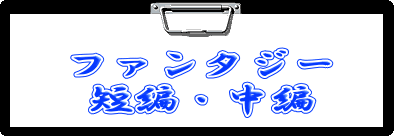
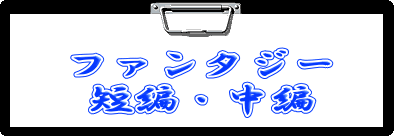
1)
バチカン特殊事例対策局専用の訓練場についたとき、あまりの静けさに耳を疑った。中を覗いてみると電気は消えていて真っ暗だ。広い訓練場の中に人っ子一人もいやしない。奥の射撃練習場も空っぽだし、シャワールームも乾いていて使われた形跡がない。
訓練の日にちを間違ったかなとも思ったが、訓練の無い日でも暇を持て余した何人かの子供たちが使っているはずなのでこれはおかしい。
子供たちというのは私の言い方であって対策局所属の神学生たちのことを示す。メンバーの年齢は十五歳から二十歳までと幅が広い。中にはエマのように成人してから入った者もいる。いずれも特殊能力を持て余している人間か、あるいは魔物である。
野放しにしていればいつか危険な存在になるか自殺する。そういった連中を早目に見つけてスカウトし、対策局局員予備軍としたものだ。
その中でもアンディは真面目でいつも開始時刻より三十分は必ず前に来て準備をしているのでこれはさすがにおかしかった。
ああ、なるほど。エマたちがまた何かサプライズを思いついたのだなと気づいた。
その期待を裏切るのも悪いので、そのまま椅子を引いてきて座って待つこと十分間。
いい加減に痺れが切れたところに清掃員のジャブゼスが通りかかったので聞いてみた。
「さあ、知りませんね。今日はどの子も見ていません」
ジャブゼスが見ていないと言うのならば本当に見ていないのだ。彼は子供たちのサプライズに協力するタチではない。
そういうわけで寄宿寮に足を運んだ。
建物に一歩足を踏み込んで異常に気付いた。静かすぎる。寄宿寮は若者たちが大勢生活する場なのだ。話し声、歩き声、怒鳴り声、そして笑い声はいつも絶えないのが普通なのに何の声もしない。
人狼の聴力を最大限に引き出して、大気の振動をすべて捉える。
屋根の上を風に押されて滑る木の葉のささやき。地下深くの配管を下り落ちる水の音。何かの虫の羽ばたき。入れっぱなしのラジオの放送。鳴りっぱなしの音楽プレーヤー。
テレビの類は寄宿寮中央の会談室だが、ここも空だ。いつもなら誰かがニュースを見ているものなのだが。
その代わりに寄宿寮を満たしているのは静かな寝息。それも何十人分もの。
ただし、話声は一つもなし。
すでに太陽は地平線を離れて高く昇っている。
どうして皆眠り続けている?
入口の横に設置されている警報装置のボタンを叩き込む。けたたましく鳴り響く非常呼集のベルの音。
だが誰も起きては来なかった。
それが事の発端だった。
2)
寄宿寮に居住していた神学生三十二人、そして尼僧見習いが一人、そのすべてが昏睡状態で発見され、対策局は大騒ぎになった。もちろん尼僧見習いとはエマのことである。
全局員に動員令が出された。
神学生全員が医療局に運ばれた。人間医学から初めて魔術治療、治癒系特殊能力者による施術まで行われたがいずれも功を奏しなかった。
患者のバイタルはすべて正常。ただし意識は戻らないということだけが判明したすべてだ。
アナンシ司教の巨大な大理石のデスクの回りに集まった局員の一人が報告を開始した。デスクの上には透明なガラスの天板が新たに置かれ、その下のゲームの駒には誰にも触れないようにされている。
このゲームの正体が何だか知らないが、その駒にアンンシ司教以外が触れることはタブーだ。
実際に触れることを禁止されているわけではないが、それは誰もやらない。前回それに誤って触れてしまった局員は、南極の果てのミッションに送り込まれてまだ帰ってきていないからだ。
「魂魄探査の結果をご報告申し上げます」
発言しているのは眼鏡をかけた理知深そうな女性だ。霊媒能力持ちでかって魔女として火炙りにされていた一族の出身である。
「予想を裏切り被害者の魂は彼ら自身の肉体の中に留まっています。これにより魂魄剥奪系の魔術の使用は否定されます」
「寄宿寮の防御結界の様子は?」とアナンシ司教。
「それが一切問題が無いのです。聖別指数も正常ですし、精霊反応も出ず。防御魔術は極めて正常に働いています。魔法の痕跡は一切ありません」
「となると薬物か?」
それに応えて別の一人が立ち上がった。
「医療班の分析の結果、血液からは何も異常な薬物は発見されていません。また食堂のメニューも調べましたがいつも通りのものです」
それは本当だ。対策局の食堂はあまりにもメニューに変化がないので子供たちからは不評を聞かされている。
もっとも子供たちは外出は制限されていないのでお金さえあれば外食で済ませることができる。たまにエマがこっそりと彼らを連れ出して自分に支給された無制限カードを使って食事を奢っていることを私は知っているが、それはまあ責めるような筋合いではないので私は知らないフリをしている。
つまるところ、これほどの現象を引き起こせるのは魔法以外には存在しないが、対策局の敷地は極めて厳重に魔法防御がされているのでそれは不可能のはずなのだ。
ここロンドン郊外にあるバチカン特殊事例対策局が存在している場所はかってラビアン大聖堂が建っていた場所だ。歴史には残っていないこの秘密の聖堂はかっての十字軍運動の残り火とでも言えるもので、イスラムから追い払われた十字軍の残党がまき直しを願って建設したものだ。
特殊な発祥に加えて、狂気のごとく行われた無数の殉教行為により、ここは一種の聖地として聖別されてしまった。その結果、この場所ではあらゆる種類の魔術の動作が狂い、減衰する。対策局が認めるただ一つの信仰以外の魔法はだ。
まさに理想的な魔術の要塞。それが対策局がここに居座る理由なのだ。
その防御がこうもあっさりと抜かれてしまった。顔にこそ出さないが対策局のお偉方は心の中で冷や汗をかいているだろう。
しかし困った。これでは原因が不明ということだ。そして原因が不明な限り、アンディたちは決して目が覚めないということになる。
会議が一段落ついたとみて、アナンシ司教が手を叩いた。
「わかった。皆は引き続き調査を続けてくれ。今日の会議はこれで解散する。それとファーマソンは残れ」
人払いということだ。たちまちにして皆が共用オフィスから出ていき、私はアナンシ司教と一対一で対峙する羽目になった。
嫌な予感がする。実に望ましくない状況だ。
「さて、ファーマソン」アナンシ司教はじろりと私を睨んだ。
言いながらもそのハムのような手で手元の駒を無意識にいじくりまわす。
それはダイヤモンドで出来た異形の駒だった。
「また何かをやらかしたのか?」
「いったい何のことだ?」できるだけ冷たく聞こえるように返した。
「とぼけるんじゃない。寄宿寮が狙われただけならまだわかる。だがエマ局員がそれに加わっているとなれば話は別だ」
アナンシ司教はその鋭い目で私を見つめた。小さな虹彩の中でさまざまな色が移り変わる。その小山のような巨体の上についているこれも大きな頭の中でいったい何を考えているのかは誰にもわからない。
「エマ局員だけは寄宿寮ではなく尼僧修道院で寝泊まりしている。つまり、彼女も被害を受けたということは、このすべてが君に関連して起きていることを明白に示している」
濡れ衣だ、と言おうとしてそのセリフを飲み込んだ。たしかにアナンシ司教は正しい。今まで気づかなかったがこれは私に対しての何者かの攻撃に違い無い。そう考えるとすべてが符合する。
それも極めて高度な何らかの手段を使ってのものだ。
アンディたちが昏睡に留まっているのは何故か?
神学生たちは私の体に組み込まれているような高度な防御魔術は持っていない。だからアンディたちをいきなり殺さないことの目的はただ一つ。
人質だ。敵は私が大事にしている者たちを人質に取ったのだ。
私は考え込んだ。
最近何か虎の尾を踏むようなことをしたことがあるのか?
偽ダーク事件に関与した悪魔たちの報復?
いや、悪魔には無理だ。彼らが使う手段そして使える手段については熟知している。彼らは獰猛で凶悪だが創造性だけはない。このような今まで見たこともない攻撃を作り出せはしない。
ではモヘンジョダロ遺跡発掘に関わる魔導書騒ぎの件?
いや、あれは結局対立する遺跡マフィア間の闘争に発展し、私の手を完全に離れた。
ドラゴンたちの結婚式を飛び入りで台無しにしてしまった件は深く謝罪して許してもらえたはずだし、バリュハーダイ大聖堂を全焼してしまった件は私の仕業だとはバレてはいない。
他に何かないか?
何もない。
「すみません。アナンシ司教。私にはまったく何の覚えもありません」
一応嘘ではない。
アナンシ司教の目がさらに細くなった。
「本当にか? 本当にないのか? ファーマソン。隠すとためにならんぞ」
アナンシ司教の脅しは単なる脅しではなく、その背後には、言ったことはかならず実行するという彼自身の保証がついている。
「本当にないんです。隠してはいません」
もちろん実を言えば隠し事はある。闇の保管庫などはその代表だ。だから真実を証言するようなギースをかけられるのもまずい。アナンシ司教は尋問のプロだ。何をどう質問すれば相手が言いたくないことを引き出せるのかは良く分かっている。
アナンシ司教がテーブルを叩きその巨体を乗り出そうとしたその時、デスクの上の電話が鳴った。
外部には公開していない電話番号に外線からの連絡が入る。間違い電話かあるいはここの番号を探りだすことのできる何者か。
アナンシ司教は太い指を電話機の上のボタンにそっと下すとトーキー機能を有効にした。
どこかで聞いたような気がする男の声が電話機から流れ出た。
「ダークの電話だな。一度しか言わないから良く聞け。お前のお大事の部下たちを二度と目覚めぬ眠りに落としたのはこの私だ。彼らを解放するための条件はただ一つ。ダークよ。お前の身柄だ」
電話が切れ、私は天を仰いだ。やれやれとんでもないことになった。
3)
この犯人もしくは犯人たちは驚くべき行動に出た。
自ら迎えを寄越したのだ。
私は指定された街角に立ち、迎えの車が来るのを待った。
周囲は対策局の面々が幾重にも監視網を張り巡らせている。物理的なもの。魔術的なもの。魔獣的なもの。透視能力から超聴覚までずらりと勢ぞろいしている。子供たちつまり神学生たちは普段から各局員の一人を選んで子弟の絆を結んでいる。だからどの局員の目も必死になっている。
それは私も同じだ。だから色々と仕掛けを用意した。
待ち合わせの時刻になると黒塗りの大型のバンが現れた。
運転席に一人、バンの中に二人。匂いからするといずれもただの人間だ。
男の一人が私の前に来ると、伝言を述べた。
「写真で見た通りの顔だ。あんたがダークだな。先に言っておくが俺たちは何も知らない。昨日雇われたばかりなんだ。あんたを指定の場所に送り届ければ俺たちの仕事は終わり。雇い主の顔も知らなければ名前も知らない。だからあんたも指示に従って欲しい。何か大事なものがかかっているというじゃないか」
なんとご丁寧なこと。
「分かった。どうすればいい?」
相手はただの人間だ。倒すのは容易だが人質を取られている以上はそうもいかない。
まずは情報を手にいれねば。動くのはそれからだ。
この機会を逃さず過去透視能力者は彼らの昨日に遡って雇主の情報が得られるかどうかを試している。私はと言えば人狼の嗅覚を使って彼らのひどい臭いの中に手がかりがないかを探っている。
うえ、こいつらが前に風呂に入ったのはいつのことだろう。
男の合図でもう一人がバンの後部から車椅子を運んできた。
「まずこいつに座ってもらおう。それからこれだ」
取り出したのは中に何かの液体が入っている注射器だ。
「心配するな。麻酔薬だ。かなり強力だがな。なんでもあんたには普通の薬だと効かないらしく特別製だとさ」
危険はないのか? もちろん危険はある。
男たちが嘘を教えられていてその注射器の中身が猛毒という可能性がある。だが私は大人しく腕を差し出した。
その度胸の良さには感心する。ダークはいつも躊躇わないことで有名な男だった。
注射器が空になると眠りに落ちた様子で車椅子の上でぐったりとする。心臓が動いているのを確認した上で男たちはバンに車椅子を詰め込むと発進した。
誰もそれを止めない。だが密かに追跡の者たちは動き始めた。
バンはいくつか大通りを通り抜けた後、さらに人気のない郊外へと出た。ビルの数が減り、周囲は荒地に変わる。
やがて日が暮れると、夜の道に霧が出始めた。
問題の車の背後で尾行していた車の中では、濃くなる一方の霧を通して先行するバンのテールランプを追っていた。やがてそのテールランプが左右二つに割れた。
そこまで来て初めて自分たちが追っていたのが二台のバイクのテールランプであることを知り、尾行が撒かれたことに対策局員たちは驚愕した。
各国諜報局よりも腕が良いと言われる彼らの自慢のテクニックが通用しなかったのだ。
車椅子の下に張り付けておいたGPS発信機の信号もいつの間にか途切れていた。
慌てて対策局の覗き屋たち、つまり透視能力者の部門に連絡が飛んだが、彼らもいつの間にか眠りに落ちていた自分に気づいて小さな悲鳴を漏らす始末であった。
あらゆる魔術的追跡はすべて無効化されていることに気づき、対策局員たちは途方に暮れた。
4)
車椅子だけ受け渡す形で、運搬している連中は三度総入れ替えされた。これでは最初のグループが発見されたとしても後を辿るのは難しい。おまけに魔術的手段で追跡を妨害している。バンを取り巻いていた霧もその類のものだ。
最期に車がついた先は荒野の先の誰もその存在を知らない暗い洞窟だった。
最後のグループが岩山の前に車椅子ごと私を放置して立ち去ると、岩壁の一部の偽装が解けそこに洞窟の入口が姿を現した。
一人の黒づくめの小柄な人物が中から現れると、車椅子の前で屈みこみぴくりとも動かない私の様子を探った。
「うむ。よく薬が効いている」
そう呟くと車椅子を押して洞窟の中へと踏み込んだ。
男と車椅子が洞窟の奥へと消えると再び偽装の魔術が働き元通りの岩壁へと変ずる。
なるほど完璧な偽装だ。これでは誰にも見つけることはできないのは当然だ。
奇妙な紋様に彩られた洞窟の中には無数のガラクタが所狭しと並んでいる。
その先はさらに大きな洞窟へと繋がっていた。洞窟の中はコンクリートの壁で無数の部屋に分割されている。
ここには覚えがある。ダークの時代に無数に作った秘密アジトの一つだ。
中央の大部屋に車椅子を運ぶと、黒づくめの男は奇妙なステップを踊りながら後ろへと下がった。
足下に普通の人間の目には見えないようにして魔法陣が描かれている。そう見て取った。魔法陣の紋様を踏まないように歩いているためそんなステップになる。
黒づくめの男が口を開いた。
「さあもういいでしょう。ダーク様。我が君。目が覚めているのは分かっているのですよ」
それまで顔を覆っていたフードを外すと、眼鏡をかけた神経質そうな顔が露になる。
「人狼ですら眠ってしまう麻酔薬。だけど貴方様には効かないと知っているのですよ。なにぶん貴方の体を改造したのはこの私なのですから」
車椅子の上でファーマソン神父が身じろぎした。その頭が上がり視線が黒づくめの男に注がれる。
「狂える叡智たるザブン・テイラス・アーダラク。まさかお前だったとは」
ファーマソン神父は口から唾を吐いた。
「いったい何が望みだ」
狂える魔導士アーダラクは両手を広げて見せた。
「おお、それはもちろんダーク様の洗脳を解くことです。我が君よ」
「洗脳だと? いったい何のことだ」
魔導士はやはりという顔をしてみせた。
ファーマソン神父は車椅子の上で身もだえしたがそれ以上のことはできない。それを見て魔導士が首を横に振る。
「無駄ですよ。その場所にはきわめて強力な魔術場を形成してあります。いかな貴方様の力でも出ることはできません」
「俺を自由にしろ。俺は洗脳などされていない」
それに対して魔導士はまたもや首を横に振った。
「お分かりにならぬのも無理はない。貴方様は天界の陰謀により洗脳されたのです。でなければそこまでの変わりようをなされるはずがない。軍勢を引きつれて天界に攻め込んだとき、私めは不覚にも大きな傷を負い戦線を離脱する羽目になりました。なれど貴方様は手を止めることなく神の玉座の間まで攻め込み、四大天使と対決なされた」
そこで魔導士は深く息を吐いた。
「それ以来四大天使の姿を見た者は居りませぬ。故に貴方様が彼らを滅したのは当然の論理の帰結というもの。しかし貴方様はその後に天界の軍勢の側に加わり、包囲していた我ら闇の軍勢を打ち破ってしまう始末。となればこれは貴方様が神の輩に洗脳されたと考えるのが理の当然というもの」
魔導士は車椅子の周囲を苛々と廻った。
「この私めが創り上げた無数の精神防御魔術を神ごときがどうやって破ったのかは分りませぬ。しかしこれが私めの不始末であることは理解しています。だからダーク様への復讐を叫ぶ悪魔たちを説得してこれまで襲撃を抑えてまいりました。あれは洗脳だからこの私が必ず解いて見せるとギースをかけて約束しましたのです」
それはとても重いギースの誓いだ。少しでも文言を間違っていたら、肉体はただの人間である魔導士アーダラクはギースの先払いで死んでいただろう。
またもやファーマソン神父が身もだえした。何か強烈な圧力がその全身を抑え込んでいる。
魔導士の瞳の中で何かの光がぎらりとした。
「動けますまい。我が君。貴方様の特殊な体ならいかに強力な麻酔薬であっても当の昔に解毒してしまっているでしょう。今回の犯人はそこまで知るまい。そう貴方様は予想し、うっかりとここまで来てしまった。
ですが薬はただの囮で本当の目的は貴方様をこの魔方陣の中央に運び込むことだったのです」
魔導士が両手を上げると車椅子の回りの床に一斉に紋様が浮かび上がった。
「これほどの魔法陣を作るのには苦労したのですよ。たとえ強化された人狼であってもその陣の中から出ることは叶いませぬ。この私が全能力を込めて作り上げた魔法陣なのです。誰にも破ることはできません。さあ、これからゆっくりと貴方様の洗脳を解いて差し上げます」
車椅子の上でファーマソン神父の目がぎらりと光った。ここまで大人しく聞いていて彼は初めて反論した。
「狂える魔導士ザブン・テイラス・アーダラク。お前は一つ間違っている」
「なんですと?」
「私はダーク様ではない」
「なんですと?」
「同じセリフを繰り返すと馬鹿に見えるぞ」彼は指摘した。体は相も変わらず車椅子の上から動けない。
「俺のことを忘れたか。アーダラク。友達だっただろう?
よくバルジャンの酒場で飲んだ仲だろう」
魔導士の目が見開かれた。
「まさか! ダーク・ワン!」
「アラバム・バルカスと呼んでくれ。我が魔王に名前を返して貰ったんだ」
そう言いながらもまた唾を吐いた。
「ぺっぺっ。麻酔薬を少し飲んでしまったぞ。何、注射された瞬間にコーティングされた胃袋を腕に作って麻酔薬をそこに貯めたんだ。それでも効くとはえらく強い薬だな。それに味も最低だ」
「待て! では我が君は今どこに?」
ドッペルゲンガーはそこでにやりとした。
「お前の後ろだよ」
半分獣の姿のまま私は闇の中から滑り出た。
「久しぶりだな。アーダラク」
綺麗な発音で彼の名を呼ぶ。獣化した喉で正しく発音するのは訓練した人狼にだけできる技だ。
「我が君!」魔導士は叫んだ。「いったいどうやって。一切の追跡は魔術で封鎖したのに」
私は狼の口を開けて長い舌を出すと喘いで見せた。
「私は魔術なんか使っていないぞ。車の後を狼になってずっと走ってついてきたのさ」
稚拙な透明化の魔法でも、ただの人間相手には効果がある。彼らは車の後を走ってついて来る見えない狼にはまったく気づかなかった。何度か撒かれそうになったこともあったが、アラバムの服につけておいた私の血の匂いが導いてくれた。
ちょっとしたテクニック。原始的であればあるほど効き目がある。誰も走って車を追いかけてくるものがいるとは考えないからだ。
そして私はいまここにいる。一番大切な瞬間に。
真面目な顔に戻って私は言葉を続けた。
「お前には二つ選択肢がある。私と戦うか、それとも私に従うかだ」
魔導士はそれを聞いて悲しそうな顔をした。
「おお、それこそ私めが戦う理由なのです。かっての貴方様ならばそのような事は仰らなかった。有無を言わせずに私の頭を体から切り離していたことでしょう」
「それでは余りにも単純過ぎる。私も少しは賢くなったのだよ」
私は彼ににじり寄った。確かに彼を不意打ちで殺すのは容易かった。だがそれでエマたちが助かるという保証はない。
彼が使役した魔術は何か恐ろしく特殊なものなのだ。彼を殺せば魔術の源は破壊されるが、もしやその魔術の源を他の依り代に移してどこかに隠している可能性もある。
それに彼はただ殺すには惜しい魔導士だ。かってはダークの軍団の魔導士長を務めていた魔法の天才なのだから。
ひどく狂ってはいるが。
彼を屈服させること。私に敵わないと知らしめること。単純な男の論理だが、どこでも普遍的に通用する理屈だ。
先手を取ったのはアーダラクだ。その手の中で光が生じる。魔力を塊にして相手にぶつける全自動追尾機能つきの厄介な魔法だ。まともに命中すれば大概のものには大穴が開く。
私の手が無意識に動き、両脇のホルスターから二本のナイフを引き抜く。魔物を殺すための聖別された銀のナイフに、魔物以外を殺すための特殊鍛造鋼のナイフだ。
飛んでくる魔弾が空中にある間にそれを素早く切断する。純粋な魔力で形作らている魔弾を切っても特に抵抗は感じない。ただ落雷に似た衝撃が体を駆け抜けるだけだ。本来の効果よりは弱くなっているが普通の人間ならば即死する。
魔力が通り抜けた皮膚がギザギザに焼け、すぐに剥げ落ちて真っ新な皮膚に変わる。
私が前進するより早く奴は飛び退いた。魔術跳躍。予め床に描いておいた印の上を高速で跳躍する。
私のナイフは宙を切ったが、偶然に見せかけて先ほどまで彼がいた床の上の印を足で踏みにじる。
魔術跳躍は瞬きより速い瞬間移動の類だが、その跳躍距離は限られているし、印から印への移動と制限されている。こうして印を一つづつ潰していけばそれ以上は逃げることができなくなる。
もちろん魔導士はそれを待ってはいなかった。今度は大きく呼び起こしの呪文を叫ぶ。
何も起きなかった。
私はにやりと笑った。
「お前がアラバムとのお喋りに夢中になっている間にちょっとばかし細工させてもらった。なに、大したことじゃない。他の部屋にあったすべての魔法陣を壊したのさ」
魔導士は悲鳴を上げた。
「あれを準備するのにどれだけ苦労したのかお分かりですか!? 我が君」
「もちろん分かる。長い間をかけて準備したんだろ?」
私は少し間を置いてから続けた。
「一年?」
「二年です。ですがこの部屋の中には手を出せなかったはず」
魔導士は手を振った。
ガラクタに紛れて部屋の片隅に並んでいた四体の甲冑人形が動き始めた。ゴーレムだ。
普通のゴーレムとは違い、それは驚くべき速さで動いた。距離を詰めると私目掛けて手に持った剣を振り下ろしてくる。
私は本気モードに切り替えた。このモードは魔力の消耗は大きいが、アーダラクは並みの魔導士とは違うし、何よりもここは彼の本拠地なのだ。手加減をしてはいられない。
飛び掛かってくる甲冑人形の胸を殴る。鋼鉄の硬さだが、厚みはせいぜい10センチ。本気モードの私の拳を受けて、その胸の装甲が大きくへこんだ。甲冑人形の体の中で何かがきしむ音を上げ、動きがおかしくなる。
迫って来たもう一体のゴーレムの額を縦に切り裂き、続いて横に切り裂いた。それで十字架の印がゴーレムの額に刻まれる。異なる精神界のシンボルを刻まれて、ゴーレムを動かしている魔術の働きが狂った。私はそいつの腕を掴むと振り回した。重量は三百キロというところか。私の筋力ならば問題はない。
投げつけられた同類の体重を受けてもう一体の甲冑人間が後ろにはじけ飛ぶ。
最後の一体の胸を全力で蹴る。大砲で弾き飛ばされたかのようにその体が宙を飛び、魔導士に激突した。
一瞬、やりすぎたかと思ったが、甲冑人形は魔導士の周囲に張られた魔術防御場に当たり、まるで玩具かのように横に撥ね飛ばされた。
「こんなガラクタをいくら出しても無駄だぞ」
私は忠告した。
「もちろん分かっておりますよ。我が君」
魔導士はちょうど術を組み終わったところだった。
巨大な火球が宙に吹き出し、それは見る見る内に圧縮されて小さな太陽へと変じた。
「これを食らえば体の大半は焼け落ちます。ですが大丈夫、我が君なら生き延びることができます」
いい加減にしろ。そんなものを食らえば私でも死ぬ。そうは思ったが口には出さなかった。相手に弱みを見せることはない。
小さな太陽が魔導士から放たれた。
私はナイフを十字に組み、それを迎え打った。
爆炎と輝き。凝縮されたマナがすべて熱へと変じる。やりすぎだ。人間の武器に例えるならば小型戦術核兵器と言ってもよい。
この洞窟ごと何もかも吹き飛ばすつもりか。狂える魔導士の呼び名は伊達ではない。
やがて魔法の輝きが薄れて、爆発の中心に何も無かったかのように立つ私を見て、アーダラクは目を剥いた。
「一体どうやって」
私は腕を上げてそこに嵌った腕輪を強調して見せた。
「これだよ。忘れたのか。お前が作ったものだぞ」
魔道具サマル。アーダラクが作り上げた本物の魔道具の一つだ。あらゆる魔術攻撃を吸収し無効化する。闇大戦の後は使うことなく大事にとっておいたものだ。
「おお、我が君。光栄です。そこまで私の作品を信じてくださるとは」
魔導士は両手を上げた。
「ですが・・」
人間は喋ることと動くことを同時に始めることはできない。彼が次の言葉を形にする前に私はその胸元に飛び込みナイフを振るった。ついでにナイフの柄に仕込まれたギミックを発動し、聖水をナイフの刃に沿って流す。
聖水はほとんどの種類の魔法に悪い影響を与える。それは魔術を構成する精神と聖なるものとの相互作用に起因し、大概の魔法はこの効果を避けることができない。
魔術防御の膜にナイフが触れる度に強烈な衝撃が私の全身に走る。削り取られて飛び散った魔力がナイフに吸収され、私の体を通じて魔道具の腕輪に吸い込まれる。ナイフと防御場との衝突の振動は少しだが魔導士にもはね返り彼の呪文の詠唱を妨害した。
私が攻撃している間は彼も魔法を使えない。こうなれば我慢比べだ。私の体力が尽きるのが先か、魔導士の魔力が尽きるのが先か、勝負だ。
私の両手は見えないほどの速さで斬撃を繰り出した。どんな攻撃でも耐えられるはずの魔導士アーダラクの防御魔術が削れていく。
その削られた分の魔力はすべて魔法の腕輪に吸い込まれる。じきに腕輪が膨れ上がると分解した。吸収した魔力の容量に耐えられなくなったのだ。
それを見てアーダラクの顔がにやりとした。
「さあどうします。我が君?」
私もにやりとした。先ほどとは反対側の腕を上げる。そこに光るのは先ほどの物と瓜二つの腕輪だ。
「まだもう一つある」
アーダラクが悲鳴を上げた。
「止めてください。それを作るのにどれだけ苦労したと思っているんですか!」
「知っている。これを一つ作るのにお前は一か月は眠らずに働いていた。生贄の処女たちも百人は使ったな」
今思えば罪深いことだ。ああ、ダークよ。お前はいったい何をしてきたことか。
気を取り直して私はナイフでの攻撃を再開した。火花・電撃・衝撃。火花・電撃・衝撃。飽くことなきそれの繰り返し。
ついにアーダラクの防御場が最後のきらめきを残して消え、私は腕を伸ばすと彼の首を掴んだ。
硬化した人狼の鉤爪が食い込まないように注意したが、それでも無理に外そうとすればその時点で首はもげるだろう。
いきなりのことに魔導士は暴れたが、その首の横に銀のナイフを押しつけると静かになった。
「呪文も振り付けもなしだぞ。アーダラク」私はその耳元に囁いた。
「魔力の流れを感じたら即座にお前を殺す」
「我が君。ダーク様。私は貴方様を助けようと」
「頼んではいないぞ。アーダラク。これ以上俺をイラつかせたらどうなるかは知っているよな?」
「私めは人質を取っておりまする」
あくまでも魔導士は折れない。
「その通りだ。だからお前はまだ死んでいない。だが以前このことについて話したことがあったよな。人質戦術はバカのやることだと。相手が人質よりも自分の命を優先したら、犯人は人質ごと死ぬことになる。そして自分の命を最優先にする者は数多い」
「貴方様は違う。以前のダーク様なら躊躇わないでしょう。しかし今の貴方様は洗脳以来・・」
その後は私が引き継いだ。
「・・優しくなったか?
だが俺はいつでもダークに戻ることができる。この変化は洗脳ではなく学びの結果なのだ。そして学ことよりも学んだことを忘れる方が簡単だ」
私は手の中の銀のナイフを少し滑らした。魔導士の首の皮膚が切れてぬるりとした血が少しだけ流れ落ちる。魔力を芳醇に含んだとても魅力的な血の匂いに思わず我を失いそうになる。
この血をたっぷりと飲み、魔導士の肉を貪ったらどんなに素晴らしいだろう。そういえばひどく腹が減ったな。
口の中に溢れ出てきた唾液を思わず喉を鳴らして飲んでしまった。
その意味するところを知り、魔導士の体がびくりと震えた。
「わ・・我が君」
「案ずるな。まだ我慢できる。さあギースを受けてもらおう。二度と私に逆らわないこと。その代償としてお前の命をお前に返してやろう」
単純な言葉。単純な取引。あまりに単純すぎるためその解釈は多岐に渡り、そのすべてを保証するためのギースのための生命力は膨大なものになる。このギースを受ければ彼は二度と私を攻撃できないし、私の命令に逆らうことはできなくなる。つまり一生涯に渡って私の奴隷になる。一方、彼の命を返すということは彼に対する他者の攻撃から私が守ってやるという意味も含むことになる。権利と義務。それは危ういバランスで吊りあうことになる。
だが狂える叡智たるザブン・テイラス・アーダラクにはそれだけの価値があるし、何より彼を野放しにするのは大変に危険だ。
今世紀どころかここ十世紀を見ても彼ほど天才で、かつ彼ほど狂った魔導士は存在しない。私の体に組み込んだ数々の魔術を作ったのも彼なら、集まったガラクタ魔道具を改良して闇の軍勢の主兵装に変えてしまったのも彼なのだ。
彼を悪魔の側に渡すことはできないし、アナンシ司教の手駒にするのも危険すぎる。
安全装置の外れた核爆弾を道端に放置するようなものだと言えば分かって貰えるだろうか?
彼はしばし私の手の中でこの取引条件について考えていた。そしてようやく口を開いた。
「受け入れましょう。ただし一つ条件があります」
「早く言え」
うん、これ以上は我慢できない。あまりにも彼は美味しそうだから。
「貴方様が洗脳されていないことを証明すること。それができなければギースは無効とします」
賢いヤツだ。ギースを受け入れればここで死なずに済むし、ある程度の自由が得られる。だがその一方で後で逃げることができる。なにぶん彼は私が洗脳されていることに確信を持っているからだ。
「いいだろう。その条件で手を打つ」
私は言い、魔法のギースの帳が周囲に降りた。私の体の中からごっそりと力が抜け落ちた。人狼の中でも最強クラスの私で無ければこの場で枯れ果てて死んでいたほどの量だ。これだけのものを取り戻すには満月を三回は過ごさないとダメだろう。
私が彼を離すと、彼は床に崩れ落ちた。ギースの代金のほとんどは私が払ったが、ギースは彼からも手付を奪っていったのだ。
「お話中のところ悪いのですが、我が魔王よ」魔法陣の中でドッペルゲンガーが言った。車椅子の上で唯一動かせる手の平をひらひらとさせる。
「ここから出してくださいませんか」